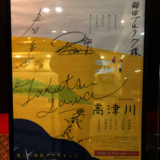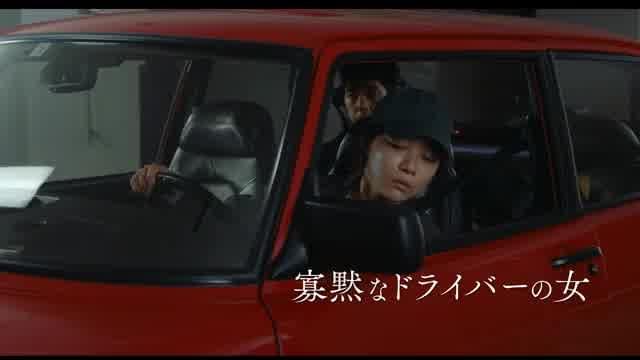ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価
全795件中、481~500件目を表示
ハルキストでないと。
ハリウッドのドライブ物に近い物をを想像していたから最後まで違和感があった映画。村上春樹文学の映画化。百々のつもり、村上文学が嫌いな人や一回も読んだことがない人にはもどかしいのではないか?一つのテーマをねちっこく伝える、舞台での手話のラストシーンでやっと(やれやれ本題の感動シーンが出てきた)で安堵した。それにしてもドライブ物はやっぱりアメリカの風景がいい。明らかにあれ?実家近くじゃんとかこの関越道単調なんだよね~。とか余計なことを思う。日本のロードはドライブ物には向かないとハッキリ解った。俳優陣も良し、中身も良しなんだけど妙に疲れた映画でした。
私が…
枯れなかった涙も
一人では居られない辛さも
償いきれない罪悪感も
ずっとずっと深い奥底に漂うようになっていったのに
生涯そのことから逃れられはしないのだ
勇気の無さが間違った結末へと進めてしまった
変えようのない過去は受け止めるしかない
逃げてはいけない
乗り越えるのでもない
共に生きて生きて生き続けなければ申し訳ない
進む勇気を少しだけ、ほんの少しだけ
また明日が来ますように
上質なチョコを食べたような映画
演劇的
話題になっていたので鑑賞
わかってはいたけど長いなぁ、、、
序章でガッツリ1時間、そこからの展開は静かにただ確実に進んでいく感覚。
ほぼ出ずっぱりの西島さんの演技すごいなぁ
個人的には無音の使い方がめっちゃ好きだった、
北海道の無音と、ラストの手話で一言も発さず終わるところ。
手話を西島さんが目で追ってるビジュアルがめちゃくちゃ好きだった。
あとは、タバコを車の上の窓から掲げるシーンとかね
なんか、ワンシーンワンシーン感じることが多くてめちゃくちゃカロリー消費した感覚、、、
正直馬鹿だから内容の半分も理解できてないと思うし、集中切れた部分もあったけど、なんか喰らうものはあった感覚。
72/100
心とは
理屈で説明できるものではないし、一面から見てわかるものではありません。
だからこそ、村上春樹は輪郭を丁寧に描き、読者にそれを想像させようとしている……と思うので、私はその中を、さまざまな角度から覗き込み、少しでも深く理解しようとします。
子どもを失った喪失感から、近くにいる異性と行きずりの関係を持つ。
……そういったこともあるかもしれません。
夫に嫉妬してもらいたいから、見つかるような形で浮気をするというような女性もいるでしょう。
サマセット・モームなら、どうでもよい相手との、期間限定の関係だからこそ、魂を昇華させられるのだと語るかもしれません。
いろいろな可能性がある中、濱口竜介監督は、もっともベタで低俗で、つまらない理由を選び、長々と3時間も理窟っぽく説明してくださったなと感じます。
心って、そんなに安っぽく、薄っぺらいものですか?
高槻の行動も、突飛すぎて理解不能です。
ただ、ユナさんの所作の美しさが光っていました。
これが「日本の映画」として、海外で評価されるのか~……と思うと、いやだなと思います。
私はいつも添えもの
いかにも日本映画っぽい湿ったオープニングに、うー苦手かもと思った。長い序章が終わり広島に向かうと色調が変わる。
音はずっと理解できない、同一化できない他者として存在する。そんな都合よくいってたまるか。
稽古シーンで「私は添えもの」と女性たちが共感し、音を愛した男2人は理解できない。
後半、とにかく心情説明のセリフが多い。もう、全部話す。車の中では物語の続きだけを話せば良かったのでは?とか北海道での2人の語り全部いらないんじゃ?とか思うけど、たぶんわかっててやってそう。言葉にする、ということに意味があったのかな。
車の中の無感情のセリフ練習、稽古、劇中劇、現実、テクスト論、演劇論と、脚本の構成が巧み。
体位で浮気がバレてたことに気がつくのが生々しい。
韓国手話の劇シーンよかった。ダンサーらしい優雅さ。生きていかなくちゃ。
初!村上春樹
長くないかも
始まって小一時間たって、クレジットが出てくる。そこから話が展開しだすので、長さを感じさせないように、うまく作っているなと思う。舞台場面も車の中も劇中劇で、棒読みのようなセリフが逆に一言一句、心に響いてくる。特に車の中でのセリフ練習の場面は映画でならではの面白いシーンだと思う。ドライブマイカーという題名はこのセリフ練習のシーンのためにあると思った。小説が原作だが、映画ならではの面白さが際立つ。ただし、多言語劇をやるのであれば、車の中でも多言語のセリフに答える形で練習してほしかった。そうでなければ、多言語でなくてもよかったのではないか。手話は印象的だったが。
すっごいすき
思い出したり、悩んだり、悔やんだり、迷ったり、頭の中でいろいろな事が起きていたとしても、それをセリフとして発するわけでなく映画で表現するのは難しが、この映画ではこれはドライブ/車を運転するという行為で表されている。同じく何をしているわけでもないのに運転していない時は思考をしていない、止めているし、自動車事故は言わずもがな。
しかしそんな説明がなくても観客はそれがわかるし、ドライブの様子を見ていることで登場人物のざわざわする心を動きを鑑賞することになる。多くの人が時間を感じないと言っているのは、その心の動きが激しくて追いかけているとあっという間だから。
この映画、唯一困るのは、レビューで何を言ってもなんか野暮になってしまって、人に勧めるのが難しい。
評判の割には
語るための装置・儀式
先日アッバス・キアロスタミの『桜桃の味』を鑑賞して、改めてイラン映画のナラティブの力強さに驚いた。誰もが語るべき何かを持っているし、それを誰かに語ることを厭わない。
こういう傾向は私の好きなラテンアメリカ文学の中にも往々にみられる。ガルシア=マルケスの『コレラの時代の愛』なんかはまるで親戚のオッサンが酒の席で披露する長い長い昔話みたいで、素気なく聞き流そうとしていたはずがいつの間にか聞き入っている。ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』なんかもよかったな。
『ドライブ・マイ・カー』を観て思ったのは、日本人はナラティブに強い躊躇があるということだ。語るべきことはたくさんあるのに、それを語る術を持たない。それゆえ他者とのすれ違い、断絶、そして死。
だから語るための装置や儀式が要る。それらを介してナラティブを始動する。本作では車や演劇がそれに該当するのだと思う。そして紡ぎ出されたナラティブは人と人を繋いでいく。
この構造は村上春樹の小説の中でも頻出する。超現実的な媒体を経由した関係性の接続。井戸、入り口の石、祠。
私も人に何かを直接語ることが苦手だ。フォーマルな自己紹介から始まった人間関係が持続した試しがない。それより飲み会の方が好き。飲み会は本当のことを語ることを強要されないから、どうでもいい話を介して本当のことを語ることができる。今いる友達なんかだいたいよくわからん飲み会で出会ったなそういえば。
日本人は奥ゆかしいとか大人しいとか言われがちだけど、それは語るべきものを持っていないということではない。ただ、どう語ればいいのかわからないだけ。
他者を大切に思う気持ちと、適切な媒体さえあれば、誰もが何かを語り出すことができるに違いない。イラン人だろうが、コロンビア人だろうが、日本人だろうが。
ちなみに、本作を観に行くために何か予習をしておきたいとしたら、村上春樹の原作よりもチェーホフ『ワーニャ叔父さん』を読んでおいたほうがいいと思う。かなりダイレクトに関わってくるので。
日本での、毎度お馴染み、TV局、新聞、出版社やらのメディア、広告代...
日本での、毎度お馴染み、TV局、新聞、出版社やらのメディア、広告代理店が連なって、内容はともかく儲けましょ「制作委員会」の制作じゃないので、こういう映画が創れたのでしょうね。
以前、村上春樹さんの映画化された「ノルウエーの森」で酷くがっかりしたので・・これもどうなんだろ・・とちょっとハスに構えて観ましたが・・。村上春樹ワールドでした♪
気になったのが・・サーブのエンジン音。ちょっと低速のギヤ比の時の音じゃないのかなぁ・・。なんだか、走行中のエンジン音だけ聞くと、ゆっくりが走ってる感覚になっかシフトアップしたくなるの、でも、画面は速く走っているので・・ちょっと違和感・・。
サーブってあんな感じの排気音だったっけ?
ちょっと今まで観たことのない映画
3時間とあって、なかなか踏み切れずにいたが、近所で再上映とあって観に行ってみた。
3時間は、思ったほど長く感じられなかった。
場面展開が激しいわけでもなく、1シーンがめちゃくちゃ長い。
情報量が詰め込まれているわけでもなく、時間にしてはシンプル。
なので、決して疲れた、とか飽きた、は全然なく鑑賞できた。
この映画はちょっとこれまで私が観てきた日本映画の中では異質であった。
まず、セリフ回し。戯曲の舞台が本作の主題だけあって、セリフが日常会話とは違う。
通常日本語は文法のように『~です』『~なんだ』のような形で終わらず、『~ですし』『~ですよ』とか『~なんだよね』『~だから』みたいな語尾が多く使われていると思うが、この映画はほぼ文法通りのセリフ。台本と言うより、やはり戯曲的だと思う(実際台本読みのシーンがあるがそこも面白い)。
また、上に挙げたように、1シーンが長い(1カットではないが)。本当、舞台のようにかなりセリフを詰め込まなければならなかっただろうな、と思うほど長い。
以上のようになかなかこういった手法の映画を見たことがないので、ちょっと驚く。
そういった意味では、この映画は新たな体験として凄く良かった。
ただ、のめり込むかとか、気持ちが入るかと言われるとそうでもない。
私を原作を読んでいないから大それたことは言えないが、正直40代の夫婦の性愛を芸術的に語ることにやや嫌悪感を感じる。性や愛を、あまりに芸術的視点で捉えていたので、ここは私の文化偏差値では付いていけなかった。
あとはラストシーンが意味不明であった。何を言いたかったのか正直わからなかった。
カンヌで高評価を受けたが、監督自身、おそらくそこは狙って作ったような作品だった。
あまり詳しくないが、フランス映画っぽい感じもしたので。
もう一回見れるか、というとちょっと厳しいかな。
三浦透子のほぼ表情の変わらぬ演技は素晴らしかった。
好み分かれるかなぁ
静かな、ゆったりとした作品。
長回しの長台詞のシーンが多くて
(役者さん大変そう)
「演技を見せる」というよりも
「セリフを聞かせる」という感じ。
たんたんと、とまでは言わないけど
引き込まれる感じがあんまりなくて
ハッキリした山場もないので、
飽きちゃう(寝ちゃう)人、多そう。
テーマも[深い]というか、
悪く言うと[こむずかしい]感じだし。
でも自分は、結構好きなタイプ。
ただ、
誰にでもオススメ、
って作品ではないかなぁ。
ラストシーンは、
「ナゼそうなった?」って感じ。
けど、あえてそうしてるのかな。
色々想像させる感じ、にはなってるから、
[説明するのは野暮]ってとこかな。
とりあえず見てみて。損はしないと思う。
手話のシーン
最近見た[コーダ]思い出した。
全795件中、481~500件目を表示