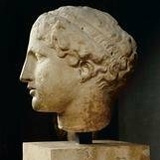ブータン 山の教室のレビュー・感想・評価
全87件中、41~60件目を表示
映画そのものが"ブータン"!
映画的に新しい要素は何も無く、ストーリーすらありきたりである。
でも幸福感に満ち溢れた素晴らしい映画なのだ!!
何も無いけど
幸せの真理だけは有る
正に"ブータンという国を表現した映画"なのですね、行ってみたいなぁ
劇中では描かれてませんが、きっと主人公は"あの場所"に戻ったのでしょうね。
堅実・・!
以前、ブータンの首相(国王ではない)が講演してる番組をテレビで見た事がある。
英語でユーモアを交えつつ、ブータンという国が何を大事にし、どんな展望を描いているか語っていた。
表情が豊かで人間味にあふれ、かつ賢い人物に見えた。
ブータンの映画って、どんなものなんだろう?と思って観たのだが、想像以上に堅実な映画だった。
ブータンの今を描写しつつ、普遍的な価値観を提示する。
脚本に無理がないし、演出もしっかりしてる。
題材をブータンの最深部にとったのもいい。
この国の短所である所得格差、山間部の貧困と、長所でもある美しい自然と素直で真っ直ぐな子供たちを同時に描く事が出来る。
首相の講演に感じた賢さを、この映画からも感じた。
今後、ブータンがどうなっていくのか。
少なくとも日本みたいにはならないで欲しいなあ、と思うけど、たぶん、この国の人々なら大丈夫・・かな。
幸せと心の浄化
標高と人口と幸せの関係
未来に触れる
心豊かに生きる
キャスト選択の勝利!
少女=ペム・ザム(ポスターの中心にいる少女)、歌姫=ケルドン・ハモ・グルンの2人がこの映画のほぼすべてを支配しており、それも最高レベルのふるまいでした。あえて演技とは言いたくありません。
ペム・ザムちゃんの登場映像は衝撃的で、こんなにかわいく明るい少女が本当に存在していることに心底驚きました。その後の歌も会話もすべてキラキラと光り輝いていました。世界の僻地の奇跡ですね。
歌姫=セデュ=ケルドン・ハモ・グルンはプロの歌手みたいですが、その笑顔、演技は自然で魅力的でした。外見的には現代の美人かどうかは難しい(もちろん一般の水準からしたらかなりの美人ですが)のですが、ふるまい、動作は絶世の美女でしょう。
場所とか時代に関わりなく、こういった魅力的な人間がいればそこは幸福度MAXになるのは必然と思わせる映画でした。
是非「大事な何かを忘れつつある日本人」に観てほしいと強く思いました。
この監督、1作目だそうですが、凄いな!というのが正直な感想。
陰翳礼讃
貴方はルナナで一生暮らせるか?
ルナナ村での暮らしは本当に幸せなのか?
ルナナ村の子供達は、純粋で無垢で優しくて、足るを知る天使なのか?
ルナナには、都会人が忘れている「大切な何か」があるのか?
私は、決してそうは思わない。
何故、ルナナの人々があれほどまでに教師をありがたがったのか?
子供達に教育を与えたかったのか?
村長が答えている。
「教育があれば、他の仕事を選べる」と・・・。
そう。村人は村の暮らしに対して、決して「満足」している訳ではないのだ。
もちろん「満足」している人も、中にはいるだろう。しかし、そうではなくて「他の生き方を選べない」から消去法で「この暮らししか出来ない」人が大半だと思う。
ウゲンをもてなした食事。ウゲンにとっては日常的に食べてきたものよりも、遥かに質素だ。
しかし、ミチェンは「こんなご馳走を食べるのは正月以来」だと言う。
村民の大半が靴すら貧しくて買えない。紙1枚だって、大層な貴重品だ。
ドルジ監督は「この映画は決して、経済的物質的な幸せと、文明が無い中での精神的な幸せ、の二項対立ではない。」と述べている。
決してルナナ村の暮らしが幸せであると説いている映画ではないのだ。
食事が身体を育む糧ならば、教育は知性と心を育む糧だ。
知識と知性が高まれば「より広い世界」を知りたくなるだろう。
社会の大きなシステムを知れば「その中で、自分はどれだけやれるか」に挑戦したくなるだろう。
教育を与える事は、同時に物質文明の扉を開く事でもある。
「教育という糧」を与えられないが為に無垢な瞳が輝いている事は、肯定されるべき事態では無いのじゃないか?
監督は谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」に影響を受けたという。
「光のありがたさを知るためには、影を理解しないといけない」と監督は言う。
ブータンでは最大の都会、ティンプーの暮らしに不満ばかり抱いていたドルジ。しかし「ルナナという影」を知ることで「自分は今まで、どれだけ光の当たる幸せの中にいたのか」に気付く。これまで不満だとばかり思っていた事の一つ一つが、どれだけ幸せでありがたい事だったのか?と。
同時に「ルナナでの貧しい暮らしの中にも沢山の精神的幸せ」がある事も、ドルジは知る。
終盤、ドルジがオーストラリアに行って本当に良かった。渡航を取りやめたり、ましてや冬場までルナナ村に残ったりするような展開ならば、この映画の価値は一気に下がってしまうだろう。
「幸せ」は「どこにでもある」のだ。
ドルジにとっては、それに気付かせてくれた原点がルナナ村になった。
オーストラリア・シドニーほどの大都会で、溢れ返る物質文明に幸せを見失いそうになった時も。ルナナ村を思えば、いつだって「今、ここに」幸せは見出すことが出来る。
西洋的物質文明は、強い光で「影を消す事」に力を注いだが、日本人は「影を認め」「光と影の中で映える生き方」を模索する。ブータンもそうだろう。
監督は
「経済的・物質的文明の中にもある精神的幸せ」と
「光(物質的豊かさ)のみを追求するばかりでなく、ブータン固有の豊かさ(文化・伝統)」を失わない事の大切さの両方を、本作で訴えたかったのだと思う。
表面的な「素朴さ、純朴さ」のみに感動するだけではなく、広い世界を知る事の大切さと、幸せは今この瞬間にも自分を包んでいる事に気付くという点に、注力している事を高く評価したい。
足るを知る
心の琴線に触れました!
誰しもが知っている物語。
田舎や離島に期間限定で都会から先生が赴任して来る。ちょっと訳ありの先生と子供達の成長物語。世界中で手を替え品を替え数多に作られてきたテーマ。その原点に立ち返ったような映画でした。
ブータンの僻地ルナナ。標高4800m人口わずか56人。電気も水道も電波もない。近代社会から切り離されたこの村に首都ティンプーから若い先生がやって来る。黒板も紙もない山の教室。1+1から始まった授業も気が付けば8の段のかけ算に。しかし村には間もなく厳しい冬が到来する。今、村を去らなければ雪に覆われ身動きが取れなくなってしまう。
裏切りもどんでん返しもない。その結末さえ誰しもが昔から知っている物語。それなのに序盤から涙が止まらなかった。
実際ルナナで撮影が行われ現地の村人がそのまま出演も果たしています。映画もインターネットも知らない。村から出たこともない子供達のキラキラした瞳。初々しさがスクリーンに見事に反映されています。そして同時に加速する近代化、外国に移り住む若者といった幸せの国ブータンの現状の一端を知ることにもなります。
壮大な景色が圧巻。山や峠に住むと信じられている神や精霊に祈りを捧げ、ヤクの歌を口ずさみながら自然と共に生きるルナナの人々と子供達。本当に優しくて素敵な映画でした。
もっと魅たかった、もっと欲しかった
『癒される』映画
輝く瞳は未来を映す
いい映画だなぁ。
ひじょうに好感の持てる、いい作品です。
西洋文化やIT社会に毒された我々にいちばん足りないものが、この映画の中にあるように思います。
これからの時代、ますますこの映画の描こうとしているものが大切になってくるでしょう。
キャストは、映画未経験のほぼ素人と、素人(実際の村人たち)で構成されているとのこと。
にもかかわらず、これだけ質の高い作品が撮れるとは、まったく驚きです。
学級リーダーのペム・ザムのかわいらしさ、けなげさに1度目のノックダウンを奪われ、セデュの魅力に2度目のノックダウンを奪われました。
村長もかっこいいし。
登場人物たち、それぞれの「歌」が心にしみます。
コントラストの効いた、光と影の美しい映像もいうことなし。
宣伝ポスターに写ったペム・ザムの利発そうで愛らしい表情と、その瞳の輝きにひかれて観にいったのだけれど、鑑賞して正解でした。
気がついたらマスクの下で微笑んでいる自分がいた。
そして、彼女の輝く瞳は希望にあふれる未来を映しているのだ、とわかりました。
今年上半期に鑑賞した中でベスト3に入る秀作です。
もう一度、観たいなぁ。
追記
マイナーな作品だし、それほど観客も入っていないだろうと思っていたのですが、意外にも(失礼!)連日盛況のようです。
僕が鑑賞したときも、たくさんのお客さん(中高年中心)が訪れていました。
こういう、地味だけど、誠実さの感じられる作品が注目されるのは、とても喜ばしいことだと思います。
この監督の次回作にも期待したいものです。
追記の追記
ずいぶん前に、テレビの深夜放送で『ザ・カップ~夢のアンテナ~』という映画を観たのですが、それがとても魅力的な作品だった(ふだん僕は劇場以外では映画は観ないのですが、たまたま点けたら面白くて観つづけてしまったのです)。
で、その映画を撮った監督の教え子にあたるのが、本作『ブータン 山の教室』の監督、パオ・チョニン・ドルジ氏であると知りました。
つながってるんだなぁ。
『ザ・カップ〜』、劇場で観たい。
観てよかった、心が洗われる。
ブータンの人々の生活や習慣を目にする機会がそんなに多くない我々にとって本作はブータンの人々の生活を知ることのできる貴重な作品である。その生活といったら、資本主義経済である日本で生まれ育った我々にとっては到底考えられないような質素で簡素な暮らしぶりだ。
なのに、なぜだろう、その生活や人々の存在が美しく尊い。この地球にこんな神々しい世界が存在するんだと。本作を見れば見るほどにひたすら消費し続ける私たちはなんて愚かな存在なんだろうと思わずにはいられない。
また“先生は子どもたちの未来に触れることができる”というセリフからも教育のあり方、教育者とは何ぞやという課題も問いかけている。
“幸せ”とは何だろうかーー。
紙一枚さえも貴重、勉強できることが幸せだと感じる人や場所がある一方で、資本主義国に住む私たちは生まれた時から多くのものを与えられ欲しがり、もっと、もっと、といった欲や煩悩に囲まれて生きている。その対象は人や物、多くの経験をすることにも向けられている。だけどもっと、もっと、とその底なしの欲望は延々に満たされることはないのかもしれない。
多くのものを知らないからこその幸せ、与えられた物や場所で精一杯生き抜くことも一つの幸せ、いや真の幸せではないだろうかと気付かされる。ため息の出るような美しい山々と生命あふれるヤクや愛くるしい子どもたちの笑顔に心洗われる貴重な作品だ。
本当の自分を探しに…
自分探しの旅は、必ずしも自分が望んで始めるとは限らない…
最初の15分ほどは苦痛だった。久しぶりに寝てしまうかと思ったくらい…
主人公、ウゲンがガザ県・ルナナの村に着いてから、急に涙が込み上げてきた「僕はこんな暮らしがしたかったのだ」と…
主人公・ウゲンの進む先が何処にあるのかは分からないが、少なくとも彼は、ルナナの村に自分のアイデンティティーを見つけることが出来たのではないかと思う。
トレッキング、という言葉の意味を知るために、この映画を観るのも良いかもしれない。丸一日バスに揺られて着いた村から一週間、起伏の激しい山道をひたすら進み、時には身を斬る様な冷たい川を渡渉り、空気の薄い峠を越える…
素晴らしい大自然を楽しむ余裕などそこには一欠片も無く、峠の神に祈りを捧げるどころか悪態を吐きたくなる。
それでも僕は、ルナナへ行きたくなった。ペム・ザムに逢いに行くために…
「教わる」ことの尊さ✨
すでに知っている、アルファベットや簡単な足し算を、先生から、大切そうに、嬉しそうに教わる子どもたち。
がらんとした室内が、やっと教室らしくなったと思ったら、厳しい冬が来る前に、先生は町へ帰ってしまう。
これまで何人の先生を迎え、見送ってきたのだろう、と思うと、切なくなりました。
先生には、ずっと村に残ってもらいたいけれど、別れがあることに抗わず、先生がいてくれる期間をとても大切にし、敬意を払っている子どもたちや村の人たちの清廉さが素晴らしかったです。
単に学びたいのではなく、「教わる」ことを大切にしていると感じました。
「一期一会」や、「あるがままを受け入れる」といった禅の心に通じるものや、万物に感謝する生き方をルナナの人たちから感じました。
日本では、「覆水盆に返らず」なのに、ルナナでは、「こぼれてもミルクはミルク」というのも素敵です。
今度、ブータン料理を食べに行こうと思います😃
全87件中、41~60件目を表示