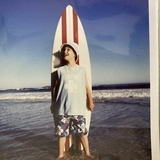「思い出は生き続ける(生々流転)」ノマドランド pipiさんの映画レビュー(感想・評価)
思い出は生き続ける(生々流転)
ラスト手前で、ようやく安堵出来た。
「思い出は生き続ける」「私は少し引きずり過ぎたみたい」
この2つの台詞にまで辿り着かないならば、私にとってこの映画は星3に留まるところだった。
数年間の流浪を経て、その域が見えるようになった彼女の漂泊は、これまでとは違う意味をもつものとなるであろう。
高齢者を放り出すような資本主義・末期症状への意見表明は、この映画のメインテーマではない。(でも、もしかしたら原作者はこのテーマ重視かもしれないな)
登場するノマド生活者の大半は「尊厳の為に生き方を選び、かえって自分自身を傷つけている」と感じた。
自分の意思で選んでいるはずなのに悲壮感が漂っているのだ。
おそらく彼らにとっての「恥ずかしくない家・暮らし」のイメージがあるとして、それを実現出来ないから、それくらいならば誇りを守る為にノマドを選ぶ。そのような印象を受けた。
(ただし、ボブとスワンキーは違う!この2人は非常に達観している。)
大多数のノマドは、帰れるものならば家(ホーム)に帰りたいのだ。経済的理由、または、家族とのわだかまりなど何らかの理由があり、仕方なく車をホームにしているのだ。
「困窮し、仕事の為に放浪せざるを得ない」のと、
日本の兎小屋みたいな狭い賃貸で
「保証のない短期バイトで口を糊する」のと、一体どれだけの違いがあるというのだ。
日本の独居老人の心に過(よぎ)る様々な想いも、彼らと大差ないだろうと思う。
だから「車上生活」「定住しない事」もメインテーマから除外する。
私自身は、明日からノマド生活を送れ、と言われたらすぐにも出来る自信がある。(出来るだけ最小限の装備で1〜2週間野営するのは好きだ。仕事が許せばいくらでも続けられるだろう。高規格は大嫌いだ。)
あんな大きなバンなど要らない。
2シーターでも構わないくらいだが、アメリカを想定するならば、1回の給油で500km以上は走れる車が欲しい。
シートが出来るだけフラットに近くなるならそれでいい。ダイアルはいちいち手間だからレバーが望ましい。
スペアタイヤ、ジャッキ、ブースターケーブル、牽引ロープは必需だ。
大体、自分でタイヤ交換やバッテリー交換、オイル交換程度出来ない人間は車自体を運転するな!と、割と本気で思っている。
ボロってのは汚れや凹みの話じゃない。塗装剥げを放っておいたら、そこからどんどん錆びて金属腐食するじゃないか。
食費など月に1万円あれば味、栄養、素材、共に充分まともな料理ができる。
学生時代は仕送り無し、塾講師で稼ぎながら月8万円で暮らしていた。家賃4万、食費1万、その他雑費すべてで3万だ。TVや電話は置かなかった。
同世代がバブルの恩恵で、六本木で踊りまくっていた頃だ。今みたいに100均などないから物価はかえって高かった。
だから550ドルの年金では暮らせないと言われても、あと500ドルも稼げればなんとかなると思ってしまう。
作品に登場するノマドの暮らしが過酷だとは微塵も思えないのだ。
電気は最低限でいい。
排泄?街中の日中なら、大型店などでどうとでもなる。何もない荒野なら、キジ撃ち、お花摘み、これまたどうとでもなるだろうよ。(ただし、適切な知識があれば。その地点における自然分解までの日数予測が出来るくらいであれば問題ないだろう。)
父から貰った皿、思い出の写真。
「思い出の品」は記憶を辿る鍵にはなるが、それをよすがにしていると過去に捉われる。
ヒロインよりも更に厳しい出来事によって「形に残るものすべてを失った」人がどれだけいる事か。
まぁ、これは実際に失ってみなければ、吹っ切れない事かもしれないが。
だから、皿が割れたシーンは本作の大切な要素だ。
多くのノマド生活者が「高齢者」である点は作品の肝だ。
ファーンも膝の痛みを抱えていた。
若い頃とは違う。気をつけていても身体のあちらこちらに故障が出てくる。いざという時に経済的理由で医療を受けられないのは流石に看過出来ない社会システムの大問題だ。
しかし、最も重要なメッセージは
「思い出は生き続ける」ではないだろうか。
喪失の悲しみは深い。
けれど高齢者であれば、誰しもが大きな喪失を経験しているものだ。
生々流転。
すべては移り変わっていく。
サウスダコタの累層に眠る化石たち。
はたまた、数万年前の姿を見せる星々。
この世に留まるものは一つも無い。
悠久に見える地球や宇宙も、星々の時間スケールで「生まれ、育ち、老いて、消えていく」
そして消えた星の残滓から、また新たな星が生まれていく・・・。
その大いなる変化に目を向けたなら。
世界の黄金律を感じ取ったならば。
失った大切な人を嘆く必要はないのだ。
すべては移ろいゆくのだから。
定住と流浪を比較する必要もないのだ。
土地はいったい誰のものだ?
人間が決めたに過ぎない法律で家と土地を所有したところで、拠り所の国そのものが揺らげば、頼りない小舟に乗っているのと大差ない。
その境地に達した時、ようやく旅は漂流ではなく漂泊となるのではないだろうか。
勝手な個人的解釈だが
「漂流・流浪」はいつか落ち着ける先を探しながら、それが見つからずさまようイメージ。
「漂泊」は、この大地すべてが家であり、この大空すべてが天井であり、自分が眠るすべての場所が寝床であると考えるようなイメージだと思っている。
ラスト手前のボブとファーンのやり取りこそが、ジャオ監督の描きたい本当のテーマだと感じた。ラスト20分。それまでのモヤモヤした気分を打ち砕く、素晴らしいホームランを放ってくれた。
夫と暮らした思い出の家と街を失い、漂流するファーンをカメラは追い続けた。新たな出会い、気付き、葛藤を積み重ねる中、ファーンの精神は「大自然の摂理」に晒されて、次第に純度を増していく。余計なものが流れ去り、漂泊(漂白)の境地を垣間見た時から、新たなファーンの旅が始まった。悲壮感や惨めさとはおそらくもう彼女は無縁だ。ノマドとして、笑顔で生き続ける事だろう。
ラストシーンで走り続けるファーンの胸に去来する想いは、きっとそれまでとは違うと、そう信じる。
おはようございます。
家族で、キャンプかあ・・。(遠い目・・)
子供達が幼き頃、よく行きましたね。
愉しかったなあ・・。
で、先日、大学生の息子が帰ってきた時に聞いたら
”微かにしか、覚えてないなあ・・”
”飯の炊き方や、焚火の熾し方など、一から教えただろうが!”
”覚えていない・・。あ、父さんにイロイロ厳しく指導されたのを思い出して来た・・”
ー こんなものでございます・・。ー
今晩は。
年齢的にエクストリーム登山から、サバイバル登山に移行しつつあるNOBUです。
キジ撃ち、花摘み・・(メッチェン)、サバイバル生活をした者であれば、普通に使いますよね。ケレド、何だか懐かしいなあ・・・。
もしかしたら、Pipiさんって、私と同類の方ですかね?
愛読書は、服部文祥さんの一連の戦慄する登山記か、千松信也さんか、遠藤ケイさんとか・・。
大学の寮は吉田寮とか・・。
私の最初に購入した車は、(お金がなかったので)、急こう配の山道をガンガン登って行けるエスクードでした・・。(で、会社の上司から無茶苦茶怒られました・・・。でも、ランクルってデカいし、高いし・・)
プライベートな話なので、返信不要です。では。
コメントありがとうございました😊そうなんですね、まさか放浪癖をお持ちとは。最近は、テレワークが進んで、オフィスレスだったりしますし、定住しないのも、家族がいなければ、ありっちゃありかもですね😸
pipi様
コメント&共感ありがとうございます
…知的で的を得た素晴らしきレビューをお書きになられてるpipi様に小ネタをお伝え出来て何よりです☺️
…片付け上手は生き方上手とも言われますしね!
pipiさま、毎度ありがとうございます。
ノマドじゃないけど思い出した映画が『ロング、ロング・バケーション』。
キャンピングカーもいいな~って思ってましたが、やっぱり駐車場が問題。大陸ならではの生活ですよね。
『マーダー・ドライブ』というホラーもあります(笑)
コメントありがとうございます。
「白人にだけ許された特権」は、橘玲氏の受け売りで僕の言葉ではないので詳しくは、橘玲氏のブログを御覧ください。
pipiさんがおっしゃるようにこの映画のテーマは、「資本主義・末期症状」ではなくて、固定的な家でなくても思い出とともに生き続けることができるということなのかもしれませんね。「漂泊」という言葉がファーンにぴったりです。もやもやしたものが腑に落ちました。