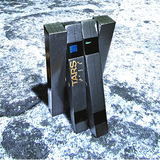アンモナイトの目覚めのレビュー・感想・評価
全68件中、21~40件目を表示
実在の二人との違いを調べるのも楽しいかも、な一作。
ケイト・ウィンスレットとシアーシャ・ローナンという、現在の映画界で最も演技力が高く評価される二人が、イギリス近代に生きた女性をどのように演じるのか、否が応でも期待が高まります。そして本作の二人は、そうした観客の期待に見事に応えています。
ウィンスレットの演技に非常に安定感があるのはもちろんですが、あまり感情を表情に表さない役柄にも関わらず、その内面がありありと伝わるような「目」の演技は、素晴らしいを通り越して凄みを感じさせます。一方のローナンもまた、『ストーリー・オブ・マイライフ』(2019)で見せた生命力溢れる人物とは対照的な、心身ともに抑圧的な状況にある女性を演じていますが、その抑圧のたがが外れた時に見せる、溌剌とした、しかし少し常軌を逸したような振る舞いへの移行を全く違和感を感じさせることなく演じています。
また本作の主要なキャラクターの多くは実在の人物なのですが、本作における主人公の立場や年齢の設定にかなり創作的な要素が含まれているとのこと。実在の人物を作品化する際に、創作的な要素はどこまで許容されるのか、論点を提示した作品でもありました。
フランシス・リー監督の『ゴッズ・オウン・カントリー』(2017)は残念ながら未見なので、これから鑑賞するのが楽しみです。
寒々としたライム・レジスの海岸
実在した化石収集家メアリー・アニング(ケイト・ウィンスレット)と裕福な化石収集家の妻シャーロット(シアーシャ・ローナン)が出逢い、関係を深めていく。
ケイト・ウィンスレットは、自然な動きが出来るよう発掘作業に取り組まれたとのこと。肉体改造もされたのでは…と想像される女優である事を封印した裸体と荒れた指、この作品に対するケイト・ウィンスレットの情熱を感じました。
透き通るような美しいシアーシャ・ローナン。クラシカルな帽子とドレスが、まるで美しい絵画のよう。
頑なな態度をとるメアリーが、シャーロットを見つめる時の柔らかな眼差し。
それを望んではいない、メアリーの悲痛な心の叫びが聞こえるようでした。
独学での功績とは…凄い。
-イクチオサウルス
映画館での鑑賞
おっさんでも胸キュン
「アンモナイトだね~あーあ、古代の化石さ~♪(プリプリのダイアモンドの節で)」と、嘉門達夫の替え唄メドレーをつい口ずさんでしまう。そんな軽い気持ちで観たのに、どうしてこうもキュンキュンさせられたんだろ。今まで見たシアーシャ・ローナンの中でベスト級だったよ。
うつ病を患っていたシャーロット。海水浴が効果的だとして、無謀な海水ダイブ。それがもとで風邪をひき、完治したときから恋心が芽生える・・・といった流れ。シャーロットの恋への決断は指輪をポケットにしまった時なのだろうか、なぜかそのシーンが印象に残った。裕福な暮らしから泥まみれと石炭まみれ。息苦しいロンドンの生活から解放されたこともあるだろう。うつ抜けから恋心・・・なんだかとても共感。
激しいベッドシーンもよかったし、サプライズの部屋もよかった。母親のこともあったし、すぐに受け入れられるわけでもない。だけど、その母親が大切にしていた動物の陶器フィギュアにも気遣うシャーロットの計らいにもキュンとなってしまった。そのフィギュアは8体あったことも、8人の子に死なれた悲しみからきたものだろう。
そんな恋愛模様以外でも、女性というだけで軽んじられていたような描写(採集者、提供者のの名前)があった。実際のメアリーは兄とともに化石採集していたようなので、兄について語られていなかったのも意味深だ。
差別へのアンチテーゼ
女性が虐げられてきた歴史を踏まえ、現在もはびこる性別や階級による差別へのアンチテーゼが主題なのだろう、と感じました。
メアリーの中には、自らが発掘したアンモナイトの化石のように、偉大な能力が埋まっている。
繊細な作業と、化石に関する深い造詣が求められる仕事だ。
なのにメアリーは、他人から評価されない。
労働者階級の女性で、学会にも入れず、論文発表すらさせてもらえない。
そして、結婚もせず子どももいないことで、この時代ゆえの「生きる価値を他人から否定され続けた人物」という設定なのが重要。
それに対する不満と怒り、恨みを胸に抱いている。
そんなメアリーは一個の人間として認められることと、自由と尊厳を何より欲し、レッテルを貼られカテゴライズされたり、誰かに囲われたりることを、心の底から拒絶しているようなキャラとして作られていました。
だから、身分も性別も超えて、文字通り裸の人間同士の愛に燃えたわけで。
それはそれとして、メアリーの恋の相手、富豪で化石収集家の妻・シャーロットを演じたシアーシャがめちゃくちゃキュート。
二人の主演女優の脱ぎっぷりがなかなか刺激的で、うっかりすると「百合ラブ・ロマンス・ポルノ」に勘違いしそう。
目のやり場に困るくらいのベッドシーンがありますが、そういう映画ではありません。
女性の愛と苦しみ
ケイト・ウィンスレットの強さ
メアリーを楽しむ
ケイト・ウィンスレットを堪能した
ケイトとともに歳を重ねたこの20数年、一本一本大切に観てきた。皺やお肉さえも愛おしい。若い人たちにはただのおばちゃんなのだろうか。
時は1840年代、イギリス南西部の海沿いの町ライム・レジスが舞台。ケイトが演じたメアリー・アニング(1799-1847)は実在した古生物学者だったのですね。
今作はメアリーのアンソロジーではなく、四十を過ぎた彼女の心の揺れを丁寧にすくい取る私的な作品。世間と距離を置く孤独な生活、表に出すことのできない性的マイノリティーの苦悩、抑えることができない恋心を繊細にとらえた。
シアーシャ・ローナンが演じたシャーロットと心を通わせる瞬間の高揚感がたまらんかった。ダークなトーンが色彩を帯び光り輝いた。
これは素晴らしい作品だった。出ずっぱりのケイトを堪能した。『愛を読むひと』のような衝撃はないにしろ、じんわりしっかり沁み入る秀作でありました。
女性解放はひそやかにはじまっていた
映画「燃ゆる女の肖像」を鑑賞した人は、本作品の印象がとても似ていると思うだろう。当方もそう思った。いずれも海辺の寂れた場所が舞台なのでますますそう思える。どこが違うのか。その相違点に本作品の価値があると思う。
まず場所と時代が異なる。「燃ゆる~」は18世紀フランスのブルターニュ地方の孤島であり、本作品は19世紀イギリスのブリテン島南岸の町ライム・リージスである。ちなみにライム・リージスから南下したところにガーンジー島があって、映画「ガーンジー島の読書会の秘密」の舞台となった。これも女性が主人公の映画である。そしてガーンジー島の南西にブルターニュ地方がある。19世紀イギリスは産業革命によって封建主義が崩壊しようとしている時代だったと思う。シャーロットが封建主義的な夫に反発するのは、女性の精神に封建主義が根付かなくなったことの現れである。
本作品は男性監督のフランシス・リーで「燃ゆる~」は女性監督のセリーヌ・シアマである。ほとんどのシーンで監督の性別は無関係だったが、レズビアンの性描写のシーンでは男性監督と女性監督の差が出てしまった。本作品の性描写は直接的すぎてちっともレズビアンらしくない。「燃ゆる~」のセリーヌ・シアマ監督によるセックスシーンの方が数段上だった。
名女優ケイト・ウィンスレットが演じた本作品の主人公メアリー・アニングは、著名な化石収集家である。実在した人物をレズビアンだったとする作品が堂々と公開されたことにはある種の感慨がある。そういう時代になったのだ。
本作品のメアリーは、シャーロットと出会う前から自分がレズビアンであることを知っていた。その相手はフィオナ・ショウが演じたエリザベスである。登場シーンから乳を揺らしていて、なんだか妙に色っぽいおばあちゃんだと思って推測したのだが、多分間違っていないと思う。
レズビアンという秘密を押し隠して、ひたすら化石集めをして細々と生活してきたメアリーだが、シャーロットに出逢ってレズビアンの欲望が疼き出す。感情を表に出さないけれども、視線はシャーロットを追っている。そのあたりのケイト・ウィンスレットの演技が見事だ。
女であることで本を出版することが出来ず、地位も安定した生活も得られないことに甘んじているメアリーは、女性の地位向上についてのシャーロットの進んだ考えを垣間見て驚く。しかし知的な女性らしく驚きを見せないところがいい。音楽会で最後列に座るメアリーと最前列に座るシャーロットの位置が、そのまま二人の関係性となっている。
18世紀末に生まれたメアリーと19世紀生まれのシャーロット。自由な女性、解放された女性としての自分を自覚しているかのようなシャーロットだが、自分の考えに他人を当てはめてしまうのが悪い癖だ。メアリーから、あなたは私のことを何も分かっていないと言われるのも当然である。
本作品には女性解放やジェンダーフリーや封建主義的な精神からの脱却など、多くのテーマが詰め込まれている。しかしそうとは悟らせないように静かにシーンを重ねる手法が面白い。原題は「Ammonite」で邦題は「アンモナイトの目覚め」だ。久しぶりに見る優れた邦題である。19世紀のイギリス。女性解放はひそやかにはじまっていたのだ。
欲求不満
良質な恋愛映画です。
同じテイストの作品「燃ゆる女の肖像」に
大変感銘を受けた僕は本作を観ようかどうしようか?
迷ってました。
比較しちゃうからです。きっと相対的に観ちゃう、、、よくないのですが。
結局・・・観ました。
まず、作品公式HPの「STORY」ページ
・・・内容書きすぎじゃないですかね?
笑っちゃうほど、全部書いてあります。いいの?これ。
というか、配給会社さんのセンスが無いのか?
それとも「ストーリーが見どころじゃ無いんだぜ!」
っていう自信の現れなのでしょうか?
ただ、観賞後読んだらエリザベスの立ち位置が
ようやく理解できました、あぁスッキリ。
エリザベスとメアリーの関係性を知った上で
鑑賞することをお勧めします。
ストーリーは恋愛映画ですね。紛れもない。
それの比重がとっても大きな作品ですね。
アンモナイトなどの化石の発掘作業と奥底に
沈めた自分の心を解き放つことを
うまく対比させた作品だなぁって思います。
キーとなる行動やイベントにうまく使われています。
今回はなんというんでしょうね。
ちょっとメンタル弱めの承認欲求の塊
(かまってちゃん)女性との出会いだったからですね。
もし違うタイプだったら、何も始まらなかったのでは無いでしょうかね?
看病がきっかけでーなんてところも、
アオハル小説かよ!って感じで。
そういう点を考えても、うーん、恋愛映画の
1つのパターンだよなぁと。
また、物語の終わり方も、なんとも恋愛映画然としていますよね。
よくある話だよなぁって。仕事にプライド持ってる人間が相手だと、あるよなぁって。
あとなぁ、そんなにいる?この情事のシーン。
ここまで描写・・・必要かなぁ?
何か意味があるならまだしも、あんな具体的な動き
必要かなぁ?ただ、そういう関係になりました。
今回はいつもより濃厚なんですってのが
わかればよかったんじゃ?妙な違和感。
誰得のシーンなんだろ?
監督が観たかっただけ?(笑)
やはり比べてしまいます。「燃ゆる〜」と。
あの情熱、狂おしい気持ち、メラメラ燃え始める気持ち、描く人、描かれる人・・・この立ち位置が副次的に物語を膨らませ美しく描いていく。。
あの、物語、映像作品としての豊かさを感じることはできませんでした。
良質な恋愛映画ですし、演者さんたちも見事でした。でも、それだけでした。
蛇足ですが、メアリー・アニングさんって実在していた方なんですね。
親族の方々はこの内容にOK出しているのかなぁ?
独特の雰囲気、、、2人の瞳が素晴らしい
余韻を残し、観る側にこれからを想像させる幕の引き方、、、
セリフは少ないけれど、少ないからこそ伝わってくる2人のなんとも言えない演技!
素晴らしいですね〜。
病弱なシャーロットが、メアリーの介抱を受け、顔色も良く微笑める健康を取り戻し、美しくなってゆく、、、無愛想ながらも、彼女を優しく看護しながら彼女もまた人の体温を感じてゆくのかな。
シャーロットがこれまでの悲しみを、吐き出すように泣き崩れ、しがみつくようにメアリーに頼るあたりから、2人の距離が縮まった感じ、、、そしてとても美しい性の描写、、、
ろうそく火が、頼りなさそうに見えながらも、実はチロチロと消えずに燃えてゆく感じ。
シアーシャの瞳が、気品とあどけなさを残す感じで、とても綺麗でした。
ケイト、ウィンスレットは、もう手の指先まで自立する女で、これまた美しかった!!
アンモナイト
メアリーが生涯独身を貫いたのも、一度だけ島を離れてロンドンに行ったのも…シャーロットがその後も地質学の世界に残り続けたのも…男社会で性別のせいで不遇な態度を受けたメアリーのためだったのかなとか……考えてめちゃくちゃ愛だって思った….ゴッズオウンカントリーでも感じたけど、すごい当たり前なのに性別だとか地位とかで難しく考えられて……でも普通のありふれた関係を描いてるんだなって…
【"互いに磨き合った、収集癖のある二人" 孤独感を抱える二人の女性が徐々に惹かれて行く様を、静謐なトーンで美しく描いた作品。】
- メアリー・アニング。イギリス南西部の海辺の町ライムに生まれ、13歳でイクシオ・サウルスの全身化石を発掘。
だが、労働者階級の彼女の業績は当時、正当な評価を得る事はなかった・・。-
■感想
・シャーロット(シアーシャ・ローニャン)が、鬱病になったのは、夫の浮気が原因ではなかったのではないか?もしくは、良家の妻としての抑圧か?
- シャーロットが、メアリー(ケイト・ウィンスレット)の家で療養中に高熱に魘されながら、口走った言葉"私は女なんか見なかった・・”から、類推。-
・メアリーの秘めた性癖も、後半明らかになり。
- シャーロットの為に軟膏を貰いに行った中年女性に”家に寄っていかない?”と声をかけられたり、後半、彼女から、掛けられた言葉。-
・メアリーとシャーロットがそれまでの抑圧から解放されたかのような、激しくも美しき性愛シーン。
- 猥雑感皆無の美しいシーンであると思う。二人の女優の美しき裸身が絡み合う様・・。-
・シャーロットにロンドンに招かれたメアリーが、シャーロットが意図的ではないにしろ、"自分を収集しようとしている・・"と気付いた時のメアリーの嫌悪の表情。
- 同族嫌悪とまでは言わないが・・。それで、二人は惹かれ合ったのかもしれない、と勝手に推測する。-
<似た者同士のメアリーとシャーロットが、大英博物館の化石を展示しているショーケースを挟んでシンメトリックな画面構成の中、対峙するシーンも、二人の関係性の変化を表すようで、今作を鮮やかで印象的な作品にしている。>
傑作
友情の話と思っていたら苦手な展開だった
シアーシャ・ローナンが出演しているので鑑賞
一方で主人公のケイト・ウィンスレットはタイタニックのころからやや苦手な俳優
スタートしてすぐに大英博物館に大型鳥類の化石が収蔵されるシーンから。元々のタグには発掘者として主人公の名前が記載されているが、博物館のスタッフにより差し替えられてしまう。
18世紀のイギリスの田舎町。海岸の近くで泥にまみれながら、時には滑落の危険もあるがけによじ登り化石を含む岩石を集める男勝りの主人公。
まだ女性の地位が低く、研究者として認められることもなく、亡き父が営んでいた化石の収集店を引継ぎ、時々やってくる収集家向けに大型化石の発掘とクリーニング、観光客向けには小さな化石を組み合わせたアクセサリー等をつくりながら老いた母と細々と暮らしている。
このお母さんがまた過去がありそうで、気難しく、娘には辛くあたり、さらに何故か8体の動物のフィギュアを入念に磨き続けている。
そんな時に、ロンドンからやってきた収集家から気鬱気味の妻を数週間預かって欲しいとの申し出。なんとも面倒な話なのだが、高額な報酬を提示され嫌々引き受けることとなる。
あまり前情報を入れずに映画を見たいたちで、鑑賞前は女性同士の友情の物語と思っていたのだが、結果的には「燃ゆる女の肖像」と同じく女性同士の秘めた恋愛の物語であった。
正直苦手である(なら観るな、というところだが、気づくのが物語の中盤となるパターン)。
純粋な感想でいくと、なぜ主人公と預かった妻が恋に落ちたのか、(実在の人物をモデルにしているから説明は不要というパターンなのかもしれないが、)結構唐突に、しかもすごく深い女性同士の恋愛に展開した理由が理解しにくかった。
これはお互いに男性優位社会に不満や横圧されている者同士が、妻の夫が不在となったことで開放されたから?とも考えられるが、だからといってそこから同性間で肉体関係を持つほどまで展開するのか?と感じた。
さらに映画のシーン作りだが、関係を持つシーンが結構ハードな描写となっていることにも疑問を感じる。
お互いに知名度の高い女優同士のそのようなシーンを入れれば、どんなに講釈を垂れてみても、どうしても興味本位に扱われるだけだと思われる。そこまでのリスクを承知の上であのような脚本としたのは何故なのか?と感じた。
預かった妻は夫から呼び戻され、主人公の母は突然亡くなってしまう。
葬儀の後、妻からの手紙を受け取り、離ればなれになった二人が、立場を代えてロンドンで再会するが、主人公は妻の申し出を拒み、一人大英博物館に向かう。
そこでかつて自分が発掘した化石の展示ケースを見つけ、中を見ている時に、ケースの向かいに妻がやってくる。対峙する二人。そこで映画は終了。
なぜ主人公は妻の申し出を拒んだのか。主人公は男社会の理不尽さ、トラウマを持つ母からの拘束、人間関係が濃密で精神的な自由を得られない田舎暮らし、それらからひと時逃れる対象としての妻との恋であったことに気がつき、妻からの申し出は再び異なる形での束縛に過ぎずそこからは自由でいたかった、という解釈をした。
ただそうであれば、いずれ時間があれば友情という形で解決できるかもしれない。ラストシーンはその余地を残したということかもしれない。
世界には男性と女性しかいないのに、なぜか女性には不遇な社会が続き、もう一方の当事者である男性は本質的な問題に気づかない、気づく能力が無いということなのだろう。
全68件中、21~40件目を表示