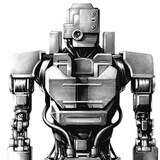劇場版 アーヤと魔女のレビュー・感想・評価
全38件中、21~38件目を表示
この映画を劇場公開する意味がわからない
NHKで放映した作品をそのままお金を取って公開する意味がわからない。
TVで見たときは、CG作品であることや、道徳的に問題のあるキャラ設定などを差しひいても、作品自体は面白く見ることができました。TVで見たときラストシーンで、主人公の母親と幼なじみのカスタードが登場したところで物語が終わったので、「なるほど、この続きを劇場で公開するんだ」と思い込み、楽しみにして劇場で鑑賞しましたが、ストーリーはNHKと同じ、というかNHKで放映したものがそのままスクリーンで上映されただけでした。壮大な情景描写や派手なアクションシーンがあるのならともかく、ほとんど家の中のシーンの連続なので、あえて大スクリーンで見る価値のある映像はありません。お金を返してほしいです。
テレビシリーズの導入部をまとめたような作品
アーヤが小賢しいヒロインで、まわりを手玉に取るところが楽しいところだとしたら、最後の方はそのあたりがまったく描かれなく、突然半年こになったので少し戸惑いました。
ストーリーを楽しむとしても、オープニングで張られた伏線はあまり回収されず、魔女12人の掟とかなに?って、questionマークが頭の中でいっぱい出てしまいました。
とりあえず人によって面白い面白くないは、あると思うので、わたしにとっては面白くない映画でした。
あっ、トヨエツさんはすごく良かったです!!
ジブリの駄作
あまりの駄作。
・出だしの会話が大根(最初から不安を感じる)
・終わりが唐突すぎる。
・12人の魔女の役割ってなんなんでしょうか。。
・男性の魔法使いが小説を書く意味や必然性がわからない。
・主人公がろくな魔法をつかっていない。
・伏線を回収するようなストーリー展開になっていない。(映画づくりが下手。。。。)
・ただ3Dで作っただけ。。。3Dの良さがいかされていない。
・主人公の女の子の適当な名前。。「あやつる」??
・主人公の女の子が小賢しいだけで魅力がない。
・メッセージ性がまったく感じられませんでした。
ジブリしっかりしてください!!
こき使われるシーンがクドい
この映画はテレビで先行放送されたみたいですが
私は完全に初見でした
ストーリーのはじまりは魔女の子どもが
他の12人の魔女に追いかけられて
それに巻き込まれないように
孤児院に子どもを置いていった
そのときに名前は「アヤツル」だったのだが
孤児院の園長先生がその名前はよくないと思い
「アーヤ・ツール」に改名したところから物語が始まる
しかし、12人の魔女の話は
まったく本筋とは関係ない
そして、ベラという魔女とマンドレークという長身の男の家で
暮らすことになり
アーヤはベラから魔法を習いたいと申し出るが
まったく相手にされず、こき使われてばかりなので
黒猫の使い魔のトーマスといっしょに
魔法を盗み見てぎゃふんと言わせる作戦を開始した
この出来事がきっかけで
アーヤはこの家で自分の思うような生活をできることになった
アーヤは他人をおだてたりして
動かし自分のやりたいことをするというヒロインという
印象があるがこき使われるシーンが長い気がするので
あまり爽快感が足りなかったような気がする
この映画はアーヤがこき使われるところと
ベラに仕返しをするために
魔法を使うことで大半の時間を使っているし
ほぼ三人と一匹だけ(マンドレークの使い魔もいるが)で
ストーリーの大部分が構成されている
だから、外にでて冒険をするということを期待するとつまらなく感じるように思う
個人的にはエンドロールにあったイラストの出来事を
映像にしたものを見たいなと思ったので
不完全燃焼な感じである
【アーヤ・ツールさんに見事に操られた作品 ”私のどこが、ダメですか?””いやいや、貴女は魅力的な女の子で、ダメじゃないけれどね・・”】
ー 孤児院で育ったアーヤは、魔法使いの太った女ベラと長身痩躯の男で作家のマンドレークに引き取られるが・・。彼女を待っていたのは、過酷な日々だった。ー
◆感想
・アーヤは、魔法使いの太った女ベラの下働きをさせられながらも、明るさを失わず、逆に自分を守るためのクスリを作るシーンは、オモシロイ。
怪しい調合場の描き方も、ナカナカである。
・但し、アーヤ・ツールに簡単に手名付けられたベラとマンドレークの”良い人達への”豹変ぶりと、過去のアーヤの母親との関係性が、アッサリと描かれる辺りは、非常に物語が薄く、軽い。
<過去の数々の名作と比較する気は毛頭ないが、幼い子供達だけでなく万民が
”夢中で何度もこの映画を見返すかなあ・・、”
と思いながら映画館を後にした作品。>
原作にかなり忠実。
宮崎駿が面白いと言っていたように、本当に余計なこと考えずにただ単純に面白かった。面白〜これからどんどんどうなるの〜とどっぷりハマっていたら突然終わった!という体感。なのでパンフレットや原作即買って読んだけど、なるほど、かなり原作に忠実なんだな。魔女の家の中が面白いし、アーヤの人たらしぶりは見応えあるし、アーヤのお母さん(なぜカタコト?)や過去のことには謎が残るけど、宮崎吾郎監督が肩の力抜いて好きに作ったというのには納得できる、楽しい映画でした。
ア・ヤ・ツ・ル・・・序章??
未だ赤ちゃんの頃「子どもの家」の玄関に置き去りにされた物事を斜に見る利発な少女アーヤが、魔女のベラ・ヤーガ、共に暮らす気難しい男マンドレーク、黒猫のトーマスらが暮らす家に引き取られ…。
CG作品ではあるが、細部迄描かれた映像は色彩も鮮やかで、個性豊かなキャラクター達も楽しめる。
大人達の愛おしさ故の言葉や振る舞いが、「アヤツル」の結果ではない事を、アーヤは学んでいくのでしょうか。
声優の皆さんのお名前をエンドロールで初めて知り、「ほぉ〜」でした。
この作品、「序章」なのでしょうか…???
NHKを録画にて鑑賞
きつい言葉 恥さらし
ジブリ映画の歴史で二流の役者を使いだしたおもひでぽろぽろ(1991)あたりから、二流の俳優によるラインの読み方に違和感を覚え、見るのに絶えない代物になっていく。
何故プロの声優を使わないのかは、ネームバリューだけで目先の利益追求だけを考えるのは仕方がないけれどもこの映画に関してはひどすぎる。
酷いことをする宮崎吾朗という方は才能は父から継承はしなかったようで先に今や国営放送局となったテレビ局で先に流し、映画館で上映する羞恥心のかけらもないらしい。
ただ、この映画.comのレビュアーの中にも自分のレビューに共感した!を自分自身でつける羞恥心のかけらもない御仁がいるのは、このコロナ禍でするようなことではない気がするけど、人の道を外すのはちょっとしたくだらないことから始まるのは世の常なのかもしれない。
アーヤはたくましい! 好ましくない人間関係を自分のプラスにする方法(長いです。ご容赦!)
今回は、CGになっていましたが、内容はジブリ! 「あやつる」は、赤ちゃんの時から、周りの人をあやつっているみたい(赤ちゃんのアーヤのあの笑顔は要注意)。 他のアニメとは質の違う作品ですね。
「あの子たちはお人形さんなんかじゃあないわ、生きてるのよ!。眺めて楽しむもんじゃないわ」
子供たちは大人のオモチャや所有物ではありません。生きて意志があり自己主張する、わがままな存在!
このアニメでは、あやつるのは、大人ではなく、子供! 園長先生も園の料理長も、ヤーガもマンドレイクもアーヤは操る。アーヤに象徴される子供は、あやつる魔女そのもの!
「あやつる」その仕方も、相手の意志や願望、欲求を無視して強制するものではなく、言葉や行動を巧みに利用して、相手の望み、才能、欲求を実現させ、自分との関係を良好なものにして、今度は逆に自分の望みを叶えてもらう、というもののようです。
と、このように、アニメの細部や内容について、いくらでも語ることができるすごい作品!
遅れてきましたが、素敵なクリスマスプレゼントでした!
●原作との違い(原作者は、ダイアナ・ウィン・ジョーンズ)
原作にないシーン
1.出だしのパイクと車の追いかけっこ(アーヤのお母さんの登場)。日本語版の絵には、赤ちゃんをホウキに乗せて飛んでいる魔女が、12人のマジに追われて逃げている挿絵が描かれている。
2.子供の家にアーヤを連れて行くところと、最後に迎えに行くところ(アーヤのお母さんの登場)
3.初めの方で出てきた、幽霊パーティとそれを目撃したおじいさん(ご近所のジェンキンスさん)の話
4.アーヤとカスタードが子供の家で本を読んでいるシーン。アーヤはコナン・ドイルの『バスカヴィル家の犬』、カスタードはR.A.ハインラインの『レッド・プラネット』。
5.EARWIGというロックグループとその音楽(アーヤのお母さんの登場)
6.アーヤがシトロエン内にラジカセを見つけるところとそのラジカセでテープを聞くところ
7. ヤーガが「りっぱな」人たちから電話で注文(自分の孫を主役にするため、他人の子供をバレエの発表会で主役から下ろす呪文)を受け、その人たちについて発言するシーン「まったく、どいつもこいつも」
8. マンドレークがEARWIGという音楽を演奏するシーン
9.マンドレークが作家であり、作品(小説?)を書いていて、アーヤがどうやら手助けしている様子
最後のエンドロールに、マンドレークとヤーガ、カスタードとの海水浴シーンなどの後日談が描かれている。
●考えてみました。
原作にないシーンを見てみると、アーヤのお母さんに関わるところと、EARWIGの音楽に関連するところ、マンドレークの作家の部分が付け加わっています。また、アーヤとカスタードが本を読むシーンも追加されています。それぞれアーヤはコナン・ドイル、カスタードは、R.A.ハインラインを読んでいます。アーヤは、エンドロールでも、コナン・ドイルの『恐怖の谷』を読んでいて、推理小説の話も、アニメ中でしています。カスタードは、初めの方で、施設の棟に上がる時、火星人の話でハインラインの名前を出しています。
音楽と本について、ジブリアニメは原作にないシーンを描き込んでいて、何かの意味を持たせているようです。
子供の家にいたアーヤは、幽霊パーティの夜、塔の屋上に登り、「どこもかしこもピッカピカ。窓も大きくて日当たり抜群。それに、おじさんのシェパーズパイは最高!」と言いますが、その台詞は、アニメでは、アーヤの母のセリフとほとんど同じです。アーヤは実際にその中にいて感じたことを言っているわけですが、母親はまるでその子供の家に以前いたことがあるように同じセリフを、赤ちゃんだったアーヤに話します。アニメでは、母もこの家にいたのでしょうか。
アーヤの才能は魔女のものでしょうか。人の欲しているものやことを巧みに実現させ、自分との関係を良好なものにして、今度は自分の希望を叶えてもらっています。アーヤにとって、ヤーガとマンドレーク、デーモンたちは操る相手としてはやりがいのある相手なのかもしれません。アーヤは、家庭に入るのは退屈で嫌だと、施設の塔の上で言っていました。施設にいるとたくさんの人を操ることができますが(しかし、それは本人が希望することをアーヤが実現させてくれるからでしょう)、家庭ではせいぜい二、三人だからです。しかし、ヤーガたちは、どうやら簡単には操ることができないようです。これはアーヤにとり、やる気をそそる状況のようです。なんとも頼もしい子供です。
ヤーガは、大声を出したり、脅して怖いことを言ってアーヤに言うことを聞かせようとしますが、アーヤは、ことあるごとにヤーガに話しかけ、操るきっかけを探っているようです(情報収集!)。アーヤの行動は、相手の行動を観察したり、周りにあるものを観察して利用できそうなものを探っています。このことから分かることは、「アヤツル」とは、決してその人の意志を無視して強制や命令で実現させることはなく、言葉(「大好き!」)や行動(抱きついたり、笑顔を作ったり)を巧みに操作して、相手の意志や才能、希望を実現させて、自分との関係を良好なものにして、逆に自分の望みを叶えていくことではないでしょうか。アニメ中では、ヤーガはアーヤに、あれをしろ、これをしろ、と命令していましたが、エンドロールの絵では、アーヤの望み(魔法を教え、海に一緒にいくなど)を叶えてくれる存在に変化しています。
ヤーガはアーヤに仕事を命令してやらせますが、アーヤは魔法を教えてもらうために我慢して従います。しかし、教えてもらえないと分かると、今度は反撃に出ます。反撃の印は、EARWIGという音楽に象徴されているようです。この音楽がなると、その後アーヤの反撃が始まるようです。そういえば、このアニメの一番初めに、アーヤの母親が魔女たちからバイクに乗って逃げるシーンでは、EARWIGを歌っていました。魔女の掟から逃れ、自分の好きなように生きる、そのための脱出中に、この音楽が使われています。
魔女のヤーガが作っていた呪文は、いわゆる「ごりっぱな」大人、「地球の友」や「母の会」のお偉方のためのようです。その注文は、自分の愛犬がドッグショーで優勝できるものや、主役の子供を引き摺り下ろし、自分の孫がバレエの発表会で主役になれる、というもの、つまり、ずる、といわれるものでした。原作では、その呪文の内容までは書かれていませんでしたが、このアニメでは、具体的な内容まで表現され、これまでのジブリアニメ(『コクリコ坂』や『ポニョ』など)に見られるロクでもない大人批判がはっきり現れています。
なんだこれは本当に
時間を返して欲しい。ストーリーに一貫性がなくなにを伝えたいのか全くわからない。原作を読まないといけないのか悩んだ。本当になにを伝えたいのか、制作スタッフと膝を突き合わせて是非聞いてみたい。
どうしてこうなってしまったのか
スタジオジブリの2020年最後のTV放送作品。
宮崎吾郎の時点で、個人的には悪い予感しかしていなかったのだが、その予感は結局当たってしまった。
予算の都合があるのかもしれないが、
・前半のシーンは余りにも無駄な箇所が多い
・後半の盛り上がりから話がイキナリ飛ぶ
・ラストシーンが意味不明
結局、視聴者が気持ち良くなるシーンが少なく、
見ていても何も嬉しくならない。
アーヤが愛されるようなヒロインには描かれず、ただただ小賢しい小娘にしか見えない。
映画的には起承転結の内、
キショ…ツ
のような展開になってしまっているので、
これからって所で話が飛んで終わる。
あとはエンディングの曲に合わせて静止画で見せるから想像してね。で終わらせている。
90分の映画なのに、45分くらいまでの展開しかないので、何も得られずに終わる。調査兵団もビックリである。
あとは、アーヤの母親の声があまりにも酷くて笑ってしまうほど。せめて歌と会話は別人で良かったのでは…。
個人的に求めていた展開としては、
1.アーヤが子供院から引き取られる
2.アーヤと魔女がもめ、色々ある
3.マンドレークキレる(本作の本筋終わり)
4.擬似家族として仲良くなる(エンディングの静止画)
5.クリスマスにバンド演奏をしようと計画する
6.母親が迎えに来て、アーヤを連れて行こうとする
7.アーヤ、擬似家族ともめて、本物の母親に連れて行かれるが…
8.最終的に擬似家族を選ぶ。バンドの演奏を行ってハッピーエンド。
みたいなのを求めていました。
何故こんなことになってしまったのか……。
昔からのジブリファンとしては悲しみすら感じました。
原作に合わせた結果だとしたら、映像脚本として原作のcmだけしてろって話だろう。
スタジオジブリの作品としてではなく、一つの作品として、
完成したものからは明らかに欠けてしまっている。
ジブリは、才能を見抜く目すら濁ってしまったのだろうか……。
予算や製作期間の都合があったのだろうか……。
宮崎吾郎氏には、もう何度も裏切られたので、
吾郎氏の作品は見ることはないでしょう。
宮崎駿氏が生きている間に、現在製作中の僕たちはどう生きるのか、を作り上げて欲しい。
間違っても駿氏が亡くなって、残りを吾郎氏が作る……なんて事になったら、きっと何かを通り越して怒りに包まれるかも知れない。
魔法(ジブリ)の再奏
スタジオジブリ最新作は異例尽くし。
同スタジオ初となるフル3DCG。
劇場公開ではなく、昨年12月30日にNHK総合で放送されたTV作品。
2014年に製作部門が一旦休止し、2017年に再開。作品としては2014年の『思い出のマーニー』以来。
そう長くはないブランクとは言え映画製作の休止、髙畑勲の死、『千と千尋の神隠し』の記録抜かれ…色々あったジブリだが、何はともあれまた新作が見れる事は素直に嬉しい。
監督は宮崎吾朗。
原作は父・駿が監督した『ハウルの動く城』と同じダイアナ・ウィン・ジョーンズのファンタジー小説。
『ハウル~』は戦争や文明社会へのメッセージ、ラブストーリー要素があり、どちらかと言うとちと大人色だったが、本作は純粋な子供向け魔法ファンタジー。
1990年代のイギリス。赤ん坊の頃から孤児院で暮らす少女、アヤツル。通称、アーヤ。
ある日、ヘンテコな男女に引き取られる。何と、二人は魔法使いと魔女!
いつか魔法を教えてくれる事を約束に目を輝かせて働くが、こき使われる毎日…。
誰の言いなりにもならない! アーヤの反撃開始!
孤児院暮らしとか、引き取られとか、勝手に魔法薬の調合とか、話的にはあるある。魔法ファンタジー物の寄せ集め感は否めず、新味は無い。
でも、愉快なのはアーヤのキャラ。
とにかく、活発、おマセ、少々生意気。そこにジブリヒロインらしいポジティブさ。もうお察し下さい。
そうでないとこの家ではやっていけない。やられたらやり返せ!
魔女のベラ。画に描いたような意地悪魔女。怖い顔の恰幅のいい体型で、ガミガミガミガミ、あれこれうるさい事しか言わない。
意地悪魔女vs活発小生意気少女!
ベラには時折イラッとさせられるが、そんな彼女が唯一恐れているものがある。
一緒に暮らしているマンドレーク。一見顔色悪く、無口、痩型ののっぽで、ベラの尻に敷かれている感じもするが、ベラが常々気を遣うほど怒らせると怖い。いつも不機嫌そうな顔で、口癖は「私を煩わせるな!」。
でもこのキャラが、意地悪魔女vs活発小生意気少女にいいスパイスとなっている。
魔法の世界なので、使い魔的な動物キャラも勿論。ジジのような黒猫のトーマス。性格、臆病で少々図々しい所あり。
アーヤはオーディションで選ばれた新鋭・平澤宏々路が射止め、ベラ=寺島しのぶ、マンドレーク=豊川悦司、トーマス=濱田岳が“声”達者ぶりを聴かせる。
トータル的には…
話はあるある。
キャラは悪くない。
CGクオリティーもそう悪くない。
つまらなくはなく、普通に楽しめる。
だけどこれはTV作品だから良かった。劇場作品だったら…。
話の展開も中途半端。思わず、「えっ、ここで? これで終わり?」と思ってしまった。
ベラとマンドレーク、そして赤毛の魔女のロックバンド“EARWIG”。
その赤毛の魔女とアーヤの関係性もすぐ分かる。
と言う事はつまり、アーヤも…。
びっくりなのは、メインビジュアルのアーヤがマイクを持って歌っているようなシーンが作中ナシ。
何か切り出すと、肩透かし点も…。
本作を起点にしてTVシリーズを作るのか、
今冬に続編作るのか、
今度は従来通り大スクリーンに魔法をかけるのか。
(それとも単発か…?)
本作の動向も気になるが、ジブリの再奏にも期待したい。
ジブリ初の長編3DCGアニメ
●映画館にて
えらく酷評がありますが、テレビのから追加されたシーンもあり、宮崎駿さんは今回褒めていたという記事を見てやはり見に行ってみました。
うん、テレビで見た時の感想と変わらないですね。
涙を見せない、心の強い女の子は、ジブリっぽくて好きかな。このめげなささは本当にすごいし見習いたいくらい。追加されたシーンはなんとなくこれかなというくらいであまりわからなかった。
確かに母親の台詞回しは気になるかな。でも歌声はカッコいい。
●テレビで拝聴。
最初は絵にびっくりして、あまりジブリっぽい感じはしなかったけど、見ているうちにジブリっぽい感じはしてきました。
孤児院に捨てられて育ったアーヤは、意地悪な魔女たちに引き取られる。自分の子供ではなくあくまでも下働きということだったが、その何にでも前向きでめげずに挑んでいく姿はとてもいいなあと思った。
いい子とずる賢さをあわせ持つが、生きていく上で仕方のないことだと思う。
手伝いばかりさせられていっこうに魔法を教えてくれないベラに、わかっていながら料理を失敗したり、悪戯したり、かと思えば褒めて甘えて見たり懐柔するうちに、ベラもマンドレークもだんだん優しさを見せてくるところはなかなかやってくれるなーというところ。
なぜ母親が逃げていたのか、ラストシーンの続きも気になるところで、一瞬つづくんだっけ?と思ってしまいました。
原作が遺作で半端なのですね…。
まるでシリーズ作品のプリクエル。 一本の長編作品としてはどうだろう…?
意地悪な魔女に引き取られた孤児、アーヤの奮闘を描いたファンタジー・アニメ。
アーヤと共に暮らす謎の男、マンドレークの声を演じるのは『フラガール』『20世紀少年』シリーズの豊川悦司。
喋る黒猫、トーマスの声を演じるのは『永遠の0』『マスカレード・ホテル』の濱田岳。
企画には『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』の、アニメ界のレジェンド宮崎駿がクレジットされている。
2020年、テレビ用長編アニメーションとして制作されたスタジオジブリ最新作。
ジブリにとって初の3DCGアニメーション作品であり、尚且つ2017年の制作部門再開以降、初の長編作品でもある。
監督は宮崎吾朗。
常に父親と比較されてきた彼だが、本作では3DCGに挑戦しており、過去2作に比べると宮崎駿っぽさは薄い。
宮崎駿の呪縛から逃れる術としてCGを使用したのだとすれば、その目論見は成功していると思う。
宮崎駿と同じ様に手書きアニメに拘っていたら、いつまで経っても父親の劣化コピーに留まってしまうことになるだろうし。
3DCGのクオリティはまあまあ。
国内アニメとしては良い出来と言えるけど、ディズニーやピクサーと比べてしまうと物足りない。予算が違いすぎるから比べるのは可哀想だけど😥
とはいえ、宮崎駿・吾朗親子を支え続けるベテラン、近藤勝也のデザインしたキャラクターは魅力的。
特にアーヤのコロコロと変わる表情はとても可愛らしく、他のジブリヒロインと比べても引けを取らないチャームがあると思う。
表情の豊かさは歴代ジブリキャラの中でもNo.1!
映画のルックは悪くない。…のだが、面白いかと言われると…。
決してつまらなくはなかったし、『ゲド戦記』の頃と比べると宮崎吾朗監督も立派になったなぁ、と思ったが、長編アニメーションとして作る話か、コレ?
アーヤの出自や魔女たちの過去、赤毛の魔女の正体など大事な伏線が全て無視されて物語が終わる。12人の魔女って一体?
まるでシリーズ作品のプリクエルか、テレビアニメの第1話〜3話を纏めた物の様。
魔女たちは昔ロックスターだったという設定は面白い。流石ロックとファンタジーの国、イギリス!
なんだけど、この設定もいまいち活きてこない。
例えばクライマックスでアーヤをボーカルにしてギグをぶちかますとか、そういうエモくて盛り上がる展開をいくらでも用意出来ただろうに…。
アニメでは淡々とアーヤの雑用が描かれる。アーヤが魔女ベラ・ヤーガにいびられながら雑用をこなす。本当にこれだけ。序破急の「序」、起承転結の「起」が延々と続く。
魔法を使った冒険とか、彼女の成長とかが観たかったのに!
アーヤが勝手に魔法を使うシーンがあるんだから、彼女の魔法が暴走してトラブルを巻き起こすとか、なんかもっと山場が欲しかった。ずっと平場の映画なんだもんなー。
アーヤの性格は面白いと思う。『魔女の宅急便』や『千と千尋の神隠し』の様に仕事を頑張る女の子として描かれるが、アーヤはどこまでも自分本位。どうすれば周りの人間を操ることが出来るのかばかり考えている腹黒少女。
今までのジブリでは絶対に居なかった、新たなるヒロイン像を作り上げたことは評価できる!…んだけど、この性格ももっと掘り下げられたと思う。
自分勝手な性格が災いしてとんでもないトラブルに巻き込まれる、とかお話をもっと膨らませられるのに!
せっかく面白いキャラクターなのに、それを活かしきれていなくて勿体ない!
あまりにも中途半端な物語のため、シリーズ化を狙ってるのか?と思っていたのだが、どうやら原作からして既に尻切れトンボな作品らしい。
というのも、本作の原作小説は『ハウルの動く城』の原作者であるダイアナ・ウィン・ジョーンズの遺作。
ジョーンズは病床の中本作の執筆を続けていたが、志半ばで他界してしまう。
やむを得ない事情から、不完全な物語になってしまった訳です。
そういう事情なので、原作が不完全なのはわかる。
でも、映像化するにあたり脚本家が手を加えて補強することは出来たはず。
そうすればこんな未完成な作品にならなかったと思う。
ギャグやキャラクターは面白いので、割と楽しい作品ではある。でも、やっぱり脚本が勿体無い。
ここから後の物語を、オリジナル・ストーリーとして描いていくことでシリーズ化するのであれば、その第1作としての価値は十分にあると思うが、そうでなければちょっと失敗作なんじゃ…💦
もしかして物語の作り方を知らない?
どうもハラハラです、今回は「アーヤと魔女」をレビューします。この映画は時間の無駄です。正直僕はこの作品の記憶を抹消したいところですが、これ以上被害が出ないようにレビューしました。
タイトルにもある魔女というのが今回重要になってくる…こともなく、登場するわけでもなければ話に絡んでくることもありません。つまり映画の中の「12人の魔女」は全く意味のない言葉です。
見る必要はありませんので見ようと考えている人は他のジブリ作品を見ましょう。現にこの映画自体ジブリの汚点ですのでそういった物に興味がある方だけ閲覧を許可します。
全38件中、21~38件目を表示