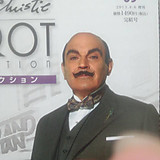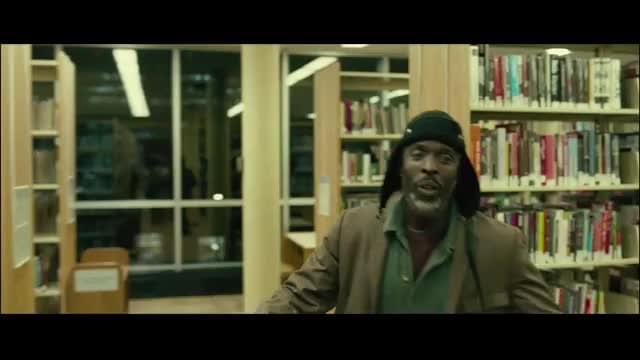パブリック 図書館の奇跡のレビュー・感想・評価
全101件中、81~100件目を表示
公共とは?を考えるとてもいい映画
アメリカの公立図書館でホームレスの立てこもり事件が起こったという物語。
アメリカ北部はかなり寒くて凍死する人が多いってのは聞いたことがある。だからホームレスが普段からたむろしてるってのも理解できる。そりゃ普段から使ってるんだから職員とホームレスも顔見知りになるよな。
本作がすごいのはホームレスの立てこもりだけでなく、図書館職員、警察の交渉人の物語もきちんと押さえているところ。
ホームレスの人たちがどれだけ苦しんでいるのかということをアピールしてるわけではないのにきちんと考えさせられた。声を上げたことの意味はあったということ。最初、パブリックというタイトルを公立図書館を舞台にしたからだと思っていたが、観終わった後は公共とはなんなのかを考えさせられる、いいタイトルだ。
涙することはなかったけど、とてもいい映画。人に勧めたくなる。
The PublicでEmilio Estevesがみせた米国の「良心」
本作を純粋なエンタテインメント作品やハートウォーミングな作品として観てしまうと、少々物足りなさを感じてしまうかもしれない。観る人それぞれが「The Public(=公共)とは何か」を考えることで、この作品が持つ優れた道徳的価値を感じることができると思う。
一般的に「公共性」とは3つの意味を持つ。
1.国や地方自治体などの公的なもの(official)
2.私的(private)に対する共通のもの(common)
3.内外に対して開かれたもの(open)
公共性に関して問題になるのは、時としてこの複数の意味がぶつかり合う場合である。
この作品においても、市の公共図書館は市民の共通空間であり、特定の人のものではなく共通の利益が侵害されてはいけないという意見。
反面、(大寒波で行き場を失った)ホームレスに対して、一個人として生存権を保障されており、彼らに対しても公共空間は開かれるべきだ、という言い分。
法のプロフェッショナルである検事や警察と、図書館に立てこもるホームレスと主人公はお互いの「正義」で対峙するが、皮肉にもお互いの大義名分は「民主主義」である(お互いの解釈は異なっているはず)。
「公共性とは何か」
「(公共)図書館の存在意義は何か」
「ホームレスは公共の場から排除されるべき存在なのか」
映画を観た後に考えさせられることが沢山出てくる。
米国のみならず日本でもリバタリアニズム(自由至上主義)の空気がひろがり、弱者が自分よりも弱い弱者を叩く風潮が強まっている。トランプ大統領が声を荒げる、米国の未来を絶望する人も多いと思う。しかし、「日本よ。米国はまだ捨てたもんじゃないよ」と米国の良心をみせてもらった気がする。
良心的な映画だとは思うが
わたしは面白かった!
タイトルなし
I'm looking for...HAIL CAESAR! 奇跡を探してるんです、見つかりますか --- 公共図書館版『怒りの葡萄』! エミリオ・エステベスが良作『星の旅人たち The Way』以来久しぶりに監督・製作・脚本・主演を務めた本作で、彼は『ブレックファスト・クラブ』(図書室舞台)と同じく図書館から行動を起こす。図書館( × ヒップホップ → ホームレス達の暮らすストリートを想起?)を舞台にした風通しのいいハートウォーミングな佳作ここにありますよ!! そんな本作にはなかなか渋く壮々たる面子・役者仲間が集結 = アレック・ボールドウィン × クリスチャン・スレーター × ジェフリー・ライト。他にもジェナ・マローン、テイラー・シリング、マイケル・ケネス・ウィリアムズ、そして楽曲も流れるラッパーの"ライムフェスト"が良かった。作品の規模感や本国での興行収入を見ても、恐らくギャラはそれほど高くないだろうが。
Make some noise!! Make some noise!! シェルターも足りない厳寒期の夜、暖を取るための屋根を求めて閉館後の時間にホームレス達が立てこもり。最初の方でジョン・スタインベックの名前が出たことから、そういうシーンがあることは想像できたけど、やはりいざくるとグッとくるものがあった。本作にもまた糞マスコミ。綺麗にまとめようとしたためか脚本においてキャラクターの一貫性や行動原理など少し弱い気のする点もあったが、最後にはやはり抗えないものがあったことも確かで、僕たちがそれが大好きだ。エンドロールの順番ではなぜかエミリオ・エステベスよりも刑事役を演じたアレック・ボールドウィンが先頭だった、彼なりの敬意の表れだろうか。ショーは終わった Elvis has left the building.
なかなかの出来栄え
ふるえながらのぼってゆけ
傑作である。スリルもサスペンスもないのにスクリーンから眼が離せない。それは人が権力と対峙するときの、ある種のヒリヒリするような緊張感に由来する。権力との闘いは勝ち目のない闘争であり、将来を棒に振り、家族が酷い目に遭わされるかもしれない。公正な裁きを求めても、三権分立は機能していないことが多く、権力側が負けることは滅多にない。
だから大抵の人は長いものに巻かれて生きる。それが賢い生き方だと思っている。しかしときには、長いものに巻かれていることに疑問を持つ。もし闘う生き方を選んだらどうなのかと想像する。その想像の先に映画があり、文学があり、歌がある。中島みゆきの「ファイト!」の歌詞は次のようだ。
暗い水の流れに打たれながら 魚たちのぼってゆく
光ってるのは傷ついてはがれかけた鱗が揺れるから
いっそ水の流れに身を任せ 流れ落ちてしまえば楽なのにね
やせこけて そんなにやせこけて魚たちのぼってゆく
勝つか負けるかそれはわからない それでもとにかく闘いの
出場通知を抱きしめて あいつは海になりました
ファイト!闘う君の唄を 闘わない奴等が笑うだろう
ファイト!冷たい水の中を ふるえながらのぼってゆけ
(1983年アルバム「予感」より2番の歌詞を抜粋)
こうして歌詞を書き出してみると、この映画にぴったりなことがわかる。そして世間は必ずしも闘う人を笑う人ばかりではないこともわかる。実際に闘えなくても、心の中では闘いたいと思っていたり、または闘う人を応援する人も意外といるのだ。マスコミのバイアスのかかった報道にも惑わされないで本当のことを嗅ぎ分けられる人がいるということである。本作品はそういった人々に向けて作られた気がする。判る人にだけ判ればいいのだ。そして中島みゆきの「ファイト!」の歌詞が理解できる人には本作品も必ず理解できると思う。
シンシナティを襲った大寒波。市の中央図書館には寒さを逃れたホームレスがたくさん屯しているが、閉館時間になると追い出されてしまう。うまく雨風を凌げる場所に辿り着ければいいが、運が悪いと路上で過ごすことになる。朝になると凍死したホームレスが運ばれていく。生き残ったホームレスは開館時間になると再び中央図書館に入って屯する。
実はいまでこそホームレスだが、その多くが退役軍人だ。ベトナム戦争やイラク戦争のPTSDに未だに苦しんでいる。J・F・ケネディは「国が何をしてくれるかではなく、国のために何ができるかを考えよう」と演説したが、国のために命がけで他国の人間を殺してきて、心に傷を抱えてホームレスになった彼らに、国は何もしない。悪臭漂う避難所(シェルター)に雑魚寝をさせるだけだ。そう言えば「ランボー」や「運び屋」の主人公も退役軍人だった。アメリカの病苦のひとつはそのあたりにありそうだ。
本作品に格好のいい行為はない。普通の人が普通に対応したらこうなるだろうなという、至って淡々とした展開である。しかしリアリティがある。それでも大団円のシーンには驚いた。彼らは英雄なのか、一般人なのか。英雄的行為は印象操作によってあとから美化されるのが常で、実際の行為は地味でブザマだ。そしてそれでいいのだ。水の流れに逆らう魚のように、傷ついて剥がれかけた鱗を揺らしながら、見苦しくのぼってゆくのである。
エミリオ・エステベスは変わらない
纏まってませんが
図書館の存在
私にはお気に入りの図書館がある。
地元の図書館だから行けないが。
東京でも、見つけれるといいなぁ。
日本だと、ホームレスがたくさんいる図書館はあまり見かけない。
でも、海外だとよくある話。
兵役上がりがホームレスに多いのも。
図書館って不思議な場所。
本が心を救うことも。蝕むことも出来る。
アメリカの実情。
どっちが正義か分からない戦い。
人によって、共感出来ない人もきっといると思うし、
理解出来ない人もいると思う。
でも、私は平等と優しさにすごく包まれた。
図書館に行きたくなった。
そして守るものが少し違うけど、図書館戦争をまた読みたくなった。
今はコロナでホームレスの人たちは図書館が閉まり
困ってるのでは。
色んなことを考えるキッカケになった。
反体制で団結が大好きなんだね
シェルターが満員でホームレスが路上で凍死したことに対する抗議の為、シンシナシティの公共図書館に籠城したホームレスと、それに荷担した職員の話。
確かに厳しい状況ではあるのだろうけれど、自身のおかれた状況を脱しようと努力しているのか。その状況を受け入れてしまっていたり、望んでそうしている人の方が多いのではないかと考えてしまいイマイチ乗り切れず。
そもそも、図書館もシェルターも、ただじゃ運営出来ないしね。
権利や自由を主張するなら、先ずは責任を果たすべきではないのかと、身勝手な言い分に賛同出来ない。
とはいえ、主人公の職員は自身の過去からの賛同という位置付けだし、都合の良い偽情報とか、踊らされたり本質を解っていないマスコミとか、それを上手く使ってなんて流れは面白かったかな。
重厚な社会派の内容で、爽快
原題「public」が示すように、民主主義社会における図書館という「公共の場所」のあり方を、本作は観客に突きつけてきます。
誰でも情報にアクセスできる権利の重要性。
そして、誰でも使える場所であること。
そこは、命が危なくなったとき、駆け込むことができる場所なのか?
誰かの権利を守るために、別の誰かの権利を抑制できるのか?
ルールと命、どちらを守るべきなのか?
社会派の内容で、見応えあり。
さらに、名を売りたいだけの市長候補やテレビリポーターの、フェイクニュースの垂れ流し具合などのスパイスに加わって、かなり重厚な作り。
そして、冒頭から仕掛けられた様々な伏線が、綺麗に回収していく上手さ。
観終わって爽快な気分になれました。
いろんな要素が入るコメディとは言い難い面白い作品
#51 何も悪いことしてないのに
何故警察や報道が出動するのか?
ホームレスは退役軍人だらけと言っていたが、それは心理的な傷を抱えてるからなのか?
さらに何故主人公はかつてホームレスだったんだろう?
結構謎がいっぱいだけど世の中悪い人ばかりじゃないって示してくれる映画。
その場所は誰のものか。公共の本当の意味
モノやサービスが溢れる現代、見た目や機能に差のないものを手に入れることでは満たされず、体験というかたちのないものが価値を持ち、所有から共有へとシフトしている。
しかし根本では人間の所有欲は変わらず、今回のコロナ禍でも買い占めというかたちで露呈した。
不景気と言われつつも、企業の内部留保や高齢者の貯蓄、富裕層の資産など一部では金余りが生じ、世界的に格差が広がっている。また飢餓で苦しむ人たちがいるなかで、日本ではフードロスが問題となっている。
お金は天下の回りもので、流通量が変わらないのであれば理論上全員が生活していくための経済は回していけるのではないだろうか。
血液と同じで、誰かがどこかでその流れを止めると滞り、本当に必要としている人たちに行き渡らない。まさに相田みつをの名言の通り、「うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる」である。
お金は信用であると同時に投資した時間の裏返しで、まさに消費するために人生で最も貴重な時間を消費しているという負のスパイラルが起きている。
反対に、何も持たないことは自由であると、この映画のホームレスたちは身体を呈して訴えている。
ただ、学びによって得られる知恵はどれだけ持っていても邪魔にならないし、未来につながる投資である。それを富める人も貧しい人も平等に享受できる拠り所が図書館だったはずだ。恵まれない境遇に生まれた人たちが立ち上がるため武器でもある。
そして、最たる所有の権化は「権力」と「メディア」の利己主義である。
それに立ち向かう彼らたちが砦とする図書館はまるでひとつのまちのようだった。これが本来の人々が支え合う暮らしの理想形なのかもしれない。
強いて言えば、テーマは鋭く、それを本に重ね合わせてストーリー(コンテキスト)で包むのは素晴らしいが、刑事と息子の物語や、クライマックスへ向かっての展開がもう少し深みがあると良かった。
本当に生きていくために最低限必要なものはなんだろうか。深く考えさせられる作品だ。
図書館員の視点とホームレスの視点の双方から深く考えられる映画
大寒波で死の危険に晒されたホームレスたちが一夜を凌ぐために図書館を占拠し、図書館員も巻き込まれ、様々な決断を迫られる物語。
図書館なのだから閉館時間が来れば退館しなくてはならず、無理やりに残ればそれは不法行為になってしまう。
「外に出れば死んでしまうかもしれないのだから、認めてあげればいいじゃない」と思う人もいるだろうけど、そう単純に解決できない難しい問題。
公共の場というのは、それぞれに与えられた役割があり、本来の役割を超えたことを行い前例を作っては収拾がつかなくなってしまう。
そんな状況に巻き込まれた図書館員スチュアート。
図書館員としての職務を全うすべくホームレスを追い出せば、彼らは凍死してしまうかもしれないし、ホームレスたちが図書館を占拠することを認めれば図書館員としての立場が危うくなるかもしれない。
まさに彼方を立てれば此方が立たず状態。
スチュアートの葛藤や決断に目が離せない物語だった。
"Make some noise!"そう叫ぶホームレスたちからは
声をあげることの意味を考えさせられた。何かしても現状は変わらないかもしれないけど、その何かをしないよりは生きるために声をあげること、
この映画を観た多くの人が言うようにBLMが問題となっている今の世の中に深く刺さる。
本来の職務からはかけ離れたことを行うことになった図書館員の視点と
生きるために声をあげるホームレスたちの視点のそれぞれにテーマがあり、観る人に考えるきっかけを与えてくれる。
全101件中、81~100件目を表示