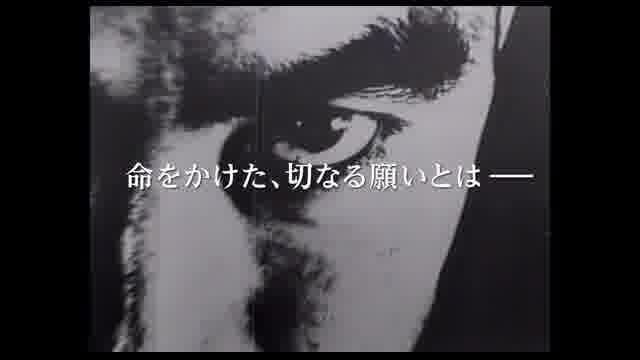三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実のレビュー・感想・評価
全180件中、21~40件目を表示
相手の立場に立つ、誠実に本気!
現役東大生(全共闘)相手に自分を曝け出してして自分の考え方を述べ質疑応答でも冷静で迷いがない、凄い人だ!と感心する。
でも真面目過ぎた!
思い込んだら命がけ!も場合による。
切腹する事なかったのに?
あんなにどんな人にも誠実に見える人はいないように思いますが、今の時代ならノーベル文学賞は川端康成じゃなく三島由紀夫だったかもね?
惜しい人を亡くしたように思います。
残念。
三島由紀夫本人が登場しているから迫力満点。 抽象的な議論に終始し、...
天皇も東大も
言葉というものの重みを感じる作品
この熱はすごい
禅問答
尊敬する高校時代の恩師が三島由紀夫を研究し、著書を頂いたのだけれど、読んでも頭に入ってこないので、映像なら理解が深まるかな~と思いDVDを借りて観た。
東大の学生と三島の討論は、私などには全くの禅問答で、それは理解できなかったけれど、その時代の「熱情」はヒシヒシ伝わってきた。
三島と学生の語り合いは暴力的ではなく、互いに落ち着いていたことに、知性を感じたかな~
知性主義ではなく。
全共闘って反体制の左翼だと思ってきたけれど、ひとくくりに左翼でかたずけられるものではないことがわかって良かった。
当時の熱い国への思いは、現代を生きる私たちにはないもので、すっかり古びてしまった感じだけれど、学生運動の「熱さ」は、ある意味素晴らしいのかもしれない。
やはり解説付きの映像はわかり易い。
これで現状積読状態の先生の著書に再び光がはいりそうだ。
圧倒的熱量の行先
これは必要な映画ではある
三島由紀夫が残した叫びを、いま鮮明に残しておく
こういったものは必要なのではないでしょうか?
映画として、よくある証言者と当時の映像を振り返る
というだけの 何の外連味もないモノではあるが
当時、革新的な子供を抱きながらも堂々と三島とやりあった
芥氏が、いまもキチンと老害ヨロシク狂っているのが最高だった。
全共闘のメンバーは、紛れもなく東大生だったわけで
いまのテレビ画面で弄ばれる東大生とは
全くの異質の存在なのが感慨深い。
それは、全国どこの学生や社会人もかつての世代とは違うわけだけど
やはりモノを考える必要は常にあると思われる。
何歳になっても勉強しなくちゃいけない。
そう思わされる。
ちなみに監督の豊島圭介は豊饒の海を読んでないのか
と、芥氏に怒られたらしい。 そら、怒るか。
でも、良いモノ作ってくれて監督さん、ありがとう。
6歳で安田講堂事件をテレビで見て、いつか自分も、とぼんやり思った変な子でした
三島は、天皇という一神教を信じ、全共闘が社会主義革命という一神教を信じていると受け止め、一神教信者というメンタリティーにおいて共闘できると信じ込み、アメリカ的価値の堕落という共通の敵と戦おうと勧誘に出向いた、という事なのでしょうか。
東大生と三島の抽象概念のキャッチボール、すごいね、頭いいとはこういう事なんだろうね、などと感心しながら見ていましたが、同時に、ただ言葉の粉飾にすぎないような気もして、本質を見極める力とは別物のような気がしないでもなかった。だから、巷のおばあちゃんなんかが、ぼそりと言う真実に打ちのめされたりすることがあるような。
三島は、割腹自殺という形で一神教に殉じた。しかし、全共闘は果たして本当に一神教信者だったのか。もともと多神教だったのか、あるいは改宗したのか。ただ、あの時代において、まじめに、かつ愚かに、そして熱く対峙する姿は、一回りほど下の私にとって限りなくまぶしい輝きを放つものでした。
全共闘は何を残したのか
1960年代後半の学生運動全盛期の時代背景が分かる映画!
ドキュメンタリーの前半で、当時の時代背景を説明してくれます。東大全共闘を始めとして、日本各地で、学生運動が起こっていた様子が伝わり、今の日本では考えられない様子だと思いました。
その中で三島由紀夫が、東大駒場キャンパスの討論会に出るという、当時の貴重な映像も見ることができるドキュメンタリーです。正直、三島由紀夫や東大の学生が議論で話す内容は、難しい内容も多く、ついていけない部分もありました。それでも、三島由紀夫の思想の一端が分かる映画だと思います。戦後の日本の歴史の中で、その時代を知る意味でも、時代背景や三島由紀夫の思想の一端を知ることができる映画だと思いました。
あの東大駒場キャンパスの討論会の会場の「熱量」は確かにすごかったと感じましたし、「言霊」の力を信じようとして、討論に臨んだ様子が映画から伝わりました。
熱と敬意と言葉と。 その頃のことを全く知らない世代で、自分達が何か...
熱と敬意と言葉と。
その頃のことを全く知らない世代で、自分達が何か行動を起こしたとして世間や政治や何かを変えることなんて出来やしないと思っているし、そもそもそんな真剣に世界のことも自分のことも考えていないと思っている。そんな私からするとこうも変革に向かって突き進んでいこうとする情熱は羨ましいとすら思う。
三島の本もほぼ読んだことないし、断片的にしか知らなかったけど、なんか一気に実在したんだ、という存在感をリアルに感じられた。
ちょっと前までは本当にこんな一人間が何かを思っていたとしても変化は起こせないと思っていたけど、最近はSNSがきっかけで少しずつでも声が届いたりするシーンも見たりする。案外まだこの時代も捨てたものじゃないのかも、まだ真剣に世の中を変えようと考えてくれる人がいて力もあるのかも。そしてその動きの根底には熱と敬意と言葉があって、それってこの全く知らない時代と共通しているんだと知った。
分かり合えなくても、頭ごなしに否定するんじゃなくてまずは熱と敬意と言葉でもって対話して知ろうとする。知ってもらおうとする。そばにいる人との関係においても、大切なことを学んだ。
三島由紀夫こと、平岡公威は、面白い奴だ‼️❓
三島由紀夫のカリスマ性に脱帽
三島かっこいい
本作では三島を一人の等身大として描いているのに好感が持てた。政治的...
本作では三島を一人の等身大として描いているのに好感が持てた。政治的な主張は感じられず、三島を批判するわけでも、過度な肯定感で味付けするわけでもなく、共に生きた人たちから見てどのように映ったのかをいろんなライトで照らし合わせていく。
俺が好意を抱いたところは三島は一人の人間として1000人以上の学生と対峙したところにある。決してねじ伏せるわけでも、説教にし来たわけでもなく、学生と話したいからきたのが男らしいと思った。と同時に意外だったのが、あの安田講堂内では哲学を題材にした三島と学生の討論が行われていたというところにある。
これは憶測にすぎないけれど、もしかしたら学生側は東大の先生とこういう難題の話をしたかったのかもしれない。しかし東大の先生の頭脳より学生側が上回ったからこそ話を聞いてもらえなかったのかもしれない。まともに話ができないからこそ、こういう議題に飢えていたのかな、と鑑賞しながら思った。
学生側の鋭い質問にも三島はたじろぎもせず答える所がこの人のすごいところなんだな。
三島はテレーズ・デスケルウ の小説を引用し、亭主を毒殺した妻は夫の目の中に不安を見たかったからと説く。それを反体制側の人間が大衆の目の中に不安を見たかったからに違いないと語っていたところが好きだし、全共闘は知性主義の東大を壊したという点で評価してたのも興味深い。
後半では三島の天皇論にも言及しており、三島は天皇を日本社会の救済概念・日本の文化伝統が集約されるもの、すなわち無意識的エネルギーの源泉として捉えている。天皇というものを現実を積極的に批判する根拠として読み返して天皇を代表とする日本文化が戦後社会の堕落に対して批判としての力を持つ。もし現実を批判するなら君たちは天皇の名においてやらなければならない、という考えは学生側が意表を突かれて笑ってしまったというエピソードも好きだった。
もしかしたら三島は初代ゴジラのように戦後の日本に喝を入れたかったのだろうと思う。
全180件中、21~40件目を表示