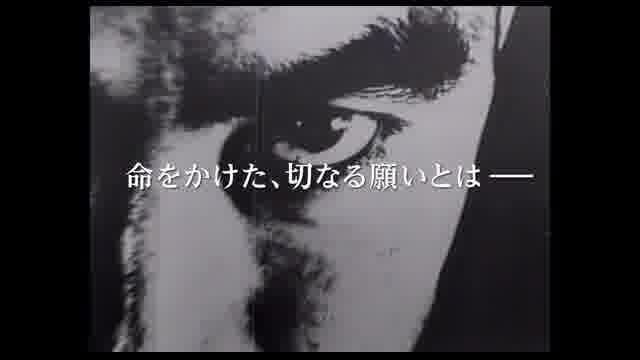三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実のレビュー・感想・評価
全180件中、1~20件目を表示
誰もが何かを「議論」出来る時代に捧ぐ
東大安田講堂事件の約4か月後、三島由紀夫と東大全共闘との討論会。この面子とシチュエーションだけで、凄まじい「言い合い」を連想した私は愚かだった。三島は自らと全共闘の思想が全く相いれないものではないことを直感的に見抜いていて、論破ではなく説得をするためにこの一触即発とも思える場に臨んだ。
口調は終始穏やかで、時に自分を俯瞰した物言いをして笑いさえ誘う。全共闘の学生達も、三島の思想は受け入れられなくてもその討論に対する誠意は序段で感じ取っているのが分かる。互いに相手の言葉が終わるまで静聴し、提示された疑問には正確に答える。時に哲学的でさえある高次元の、本物の討論がそこに成立していた。
今、ネットを中心に多種多様な言論が渦巻く中、イデオロギー死守ありきの論争や枝葉末節の論破で「勝ち負け」を決するような「言い合い」が巷にあふれている。熱情と、勝敗ではなく真実を求める真摯な言葉、そして相手への敬意を終始保ったこの討論会は、誰もが見知らぬ誰かと議論できるようになった現代において、より示唆に富んだものになるのではないだろうか。
相手の敬意を持つこと
当時を知らない筆者は、全共闘にも学生運動にも三島由紀夫にも思い入れはなく、歴史の中の出来事と言う感じなのだが、この映画は今を生きる人間に響くものがあると強く感じた。
安田講堂事件を引き起こした左翼学生グループの全共闘が、保守の論客でありスーパースターの三島由紀夫と激論を交わす。互いに思想信条は相いれないはずだが、議論の果てには共通の敵のようなものが見えてくる。全共闘メンバでーでこの論戦でも壇上で三島を激論を交わした芥正彦は、当時を振り返って、それは「あいまいで猥褻な、この国」と表現する。
映画を通して感じられるのは、互いへのリスペクトだ。豊島監督は映画を作るにあたり、仮想的として現代のSNSの議論を思い浮かべていたそうだが、たしかに敬意なく罵詈雑言に終始し、マウントを取ることばかり考えているかのようなSNSの空間と、この講堂での熱は対極にありそうな気がする。
三島の天皇論もわかりやすく披露されており、三島由紀夫の思想を知る上でも貴重な資料になる作品だと思った。
三島由紀夫も東大生もアツい。ウザい。
ノンポリ世代も見やすい「三島由紀夫という右翼」指南
ドキュメンタリー映画化を依頼されたのが豊島圭介監督という人選が面白い。東大卒という経歴が理由だったのかは知らないが、豊島監督はこの討論会の時にはまだ生まれておらず、政治的なステートメントを押し出してきた映画作家でもない。だからこそ本作は、三島由紀夫や学生運動を知らない世代に、とてもエネルギッシュで面白い人たちがいた、という事実を提供してくれている。
特に驚いたのが三島由紀夫の佇まいや論法で、世代が違う若者たちの土俵に敢えて乗ろうという姿勢は、頭の凝り固まった老害ではまったくない(老害というにはまだ若いが、当時の学生たちには老害に見えていただろう)。マッチョ信奉で極右化した文豪、という雑な先入観がこの映画によって書き換えられたのは大きな収穫だった。
ただ、ノンポリな姿勢故に、この映像が現代にどんな意味を持つのかを提示するまでには至っておらず、興味と好奇心を刺激された者として、もっと踏み込んだものが観たいと感じはした。ともかく入口としての機能は確実に果たしてくれていると思う。
三島以上に、赤ん坊を抱いた男の印象が強烈すぎた・・・
三島の本は2、3冊しか読んでないし、その内容もはっきり覚えていない。そんな自分がこの濃厚な香りが充満するドキュメンタリーを見て何か感じるものがあるだろうかと、多少なりとも尻込みして臨んだ本作。いやいや、この圧倒的な熱量には度肝を抜かれた。何かを表現するたびに右だの左だので喧々諤々となる昨今、ひとつ間違えば本作もその格好の餌食となりそうなものの、しかしこの映画は決してそうならない。作り手の豊島監督が証言者たちに色々教えてもらいながら当時を振り返るというスタンスゆえ、映画の視座そのものがとても観客に近い、とでもいうべきか。主義主張の異なる両陣営が暗黙のルールを侵すことなく、さらにはユーモアという武器を駆使しながら戦う様は見ていて痛快だった。何よりも登場人物一人一人のキャラクター、特にあの赤ん坊を抱いた男の存在が際立っている。史実をあまり知らなかった私は、一本の映画として本作を楽しんでしまった。
東大熱血教室
三島由紀夫はむつかしくて確か「F104」と「侯爵サド夫人」くらいしか読んでない。。
そのため平野啓一郎の弁をカンペにすると、三島由紀夫は戦中、出征していった学生同様、自分も昭和天皇に殉じるロマンチシズムに取り憑かれてたのに、終戦でハシゴを外され、望まざる戦後の自分、社会、天皇の姿に忸怩たる思いを抱えていたようだ。
それらを照らし出すために「楯の会の三島由紀夫」というキャラを生み出し、自ら演じることに熱中していったのが晩年の彼の姿。
つまり彼自身がお芝居「三島由紀夫」として自作を演じ、そのクライマックスがあの市ヶ谷駐屯地でのスピーチっていう。なるほどねぇ。。
みんな大小何かしらの人生ストーリーを演じているわけですが、彼の場合はずば抜けてマジメ。
幼き頃より肉体労働のマッチョ男性に憧れ、不器用ながらもあるべき自己像を目指して決意、努力、実現した。まるで叶恭子さん(もしくは木嶋佳苗)のよう。。
そんな必死のセルフプロデュースに冷や水を浴びせる芥正彦。そもそも小説はひとつの独立した時空なんだから、そこで多くの人生を生きてきたはずのアンタがなぜわざわざ別人になろうとする?って言ってるように思えた。さすがの三島も大苦笑。
それでも三島は「意地」というワードを盾に、あくまで自分の生き方に固執するポーズをとる。自分の滑稽さはとっくに織り込み済み、わかった上で、じ、自覚的に選んだ道なんだな。
一方で、ほんの紙一重の差で、目の前の若者たちに共感と共闘の可能性を示したりするし、なにより本人、めちゃくちゃ楽しそうに学生の弁に耳を貸す。中には未熟な主張もあっただろうに、イラついたりピリついたりせず、えらい知識人が思い上がった若僧を論破…なんてセコいスタンスはとらない。きちんと大人。ナイスガイだ。
この900番教室において三島は、理想的な熱血先生であり、キュートなアニキであって、わずか2時間の間に、学生とほのかな友情さえ通わせる。
市ヶ谷の事件を受けて芥正彦は、「やりやがった」的な祝福コメントをしていたけど、これには三島も、草葉の陰でニヤリじゃないかな。
彼は日本人として2番目のノーベル賞作家の栄冠より、自分が作った三島由紀夫というキャラを演じきる方を選んだ。
だから完遂を喜ぶべきなんだろうけど、もしそうでなかったら、こうして若者たちと交流しつづける道もあったんじゃないかな…と少し惜しい気持ちになった。
1969年日本、若き知性と熱気を封じこめた異空間
三島由紀夫が東大全共闘と議論した、東京大学駒場キャンパス900番教室。
TBSに保管されていたフィルムから、議論の流れと参加者のその後を追う、意欲的な108分のドキュメンタリー。
なんかね、引きこまれました。
全共闘と楯の会、いずれの人物もおもしろく、なにより三島由紀夫のやわらかな語り口がいい。
彼らの言うことをときに認め、ときに分解してさらなる説明を求め、あくまで自分の論と対比させる。
こんなの自分そのものに、絶対的なよりどころがなければ無理ですよ。
自分だと、開始10分以内で半泣きなってツバ飛ばしながら意味不明な罵倒語わめきちらしそう。
とちゅうから(なかまによばれて)参加してくる、芥正彦がまたいい。
乳幼児の娘さんを片手に抱き、諧謔的(ユーモラス)に、表現者として対決してくる。
組織最強の論客ながら、当人は東大全共闘なんて必要としておらず、一舞台人として、一表現者として三島に向きあう。
日本を代表する作家相手に一歩もひかず、堂々あなたはカッコわるいと自論を突きつける。
ゆーて日本の学生運動ですから、多くの登場人物はご存命でインタビューにもでてまして。
中でもこの芥正彦、なんかカッコいいジジイになってて、三島の決起を見て
「ああなんかまたバカやってんだな」
「死んでよかったよかった」
「あいつは一世一代の大芝居を、さいごまで演りきったんだ」
なんて粋なセリフを口にしてます。
本人は、カッコいいとかジジイとか、ぜったい言われたくなさそう。
でもカゲで喜んでくれてそう(ひどい矮小化)
かんじんの議論じたいは、当事者には切迫したものであったんでしょうけど、生きた時代も知力レベルもちがう田夫野人の自分には理解しがたく、うわついた言葉遊びに思える場面も多々ありました。
それでも、最高の知性と知性の理性的な衝突は、ストレスよりも知的な興奮を喚起するものでもありました。
もっと罵声とびかうメチャクチャなののしりあいを予想してたんですけど、最初に三島由紀夫が対決姿勢を語る10分間が、その後の議論をフレーミングしたおかげもありましょう、東大生たちはみな、みずから発した言葉に熱中していて、そのみずみずしさは好ましく思えました。
国体についていろいろ考えさせられる部分もありましたけど、それよりも三島のヒーロー性に焦点の当てられたフィルムかなと。
当時の時代性を知る資料として、はたまた押井守がよくネタにする全共闘の知識として、映画ファン目線で見てもおもしろいですよ。
期待はずれ
これを映画としてまとめた人、討論の中身と背景、時間軸を消化しきれてないよね。
大見出しでまとめていくのは全然いいのだけれど、全共闘も三島も観念論、哲学論のやり取りが大半で何を言っているのか分からない。だから、大衆に語りかける言葉を持たなかったので、双方ともに大衆運動にはならなかった(なれなかった)し、自分らだけが分かっている(つもりになっている)ので先鋭的にならざるを得なかったんだけど、そのところがすっぽり抜け落ちている。だから、討論(そもそも討論なのか?全共闘が三島の講義を聴講しているだけじゃないか?)の因果が弱いと感じた。
面白いところもいくつかあったが、
・解説してくれる人たちの知識量はすごい。両者への思いは強い。
・名は体を表す。クズはクズ。ゴミはゴミでしかない。
・小僧は小僧でしかない。ファッションとしての学問と飯食ってる学問では天地以上の差はある。
・討論の最後。お互いに歩み寄ろうとする、特に、全共闘側のセリフは左翼特有のセリフ。自分が民青同盟に勧誘され議論して相手を打ち負かしたあとに言われたのと全く一緒なことを瞬間的に思い出した。お互いに啀み合ってもDNAは一緒なんだろう。同族嫌悪か。
全共闘と三島の劣化コピーが山本太郎(とれいわなんとか組)なのだろうな、という茫漠たる思いで劇場を後にした。
言葉というものに真摯で誠実な人だった
友人に勧められて。
「おお…三島由紀夫が生きとる…動いとる…」ということにまず何か感動してしまった。
討論の内容は私には難しいものだったけれど、気迫と雰囲気と、そして三島由紀夫の語り口のあまりの嫌味のなさ、雄弁さに圧倒されて100分間食い入るように没頭して観てしまった。
学生たちの弁に対して一切の否定もせず喧嘩腰にもならず、題材は難解なのに何も知らない私の頭にもすらすら入ってくる分かりやすい答弁。
言葉というものに真摯に誠実に向き合い、それを伝えることに対する努力を常に怠らなかった人なのだなと思った。
それと同時に、たしかにここまで誠実で真面目な人が志を保ったまま生きていくのは、この時代にあっても相当に困難なことだったのだろうなと感じた。
三島由紀夫作品は初期の頃のものしか読んだことがなかったけれど、あらためていろんな作品を読んでみたいと思う。
そしてそして時代の熱気に感服しっぱなし。
国と個人の運命が共にあり、国と個が同一だった戦争の時代が終わり、そしてそこで「生き残ってしまった」と考える人たちが葛藤を抱えながら生きて生きてつくった時代。
国と個人が完全に別れてしまった現代では考えられないほど、若者が世の中や国について真剣に考え、当事者意識を持っていたんだろうなと思った。
今みたいに時間を潰せる娯楽が死ぬほど溢れかえっている世の中では、きっと人は無限の娯楽の消費に必死で、こういうことを考える時間も思考もなくなってきちゃってるんだろうな。
学生運動に参加していた熱量の高い若者、それに三島由紀夫が生きていたとしたら、一体今のこの令和の世を見てどう思うんだろうか。
こういった映像がちゃんと残されており、一般人でも見ることのできる形にしてくれたことに感謝。
本や教科書だけでは感じられない生きている人間や時代を感じることができ、本当にありがたい。
忘れていた情熱を思い出させてくれる
三島由紀夫について、少しでも勉強になったらいいかなという程度で検索したら出てきた映画。
タイトルだけ見れば、自分の考えをお互いに押し付け合うむさ苦しい映画かと思ったが、違う意味でむさ苦しく、観ていられないほど熱かった。
失敗したくない、恥ずかしい思いをしたくないと涼しい顔をして生活していたが
この映画を見て熱く、恥ずかしく、とことん向き合い、何かに取り憑かれることが人の心を動かすのだなと勇気をもらった
全共闘、当時のエリートたちは何を思っていたのか。
圧倒的熱量
三島由紀夫vs.東大全共闘というタイトルからすると、単純に右翼対左翼の激論が展開されることを想像した。確かに、両者の理念は正反対で、議論は噛み合っていないのだが、実は反米愛国という部分では一致していて、全共闘側はできれば三島と手を組みたかったのだということが、終盤でわかった。
議論は、時間、他者、国家、天皇などをテーマに観念的、抽象的な言葉が熱情をもって交わされ、ハイレベルな哲学の講義のような光景が繰り広げられる。言葉というものにまだ力のあった時代で、言葉で人を説得し、言葉によって世の中を変えていけるということが信じられていた、純粋で真摯な時代だったのだ。
圧倒的熱量を持った議論など失われてしまった今、コロナショック後の世の中は、変わっているのか、変わっていないのか。
論争の先に見えた本当の敵は何か?
私は世代的に学生運動を殆ど知らない。まして三島由紀夫という人間も、歴史や国語の授業で聞いたくらいの門外漢だ。そんな私でもこの論戦からは目が離せなかった。何故なら、そこには日本の未来を憂う両者の"熱"があったからだ。
立場、思想は違えど、日本の進もうとしている方向に疑問を感じ、行動してきた両者。
だからこそ、彼らが舌戦の末に共通の敵のような物を見出した時の感覚には興奮するものがあった。
そしてその敵は今も変わらずそこにある。
悲しいかな、彼らは歴史に敗北し、我々はその後の日本を生きている。主体性のない国、空虚な日本というこの国で生きている。
もしも彼らの情熱があの時代を革新していたら、我々が住むこの国はもっと良い形になっていたのだろうか?
IFを語っても仕方がない。
理屈ではそう分かっても想像せずにはいられない。
一つだけ言える事は、熱情こそが世界を進める糧であってほしいという事だ。
熱情なき政治の先には腐敗しか待っていないのだから。
対立しているはずの全共闘の若者の演説を、どこか満足そうに笑みを湛えながら聞き入る三島の表情が印象的だった。彼らの熱情を見て、三島自身「この国もまだ捨てたもんじゃない」と、そんな希望をどこか見出していたのかもしれない。
未来を作るのは老人ではない、彼らのような活気ある若者であってほしいものだ。そんな未来に私は生きたい。そう思った。
議論が出来てるが、頭良すぎてバカになってる。
内容は国体思想vs共産革命の議論。議論は民主主義の根幹。実際は思想のぶつかり合いでしか無いが、議論はしていた。
思想の軸が真逆なのに議論をする。
今の政治には無い。
議論はしているが歩み寄ることはない。後日談で三島が全共闘のメンバーを勧誘したって話はあるが現場では軸を譲る事は無かった。
それでも笑い声が上がるユーモア、理解はするが交わらない態度。真剣勝負の議論はいつまででも見ていたい気にさせられた。
しかし議論の中身は思想的なもの、屁理屈vs屁理屈。テーマの立て方はボンヤリしたもの、それに三島が持論を展開。そこからあとは理屈の応酬。
それでも不思議とキャッチボールが成り立ってる。
ただしキャッチボールみたいに取りやすいところに投げるのではない。厳しい場所に速球を投げ合う。
「これ受けれるか?どうだ手が痺れるだろ」と言うようなやり取り。
学生だから出来る議論に三島が合わせる。余裕を見せつけると言うが三島には余裕があったのだろう。対芥以外は相当の余裕が見えた。
余裕が議論としての歩み寄りに見える雰囲気を作り出したのだろう。
こう見えるのは演出の賜物だろうな。面白い作品になった。
右か左か、勝つか負けるかでは無く
全180件中、1~20件目を表示