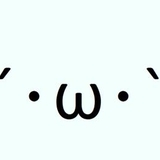TENET テネットのレビュー・感想・評価
全979件中、621~640件目を表示
今年最大の楽しみと言っても過言ではない「TENƎꓕ」 公開初...
今年最大の楽しみと言っても過言ではない「TENƎꓕ」
公開初日と中2日空けて2回鑑賞
初日は、映画館に向かう電車に乗ったら、3,4駅くらいで電車が運転見合せになったり、タクッたら渋滞に巻き込まれて間に合わないんじゃないかとヒヤヒヤしたりとトラブル続きでしたが、何とか予定通りフルIMAXスクリーンで観られました。
公開前から「難解」「難しい」ってワードが先行していたので、出来る限りそのフィルターを外すように鑑賞しました。
評判通りの難しい描写はありましたけど、面白かった!
スパイアクションとスペクタクルな映像に《時間軸》と言うスパイスを加えた素晴らしい作品でした。
ノーラン監督を「時空を操る宇宙人」と勝手に呼んでいますが、本作でも時間軸を上手く使ってこちらの脳を右へ左へと刺激してきますねー。
あるシーンまでは刺激よりも、
どう展開するかという興奮とド迫力の映像、キャット(エリザベス・デビッキ)の美しさに目を奪われました。特にあの腰の高さからヒールまで一直線に伸びるラインの優美さよ。
Netflixの大好きなドラマ「ザ・クラウン」では次々回位のシーズンでダイアナ妃を演じるみたいでこちらも楽しみです✨
そして、ニール(ロバート・パティンソン)の存在。パティンソンは「トワイライト」の青白いイメージが強いですけど、本作でのパティンソンは役どころも含め、ただただ尊い。
1度目の鑑賞の時は何気なく聴いていたニールのセリフが、2回目鑑賞では、ニールの全てのセリフがいとおしくなるんです。
2回観たから言えるんだと思いますが、
キャラクターが結構面白いんです。
セイターの部下のオルコフとか、
空港のフリーポートのマネージャーとか(ジャック・カットモア・スコット)
このマネージャーさんみたいな人、いっこく堂の腹話術の人形みたいな赤いホッペで喋るから見てて面白い。ヨガのくだりからの彼を見てニタニタしてます笑
あと、セーリングシーン。あのヨット、F50って言うそうなんですけど、速度100キロで、
乗ってる人の体感速度は200キロ位あるそう。
撮影の時はもう少し速度は落としてると思いますけど、この作品のなかでも好きなシーン。あそこで、ジョン・デヴィッド・ワシントンが必死に回しているところが、僕には時間を巻き戻してる画に見えてここでもニタニタしてます。
それから、スコア(劇伴)
ノーラン作品といえばハンス・ジマーだったんですが、本作はルドウィグ・ゴランソン作曲。
初回鑑賞したときは、少しスコアの印象が弱いかなと感じたんですが、再び鑑賞して聴き込んでみるとなかなかハマるスコア。
ハンス・ジマーのような感情豊かなメロディラインにプラスして、ベース音を効かせかたやエレクトリックな楽曲が作品に馴染む。
毎日サントラを聴いてるんですが、好きなスコアを聴き込むのは本当に楽しい。
時間軸がどうなっているのかの技術的なところを探るのも本作の楽しみの一つだと思いますが、割りとわかりやすい伏線回収な描き方や、人間くさい愛憎劇を全面に出してるところや、セリフをしっかり聞いていると謎解きが出来る気がしているので、人物像に比重をおいてみると楽しさが増す作品かもしれません。そして何度も観たくなる(見直したくなる)作品なのは間違えないと思います。
それと書かずにはいられない撮影と編集の素晴らしさ!
スタルクス12なんて、なんなんでしょうね、ビルがぶっ飛んでまた元に戻って吹き飛ぶとか、もうあれを観てるだけでニタニタできるし元を取った気分です。
初回観たときも2回目観たときも若干の中弛みを感じたのも事実なんですけど、次回観るとそこがどう感じるのかを確かめるのも楽しみです。次はドルビーシネマと通常スクリーンを観て映像見比べ予定。
観れば観るほど自分の感じる作品になっていく気がしてテネット熱は当分続きそうです。
私には無理
摩訶不思議な映像体験でした
しかし難解極まりなく(ただたんに私の脳が理解できる範囲を超えていただけかも知れませんが前半をもう少しゆっくりと咀嚼しながら再度みたいと思います)不覚にもほんの数分気を失ってしまいました(居眠りとも言う)
この感覚はキューブリック作品を見た時と似ている
あの『2001年福助の足袋』(こんな映画は無いと思います)じゃなくて超大作の方です、そのラスト間近のサイケな映像のあたりからどんどん睡魔に襲われて毎回逃げ切る事が出来ないのです
もうすでに理解しようと言う考えはとうに捨てました
ピカソや岡本太郎などもその部類です
ダリさんは何となく感覚的にはまだついて行けそうですが
わかりやすい作品というのもどうかと思う一面わからなさ過ぎるのもね〜
わかったフリして人にものも言えないし正直に打ち明けた方がお互いスッキリするんじゃないかと思うのですよハイ
とにかく映画館でですから巻き戻しもスローも一旦停止も出来ずどんどん作品においてけぼりにされてしまいました
そんな楽しい作品でありました
必ずまた見るぞ!
時間の「逆行」って、便利、、、、、じゃないよね
おもろかったーー!けど3.5点
2020-25
思考回路はショート寸前。
映画館に来たのは2か月ぶり、新作映画を観るのは半年ぶりです。ご無沙汰してます。
『ムーラン』だけを楽しみにこのコロナ禍を過ごしてきた(わけでは全くないけど)私は、『ムーラン』はディズニー+で見てねと言われたら、映画館に行く理由がなくなりました。
ただ、『ムーラン』の次に楽しみにしていたのが本作でした。
とりあえず心が興奮して、キラキラしちゃってまして、いつも以上にまともな文章が書けません。
ネタバレや解説を書けるほどの語彙力がないし(やべー&すげー&はんぱねーしかない)、他のレビュアーさんのレビューが素晴らしすぎるので、私が気づいたことを4つほど。
①ノーラン監督の作品って、どれを観ても「これがノーランだわ」って思うのに、1つとして「似てるわ」とは思わない。
②ノーラン監督の女優さんの趣味は、リュック・ベッソンのそれより自分好み。
③『ターミネーター』をリメイクするなら、ジョン・コナー役でもいいけど、むしろカイル・リース役にロバパティさん!
④やっぱ『ターミネーター』ってすげぇな。
遠ざかっていた映画館ですが、ぼちぼち映画館日和を再開したくなりました。ありがとう『テネット』。
追記(観賞翌日)
①朝起きてみると、昨日は興奮だらけだったのに、今日になったらめちゃくちゃもやもや(笑)何でもやもやするのか、わからないのに。
②やっぱり、『イエスタデイ』の彼だよね!
③え、あの出来る男はアーロン・テイラー・ジョンソンだったの?!
第三次世界大戦…
・非常に分かりにくい内容でした。
・一つ一つのシーンが、カッコいいので、楽しめました。
・ニールは何者なのか…。
・悪役の動機…。
・いろいろ謎や疑問点はありましたが、引き込まれていく魅力がありました。
時間の逆行は物理的に可能なのか?
分からん。
目まぐるしく。
何の知識もなく見にきた。掴みはオッケー。凄い勢いで話は進んでいく。ん?あれ?どれ?ってなって置いてかれたのか、何回か落ちました。
理解できれば楽しいのかな。
私の頭では一度では理解できなかった。
理解しようとパンフレットは買ってみた。
読むかはわからない。。
全979件中、621~640件目を表示