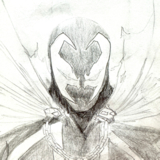フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊のレビュー・感想・評価
全16件を表示
個人的には1話目推し!!
本作品は、エピローグ、プロローグ、そして3篇からなるオムニバス形式。
全体で2時間近くの作品だが、豪華俳優陣をして、ややまとまりに欠ける印象は否めなかったか。
とは言え、圧倒的な個性と世界観、実験性はこの監督ならでわのもの。そしてその中でも個人的には、1話目の「確固たる名作」を推したい。どうせなら、このエピソードだけで1本撮ってもよかったのでは?と思えてしまう。あるいは、さらに短編の5篇編成のオムニバスぐらいのほうが作品として間延びせずに収まりがよかったのではと思えてしまった。
話を1話目の「確固たる名作」に戻すと、頭からいきなり圧倒されてしまう。色の無い世界に無表情のボンドガールのヌード・・・。かと思えば、裸体からの看守服!! この緩急の付け方、奇をてらった演出には正直唸ってしまった。
そして、個人的な発見はやはりベニチオ・デル・トロの役どころ。これまで、「ロープ」や「ボーダーライン」シリーズ等で比較的硬派な役の印象が強かったから、本作では正に新境地、ある意味ではまり役だった。(そのいでたちに「チャールズ・ミンガスかよ!」と思わず突っ込んでしまったが、ミンガスというより晩年のモネのほうが似てるな。白内障期のモネ作品が 「 抽象画の夜明け 」 説は私も支持している。) また、画商役のエイドリアン・ブロディもいい味を出している。画商ならでわの、クールさとうさん臭さの両立に成功していた。個人的に印象的だったのは、冒頭のスケッチのシーンに加えて、エイドリアン・ブロディ扮する画商がデル・トロ扮する囚人画家の才能に気付き、作品を購入するべく交渉するシーン。狭い監獄の中で画家と画商が向き合い、たばこ「70本で」と提案する画家に対して正当な対価を払いたいと諭す画商。画面正面には、小窓からその掛け合いを覗く看守役のレア・セドゥ。この場面は、個人的にお気に入りのシーンだ。
後半、傑作が刑務所の壁画だったシーンについて、画商の「芸術の良き理解者」としての側面と、「ビジネスマン」としての側面の2面性(相互矛盾)がうまく表現されていて面白かった。因みに、あの壁画のシーンを見て、真っ先にマークロスコのシーグラム壁画をイメージしたのは私だけだろうか?それから、今や完全にオールドクラシックと化したヌーベルバーグ的手法を現在に蘇らせている点においても一見の価値ありだ。
続いて2話目の「宣言書の改定」については、言葉を選ばずに言えば、名女優フランシス・マクドーマンドとイケメン俳優ティモシー・シャラメの無駄使いだったかなと。若者の革命に対する熱量がいまいち伝わってこないのと、年上女性への禁断の恋的な部分ももう一つだった。
3話目「警察署長の食事室」の料理人については、見た目からしてレオナール藤田やん。以上。アニメーションのシーンはある意味実験的で新鮮だが、ちょっと尺が長かったかな。
3篇からなるオムニバスだが、1話目以外は時間的にもやや中途半端感(間延び感)が否めないか。いっそ割り切って、もう少し短めにテンポよく5話編成などでもよかったのでは?というのが個人的感想だった。
睡魔との戦い
相変わらず北欧風のポップなカラーリングと固定カメラの芸術的な構図で魅せていくスタイルのウェス・アンダーソン監督。
同じく睡魔を呼びよせるスウェーデンの名匠ロイ・アンダーソン監督の親戚かと思いきや全然違って、ガッツリアメリカハリウッドの監督でした。
映画の構成が雑誌の構成そのものになっていて、3つの特集記事をそれぞれ担当する記者の目線の三幕構成になっているのは面白いと思った。
第一章のベニチオ・デルトロ演じる囚人アーティストはハマり役だったし、美しい裸体を曝け出すヴィーナスことレア・セドゥさんも素晴らしい。
結局、抽象画の中からヴィーナスを見出せるかどうか、画商のプライドと囚人の皮肉がぶつかる。コミカルな幕開け。肝心の記者が誰だったかもうすでに分からなくなっている笑
第二章はティモシー・シャラメ君演じる学生運動団体と、彼の声明文を代筆するフランシス・マグドーマン演じる記者の話。仕事一筋の彼女がシャラメ君に惚れてしまい、声明文が恋文に。そして学生団体と権力側がチェスで争うというぶっ飛んだ世界観。瞼が重くなってくる。
第三章。誘拐劇。金が掛かりそうなカーチェイスシーンがアニメになっていた。半分寝ていたので何が起こっていたのかはさっぱり分からない笑
最終章。リーダー的なおっちゃんの死。あれ?編集長が死んで始まらなかったっけ?彼が編集長?あれ?誰?
混乱。
そしてエンディング。
終劇。
ティルダ・スウィントン、ウィリアム・デフォーが出演していたことを知る。
おもちゃ箱のような世界
整然と構成された構図と幾何学的なカメラワーク、ポップでパステル調な色彩設計、飄々とした表情の人物たち、シュールでシニカルな事象。正にW・アンダーソンにしか作りだせない世界観が構築されている。
物語は「フレンチ・ディスパッチ」の編集部に集う人々の日常を起点に、彼らが書く原稿を再現した劇中劇で構成されている。編集部のシーンは軽めの描写に終始し、本作のメインとなるのは再現ドラマの方である。
序盤に紹介される自転車のレポートをプロローグとして、全部で3つのエピソードが登場してくる。
1話目は、殺人罪で収監された画家と美術商、絵のモデルとなった女性看守の物語である。いわゆる現代アートとは何ぞや?という皮肉が込められているような物語で、そこをW・アンダーソンが持ち前のアーティスティックな感性で描いている所が面白い。モノクロとカラーを使い分けた映像も刺激的である。
2話目は、学生運動のリーダーと彼に恋する女性活動家、それを取材する記者の愛憎渦巻く関係を描いたロマンス劇である。記者の実体験という形で書かれる逸話だが、明らかに”五月革命”を想起させるあたりが興味深い。W・アンダーソンは当時の闘争を茶化すかのように軽妙に描きながら、革命は所詮「夢」に過ぎなかったということをメルヘンチックに描いている。
また、当時のフランス映画界と言えばヌーベルヴァーグである。これまでW・アンダーソン作品でそれを意識したことはなかったが、今回のこのエピソードにはそれが強く感じられた。例えば、バスタブに入って煙草を咥えながらメモを書く活動家リーダーは、ジャン=リュック・ゴダールの「気狂いピエロ」のジャン=ポール・ベルモンドを連想させた。あるいは、彼に恋する女性活動家のコケティッシュな造形などはゴダールのミューズ、アンナ・カリーナにどことなく雰囲気が似ている。
3話目は、美食家の警察署長とお抱えシェフが誘拐騒動に巻き込まれるアクション・コメディとなっている。本来であれば凄惨になってもおかしくない話だが、ユーモラスなアニメーションを交えながら屈託なく描いており、これまた唯一無二な快作となっている。
特に、クライマックスとなるカーチェイス・シーンは、過去にも「グランド・ブタペスト・ホテル」で似たようなことをやっていたが、氏のサイレント映画に対する敬愛が感じられた。
それぞれの話には関連性がなく完全に独立しているため、映画全体を通してのテーマやメッセージと言ったものは感じられない。そのため確かに物足りなさも残るが、軽い気持ちで観る分には十分に楽しめるエンタテインメント作に仕上がっている。ヒューマン、ロマンス、コメディ、サスペンス、アクション。様々な要素をまんべんなく盛り込んでいるので、上映時間約100分という短さながら意外に濃密な映画体験をすることが出来た。画面の情報量の多さも特筆すべきで、2度、3度観て楽しめる映画ではないだろうか。
「雑誌」の映画化
中々に長いタイトル、雑誌の表紙のようなポスターに惹かれ遅れながら鑑賞。
中々楽しめた作品でした。アカデミー賞に何部門かノミネートされるのかな?と思いつつ先日の発表を見ていましたが悉く外れており残念。撮影賞あたりはとっても良かったんじゃないかな…
まぁともかく今作とっても斬新な雑誌の映画化ということで、記者の書いたコラムを実写の映像に、4コマ漫画のような絵はアニメにするなど、随所に拘りが感じられて楽しかったです。
ウェス・アンダーソン監督作品は初めて鑑賞しましたが、撮影の仕方が超個性的で驚きました。とにかくキャストを真正面から撮っているシーンが多くて、良い意味で狂ってるな〜!と思いました。真正面からブレずに撮ることによって役者の表情の変化が逐一分かりますし、たまに斜めや横の画角で撮るときに新鮮味を感じられたのも良かったです。
1番面白かったエピソードは「芸術家」のコラムで、現代と過去を行き来しながらテンポよく物語をナレーションベースで進めていく短編です。過去パートではバラバラ殺人だったり、囚人による復讐が行われているなど、文章面ではおっかない事が起きているのですが、割とコミカルに描いているおかげか、そのシーンに特別嫌悪感を覚える事はなく、そんな事があったのか〜と軽く見れてしまうのも今作の面白さの一つだと思います。あと今作、特別な指定とかはなくGのまま公開していますが、女性の役者の方の乳首は丸出しですし、股間部分も遠目とはいえ映っているのにも衝撃的でした。未成年が少し車を運転する映画にはPGをつけるのに、おっぱいぼろーんには何も指定つけない映倫さんに思わず笑ってしまいました。この囚人ながら確かな才能に溢れる人間をコミカルに描くことによって残虐性を見事に中和しているのもお見事でした。他の3篇の映画も面白かったですが、1番印象に残ったのはこの作品でした。
正直、置いてけぼりにされそうなシーンも多々ありましたが、なんとかしがみつく事によって面白さの分かる、そんな尖りまくった作品だなと思いました。監督の過去作もたくさん見てみたいと思い、良い収穫でした。
鑑賞日 2/8
鑑賞時間 15:40〜17:40
座席 G-12
好き好き
画面の中の情報量が多くて これはおかわり確実映画
構成のためかページのボリュームで章の時間も配分されてるのかな
個人的にはレアセドゥとデルトロの所が好きねぇ
キャストが豪華なのにクドくないのは 人によっては薄口に思えちゃうかもな
祖国を去った者、文化を背負い旅をする。
本作はまるでマガジンのページをめくってみていくかのような、
多くの要素とイデオロギー、大量の情報のごった煮を
ものすごいスピードで浴びせられていく映画である。
初見で感じられるのはまずヨーロピアン主義のウェス監督が
前作グランドブダペストホテルの東欧ヨーロッパから
ついに本丸フランスに侵攻したという事、
そして今まで小出しにしてきたやりたいことをすべて凝縮して詰め込んだ
ということが分かる。
その情報量とスピードからなんかよくわからんという評価を下しがちだが、
過去作から一貫して同じテーマが本作にもある。
それは故国(ホーム)を去って文化を背負った人々の話である事。
かくいうウェス監督もテキサス州ヒューストンの生まれでありながら
ヨーロッパの古き良き姿を一貫して描いてきた。
本作は実在する週刊誌ニューヨーカーをモデルにフレンチディスパッチ誌の最終号を映像化したという作品であるが、
文化の担い手がそれを発信し残していく美しさを、ウェス監督が思う存分描いたと言えるだろう。
例えば美術のページの看守シモーヌは移民であることや、ジェフリー・ライトが演じる美食のページのジェフリーライトがふと語る美食をなぜ取り扱うかという点、最後警察署長お抱えの料理人ネスカフィエが大根の毒にやられ死にかけた際に語る言葉、またビルマーレイ演じる編集長もいち早く故国を去っておる点など、アイデンティティのありどころについてを中心に置いている。
グランドブダペストホテルの主人公2人も祖国を去った(追われた)二人だった。
おそらくウェス監督自身がテキサスという土地に、自分の感覚と合わない場所だと感じていたのではと思う。アメリカ南部に位置し、差別が色濃く残り、男臭くカウボーイ色が強い州であるので、ヨーロピアンテイストとは程遠い。
内容。
冒頭述べた通り本作は週刊誌ニューヨーカーをモデルにしたフレンチディスパッチ誌の最終号として描かれる。
内容はオーウェンウィルソンの導入、美術、学生運動、美食で構成される。
マガジンのような作りであるからか、カラー/白黒や画角、アニメーションが人々の感情や場面に応じて切り替わる。
以下各ページを深読み。
・オーウェンウィルソンの導入
フランスの架空の町アンニュイ=シュール=ブラゼを過去と現在で見せたり社会問題を包み隠さず述べる。過去も今もあまり変わっておらず、悪い部分が印象的である。
(文明が進化しても世界が良くなっていないことのメッセージしている?)
・美術
凶悪犯にして天才画家のモーゼス・ローゼンターラーと、看守にして画家のミューズのシモーヌの話。ジャン・ルノワール監督『素晴らしき放浪者』(1932)をモデルにしているページだが、デルトロは画商から無理やり商業の為の絵を描かされ、最終的に刑務所の壁に10枚の絵を完成させる。昨今ブロックチェーンをベースにしたNFTアートやインスタグラム等デジタル上に存在する写真やアート、サブスクリプションに代表されるデジタル上の音楽サービス等実体のないアートの媒体の変化を揶揄しているように感じられた。
・学生運動
シャラメ演じる学生運動のリーダー、フランシスマクドーナンド演じる中立の記者のフランス五月革命の話。学生運動そのものは何を皆争っているのか本質は深く述べられていないが、若者がエネルギッシュに戦っている。(実際はベトナム戦争を発端とした大学教育改革に対する大規模な抗議活動)
議論の為に議論をするというセリフがあるように、我々がコロナ渦で出来ていた対面で熱く何かを語り合い議論するという事のすばらしさがあると思う。
またマクドーナンド演じる独身女性が仕事に生きる事を良い事として述べている点は女性のこれからのベーシックとして強調していると言える。
・美食
ジェフリーライト演じる警官兼貴社がリス料理家ネスカフィエを取材しようとすると所長の息子が誘拐される話。
人種差別問題は各国でいまだに残る問題としてあり、外国人は現地人の何倍も努力してその地位を手にするという事を述べている。なぜ体を張って毒を食べたのかという問いに対し、ネスカフィエが「失望されたくなかった」と答えるのが強く悲しいメッセージだった。
全編を通して感じられるのはバラバラのパーツ(人種、性別、年代)を一つにする、実体のあるマガジンを皆で議論しながら熱意をもって取り組むことのすばらしさ、そして昨今其れが薄れていってしまう嘆きをウェスアンダーソンは語っていたと感じられた。
見終わってから、レコード屋で友人とあれやこれやと語り合いながらジャケ買いをしたくなった。
今シーズン観るべき映画のひとつ
難点は字幕だってことくらい。
画面のあちこちでいろんなことが起こってて字幕見る暇ないんだもん。だからって吹き替えならいいってもんでも無いだろうから語学力のなさを嘆くしかない。
スクウェアの画角で繰り広げられるストップモーション、ロマンス、コメディ、気がつきゃアニメよ。
ハートフルに締め。
レア・セドゥは間違いなくミューズだし、ティモシー・シャラメの色気とシアーシャ・ローナンの青い瞳にやられる。
あ、あと観に行った人友達たちが、一章寝ちゃったとか、二章で寝ちゃったとか、人ごとに違ってて趣味嗜好も分かる映画やったね。
独特なユーモアを織り交ぜた物語
映像自体の描写それぞれが1枚の絵の様な雰囲気とユーモアを醸し出してます。
この映画、独立した物語(短編)を雑誌に載せる記事という括りでまとめ、その上その雑誌の編集者を描く二重構造を取ってる点はかなり工夫されてて面白いです。
またダークなお話もこの監督が持ってるユーモアのセンスによりマイルドに中和され、どこか親しみを感じます。
ただ好みが分かれる作品でもあるも思います。
編集長を追悼する映画
映画冒頭で宣言された通りの追悼映画。
編集長が亡くなって、あんなこともあったねぇと回想する記者たちに混ざったかのような。編集長の人柄を思い温かく切ない気持ちになった。
追悼としては、3つ目のエピソードが重要だった。鶏小屋から好待遇で助けてくれた編集長。
脳内ドックイヤーなど、おもろい言い回しも3つ目のエピソードが1番かな。
1つ目はアートの話。
2つ目は学生運動の話。記者の寂しさにぎくっとした笑「僕も君が初めて。彼女を除いてね」に隣の席の人がふふってしてたなあ。
ウェスアンダーソン監督作品は役者の演技まで明らかにウェスアンダーソン監督とわかる。エンドロールまでこだわりを感じる、ウェスアンダーソン作品でした。
追記:グランドブダペストホテルのように刺客に追われたり脱獄したりずっと続く緊張感はなく、本を読むような感覚。雑誌の映画だもんな。
映画のinstallation
ウェス・アンダーソン節前回で、アニメーションよりも此方の方が色濃い。とはいえ、今作もラスト前はアニメを挿入しているので表現方法の多様性を模索しているのも印象深い。
レア・セドゥー、リナ・クードリ、シアーシャ・ローナン等、惜しげもなく女性美を表現していても、決して官能性を押し出すでもない表現は、それでも観客に対して否が応でも釘付けになる美しさを与えている点も見逃せない。
ストーリー的には2番目が面白かった。
監督的には3番目が推しなのかもしれない。フランスで東洋人といったら、レオナール・フジタと直ぐにインスピレーションが湧くが、ネスカフィエは正に風貌通りのところもニヤつくw
映画と言うよりアートとして鑑賞することに意味のある作品である
活字→映像という娯楽への移り変わり
情報量の多いウェスアンダーソンの映画。字幕もはやいし、映像美に見惚れていると字幕を見逃してしまうから、一回見ただけでは理解しきれず、誤読をしていそうだけれども、
映画全体の構造が、フレンチディスパッチ誌の編集長の追悼号(最終号)を最初のページから最後のページまで、映像化したものになっている。
フレンチディスパッチ誌はおそらく普通の総合雑誌で、いたって真面目な記事の筈なのだけれども、死んだ編集長が書き手を甘やかしすぎて、元々個性派のライターたちがもう好き勝手にたのしく記事を書いていて、他の雑誌ではないような奇想天外な内容になっているのだと思われる、
活字というのは、読む人によって、多様な解釈や多様な想像(イメージ化)がなされるから、それが、ウェスの映画では、コラージュ風になったり、ストップモーションの映像になったり、アニメーションになったりするといったように表象されるのだと思う。
映画を見終わったあとに、ああそうだ、活字って、ほんとうはイメージが無限に広がるもので、読む人の数だけそれぞれのイメージが存在するんだった、ってなんだか感動してしまった。
現在はゲームの世界が3Dになったり、スマホで娯楽は事足りてしまうけれど、昔は、活字こそが、世界の人々を楽しませていたのだなと、改めて思う。だけれども、フレンチディスパッチ誌は、編集長の死とともに、廃刊になってしまう。活字を愛した人の死が、活字のおもしろさが廃れて、ほかの娯楽にすり替わっていくその様を表しているように思う。現に、この映画では、活字が「イメージという映像」で表現されているのだから。
ウェスの映画は、ひとつひとつのシーンをポスターにしてしまいたいくらい、ほんとうにかわいい、序盤のウェイターのところ、かわいい建物たち、色使い、料理のシーン、逃亡劇がアニメーションになるシーン。全て可愛いのに、あまあますぎないのは、わりとテーマに設定しているものたちが重かったりするから。バランスが絶妙なの。何度でも見たい、ウェスアンダーソンの作品でいちばん好きだと思った。
この映画は、ウェスアンダーソンかもしれない、ひとりの活字の読み手が、活字を読んだ時に引き起こしたイメージをそのまま映像にしようと試みた作品なのかもしれない。
青い瞳に魅せられた
この作品、面白かったて書くとスノビッシュと思われないか、面白くなかったて言うと馬鹿にされないか、気になって評価しづらい。
好きではある。
昔、トムとジェリーの間にこんなテイストの漫画あったな。男の一生を足早に紹介するような。
絵も俳優陣も贅沢で、遊び心満載。オモチャ箱のような作品だけど、字幕読んでる間にどんどん進んでっちゃうから、忙しい。
何度も繰り返し観たら、観るたびに面白い作品だろうけども、ストーリー重視で感動したい派の、残された時間の限られた年寄りにはそんな余裕がない。
2本立て(もうないか)の幕間に少しずつ観たい。
ティモシー・シャラメ目当てか、女の人たくさんいたけどシーンとしてた。
クスクス笑いながら観る作品なんだろうけどね。いっそ吹き替えにしてくれたら良かったかも。
それにしても青い瞳の美しかったこと。
タイトルなし(ネタバレ)
独特の世界観、キャラクター。ウェス・アンダーソン監督の持ち味がこれでもかと盛り込まれた作品。
好みは分かれるが、趣味が合えばブッ刺さること間違いない美術や服飾にニヤニヤが止まらなかった。ただ難点を挙げるなら、画面の情報量が多すぎて字幕を読めない。字幕を読もうとすると画面が追えない。複数回視聴確定の本作である。
白黒パートとカラーパートが次々と入れ替わるので、本当の雑誌を読んでいるような錯覚を覚えた。映画では初めての体験だった。
【ウェス・アンダーソン監督ならではの、シンメトリックワールドに只管に浸る作品。モノクロ、カラー、アニメーションの使い分けも面白い。ウェス組常連俳優、初登場の大物俳優など多数の俳優も出演しています。】
ー 米紙がフランスで発行する人気雑誌「フレンチ・ディスパッチ」。
名物編集長(ウェス組大常連のビル・マーレイ)が急死し、遺言により廃刊が決定する。
そして、編集長に育てられた海千山千の記者たちによる、最終号にして追悼号を飾る企画が、シンメトリックな画を中心にモノクロ、カラー、アニメーションを交えた映像で展開されるのである。-
◆感想
・劇中劇が三作、描かれる。
#1 “確固たる名作”
まさかの、ベネチオ・デル・トロが囚人として、ウェス・アンダーソン作品に初登場。
看守のシモーヌ(レア・セドゥ)をモデルに、油絵を描くモーゼス。
- 驚いたのは、レア・セドゥがフルヌードでモデルになるシーンである。又、二人の関係性も面白き短編。
#2 ”宣言書の改訂”
これまた、まさかのティモシー・シャラメが初登場。
学生運動のリーダーを、演じている。
#3 ”警察署長の食事室”
マチュー・アマルリック扮する警察署長の一人息子が誘拐されて・・。
・ウェス組大常連のビル・マーレイを筆頭に、オーウェン・ウィルソン、ティルダ・スイントン、エイドリアン・ブロディ、フランシス・マクドーマンド、エドワード・ノートン、「グランド・ブタペスト・ホテル」で一気にスターダムを駆け上がったシアーシャ・ローニャン・・。ウィレム・デフォーという、常連組も大集合。
クリストフ・ヴァルツも何気に顔を出していて・・。皆、好きなんだなあ、ウェス・アンダーソン監督作品が。
<今作は、様々な人物から、影響を受けているようで、パンフレットを読むのが今から楽しみである。細かい部分は気にせずに、ウェス・アンダーソン監督ならではの、シンメトリックワールドを楽しみたい作品である。>
The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun
・こういうシュールでおしゃな映画を楽しめたら自分もおしゃだな、という憧れを持った(-1)
・セリフが早くて多いから英語がスラスラ読み聞きできればもっと面白いはず(-1)
・という上2つの理由でウトウトしてしまった(-1)
・記憶に残ったのはアニメーションの大男に笑ったのと、レア・セドゥの裸(+1)
・出演者が豪華 ↓(+1)
ベニチオ・デル・トロ
エイドリアン・ブロディ
フランシス・マクドーマンド
ティルダ・スウィントン
レア・セドゥ
オーウェン・ウィルソン
マチュー・アマルリック
ビル・マーレイ
全16件を表示