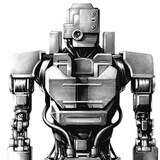シン・ウルトラマンのレビュー・感想・評価
全1267件中、441~460件目を表示
カットの数は邦画史上屈指で……
最初は斬新なショットの連続に魅了されました。然し、カット割りのタイミングが、登場人物達が台詞を喋る度であることが多いことに気づくと、微笑ましい気持ちになりました。アニメみたい。
そして、カットが割られる度に視線の移動を強いられ、(実写版キャシャーンかよ)と心の中でツッコミを入れてしまいました。
幼児の時、再放送されたウルトラマンのエピソードで、巨大化したフジ隊員に何故か性的興奮を覚えた老人としては、長澤まさみさんが巨大化したシーンが観れて大変、うれしかったです。ブルーシートに覆われてる長澤さん、ウルトラマンに蹴り上げられて手足をバタバタさせ、びっくり顔でカメラに迫って来る長澤さん。とてもチャーミングに撮られており、印象に残りました。
いろんなカイジュウや星人が登場して、ストーリーもスピーディーに進んで行き、CGも巧く出来ていたと感じました(担当したのが『白組』だとエンドロールで知り、描画の独特なクセが無くなっているのに感心しました)。
では、なんでこの評価なのかと云うと、クライマックスシーンの盛り上がりの欠如!!これに付きます。エモくないのです。ちっとも。エンドロールで流れるJPOPも、ファンの方には申し訳ないのですが、扇情的要素が一切無く、ありきたりなリリックで紡がれるメロディラインには、魂を鼓舞されませんでした。まぁ、老人の感想なので多めに見てください。
最後に、台詞の中にやたらと理論物理学のジャーゴンが出てきますが、ブレーンワールドもマルチバースも現時点では仮説に過ぎませんのでアナクロ化する可能性が高いと思いました。
因みに、匂いは数値化出来ます!
字幕を付けてくれ!
自分のウルトラマンの知識はほぼ皆無です。(スペシウム光線、3分だけしか戦えない、、、くらい)
この映画で初めてまともにウルトラマンを観ました。庵野秀明作品なので、シン・ゴジラは見ていたし、期待していました。
結果は期待を大きく上回り、映像的に面白いなぁと満足しました。
しかし、自分のウルトラマンの知識が無い事で、ファンの方がニヤリとするシーンだろう場面とセリフが分からない。また自身のそもそもの学歴が低い為か知識が足りない為か、何を言ってるかサッパリ分からん!恐らくこういう事だろうと考えながら見る場面が多々ありました。
字幕を付けてくれればもう少し分かったかもなぁと思いました。
あと分からない事だらけだったのて、初代ウルトラマン
を見直そうかと思えたのは逆に良かったのかも。
とにかく字幕を付けてくれ!
星4なのは、CGがCGと分かるのが気になったので…。
ツボにハマったw
いや〜面白かった!
ウルトラマンは子どもの頃見た記憶はあるけど、内容は全く覚えていないので、ほぼ初見、特撮も特に興味はない状態での鑑賞だったけど、なんか昔の特撮を取り入れてる感じとか、逆に新鮮で楽しめた。
笑っちゃいけないんだろうけど、ウルトラマンの戦闘シーンのクルクル攻撃やひたすら固定して飛ぶ感じ、ブラックホール?に吸い込まれる所とか、つい動きが面白くて一人でニヤニヤしていた。
状況でもウルトラマンとメフィラス星人が居酒屋で酒飲んで地球侵略の話を真面目に語ってたり(割り勘とかw)、神永と浅見の噛み合わない会話とか、やけに礼儀正しい外星人とか、個人的にも面白く、分かっててやってるお遊びみたいな昭和感がとても楽しめた。
映画としてはもう少しウルトラマンの地球に執着する動機的な所の掘り下げが欲しかったかなぁとも思ったり、怪獣の出現の原理などももっとあっても大人は楽しめたかも。
最後は人類に託す感じで終わったけど、実際は守るウルトラマンもいないし、全宇宙の外星人に標的にされてる感じを見ると、その後の地球の行く末はかなり心配かな。
何はともあれ意外な面白さにハマってしまったので、また考察動画など見て、見識を深めてから2回目行くかもしれません。
2時間ならこれが限界かな
ピンチと肉弾戦成分薄めの「半神」の如きウルトラマンは、庵野の自己投影なのか?
庵野/樋口の特撮シリーズってのは、正直けっこう「ずるい」(笑)作りの客寄せホイホイだ。
現代に生きるオタクでおそらく一番偉い人が、日本を代表する特撮コンテンツを題材に、昔から脳内で培ってきた「僕の考えた最強の●●」を、満を持して発表します、と訊いてスルーできる人間は少ない。まして、シン・エヴァを完結させた庵野がこれから手掛ける仕事には、彼の人生の「総まとめ感」が漂っている。
要するに、このシリーズは、面白いとか面白くないとかの次元を超えて、「まずは観ておかなければならない」マスト感が只事ではない。
封切り前から、その内容いかんにかかわらず、この映画は「勝つ」ことを運命づけられているのだ。
逆にいえば、単なる個人的な「評論行為」を「エンタメ」にまで昇華できる庵野(および実作代行者の樋口)という人は、やはり凄いと思う。
もちろん、「庵野にとっての究極のウルトラマン」の披露は、幼少時(もしくは青春時代)にウルトラマンに接し、それに耽溺した多くの人間にとっての「ウルトラマン」の私的なイデアとのぶつかり合いになる。
誰しもが、心の奥底に持っている、自分だけの「ウルトラマン」。庵野の研究発表を前にすれば、観る者は必然的に「彼のウルトラマン」と「僕のウルトラマン」を突き合わせざるを得ない。「シン・シリーズ」とは、そういう「答え合わせ」の要素を生得的に宿している。
結論から言えば、庵野(と樋口)の呈示した「ウルトラマン」は、僕が私的に思っていた「ウルトラマン」よりも、ずいぶんと「潔癖」で「健康的」で「概念的」な、「健全」なウルトラマンだった。より正確に言えば、「人間くささ」よりは「半神性」を、より前面に押し出した「英雄的な」ウルトラマンだった。
もちろん、次々と襲来する使徒1号、使徒2号みたいな「禍威獣」と、奇妙な起動とぎこちない動きを見せつつ、ときどき「色の変わる」、得体の知れないウルトラマンというのが、びっくりするほどにそのまんま『エヴァ』みたいだというのは、僕も当然思った。ああ、『エヴァ』ってのはロボットアニメだったからその印象が薄いけど、もともとは大学時代に『帰ってきたウルトラマン』の同人映画を自作自演で創っていた庵野からすれば、まるっと「ウルトラマン」オマージュそのものだったんだなあ、と。
だが、『エヴァ』と『ウルトラマン』の比較論に関しては、僕なんかより詳しい『エヴァ』ファンの方がたくさんいらっしゃるだろうし、そういった皆さんにぜひおまかせしたい。
僕がここで触れておきたいのは、僕の、個人的な「ウルトラマン」観だ。
ちょっと気持ちの悪い話かもしれないので、あらかじめお詫びしておく。
幼少時の僕にとって、ウルトラマンは、なぜか性的な興奮と直結していた。
性的には未分化だが性欲はすでに充分に強かった4歳~5歳児の僕は、タロウやエースがボッコボコにされるたびに、不思議なことにギンギンに怒張していた。ヒーローが痛めつけられることに猛烈に興奮していたのだ。たまにウルトラ兄弟が殉職すると、それはもう強烈なカタルシスに襲われた。逆に、ヒーローが順当に勝つと退屈で仕方がなかった。
小学校にあがると、僕の性的興奮の対象は『大江戸捜査網』の梶芽衣子や『江戸を斬る』の松坂慶子のヒロピンに移行することになるが、それでも僕にとってウルトラマンは原初的なエロスと直結したキャラクターであることに変わりはない。
その理由はおそらくはっきりしている。
日本の特撮ヒーローのなかでも、ウルトラマンほどに「ピンチ」を際立たせて作られたヒーローはいなかったからだ。
圧倒的なスペックと、それに反しての「活動時間制限」と、その象徴としての「カラータイマー」。
ショッカーのような雑魚キャラとの殺陣が存在しない、裸と獣の絡まり合う一対一の肉弾戦で、出だしは優勢だが、必ず中盤で「ピンチ」が訪れる。さらにはタイムアップが迫り、ヒーローにとってはぎりぎりの闘いが繰り広げられる。そこで、必殺技が出て大逆転勝利。ここまでがひとセット。
ウルトラマンにおける子供たちの「はらはらドキドキ」を喚起する中核は、無敵の「強さ」というよりは、むしろベイビーフェイス的な「弱さ」だったのではないか。強すぎる「なろう」的な「マシズム」よりは、弱さを併せ持つ「マゾヒズム」が少年の心を揺らしていたのではないか。その意味では、等身大ヒーロー系でいえば、「イナズマン」や「キカイダー」に近い、「やられ方にそそられる」要素が強かったのではないか。そこが、僕の内なる「ヒロピン」属性に響いたのではないか。
もう少し、僕の個人的性癖より普遍的な話に敷衍すると、ウルトラマンは、間違いなく「プロレス」を祖型としている。
これは、東映系のライダーや戦隊モノが「時代劇」を祖型としているのとは、とても対照的だ(あっちは、雑魚戦闘員による「殺陣」をこなしてから、メイン武者の一騎打ちがあって、成敗という典型的な「チャンバラ」の構図を援用している)。
そして、プロレスのもたらす熱狂は、そもそもそのホモソーシャルな外見につい騙されがちだが、実はセックスとのアナロジーによって説明され得る、と僕は常々考えている。要するに、裸どうしの人間がくんずほぐれつして、最初は軽いジャブ(前戯)から入って、しだいに大技の応酬になり、お互いがくたくたになってきたところで「フィニッシュ」して大層気持ちいい、という構造上のアナロジーだ。この興奮を喚起する物語構造は、いわゆる他の「格闘技」のもたらす興奮とは大きく異なっている。プロレスだけが、セックスのまねびとしての(ちょうど性的に無毒化されたワクチンのような)擬似興奮作用を有している。
で、ウルトラマンが「プロレス」を祖型とする以上、ヒーローと怪獣の息を詰めたような(あたりに破壊の限りをもたらす規模の)究極の「肉弾戦」もまた、セックスのアナロジーとしての解釈が可能だ、というのが、つまるところ僕の「ウルトラマン」観だ。
といった話を5歳くらい年上の会社のSFマニアの先輩にすると、「それは君がタロウやエースの再放送をメインで観ていたからそう思うのだ」「ウルトラマンがボコボコにされて特訓して鍛え直したりする流れは新マン以降の付け加えだ」「最初のウルトラマンはもっと『強い』キャラクターだったはずだ」などと、いろいろ諭されてしまったんだが(笑)。
で、この長い前置きを前提に、『シン・ウルトラマン』を観てみると、少なくともここでのウルトラマンが、そういった「ピンチで」「やられる」「肉弾戦の」「プロレス的な」一連の方向性とは、ほぼ対極に位置する存在であることが痛感させられる。
要するに、庵野(と樋口)は僕が幼少時に受容していたウルトラマンの「らしさ」を、ほぼ完全に「スルー」した形で、自らのウルトラマン像を再構築しているのだ。
本作のウルトラマンには、ピンチらしいピンチがない。
敵はドリル怪獣ガボラを筆頭にかなり強い印象を与えるが、そう苦戦しているという感じもしない。
結構な余力を残して、相手を制圧している。
何より、このウルトラマンにはカラータイマーがない。
すなわち、時間制限という最大の「弱点」が克服されている。
正確には、消耗が激しく活動限界があるという話はきちんと作中で成されるのだが、それをカラータイマーという形で「誇示」し、第三者に「見える化」することを敢えて辞めている。
庵野/樋口が描こうとするウルトラマンは、もっと崇高で、もっと半神的な存在だ。
地面に這いつくばりながら、怪獣とのプロレスショーを人間に見せてくれる泥臭い一面より、「人間より圧倒的に高度な文明からやってきた絶対的上位者」としての一面の方を、常に強調して作られている。
『涼宮ハルヒの憂鬱』の長門のように、辞書をぺらりぺらりと読み続けるウルトラマン。
地球人の流儀を「実に面白い」とか、おおよそ上からの外星人目線で評価するウルトラマン。
ザラブやメフィラスと、下等な人類の生殺与奪をほぼ握る「神」の目線で、人類の未来についてディスカッションするウルトラマン。
本作のウルトラマンはあくまで、「外星人」であり、「上位者」であり、ほぼほぼ神様に近い存在である。そのぎこちなさや、得体の知れなさも含めて、「戦闘ヒーロー」というよりは、「友好的宇宙人」の側面が強調されている。
ラストのゼットン戦にしても、同身長の怪獣に惨殺される元版の衝撃と比べれば、横スクロールシューティングゲーのボスキャラみたいな巨大要塞に特攻して墜落する流れは、「痛みを伴わず」「なぶり殺しの怖さがなく」「そもそも殺されていない」。
要するに、このウルトラマンには、生臭さがないのだ。
肩で息をしながら、ボロボロになって闘って、痛みの実感を伝えてくるよりは、
とても、強くて、正しくて、でも無機的で、得体の知れない、知的で健全な存在。
なんだろう? こういう言い方をすると語弊があるかもしれないが、「アスペルガーの神様」っていうのかなあ。
アスペっぽい挙動がマイナス査定されずに、逆に人間を超越する存在の証として前向きに評価されている幸せな世界軸で、逆に「人間を愛してる」とか言っちゃってみせる偉大な存在というか。
もしかすると、庵野は、ウルトラマンという「人と異なる存在」に、「オタク」というアウトサイダーとして生きる自らを仮託しているのかもしれない。
そして、なぜ自分が人と異なるかといえば、それは「人より自分が高次元の存在だから」と、その全てを肯定しちゃいたいという庵野の内的欲求がおのずと現れた結果なのかもしれない。
自分のウルトラマンと庵野のウルトラマンの「ズレ」は当然興味深かったが、「ズレ」ているがゆえにハマり切れなかったのも確かで、その辺が星評価にもつながっている。
さて、中盤でどうでもいいことを書きすぎて、紙幅が尽きてしまった(笑)。
1点だけ、冒頭あたりの長澤まさみの撮り方が窃視的って意見があるみたいだけど、むしろこれって、ダーレン・アロノフスキーが『レスラー』とか『ブラック・スワン』でやってた「尾行撮り」だよね。てか、異常に量の多いカット数とか、窮屈そうなドアップの連続にもアロノフスキーのヒップホップモンタージュっぽい感じがすげえ出てる気がするんだけど、影響関係とか、どうなんだろう。
全体的に、長澤まさみに対してセクハラ的かと言われれば、まあそれはそうなのかもしれないが、最初から言っているとおり、特撮やアニメというのは、性的に未分化な幼児にとっての原初的な性志向と激しく密接に結びついたジャンルであることは間違いないわけで、特撮オマージュで作られた特撮にセクシャルな要素が介入してくるのは、むしろ「当たり前」のことである。
そのセクシャルな内容が、大人の仕事のできる美女(庵野は怒るだろうが、安野モヨコもしくは、安野モヨコの描いた「働きマン」のような女性)を性的対象とした、女体の巨大化だったり、匂いフェチだったり、下からの仰視アングルだったりというのは、むしろ健全すぎて、本当にびっくりするくらいだ(笑)。
少なくとも、少女性や処女性に縛られつづける宮崎駿&新海誠や、ケモ耳フレンズの細田守よりは、よほど「健やかな」フェティシズムだと僕なんかは思うのだが。
追記:この感想を書いてから5日後、売り切れだったパンフの再入荷分があったので買ってきた。
「ネタバレ禁止」との紙帯が巻いてある。外してざっと読んでみた。
まさかの……「庵野」成分ゼロ!
インタビューがないどころか、彼のスタッフ紹介すらどこにもない!
てか、庵野に触れた頁自体、1頁もない! 鷲巣さんや米津くんですら、1頁もあるのに??
「庵野の不在」が帯でバレ禁止にされてる「ネタ」ってオチか??
どうやら、別途販売されている『デザインワークス』のほうに、庵野成分はすべて分けてあるらしいのだが、客にだまってそんなことするか?
これってさすがに詐欺なんじゃないだろうか……「これは樋口の映画」ってことにしたいっていう庵野の意思表示なのかしら。うーむ。なんか釈然としないぜ。
「百聞は一見にしかず」私の好きな言葉です
観るまで不安はなくはなかった。
が、観れば分かる!
期待どおりの面白さだった。
監督補:摩砂雪
副監督:轟木一騎
准監督:尾上克郎
総監修:庵野秀明 / 監督:樋口真嗣
…これ、本当の監督は?
樋口監督が庵野秀明のイメージを職人的に実写化したのかなぁ…とは思うのだが、『シン・ゴジラ』と同様の“庵野組”による布陣は役割分担がよく分からない。
手前に障害物を置く窮屈な構図と、人物を仰角で捉えるエゲツない構図のオンパレード。
イントロダクションの読ませる気がない明朝体テロップ、早口で聞き取り難いセリフ、長澤まさみの尻叩き…と、庵野のオタクぶりが散りばめられている。
いったい、樋口シンジくんの演出はどこだろう?
基本的には原典シリーズの幾つかのエピソードを再構成しているのだが、大筋を崩さない程度のアレンジでありながら、結局は庵野ワールドへ着地させているのだから見事だ。
しかも、物語がトントン進んで心地よい。
究極はゼットンを生物型の最終制圧兵器にしたアイデアだ。つまりは「使徒」だと言ってしまえば簡単だが、いかに庵野の中でエヴァの世界感が確立されたものであるかが解ろうというもの。
ただ、ウルトラマン対ゼットンの闘いは、熾烈な“格闘”であって欲しかった。ウルトラマンシリーズの魅力は、肉弾戦にあると思うから。
付け加えて、ゾフィーの役割の改変はほぼ反則。
成田亨氏の初期デザインに拘ったと聞くが、カラータイマーは置いておくとしても、ウルトラマンの細身のフォルムには違和感がある。テレビシリーズでも数話目でリフォームされた姿は大胸筋が大きく力強さがあった。肉弾戦には体の厚みは必要だ。
原典の設定では、護送中に逃亡したベムラーの追跡にハヤタ隊員を巻き込んで死亡させてしまったウルトラマンが、彼と同化することで生き返らせたのだが、人間の姿の時はあくまでもハヤタだった。
本作では、命を捨てて子供を守った神永シンジ(斎藤工)の行動に興味を持ったウルトラマンが、シンジに身を宿してカトクタイに入り込む。シンジの姿をしていてもウルトラマンなのだ。
また、ハヤタがウルトラマンだったことは誰にも知られずに終わったはずだが、シンジがウルトラマンだと早々に知られたうえに、“ウルトラマンの男”の争奪戦が起きる。
こういうところは大人向けの捻りが効いていて、感心する。
浅見弘子(長澤まさみ)のキャラクターは葛城ミサトに近く、庵野の女性観が反映している。
原典のエピソードで巨大化したアキコ隊員は本物ではなかった(本物は幽閉されていた)と記憶するが、浅見は本当に巨大化させられていた。ブルーシートの中で元に戻った時のセリフが絶妙だ。
浅見はスニーカーで出勤してオフィスでハイヒールに履き替えるが、普通は人目に触れる通勤ではおしゃれをし、勤務場所では楽な格好をするのではないかと思う。
逆の行動をさせて、浅見の合理主義者ぶりを示しているように思う。
「宇宙人」を「外星人」(←この字か?)と言うのは良いが、「禍威獣」という当て字は高架下の壁の落書きみたいで戴けない。「怪獣」で良いと思うのだが、「科特隊」を「隊」ではない怪獣対策の専門室に設定を変えても略称をカトクタイにするためには、“カ”という一文字が欲しかったのだろう。よく考えたな…とは思うが、やっぱり戴けない。
キャスティングが効いている。
長澤まさみがなんと言っても一番良い仕事をしている。男勝りで色っぽく、説得力を持って台詞が吐ける女優は他にいないのではなかろうか。
斎藤工は役者としてはあまり好きではないが、あの無表情が人間の姿でも外星人である設定に合致していた。
島田久作の総理大臣は意外性があって面白い。一方で、ゾフィーの声が山寺宏一なのは安直。
名無しの役人で竹野内豊が出演していたので、長谷川博己のカメオ出演もあればよかったのに。
絶好調!長澤まさみ
絶空調!斎藤工
激ヤバ光線!
マルチバース・・・これは私の好きな言葉です。印象に残る台詞もいっぱいありましたが、ほぼ笑ってしまったために覚えているのメフィラスの山本耕史のみ。忘れっぽくてイヤになってしまいます。
オープニングから凄い!絵の具をぐしゃぐしゃにした逆回転からのウルトラQ、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンへとタイトルが変わる!これはTV版ウルトラマンのオープニングも「ウルトラQ」から「ウルトラマン」へと変わるのと同じ。ずっとウルトラQのテーマ曲が流れているのも驚き。そしてウルトラマンの造形。美しさを強調したあまり、カラータイマーが無い!あぁ、これだ。スペシウム133なる元素についてもね、すごく嬉しかった。あぁ、なるほどね。そういう意味があったんですね。などなど。
数々のオマージュとパロディが組み合わされ、『シン・ゴジラ』のように早口言葉で専門用語をまくしたてる。カイジュウは中身が同じ(使徒っぽい)?これは円谷プロがカイジュウの着ぐるみを使い回していたことのギャグなんでしょうか。
宇宙人を「外星人」と呼ぶのも興味深いし、メフィラスが名刺を差し出したり、皮だけの存在だったのも面白い。長澤まさみが巨大化させられたのもオリジナルと同じです(オリジナルではバルタン星人が化けていた)が、それよりも匂いを嗅いで追跡するシーンが最高!あ~~風呂に入ってないのに~
『大怪獣のあとしまつ』では国防大臣だった岩松了が今作では防災庁大臣。『シンゴジラ』でも『大怪獣のあとしまつ』でも外務大臣だった嶋田久作が今作では総理大臣。微妙に絡んでるんですね。そして最後はゼットンの登場。着ぐるみではなく、『エヴァンゲリオン』に出てくるような動かない奴。敢えてマルチバースというワードを使ったことで、『シン』ユニバースの存在さえ想像させてくれた。ゾフィーは当時の児童誌での混同から着想を得たという存在になっていて、今後のウルトラ兄弟の物語はややこしくなるだろうね。
それにしても諸外国との政治的駆け引きや、簡単に外星人と条約を結んでしまう愚かな政治家達。風刺も含んでいて面白かったけど、ちょっとやり過ぎ感があった。特にアメリカの援助。「空想」と名をつけるのなら、もっと違った設定が良かった気もします。それにしても、禍特対の本部ってオリジナルの科学特捜隊と違って、単なるオフィスみたいでしたね。みんなサラリーマン風だし・・・
映画館リピはないけど円盤で確認したいところはある
ウルトラマンと融合したあとの神永の無表情とか、死んだ神永をみる神永(ウルトラマン)とかドッグタグとかよく考えられてるし、巨大化した女性隊員とかいろいろオマージュを感じるし、外星人もウルトラQ味あるし、巻き戻してみたいシーンも多々あったし、多分特撮映画として良い出来だとは思います。
しかし。ハッピーエンドを求める私にはラストが悲しすぎたし、私が半世紀愛してきたゾフィーを返して。
マニアの予備知識が必要?
1966年の初代ウルトラマンのストーリーと大伴昌司監修 「怪獣ウルトラ図鑑」(1968年)の間違いネタが下敷きになったリブートで随所にマニア泣かせの演出が散りばめられた仕上がりになってます。
巨大生物が街を破壊する政府の対応はエヴァ、シンゴジラと共通してグダグダな組織イズムを描きつつも、異星人を国家がどう扱うかが庵野色が濃く出ています。
もっとあっさりしても良かった。
つまらなかった↓
深いウルトラ愛は感じる、でもセリフ回しはかなりきつい
特撮映画、特に昭和時代の作品への愛は『特撮博物館』で見知ったつもりだった。とりわけウルトラマンの愛は殊更なのも、しかしここまでとは…正直想像を超えた。昭和時代の特撮を現代で大真面目に再現したのを滑稽と取るか敬意と取るか、一応敬意と取ったが巨大化するヒロインはどうしてもシュールでしかなかった。
映画冒頭は怪獣(禍威獣だが馴染みの呼称でいく)と人類による戦いの歴史に始まり、怪獣退治専門組織『禍特隊』創設から現在に至るまでのあらましが描かれ、テンポの良さと掴みバッチリな雰囲気で没入感が凄い。巨神兵の頃からだが本作も劇中曲と効果音は昭和作品のをそのまま使用している、今後も庵野監督の関わる特撮作品ではお約束になるだろう。加えてマニア要素も取り入れており初代ウルトラマン(以下初代)で有名なマスクタイプABC(それぞれ顔の造形が異なる)を本編ウルトラマンで再現、スーツを使いまわして生まれた怪獣が似てしまう点をパシフィックリムの怪獣よろしく生物兵器という位置づけで整合性を付ける等、当時の制作で起きた事情をストーリーにうまい具合に落とし込んで活用している。
この試みは恐らく本作品が初ではないだろうか、エピソードのオマージュはともかく、制作現場で起きた事象を物語に採用するなんて、どんだけ好きなのかと。
もちろん昭和の雰囲気再現もしっかりしてる、宇宙人(外星人だが同上)との対話シーンは国会・公園・居酒屋と、昭和のノリだが違和感はなく面白い構図だった。
ただ怪獣が暴れまわっているにも関わらず被害状況とか一般人の視点が無く、ウルトラマンが大抵どうにかするので緊迫感は感じず、何より会話劇がかなり・・・いや非常にきつかった。専門用語とカッコつけすぎてる台詞はシン・ゴジラでもそうだったが、本作はそれ以上に芝居がかっていて恥ずかしくなった。
小難しい用語も、本編の話そのものには関係なく怪獣の攻撃を理系っぽく解説してるか国際情勢を回りくどく言ってるだけ、本筋は見てれば大体わかるので意味のない難解さだ。結末も大急ぎで締めくくったみたいで初代ウルトラマンの拳を突き上げながらグングン画面に向かってくるあの有名なポーズが出てきても唐突感が強めな印象、ただファンなら堪らないだろう。
以上、本作は面白いのは事実だが大変熱心なファンが大金掛けて制作したファンメイドでもあり初代ネタをありったけ入れたら少々チグハグになりましたといった印象。まぁ【最後のジェダイ】みたいに拗らせすぎて僕の考えた最高の話ではなく、終始初代への敬意を感じる作風だったのは紛れもない事実。
スタイリッシュほどほどの、昭和の雰囲気を残したリブートを想定して制作したのなら本作はとても良く出来ている。
・
・
・
余談だが、出演者には『大怪獣のあとしまつ』に出ていた役者がチラホラ出ていた。同じ特撮映画なのに、愛の差でこうも違うのかと思う一方、ファン過ぎてもそれはそれでバランスを保つのが難しいなと思う、ゴジラへは程々の感情で作っていたからいい感じになったが、仮面ライダーは・・・凄いことになりそうだ。
アクションシーンは中盤あたりがピーク
本作は初代ウルトラマンのリブート作品らしいが
ウルトラマンのことは設定などを知っているくらいで
あまり詳しくないです
個人的に「エヴァンゲリオン」の庵野秀明脚本で
エヴァは好きなので
どのような作品になるのか興味があって見に行きました
ちなみにシンゴジラは見てはいないです
映画で最初に日本に「禍威獣」ドンドンでてきて
それに対抗するため「禍特対」ができる部分が紹介されるが
あんだけ禍威獣がでてきたら、現実だと日本滅びてしまうよなと感じてしまった
最初と2回目の禍威獣は
ウルトラマンによって倒される
ザラブ星人、メフィラス星人らの外星人により
人類をはるかに超えた科学力を見せつけられ
彼らとの交渉を日本は余儀なくされる
そして、ゾーフィが人間を消滅させるために
ゼットン使ってくる
ウルトラマンが一度ゼットンと闘うが
圧倒的な差でまけてしまう
シン・ウルトラマンのゼットンは
巨大でウルトラマンの何倍もあって
そのシーンの絶望感は圧倒的だった
そして、ウルトラマンが残したヒントを人類が活用し
ゼットンをウルトラマンと協力して倒すことで
圧倒的な科学力の差をひっくり返したというのはよかった
アクションシーンについては
メフィラス戦がピークでそれよりあとはアクションシーンは
ほとんどなくなっている
あとは、話の展開がメフィラス星人がでてくるときまで
ちょっと駆け足だなと感じたし
メフィラス星人も途中で闘いをやめて帰っていった
ラストのゼットンとの闘いがあまりにも短かったし
終わり方も唐突な感じがした
それでもウルトラマンを知らない自分でも楽しめる映画だと思った
ウルトラマンと融合する前の主役の神永新二については
ほとんどわからなかったのが気になったが
ウルトラマン全39話を貫く一つの物語
あおる構図とレトロモダン
子供の頃、「帰ってきたウルトラマン」を見て育った。
これは見逃せぬと鑑賞。
まず映像。
新しいのにどこか古い。このバランスが絶妙だった。
物語の展開はかなり早く、矢継ぎ早でみのがしたものも多いと思っているが、
デティールの贅沢さ
(重機に銃器、モブ等人海戦術、ジオラマ&CG混合、小道具、質素だがあんがい仕立てよく見える衣装等)には新しさを、
しかしながらゴチャゴチャさせない淡泊な見せ方にレトロを感じた。
あいまれば子供向けとは言い難い落ち着いたシブさが漂い、
カイジュウが暴れたところで着ぐるみを連想することなく、いい大人ものめり込んで鑑賞できた。
かつ、凝った構図のショット、特に多用される「あおり」アングルがいい。
どのシーンも相当こだわっているように見えたのはわたくしだけか。
空間を魅せる遠近の妙。
心理的効果を狙ったアシンメトリー配置の手練手管。
抜かりなくスタイリッシュだった。
そもそもウルトラマンは大が小に、小が大に見えてしまう錯覚、「特撮」のキングである。
あおりの多様には、そうした放送開始当時へのリスペクトすら感じている。
次に物語。
おそらく「シン・ゴジラ」的なものを期待して鑑賞するだろう観客に
しっかり応えているあたり、優しい。
政治も物理もなかなかハードな語彙と展開が矢継ぎ早ながら
100%理解できずとも、物語にはついて行けるギリギリのラインが
これまた絶妙と感じた。
淡々と進むがあんがいと壮大な事件で、座して死を待つ人類には
リアル世界のいつ第三回目の大戦がはじまっても・・・を過らせ少し寒くなる。
そのほか過去作に登場したエピソードやキャラクターでは、
と思えるものも多く詳しいファンであれば、
焼き直し総集編としてまた違う楽しみ方が出来るのだろうなと感じている。
もうひとつ、印象的だったのは本作における「女性」の撮り方だろう。
うるうる、きらきら、アイドル、アニメ調ではなく、
働くそれでも美しい女性の生々しいリアルさが全面に押し出され、
存在感に圧倒された。
わたしはこの撮り方、洋画に近く、大変好感を持っている。
「大怪獣のあとしまつ」と対にしてみると、似ているが違う点が強調されて、
より双方を楽しめるのでは、とも振り返る。
全1267件中、441~460件目を表示