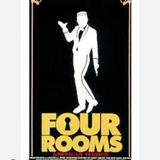シン・ウルトラマンのレビュー・感想・評価
全1268件中、301~320件目を表示
愛すべきリメイクではあります
作品への愛はもちろん、オマージュも随所に。ザラブ星人のパートは涙腺刺激レベル。
IMAXだったので音は凄いしCGも美しい。けど幼少の頃の熱い気持ちが蘇るまではいかない。はい、自分が大人になったからですw
禍特対員たちのキャラ描写が乏しかったかな。誰かに感情移入できていれば。
エンタメとして十分楽しめた。
周りの評判を聞くと子供や若い人には受けているがウルトラマン世代では批判的な人もいるのを聞いていたため、それほど期待せずに見に行ったが面白かった。テーマ性については薄かったと思う(神永は終始人間側に立って戦うという意思を貫いており、その意思は高尚ではあるが彼と彼意外も含めて葛藤や成長を描いていないという意味においてである)。
内容に関して言えば、地球に来た宇宙人であるザラブもメフィラスもゾーフィでさえも地球人の命や尊厳を見下しているというのが示唆的に感じた。地球人とのハーフ的な神永だけが、地球人側に立つことができたことも。とは言いつつも、ザラブもメフィラスも宇宙人が登場するSF映画にありがちな『知性が人間よりも野蛮な宇宙人像』、つまり、貴重な生命体、資源である自分より発展していない人間を無駄に殺す愚かな異星人像ではなかったことには好感が持てた(原作でそうだったのかもしれないが)。
出てくるならば生物として地球上でウルトラマンと相対してプロレスすると思っていたゼットンが実際は光の星の宇宙兵器的なゼットンだった、というのが衝撃的だったし、そのギミックもかっこよかった(そもそも生物なのか兵器なのか知らないが)。二枚のディスクが自律的に自分の構造を巨大兵器仕様に変化させていく描写が面白い。地球の衛生軌道から見下ろすゼットンの描写(遠近法を正確に描写したものか知らないが雲のように白)を見ると、グレンラガンの最終話で似たような展開で空の向こうに巨大な敵グランゼボーマが見える様子を思い出した。
見ていて違和感を感じた部分もある。一つは作戦会議の場所で皆がPCを開いてポチポチしているシーン。一生懸命みんなで大きな問題にあたっていることを表現するシンボリックな表現だと思うが、もっと違う表現方法はないのか。もう一つは、禍特対の人たちが状況を説明するためにかわりばんこにリレーしながら怪獣の進行状況やどうすればいいかを説明するシーン。その説明手法はスピード感があって説得的ではあるがリアリティは無い。もう一つは政府高官が早歩きで視聴者側に向かってあるきながらどう対応するか忙しそうに話すシーン。これもそのシンボリックな意図(問題は切羽詰まっており、それに対して実直に対応している)を視聴者に投げかけるものだが、シン・ゴジラでも見たし、邦画(あまりみないが。例えば踊る大捜査線か?)でも多様される手段で、その使い古された様式はPCぽちぽちシーンと同様に没入感を邪魔する。もっとリアリティのある自然な描写はできないか。そして最後に一つ。それは、浅見弘子さんの特に神永に対して過剰に反発感による感情表現を直接投げかける所にリアリティの無さを感じた。これについては物語の視聴者へのインパクトを強めるために必要な手段だったのかもしれないとも思うが、それでも過剰に感じたのは確かだった。
最後に、米津玄師のM八七は良い曲だと思う。この曲を聞いてこの作品を見てみたいと思った。
ウルトラマンってどんな奴?
いやー、面白かった!
本作最大の特徴はウルトラマン本人が地球人と会話する点だと自分は思う。
元のテレビ版ではウルトラマン本人が自分の意思を口にするのは第一話・ハヤタ隊員との融合時と最終話・ゾフィーとの会話の時だけである。会話時間も僅かだ。人間体の時はハヤタ隊員の意思で動き、ウルトラマン時はウルトラマンの意思となる。
しかし本作は違う。外星人、宇宙人としてウルトラマンが地球人と対話する。そして地球人を理解しようとしている。
庵野さんが学生時代作った自主製作映画、帰ってきたウルトラマンでも庵野さんが(庵野さんの顔で!)ウルトラマンを演じていた。
庵野さんはウルトラマンに変身する人間をやりたいのではない。ウルトラマン本人という宇宙人になりたい人なのだ。
だからウルトラマンが本人の意思を人間の体を通じて話してくれる。
で、そのウルトラマン。人間臭くて良い奴だった。
この映画、とにかくテンポが早い。情報マシマシ、いつもの庵野映画だ。
映画が始まってすぐ怪獣(禍威獣)を見せてくれる。ごたくは良いから早く禍威獣を見たいという欲望を理解してくれている。
この映画、シリーズ第1作のウルトラマンを見ているとより分かりやすい。どこがテレビ版ウルトラマンでどこが違うのか、ちょっと気づいた点を列挙してみた。
まず元のウルトラマンと同じ点
・シンゴジラタイトルからシンウルトラマンへのタイトルクレジット変更(ウルトラQからウルトラマンへの移行と同じ。前作から本作への引き継ぎクレジット)
・ウルトラマン本人のきっかけで命を落とした地球人とウルトラマンが融合する。
・ザラブ星人がウルトラマンを監禁し、ザラブ星人がニセウルトラマンとなり街を破壊する。
・メフィラス星人が地球人の女性を巨大化させて街を破壊する。
・メフィラス星人とウルトラマンの対話、論理のぶつかり合い
・最終怪獣ゼットンに敗北するウルトラマン
・ゼットン撃退を人類の力で行う
・最後のシ者として現れるゾフィー
・ラスト、融合したウルトラマンと地球人の分離
テレビ版ウルトラマンと違う点
・カラータイマーが無い
・ウルトラマンと人間が融合するきっかけが元のテレビ版はハヤタ隊員とウルトラマンの宇宙船の衝突であるのに対し、今回は神永が子供を守った為、命を失った。これはウルトラマンというより帰ってきたウルトラマンである。
・体力が無くなると緑色になるウルトラマン。これも帰ってきたウルトラマン放映時に児童書に記載された設定だ。
・ザラブ星人の身体。着ぐるみの時は3Dだが、平面構成の2D怪獣。現代で無ければ表現できない外星人だった。
・メフィラス星人とウルトラマンの対話が人間体。そしてなんと居酒屋!ウルトラマン、日本酒飲むんだ(笑)そういえばウルトセブンでもセブンとメトロン星人が木像アパートの一室でちゃぶ台を囲んで地球の存亡を掛けた会話をしていた。ザ・ウルトラマンという漫画作品でも帰ってきたウルトラマンが酒飲んでたな…
・ゼットンの起動理由。テレビ版はゼットン星人の地球侵略だったが、今回は光の国側の地球殲滅。
・ゾフィーの体色。
(訂正・ネットの考察を拝見してゾフィーの体色は成田亨氏デザインのウルトラマン神変というウルトラマンのデザインが黒と金色だそう。またゾフィーがゼットンを起動させたのは、テレビ版放映時の児童誌でゾフィーがゾーフィという名前でゼットンを連れてきた敵宇宙人として紹介された誤記かららしい。)
・ゼットン、デカッ!
とりあえず思いつくものを挙げてみた。自分はウルトラマンもそうだが帰ってきたウルトラマンの影響も色濃く受けていると感じる。
また演出上、ウルトラマンをリアルタイムでテレビで見ていたら出会っていただろう映像体験を伝えようともしていると感じた。
まず冒頭5分(ここも情報過多(笑))で登場するウルトラQ(ウルトラマンの前番組)の怪獣達がなんとなくモノトーンな感じなのだ。
モノクロ作品で作られたウルトラQに対し、ウルトラマンはカラー作品。その変化を示すためにモノトーンな画面、色彩を抑えた禍威獣を出したのではないか。
さらにウルトラマンが初めて地球に来た時、体色が灰銀色、口元にシワが寄っている。
これもカラーテレビが無い家庭ではカラー作品のウルトラマンを白黒でしか見れない。
さらにテレビ版序盤の口元にシワが寄ったザラついたマスク造形(ウルトラマンを喋らせようとしたという説がある)を再現しているのでは無いか。
そんなウルトラマンが人間と融合することでカラー作品ウルトラマンが始まる。
何点か疑問点もある。
・一戦目、二戦目の場所、山地が連続してしまうのはちょっと飽きちゃう。
・長澤まさみのセリフ回しがシンゴジラの石原さとみ、アスカ、ミサトと脈々と受け継がれる庵野さんの有能女性セリフ、ちょっとダサい。
・メフィラス星人のベーターボックス、メフィラス星人が出現させた時に掴むんなら匂いで追う必要性あった?
・日本に出現した禍威獣は古代に埋蔵された生物兵器?ちょっと分からない。
・ベーターカプセルの原理が伝わりずらい。
・メフィラス星人とゼットン、まんま使徒
・全体的にちょっと情報過多過ぎて追うのが大変だった。
だけど自分としてはこんなの重箱の隅つつくようなものだった。いやー、本当に面白かった!
多くの人は幼稚園や小学校低学年でウルトラマンを、ヒーローを卒業していく。
しかし、ウルトラマンはなぜ人類の為に戦うのか、どんな変身原理なのか、そしてウルトラマンと話してみたいと50年間本気で思っていた人が作った映画だと思った。
その50年間真剣に考え続けた人物とは勿論、庵野秀明だ。
ウルトラマンにセクハラさせるってどういうこと?
2020年台に日本人は子供向けコンテンツを子供向けに作ることさえできないのか。わざわざウルトラマンにセクハラさせる台本を書ことの意味がわからん。
それとシンゴジラを見た時に石原さとみが演じたカヨコ・アン・パタースンが本当にひどくて、それが石原さとみのせいかと思っていて、今それを石原さとみに本当に謝りたい。あれは石原さとみのせいでなく、書かれた台詞と演出をつけた側の問題だったことを今回長澤まさみを見てわかった。あの不自然な台詞で不自然に演技をする演出するっていうのは一体なんなんだろう。
かいじゅうとのレスリングはもうちょっと長く/多くてもいいかなぁと思った。
人間ドラマはほぼ皆無な代わりに外星人同士の話し合うシーンが盛り込まれてる。観客は人間のことはよくわからないが外星人に対して理解が深まる。ただ戦いシーンのCGはペラペラした感じでいただけなかった。
それと大きな劇場で劇場でしか見れない映像を見たいのにiPhone映像を見るのもなかなか厳しかった。
上がり過ぎた期待値
シンゴジラの成功で今作は期待値が高過ぎましたね
エヴァンゲリオンの出来を考えるとゴジラが奇跡でこんなもんでしょう
しかもゴジラは基本単独の1本映画として出てるものをリメイク
ウルトラマンは極端に言うと全話の中から抜粋して1本にまとめた形です
ぶっちゃけゴジラでうまくいってたのだから2部作とかにしてもなんとかなったのでは?と思う
簡単に内容説明するとしたら
「ウルトラマンをより現実的に」
なんだけど
庵野の性格がよくでてるというか
よくある疑問点とか
ウルトラマンの初期設定とか児童書のマニアックな設定をひろってる感じでした
一番わかりやすいのは
カラータイマーなし
初期デザインではなかったって有名なやつですよね
あとはウルトラマンは全裸なのか
とか
最後しか撃たないスペシウム光線(今作はバンバン撃つ)
とか
ベータカプセルってなんで必要なのか
とか
なんでウルトラマンなのがバレないのか(今作はすぐ全人類レベルでバレる)
とか
色々ありましたね
ゼットン=ゾフィーってたしかなんか適当に描かれてた児童書かなんかに載ってたやつですよね?
ゾーフィとか私にはよくわからない変更もありました
正直この光の国の設定はイマイチだなと私は感じましたし、マルチバースって言葉も今の流行りで無理矢理取ってつけた感があって嫌でした。
また庵野のらしい捻くれなんですが
バルタン星人とかベムラーとかレッドキングとか有名どころは出してきません
庵野らしいといえばらしいのですがちょっと捻くれ過ぎててここもイマイチでした
あともう最初の予告からわかってたのですが
CGが酷いですね
予算が全然違うから仕方ないんですがマーベルなんかを見すぎた我々にはCGがPS5にも負けてるのでは?
レベルでした
とにかく浮いてる
ウルトラマンのスタイルはたしかに人が入るスーツでは無理なのはわかりますが
あのレベルのCGなら怪獣含めてスーツの方が良かった
キャラクターもシンゴジラと同じような人ばかりで
あまり魅力がなく
またこういうキャラかみたいな感じでした
ルー大柴みたいなキャラがいなかっただけマシですかね
とにかく全てがイマイチでした
最後もブツ切りが酷くて
どうせ
「この先は皆さんの想像に」的なあれですよね
庵野もワンパターンですよ
ゴジラと同じ
たぶんこの作品を評価する人はただの庵野信者か庵野の性格的な部分とかも気にならず完全にフラットに観れる人だけでしょう
私は庵野の捻くれ具合等々とゴジラとの被り具合など色々気なってしまいダメでした。
まぁ逆にシン仮面ライダーの期待値が相当下がって良かったかもしれないです
予告の時点で非常にスタイルの悪い足の短い1号
ポーズを取るも中が素人なのか面の向きが全然合ってない2号など不安しかないですからね
とりあえずシンゴジラが奇跡の出来だったのがよくわかりました。
今作は監督は庵野じゃないとツッコミが入りそうですが
作風的にもスタッフロールの庵野登場具合からも実権は庵野だったのは間違いないでしょう
スミマセン,一寸舐めていたかも…⁉︎
最高やんか!
もっとスカッとさせて欲しかった
見事な特撮映画。チープさと高度なCGの共存
シンゴジラみたいな現実世界の延長線の世界を期待していたので、それほど政府やお役人がオタオタする描写や、一般人が逃げ惑う姿などは少なく、そこはちょっと物足りない。しかし別物として観ればこれはこれで良い。
斎藤工の佇まいが美しい。特に山林で神永自身を見つめるウルトラマンが、ゾフィーと語るシーンはグッとくる。
矛盾に満ちた未熟な人間を愛してくれたウルトラマンの想いに、人間も頑張らないと…と思わされる。
特に、外星人の巧みな交渉に振り回されるお役人の姿のあとで。
何でウルトラマンはここまで人間を好きなのか描写が足りないというコメントをレビューで見たけど、
神永が死を賭して子供を助けようとしたこと、バディ浅野や特務隊との友情だけでも、充分ではないか?
ストーリーの説明をいちいちセリフで行っているので、特に論理破綻もなく、あれどういう意味?みたいな、観客に解釈委ねるようなところがないのも良かった。
代わりに説明の長台詞に振り回されて、若手の早見あかりと有岡大貴の役不足感が否めない。
西島秀俊は、「きのう何食べた」の印象が強すぎて、シロさんが出てるみたいだった笑
山本耕史も、同じく、「きのう何食べた」に出ていたが、こちらは演じ分けが見事。
外星人メフィレス役を怪演していた。
最後は、特撮映画と円谷プロ、原作ウルトラマンへの敬意と愛情が良かった。
着ぐるみ感や、ミニチュアフィギュアの不自然な映像が、高度なCGと同居している歪さが良かった。
もう少し面白いと思った
邦画はあまり見ないけど「シン・ゴジラ」が面白かったので見ました。
もっと政治のゴタゴタや権力闘争に巻き込まれ力を発揮できない隊員主軸の話に
なるのかな、と勝手に思っていましたが、そんな感じではなかった。
ウルトラマンが超絶パワーでだいたい解決してくれました。
上記の展開は私の勝手な希望なので採点に影響しないとして、
現代風にリメイクした怪獣特撮映画って感じで新しい感動はなかったです。
心が動かされた
全1268件中、301~320件目を表示