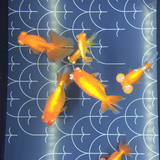ミッドサマーのレビュー・感想・評価
全189件中、121~140件目を表示
素人映画っぼい
絶賛する声、トラウマムービーときいて、
グロもホラーも耐性のあるわたしは喜び勇んでみにいった。
結果からいうと、、不条理系のつまんないやつみたいな感じで、ハズレだった。あまり練られてないシナリオを、いかにも意味ありげ〜に撮ってみた!って感じ。
たいくつなシーンが多すぎる爆睡ムービーでした。
まず、「男の旅行についてきちゃう空気読めない女の子」「いるいるこういう女!」
ってレビューしってたので、さぞかしウザ女がでるんだろなー。って思ってたら、、
その感想のひとたち、、冒頭10分みてないんけ?と呆れた。。
たしかに地味で暗くてメンヘラ気味な彼女だが、ウザいのはどちらかというと子供っぽい男連中じゃん。カレピっぴ大好き♪って感じでついてってねーよ。ダニーの心象風景わからんアスペのレビューなのか、違う映画みてんのかと思った。
んでまあ色々あってしょっぱなからハートが崩壊寸前な、暗い女の子ダニーの心象風景ままに、ストーリーが進む感じ。
「終始光に溢れて明るいシーンで怖さを表現してるのがすごい!」
ってレビューもきいてたんだけど、、これも、どこが??って思ってしまった。
輝度明度でいうなら確かに昼間だったり白夜に近く夜も明るいわな。
でもずーーーっと作中、いやな感じ、いかにも怪しい雰囲気が漂っててとてもアッパーな感じはうけない。
夏至祭はあるけど村入る前からみんなクスリきめてるし、よくわからん遠い地の怪しい儀式?が続いて、におわせもあり、漂うのはダウナーな印象ばかりだ。
ステキな村に優しいひとびと♪たのしいたのしいお祭りだーー♪♪って純粋に楽しんでるキャラもいないしね。
まあそれもいいとして、ウリであろう、衝撃?シーンも、、ふーーん、、その程度?あ、いやもっとみせろ!
って感じで物足りない。。バイオハザードやサイレントヒルの方がよっぽどグロい。
っていうか畳み掛ける展開もないから、時々意識とびかけるほど眠くなる。
主演の女の子の低い声はすきだった。
以上。観て疲れるだけでおもしろくも怖くもなかったー。残念。
予想してた内容と違ったが、それよりGOOD
予告編を見た段階では、
「若者たちがあるコミュニティに入る。最初は快適だったが、次第にその闇・狂気を知り、逃げ出そうとする…」って話だと思った。
(どっかで見た話だな。「ザ・ビーチ」ってこんな感じだっけ?)
良い意味で予想を裏切られた。
このコミュニティはカルト宗教を思わせるが、そういった特殊なモノに限定すべきでなく、(程度の差はあるが)どんな「組織」でも似たようなコトはあるのでは?
国家、会社、地域社会、学校、そして家族。
どんな組織であれ、合理的でない習慣、意味不明な習慣があるが、それに疑問も持たず生きている。
前半の自殺シーンはかなりビビるけど、
日本でもちょい前まで、「切腹」が美徳とされていて、トドメをさす人間もいた。本作とどう違う?
主人公の彼氏は常にラリってる状態だけど
(風景が常にユラユラしてる。お茶にドラッグが混じってる?)
酒だってある意味「ドラッグ」だし、ソマリア(?)のように、そういう植物を日常的に摂取する民族もある。
「自ら生贄にはならないだろう」と言うかもしれない。
でも、「自己犠牲」は最高に尊敬される行動だ。
それは自爆テロだけでなく、戦争はもちろん、子供向けのアニメでも同様(映画「シュガーラッシュ」参照)
女王になったのも、出来レースだったろうし、
彼女に彼氏のSEXを目撃させるのも同様。
SEXに至る過程にしても、「恋愛」が普通とは言えない。日本でもちょい前まで、親同士が決めた相手と結婚するのが普通だったし、今でもそういう国・民族はある。(映画「ビッグ・シック」参照)
主人公は彼らの一員となり、満足そうな笑みを浮かべる。
今まで自らが所属してきた「組織」から浮いていた彼女が初めて受け入れられた瞬間だ。
必要以上にグロい映画だけど、
自分が所属する組織とか、客観的になることとか、いろんな示唆に富む作品だと思う。
何が不快かというと…
いやはや不快感の玉手箱とでもいうべきキテレツ映画であった。
今日からはディレクターズカットも封切りなようだが、もう観る気にはなれない。
映像も、役者の演技も、音響も、とにかくこれでもかこれでもかと観る者の神経を逆撫でする。
鑑賞者の多くは、このような感じ方をしたのではないか。
ただ、鑑賞後、時間を経て熟考してみれば、舞台となった架空の村ホルガの自然観や死生観は、決して奇異でも異常でもないことに思い至る。
しばらく飼われていたであろう檻の中の熊が、終盤で解体されるくだりは、アイヌのイヨマンテの儀式に酷似していた。
死を、魂を現世から解き放ち、次の生につなげる重要な通過儀礼とする解釈も、アイヌほかたくさんの民族に共通する思想が存在している。
やや過激な崖やハンマーの活用場面はあるものの、古くからの因習を大切に保持した、今となってはかなり稀有な民族だと見ることもできる。
ホルガに訪れたダニーたち異国からの訪問者は、村の祝祭で目にするもの全てに対し、嫌悪し、嘔吐し、激怒し、研究材料として搾取し、愚弄する。
彼ら異国からの来訪者のマジョリティ然とした振る舞いが、徹底的にこの村の習慣や人々を異化し、異質性を強調する。
村が一つのカルト集団に見えるのは、観ている側が、異国からの来訪者の視点を取らざるを得ないがためではないか。
マイノリティに対し違和感と不快感の眼鏡を与えたこの作品の視点自体が、実は不快感の源泉だったのだ。
ラストショットのダニーの笑顔は、悲劇的で絶望的にしか感じられなかった家族の死から、このコミュニティの死生観によって解放されたことによる。
それが洗脳の不気味さに見えるのは、よそ者の視点に浸った者の見方である。
と、ここまで考察して、もしかして自分もすっかりあの祝祭の歌声に心奪われ、その残酷だけれど美しく清らかな自然そのものの生き方に洗脳されているのか、とも考える。
全ては夢うつつのことのように思えてならない。まさにそれこそアリ・アスター監督の術中にはまっているのだろうけれども。
期待値より低かった
話題のミッドサマーをみよう!と友達に言われ一緒に見に行きました。
感想としてはTwitterで言われてるほどではない…という感じです。たいしてゴア表現があるわけでもなくカルト宗教紹介PVといったところ…
しかしミッドサマー別にたいしたことではなかったわ笑たいしてエグくないし笑とTwitterで言えばイキリオタク決定ですですのでここに感想を書きます。
前半はなんだか見ていて可愛そうに、というかんじだったのですが友人(ODをよくする鬱病だと思われるが鬱病のカウンセラーはイヤでは?といい精神科に行かない友達)はそこが一番つらいと言っていました。
「ODするとあんな感じなの?」ときくと「失敗するとまんまあれゲロ吐くし」と半ギレしてたのでそうなんだと思います。
私は健康な精神だと思うので特に何も感じませんでした。
九十年に一度ではなさげだと思いましたがどうなんですかね?警察は?とか思いましたが可愛い女の子たちが楽しそうに踊っているのを見るとこっちまで笑顔になりました。あと飯食うのだるいですね
モザイクシーンではそんな同人誌でしか見たことないようなセリフ言うことある?って笑ってしまったり最後のシーンではなんだか北海道のゆるキャラみたいなのが出てきて可愛いじゃんと思ったんですが調べてみたらゆるキャラの方が怖かったです
芸術性がある?いや…ないな
サイコスリラーのカテゴリーか?芸術作品か?まぁ、よくぞここまで作り込んだなと感心はする。
ただ、宗教系とドラックと巻き込まれるる若者を描く王道をいき、そこにグロとエロティシズムを混ぜこぜにした意欲作!と言えば聞こえは良いが、グロ/エロの描写は不快だった。
映像が美しいとの評判もあったが、大自然の山の中で花が溢れ、北欧系のブロンド女性が登場しているだけであって、決して映像が美しい訳ではない。
個人的には上映時間が長いにも関わらず、多くを詰め込みすぎてかなり消化不良かなぁ…
コンセプトに賛辞を贈ることができない
結論から言うと面白いと呼べる映画ではなかった。
正直に言えば、あまりにコンセプト・技法ともに全く評価できない。これに絶賛の声を送る方とは、私は価値観を共有できないのだろうな、と考えでしまうほど私はつまらないと感じた。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本作はアリ・アスター監督によって作成されたホラー映画。
主人公は精神疾患を抱えた大学生のダニー。家族の死をきっかけに精神状態を悪化させてしまうが、そのような状態の彼女を彼氏のクリスチャンは疎ましく思っている。クリスチャンは大学の同期たちとともにスウェーデンの夏至祭に招かれており、そこにいこうと計画しているが、それにダニーも同行することになる。
夏至祭は牧歌的で美しい小さな集落で行われていた。ホルガと呼ばれる集落は緯度の高い位置にあり、夏至は白夜になっている。一日中太陽がカンカン照りで、そこに暮らす村人も歌を歌って、皆が互いを「家族」と呼んで仲良く暮らしている様子である。
夏至祭は全部で9日ある。詳細は割愛するが、ホルガでは老人は72歳まで生きたら自死をする習慣があった。夏至祭序盤で二人の老人が高台から飛び降りて自死をするシーンが非常にゴアな表現で描かれている。そこから楽園に見えたホルガは歪で不気味なものへ変容していく。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「精神衛生に大変悪い」「心がえぐられた」「気持ち悪いのに好きになった」等、レビューがSNSに多数投稿されていたため、気になって劇場で視聴しました。
良い点が1つと、つまらないと感じた点が3つあります。
良い点は非常に美しい映像づくりが意識されていることです。ホルガの暮らしは基本的に明るい色調で色とりどりの花々が美しく飾り付けられています。その暮らしぶりはまさに夢のようで、少なからずあこがれを抱くような世界観でした。
しかし良いと思ったところはここまで。
私がつまらないと感じた点について。
①カット割り、ストーリー展開そのものが冗長。音声効果も古典的で退屈。
特に前半はそうなのだが、見どころが少なく見ていて退屈でした。加えて作品中で一貫して、思わせぶりなシーンの伏線が回収されず、「あそこのシーン何の意味があったんだ」と思うことが多かったです。劇中で学生が殺害される場面で、殺人者の顔が数秒映し出されるシーンがあったのですが、特にその後の展開に全く影響もなく、苛立ちを感じました。弦楽器の重低音や歌声の不協和音でホラー感を演出する手法は非常に古典的で、正直言って手垢のついたやり方に思います。
この内容の映画なら90分で十分かと思いました。
②ゴア表現や不快感を煽ることで話題性を作り出そうとしている印象を受けた。
美しくて明るいビジュアルと対照的に宗教的で不快なストーリーやゴア表現を用いることでホラー要素を浮き彫りにするのはシンプルに面白い試みかと思いましたが、一方で、死体の損壊や臨死時の喘鳴が劇中で登場するし、宗教的儀式として性的描写も長々と登場します。これらの描写で、どんな効果を劇中に求めているのかが不明でした。観客に恐怖体験ではなく、単なる不快感を与えることが目的であるとしか思えず、そのような目的をもって映像作品を制作すること自体に苛立ちを覚えました。
③製作者の文化に対する理解
前述の自死シーンを目にして、クリスチャンは「(自分たちの常識とは大きく異なるけど)彼らの文化に偏見を持ちたくない」と言って、冷静にホルガの文化に対峙しようとします。この態度には私自身も共感します。しかし、劇終盤ではこの文化の狂気性が際立ち、映画全体として、非科学的で宗教的な文化を極めて否定的に感じられる形で描いています。このようなテーマに安易に踏み込み、不快な対象として客集めに使うこと自体がタブー視されるべきものであるように感じられてなりません。
アリアスター監督は本作を『恋愛映画』と呼んでいます。生死さえ関わり、あまつさえパートナーを殺めるような、狂気的な感性が恋愛の本質なのだと監督は考えているのかもしれません。
そのメッセージ性に私は共感できず、映画全体の技術面を含めて面白いと感じる要素に欠いている作品だと思いました。
地球外知的生命体
実話を元にした映画とかだったら申し訳ない。被害に遭われた方達へお悔やみ申し上げます。
ただ、そうでないなら…クソ映画。
監督の前作「ヘレデェタリー」だかなんだかを見てるかどうかで評価が分かれそう。
俺は見てない。
見た人は期待するよねー「あの作品を撮った監督だ。絶対何かあるに違いない。」
色々こじ付けたい気持ちは分かる。映画通としてのプライドもあるだろう。周りの知識人がアレやコレや言い出したら同調圧力みたいな事を感じる事もあるだろう。
でもね、勇気を持って言おう。
「この映画はクソ映画です!金と時間を返せ!クソバカヤロウがあぁぁっ!!」
何十年ぶりかに出会った不条理映画だった。
いやー、つまらなかったわ。
ひたすらに退屈だったわ。
現在の世界の何処かで、実際に行われている事だとしても…その一点だけでホラー映画であると言えなくもないけども、まぁ、つまらない。
脈略などありそうもない。
…ああ、そう考えればコレはコレで現世の理から外れた存在に翻弄されてるのでホラー映画にカテゴライズされるのかもしれない。
いや、ぶっちゃけどおでもいいか…。
俺にはクソ映画でしかないのだから。
釣られたわ…。
踊らされた。
なんかディレクターズカットなんてものを上映するって言うから、そんなものが公開される程面白いのかと、まんまと騙されたわ。
クソー、ムカつく!
追記
なんかとても的を得たレビューがあって、ほーそんな見方もあるのかと感慨深い。
詰まる所アレだ。
俺はこの監督の言語が理解出来ないって事だった。
あれですね
マニアック2000と同じ構造ですね。
出血量少な目のハシェルゴードンルイス。
外界から隔離されている地域の無垢な住人によるお祭り。ホラー映画の伝統的なジャンルです。
ただ、広大な大地と白夜という空間と時間のスケール感が前述の同ジャンルによる既視感=退屈さを感じさせません。
画の繋ぎも、小気味良くしがちなところをよく抑えて
ゆったりさせており、牧歌的な環境での狂気を際立たせています。
結局、彼女も双極性乖離障害(躁鬱病)だったんだね。
あっ、笑いもありますよ。
監督、スタッフが優秀なので次回作にも期待。
一体何を見せたかったんだろう。
自分にしか描けない世界観? アートのような美しいサイコ映画? 監督が届けたいことがさっぱり入ってこない映画だった。美術を頑張ってるのも、作りたい絵があるのも分かるが、それだけで120分はのめり込めない。なにより、その世界観というのが、どこかでみたことがあるような、なんとなく既視感があるものばかりだったし、話にドラッグを登場させることで、都合よく撮ってみたい絵を撮っているようにしか感じられなかった(妹の死についても、ありがちな一家心中で、妹と家族とのつながりも何も分からぬまま死だけ描かれるので、ただかわいそうな経験をした鬱気味の主人公、程度にしかパーソナルを掘り下げられてなかった)
儀式のありよう、恋人とのうわべだけの関係性、馬鹿な男友達、集団による強迫観念、喜びや悲しみのない生と死。どれもがステレオタイプの描き方。一見、ステレオタイプに見えないのは撮り方や美術をすこーし凝ってるから。ただ、それだけだった。
冒頭20分、村に着くまではそのすこーし凝ってる、だけで楽しめた。これから先、本質が出てくるんだろう、、、と思って。でも、村に着いてから、凝るだけ凝って、中身はスカスカ。踊って、人殺して、裸写したり、セックス映せば、なんかすごい映画!ってなると思うなよ!
時間の無駄でした。
生命のループの美しさ
個人評価:3.8
こういったジャンルでは良作であり、作品性も高いと感じる。生命のループを描いていると感じ、草木や花など動植物では当たり前の理を、人間に当てはめ描いている。生命の引き継ぎの美しさが根底に流れているので、草木・花や自然の素晴らしさを同時に描くのはテーマと一致し、映像の美しさと恐怖がリンクしている。
また最後に主人公が生命のループに加わる事で、苦悩や恐怖から解放され、単なる恐怖映画ではない想いを受け取る事ができる。
しかしながら生贄を外部から連れてくる事と、この村での鉄の掟が一致せず、その部分の掘り下げが足りない。これでは生贄系の量産型ホラーと変わらない構図になってしまう。他にも表面的なグロテスク描写や、意味の無いホラー要素が作品性を低くしてしまってるのも残念。そのマイナス評価の違和感があるシーンを、完全版で説明してくれれば、そちらも是非見たい。
まるでサウナ
公開前の評判がすさまじかったこの映画。ふたを開けてみれば、期待以上にえぐかったとか、期待しすぎて拍子抜けだったとか、いろいろな感想がネットを駆け巡っていた。
私には正直、映画のほとんどが退屈でつらいもののように感じられた。それはまさに「サウナで整うってことを教えてやるよ」と先輩に言われて嫌々交互浴に付き合う後輩社員の気持であった。しかし、私はミッドサマーでしっかりと「整う」ことができた。
まず、ホルガに行くまでが長い。カメラワークも独特で、これから観客を不安な気持ちにさせてやるぞ、という製作者の気持ちが見えるようであった。その状態でおそらく30分…しかもカメラワークだけでなく、内容も面倒くさいダニーとうじうじしているクリスチャンのグダグダ喧嘩がほとんどで、スウェーデンの明るい青空と緑が現れた時にはホッとした。
そしてそこからがまた長い。前振りとして人物紹介をし、コミューンの明るさの中にある不気味さを醸し出していく。特に儀式で命を落とす2人を待っての食事シーンにはイライラした。マークの気持ちもわかるというものだ。
そしてやっと最初のグロシーン。老人2人が崖から飛び降りて顔面や脚をぐちゃぐちゃに破壊する。あとから飛び降りた死に損ないの顔を若者たちがハンマーで砕くシーンは中々。だが、それほどグロくはない。アイアムアヒーローやロボコップが平気なら大丈夫なレベル。
ここまででたぶん、90分くらい。つまり、最初の山場までですでに上映時間の半分以上を使っている。正直、しんどい。しかもここからめくるめく邪悪な儀式に邁進するでもなく、じっとりとした不穏な空気をじわじわと醸し出していくのみ。
しかし、今思い起こすと、不穏な空気の作り方が非常に優れていた。誰かと誰かが険悪な雰囲気になるだけではなく、画に映る全員が各々の目的を基に、一丸となって、”観客に”ストレスを与えるために行動していたのではないかと思わせるほどに、事情が複雑であり、それでいて理解の及ぶものでもあった。大変すばらしい。
ただ、”お客さま”たちをグロテスクな方法で殺害したのは、正直意味が分からなかった。禁忌を犯したマークやジョシュはわからないでもないが、サイモンとコニーは何かしたのか?お客様たちは儀式的な方法で殺さなければならないが、コミューンのメンバーは自分らの自由に死なせていいってのはムシが良すぎないか?
と、コミューンの面々が何を考えているのか全くわからずに、ダニーとクリスチャンの仲もまったくよくならなかったので、いったいこれでどんな着地をするつもりなのだろうとずっと不安だった。クリスチャンが生贄として炎の中で死にゆくときも、考えていたのは「おいおい、あと数分しかないぞ!これで本当に終われるのか!?」だった。
だからこそ、最後のダニーの微笑みで衝撃を受けた。これはコミューンに囚われた哀れな観光客の話でも破局寸前のカップルに起こった悲劇でもない。ダニーの心が救われて”家族”を得る話なのだと。
そこに気が付いた瞬間、私は整ったのでした。
…この整いを大事にしたまま終わればよかったのだが、公式HPで観た人用の解説ページを読んでしまったので、ちょっともやった。簡潔にまとめると、「アリ・アスター監督はこんなにディティールに凝っているよ」という話が延々と続いているのだけど、正直どうでもいい。
もう一度観れば新しい発見もあるだろうが、それはダニーとシンクロして得られる「整い」を上回るものなのか?ダニーはコミューンで共感してもらうことで救われた。ならば我々もダニーに共感して整うことを重要視するべきなのでは?
ルーン文字の意味や儀式的な殺害方法の意図、「隠された顔」など、分解すれば面白いものがたくさん出てくる映画だとは思う。しかし、観るときは無心になって、ぜひ「整う」ことを優先してもらいたい。
2020年ベストムービー!⭐️✨
なんともBad Tripな映画でした…(笑)
仲間が行方不明になり始めてからは、もう最後までただただ悪夢を見せられている…そんな作品でした。
この作品に解釈なんて必要なんでしょうか?(笑)
異文化の中の、アメリカ人の節操の無い感じとか、その不快さとか、分かりやすかったですね…演出だったのかどうかは知りませんが(笑)
この作品、大好きですわ!(笑)
コメディ映画
SNSの前評判にて「アメリカではカップルが観た後に別れてしまった時のためのセラピーが用意されている」とか「途中退出続出」とか「白いドレスにトラウマが残る」とかとか、話題性が話題性だったので、怖いの観れない映画好きに頼まれた&自分の精神力を試す目的で見に行った。
今回はネタバレなどの予習なしで鑑賞。
コロナ自粛モードの平日昼間なのに場内はほぼ満席。若い人たち沢山。たぶん彼らもSNS流入に違いない。
で、普通にカップルも来てる。口コミ知ってるよな?自分たちを試そうという儀式的な役割がこの映画に生まれているのか?どんな思考回路で一緒に観に行くことにしたのか、そこが気になって仕方なくなる。
そわそわしつつも、映画が始まっていく。
冒頭題名表示でなんでsummerじゃなくてsommerなのかが気になって仕方なくなる。
後から調べて解決
主人公の女の子は、ちょっとメンヘラでヒステリックな感じ。
双極性障害の妹の話とか、両親+妹の死とか、伏線としてどこまでの意味があったのか結局よくわからんしもはやどこからどこまで彼女の妄想なのかわからない。
ペレ怖すぎやろペレ。
序盤からサイコ感ある表情がすごい。
他の4人を上手くはめて連れてきてる時点で、自分たちの共同体の異質さがわかってるんじゃねーか。
村の常識を疑わない姿勢を貫いて欲しいのに、村のおっさんたちは自分たちが罪を犯した人を殺したことを隠そうと残りの仲間の仕業にしようとする所とかよくわかんなかったんだよなあ。
最初はホルガきれー、みたいな感じだったのが、72歳の男女の儀式で急にグロに路線変更。
グロを随所で強調してくるところとか、もはや何がしたいの?って思った。そゆことしてるとメッセージ(あるのかは知らんが)が滲むと思うぜ。
ロンドンの男女は騒ぎまくって逃げようとしたけど結局生贄になっちゃってたね。そこもおっさんたちが嘘ついてたの悪意しかないじゃんよくわからん。
近親交配をわざとさせて障害者≒賢者を生み出し、外部からの血を混ぜることによって種の存続を図ろうというロジックはよく分かったのだが、だったらそんなすぐ皆殺ししちゃう意味がわからない。90年に1度なのに、よくわかんない年の偉い感じのおばちゃんが「私もいつかは喜んで差し出すのよ」的なこと言ってたの、毎年72歳の人はいるだろうから結局この祭り毎年やってんじゃね?ってことなのかな計算が合わなくてモヤモヤした。
笑っちゃったポイントが多くあって、まず子供作りの小屋の中ww
さすがにあれは狙ってるでしょ。小屋からクリスチャンが逃げてくシーンも笑わざるを得なかった。
生贄の目に花が刺されてるのも一緒に行った人が笑ってた。
フューチャーされない、背景の中でなんか村人が儀式っぽいことしながら踊ってるのとかもギャグかよってなったし。
あとは音の不快感と劇中幾度となく出てくるヤクな。
あの村の中には絶対的なリーダーがいるわけではなく、共同体の信仰心として狂気が充満してる。それがわかっているからこそのヤクなのか、良心がどこに存在しているのかわからない。
総じて、何を見せられとるんやという感じの映画でした。
SNSに踊らされたなあ。長い時間を費やしてしまった、、
ラストについてだが、9人を数えるのに必死だった。洋画において顔が一致しない相貌失認の傾向があるので、同じ顔のやつ3人いるぞって思っちゃって混乱した。
最後のダニーの微笑みは理解できるものだったが、彼女はあの後共同体に吸収されてしまったのだろうか。なんで母親を見たのだろうか。。。
冒頭で触れたSNSの前評判は信用できないということが大いにわかった。冷静に見ればツッコミどころ多すぎてトラウマとかになりようがない。カップルでみて別れるくらいなら別れとけ。
でも、マヤがクリスチャンのベッドの下に木の札を置いてくシーンだけは好きだった。殴り書き失礼しました。おしまい。
ソーヘビー!
苦手なので普段あまり見ないホラー系。
避けている理由は鑑賞者を怖がらせようと音や雰囲気、あらゆる手段を使って恐怖のどん底に落としにくるから。
でもこれは「怖くないよ〜大丈夫だよ〜」って笑顔でどんどん寄り添ってくる恐怖だ。
しかもちょくちょく登場する恐怖シーン(だと思っている)では、
あくまでも「あっちょっと怖かったね〜ごめんね〜でもほら素敵でしょ?」って見せつけてくるお節介な親戚みたいなスタンスで嫌でも入り込んでくる。
おっかなびっくりホラー映画とは違って最後まで見れたけど、もうお腹いっぱいです…
ホラー映画ではないとすると、感じた恐怖はどこからやってきたのか。
おそらく、自分の常識の範疇を超えた人間の使い方をしていたからだろう。
ミッドサマーに出演していたのは、人のかたちをした何かだった、と心の整理をつけた。
理性も喜怒哀楽も痛みもない世界。
喜楽だけの天国に見えるけどなにもない。
鑑賞後はほんとに笑うしかなかった。
祝祭の締めで、炎に苦しむ人間をやっと見れてホッとしてるよく分からない感情に包まれる。
燃える家を見て笑い転げてる村人。
ねえペレもしかして笑うフリして泣いてる?
えっなんで泣いてるの?こんなに素敵な祭りができたのに
ってホルガ民の気持ちを追体験できるくらいにはひどすぎて洗脳された。
…と思っていたら、解説とかレビュー見たところあれはみんな泣いてたのか?
どうやら私がおかしくなっていた模様。
全体的に音楽の効果は好きだった。
あのミートパイ、サイモンだと思ってヒヤヒヤ見てたけどそっちかー!
吐きそうになったので食前食後はおすすめしない、、
鑑賞後時間が経つにつれ、二度と見たくないと思ってたのにまた気になり始めている。
儀式の先
予告を見て、明るい儀式に一種異様なザワザワ感を感じ儀式の先に何を見せてくれるのか期待と不安で鑑賞・・・儀式の終わりは不思議なグロテスクユーモアでした。○○の皮を着た姿につい笑ってしまった自分が怖い・・
SFで言うところのファーストコンタクトもの
ヨーロッパ人が世界征服の際に原住民に殺されたファーストコンタクトに対する恐怖(この際原住民をその何千、何万倍も虐殺・収奪した歴史は無視する)を題材とする物語は、ジャンルとしてはSFが良く取り上げるテーマですが、異文化をヨーロッパの非キリスト教と定めた上で直球でホラーとしてやり切ったことはスゴいですね。
こーいうのはルーマニアあたりの架空の吸血鬼信仰をでっち上げて作劇するモノだという先入観がありましたけども、実在の信仰を取り上げたことで非常に高い緊張感を作品に与えていますので、全く効果的だと感じます。
当該宗教に対する差別的感情を喚起しそうな気もしますが、ひょっとすると残念ながら当該宗教は既に駆逐されており、要らぬ心配なのかもしれません。
さて、中盤頃から原住民の特異な死生観が露わとなり、現代人から見ると命がいかにも粗末に扱われているように感じ、また悪気なく禁忌を侵してしまった事により仲間にも被害が出るに及んで、「これは生麦事件と同じだな。つまりこれはファーストコンタクトをテーマにしたホラーなんだな」と感じてしまい、前段の感想を持つに至りました。
これが正統な評価なのかも自分では判断できません(まぁ生麦事件は直接的なネタ元ではないでしょう)が、一度そう感じてしまってからは原住民であるところの日本人としては、「こちらの倫理を理解できない不気味なモノとみなし、未開の蛮族とその信仰としてのカルトとして描画しやがって、ムカつくな」と感じるところもあり、しかしながらその描画、演出は真に美を追求しており決して粗末には扱っていないと感じるところもあり、感情が(久々にレビューを投稿する程度には)ぐちゃぐちゃに乱されました。感情を一つの所に納めきれないので、表層的に「ファーストコンタクトものを直球のホラーとして描くなんて凄いなぁ」程度の第一段として置くのが精一杯です。
(感情が落ち着いた頃にレビューを書き直してみたいかな)
ポスター綺麗だからと観たら、、、、、
私もビビリなのですが、ビビリ友達とポスター綺麗だしと、そこまで怖くないでしょ!と安易な気持ちで観に行ったら2人で見事沈没しました。もっと調べたらよかった、、、、、、
嫌な怖さです、、、ほんとに、、、、
でもちゃんと伏線が張ってあって、終わった後に取り敢えず心を落ち着かせるためにカフェに入って話していると、「あー!!なるほど!?」みたいになりました。でもやっぱり怖い。
ペレの両親が「炎に焼かれて死んだ」っていうのは、、、、ゾッとしました。
怖いのが得意じゃない人が観るものでは無いと思います。怖いのもグロイのも大丈夫な人なら楽しめるかと…
現代の日本に生まれてよかったなって思いました。
Skåååålll!!!!
1.はじめに
映画「ミッドサマー」はやたらと「9」という数字に拘っていたので、この感想文も9つの章に分けて書き連ねてみることにした。
完全に見切り発車である。やりづらい。
ちなみに鑑賞したのは一週間前なので、この感想は鮮度を失っている。熟成肉である。
2.いきなりの総評
快感の強い映画だった。
インパクトの付け方、モチーフの数々、ストーリー展開、全てたまらなく好きだ。
しかしどうしても苦しくない。
気持ちよくて気持ちよくて、圧倒的に痛みと恐怖が足りていなかった。
いっそのこと終始トランス状態に陥ってしまいたいのに、盛り上がってきたところで現実のテンションに引き戻されてしまうのがなかなかに辛い。
3.まだ続く総評
そもそもストーリー自体はかなり単純でありきたりだ。
ヤバい田舎のヤバい儀式に巻き込まれる系。
それをものすごい熱量で作り込み、やたらと仰々しく勿体ぶって描き、ドヤドヤのドヤ顔で観せてくるものだから、こちらは若干萎えてしまうのである。
しかし、表現力の強さは凄まじいものがあった。
後を引いてたまらないのだ。
この映画の中の色々な物事について、悶々と考えを巡らせてしまう。
そうさせるパワーがあるというのは、実は結構すごいことだと思う。
4.祝祭の開催頻度について
「90年に一度」は絶対に嘘だと思っている。
村人たちの受け入れ方、所作とパフォーマンスの揃い方、慣れ方、女王の写真の数。
それらを見れば、この祝祭が一生に一度あるかないかの催し事ではないことは明らかである。
毎年やるほどの体力は無さそうなので、「9年に一度」が正解ではなかろうか。ほら、だって、9だし。
もし万が一、本当に90年に一度開催しているのであれば、村人たちの練習量は相当のものだろう。
運動会だって卒業式だって練習するじゃない?ああいう感じで何回も何回もやってきたんだろう。
練習風景を想像するとシュールで可笑しい。
5.ダニーとクリスチャンについて
家族全員を失ったトラウマガール、ダニー。
主人公にしては魅力の薄さが気になるが、後半の彼女はなかなか輝いていた。
拒否、共鳴、同化、決別、昇華。
彼女に新しく家族ができて良かった。
あの家族たちはなかなか絶えないだろう。安心して良いんだ。
きっと、あのようにして増えた仲間が何人もいるんだろう。
恋のおまじないを描いたタペストリーの通り、村の少女に堕とされゆくクリスチャン。
「スウェーデンでヤリまくる」という宣言が実現する皮肉さよ。
少女の陰毛を喰らったことしか言及していなかったが、飲んだジュースには少女の血液が混ざり赤みを帯びていた。
あの血液。絵を見たときには経血かと思っていたが、「自分で性器を傷つけて採ったもの」だと認識し直した。そうか、破瓜か。
6.人肉について
明確に人肉を食べている描写は無かったが、喰ってないわけないだろうと思う。
死んだ人間の肉を食べてこそ、村の中で生命が廻っていることになるのではないか。
名前を受け継ぐ〜とか生温いこと言ってる場合じゃない。人肉を喰え人肉を。
崖から落ちた二人の死体を綺麗そのまま焼いていたシーンが信じられなくて、唖然としてしまった。
いや、綺麗そのまま、なわけない。
きっと身体の肉をくり抜いて、中に詰め物か何かして、火葬に出したのだろう。
あのミートパイの中身は二人の肉だったと、私は信じている。
7.ゴア表現について
人体破壊の描写、造形、映し方、インパクト、どれも申し分ない。
完全にパワフルでショッキングだった。
願わくば、その過程を見せて欲しい。
破壊が完成されている肉体をただ見せられても、痛みが伝わってこない。
コニーの絶叫の際、何をされたのか。観たいのだ。
身体を開かれ吊られてもなお息をしていたサイモンの苦しみ。感じたいのだ。
生意気なマークの皮が剥がされる瞬間の歪んだ顔。そのものを見たいのだ。
8.しつこく三度目の総評
最初にも述べたが、恐ろしくない映画だった。
村での出来事よりも、ダニーをめぐる友人たちの気まずい空気の方がよっぽど怖い。
明らかに敬遠したいマーク達と、それに気付けないダニーの構図。ゾワゾワするでしょう。
とはいえ、ここまでの量の感想を連ねるほど、力のある映画だった。
まんまと手の内に嵌っている、ということなのだろう。
正直微妙だったな…と思いつつ、きっと私はこの映画が好きなのだ。
そりゃそうだ。
ホラーなんて、どんなにつまらなくても嫌いにはなれないのだ。
ただし、公式サイトでめちゃくちゃに解説しまくるその姿勢は好きになれない。
「あれ、もしかして…」の状態になるのが一度良いのだ。私はそう思っている。
言われないと気付けなかった点もあったから悔しいんだけどね。
9.おわりに
この一見ボリューミーな感想文は、全然大したことを言っていない。
とりとめなく巡る私の想いを、仰々しく勿体ぶって綴ってみただけなのである。
いかにも「ミッドサマー的」かなと思って、小賢しいことをしてしまった。
いつもの文体とは違う形を取ってきたので、私自身やりづらかったし、読みづらいものになってしまったと思う。
しかし思い返してみれば私の文章はいつ何時も読みづらいものだったので、まあ良しとする。良しとしてくれ。
そもそもこの文章を読んでくれている人はどれくらいいるのだろう。どう考えても長すぎるだろう。ここまで辿り着いた人はいるのか。
実は私の文章を一番読んでいるのは私だと思う。
映画の感想を記録するために始めたものだけど、文章を作ることに楽しみを見出しているのもたしかなのである。
たまにはこういう試みもありかもしれない。
しかし、こうやって長々とずるずると語り続けてしまうのは悪い癖だなとつくづく思う。
「映画の感想」の範疇を明らかに超えている。いや、実は締め方がわからなくなっているだけだ。たぶんあと50行くらいは文章を生成できる。
やめておこう。この辺で。
とりあえず「Skåååålll!!!!」
不思議で、面白い。
映画なので、自分の知らない世界を疑似体験できるのも、楽しみ方のひとつなので、アリの映画。
不思議な体験として、記憶に残る。
この、共同体的人間関係の世界は、
ある種のムラ社会であろう。
現在の都会の個人がバラバラの希薄な人間関係の世界と、
映画の中の濃密な関係性の世界は、
どっちも、隣の芝生になってしまう。
だから、田舎出身で、都会で活躍するしてて、
疲れたら田舎帰るなんて出来る人が最強だよな!
日本なら、すぐ思い出されるのは、オウム真理教だけど、
アレも、ある種の濃い共同体内の犯罪。
それを、実社会に影響させたから、犯罪となったわけで、
内部だけで、ポアとかしてても、
外の人が知らなければ、犯罪として立件できない。
家族としては、困ったものだけど。
老後の問題も、実は結構深刻。
18×4=72で人生終了とか、ひとつの考え方。
日本とかは、干支の12年が単位で、
12×5=60で還暦のひとまわり。
そこから12年で72だね。
現実の日本は、あと12年の84が
女性の平均寿命だから、すごい幸せだと思う。
幸せな悩み。年金が少ないなんてのも、
無い国だってあるのに、幸せな悩みのひとつ。
よく、厚生年金で、生活できないから、ヒドイ国だ、
なんて報道あるけど、
もともと、国民年金の、ヒトはどうなんだって!
たくさん払ったって言ったって、半分は会社が払ってるんだし。
あと、定年制なんてのも実は老人差別だよ。
働きたい人は、いくらでも働けばいいじゃん。
日本がサラリーマン社会になったのなんか、
戦後から、だからまだ最近の話なんだぜ。
取り留めないので、おしまいです。
白い衣装は、世界共通?
全189件中、121~140件目を表示