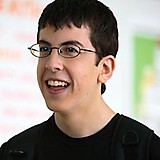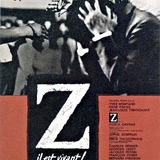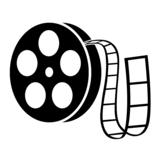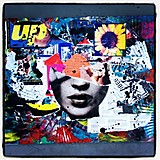ミッドサマーのレビュー・感想・評価
全631件中、581~600件目を表示
めちゃくちゃ美しいけどめちゃくちゃ胸糞悪かった
今作はセットがメルヘンで色鮮やかで美しく、白夜なのでずっと明るい。それらが、幻想的というか違和感を引き出してた。そして、容赦無い描写の数々で普段見慣れてないから滅入っちゃった😓
最初の方は主人公が家族を失った悲しみでちょっと狂ってるのかなぁぐらいだったのが、夏至祭が進むにつれ段々と感じる違和感、そして崖から飛び降りるシーンから「えっ、あかんでしょ」と常軌を逸しまくりの村人の文化、思想が明らかになる。あんなことしといても馴染み深く、愛着を持っている文化故、罪悪感どころか幸せそうなのが怖い。
クリスチャンが他人の文化は尊重しなくちゃみたいなことを言っていたが、その文化の外にいる人に危害を与えてる時点で尊重すべきでないだろうと思った。
そして、村人たちの同調意識?の異常な高さ、皆んな同じリアクションをすることがある(同調した方が楽だもんね)。最早理性を失っているように感じた。例として終盤、ダニーがクリスチャンの裏切りセックスを見て、泣き叫んでる時周りの女たちも叫び出す。
ラストシーンの笑顔も、全て吹っ切れたからか、それとも周りと同調することを選んだのか?
後フローレンスピューの出てる作品初めて見たけど、結構ハスキーボイスなのね。ポストスカーレットヨハンソンになるかもね☺️
個人的に好きになれない監督とわかりました
「肉体は無条件でいつか僕達を裏切る」
ラジオ番組“アフター6ジャンクション”内でアリ・アスター監督が答えていたパンチラインである。心気症でもあると告白されていた監督ならではの、精神と肉体の乖離、又は不一致性を端的に今作品に表現せしめた“金言”である。それを如実に印象づけている幾つかのシーンの重要なアイテム達を羅列してみると、幾度となく使用されるドラッグや媚薬は説明するまでもなく、肉体を制御不能にさせるモノ。そして、『Ättestupa』は日本『楢の山節考』のよりアグレッシブ版として、肉体の老いに対する一つの結論。そして主人公の女が恋愛、家族の不幸、そして奇っ怪な集団に駐屯している状況の中で、肉体が自然と同化していく幻想(手に草が生える、足も土に溶けていく感覚)。そんなシーンを散りばめる中で、強迫観念にも似た心身の不同一を丁寧に表現している手腕には狂気すら覚える程の作り込みである。更に、精神にも異常を故意に与えることで、正常性を排しそれを超えた別の社会性への帰依を図るカルト宗教的手法を表現することで、人間の脆さをも訴える構築となっている。マチズモの代表であるアメリカ人達が、次々と血祭りに上がる件、そして単なる“子種”としてしか必要とされていない対象、“メイクイーン”と呼ばれる、女性が長である社会性、心情を軽くスルーするやり方や、一方でオーバーリアクションを演劇やコンテンポラリーダンスを彷彿とさせる“型”に落とす動きで日常性の排除を催す動作に、精神さえも剥がれ落ちる若しくは脱皮するかのようにラストのクライマックスでの何とも言えない笑顔は、“狂気”という言葉さえ当てはまらない炎極がスクリーンに映し出される。これを34歳の若い監督が描いている事実に、驚愕という言葉でしか言い表せない己の陳腐さを嘆かざるを得ない。
ゴア表現ばかりが取り沙汰されるが、確かにジャンル映画としてのホラーでもあれだけの攻めた演出は、R指定を避けたいコマーシャリズムに果敢に挑戦していることをハッキリ見て取れるが、それ以上に注目なのは劇伴の細かいアレンジ調整の妙である。例えば、崖の上から投身するシーンでは掌の裂傷の前迄、音楽がメジャーコードなのにそこからマイナーコードへと転調することで不穏不吉さを劇的に演出たらしめている。音楽との親和性の高さ、そして裏切る演出も又サイコホラーとしてのジャンルの新機軸かも知れない。
今迄の家族をリセットし、新しい家族に取り込まれる。家族という共同体からは一切逃れられず、その十字架を次の世代へと背負わす。日本の昔の因習と同じ土着社会は実は世界共通であったことをありありと本作は突きつけてくる作品である。
本作は、他の数多くのレビュアーが仰るように、観る人を選ぶ特異な映像である。所謂『なんだ猫か・・・』的手法とは真逆の位置にある、決して陽が沈まない明るさの中での気が狂う殺戮のアイデアを提示している。身体は眠いのに、頭は冴える。そのアンナチュラルな季節を経験したことがない自分としては、バッドトリップの想いに耽るうってつけの、ジャストフィットな作品であった。多分、監督のバイブスに自分はかなりシンクロ率が高いのではと、勝手に判断してしまう悪い癖である。
【明るすぎる白夜の下の、唯一無二の”集団パラノイア”】
アリ・アスター監督は、つくづく”因習”、”継承”というワードがお好きだと見える。
そこに”A24"が絡むのだから、普通ではない作品になるよな、と思いながら独特過ぎる世界感にどっぷり嵌る・・。
物語は、序盤から、不穏な空気が立ち込める。
家族を事故?で失ったダニー(フローレンス・ピュー)は失意の中、彼氏のクリスチャン(ジャック・レイナー:久しぶり)の誘いで彼の友人達(含む、ウィル・ポーター 君がいるだけで、怖そうだぞ・・。)たちとスェーデンの”どこか”で行われる祝祭に参加する・・。
ほぼ一日中明るい土地で行われる、数々の因習を見ているうちに、こちらまで”何かを飲まされたかのように”脳内トリップ”していく。
”私、今を何見ているのかな?”
白を基調にした、貫頭衣のような衣装が印象的な人々の姿。(刺繍された花柄及び幾何学文様が素敵。一着欲しい・・。)
妖しいが、美しい。美しいが、妖しい・・・。
<見事に夏至祭の”サクリファイス”になっていく”外からの訪問者達の姿”も印象的な、アリ・アスターワールドを堪能した。>
ー 今作、地元のシネコンでまさかの上映。
いそいそと足を運んだが、当地では良い感じの客の入り(3割位かな。)で少し、ホッとして(何故?)劇場を後にした作品。ー
省みることの外側にいる人間
気持ち悪くなる映画
まず、気持ち悪くなった。
始めのほうの車が走っている時に上下が逆さまになるシーンや、会場に向かう人たちを上から見下ろしながらカメラがぐるぐる回るシーンなど
「この映画は気持ち悪くなりますよ」というサインだったのかもしれない。
なぜこんなにも嫌悪感を覚えるのか。
それは我々がいつもの生活で無意識に触れないようにしていることを、この映画は普通に見せるからだと思う。
死、性、近親相姦、ドラッグ
どこかタブー的なところがあるものたちがいとも容易く行われる。
崖を登る時に「飛び降りるかも」と誰しも思ったはず。
でも、「まぁ違うだろうな」とそうなって欲しくないと思う。
でも普通に落ちる。
始めのほうに、陰毛を食べさせたりして最後は結ばれる的な絵があった。
誰しもが「この通りになるんだろうな」と思い、「でもそうならないで欲しい」とも思う。
でも普通に性交をする。
胸糞悪いという表現は合わない、なんとも言えない嫌悪感にやられてしまった。
美しすぎて狂いすぎて良い意味で二度と見たくない
凄いぞ!!この世界観!!!
わかりやすい人生の参考書
凄く現実的な作品でした。小さな世界で人生の縮図を見せられている気分になりました。人の命は有限であり、群れる生き物だからこそルールがあり、学び悟り次世代へ引き継いでいく。とてもわかりやすく表現していました。
ただ…見知らぬ村の戒律を見せつけられている観光客を、お金を払って私が見てるっていう滑稽さ。たまりませんね。ドMではありませんが。
あれだけグロいシーンを目の当たりにしながらも、最後はダニーが笑顔になれて良かった、ペレは良い家族になれるだろうな、とハッピーな気持ちになれたのが不思議でした。
久々に。。
カルト/オカルトじゃない、オーガニックホラー
夏至云うてんのに冬で始まる白いゲットアウト
ゲットアウトとテーマは違うけど。
ヘレデタリーとはまた違ったテイスト。
英語間違ってる?と思ったタイトルはスェーデン語でミィドソンマルと読むらしい。
ホラーではないがグロ映像とボカシありのセックスシーン(裸の女性陣に囲まれながら)や全裸男性がウロウロするのでR15+指定。スリラーとしてみた。ブラックコメディ?違うような。。。
スェーデンの山奥にあるコミューンという設定。ハンガリーブダペストがロケ地なのか
パニック障害のあるメンヘラ女子とその彼氏と男友達大学生3人のうち一人の故郷の祝祭を見に行く夏至の9日感。
人類学異文化研究の論文の為、と言いながらドラッグにフリーセックスを期待して来てみたらさあ大変!
正に白日夢を見ているかのような気分
人間の一生を四季に分け生命はリサイクルされているという輪廻思想のコミュニティ
最後は笑顔で〆てもらわんと!な流れで納得のラストではあるけど、あれを見てハッピーエンドと捉えられるほど思想には入りこめなかった笑
崖から飛ぶ前ぐらいはリコーダー音色で睡眠導入されたけど、それ以降はゾワゾワさせてもらったしでかいスクリーンで観られて良かった。
トリップ映像も良き。素面で観ない方がトベるかもww
祝祭のクライマックスの炎には女王の笑みがよく似合う
どうやら『ハウス・ジャック・ビルト』を観ていたおかげで免疫ができていたようで、比較的冷静に鑑賞できました(ホッ)。
そうでなかったら、なんでこういう映画を作るんだろう、と悩んで終わってしまうところでした。
ネットで調べてみたら、実際のスウェーデンの夏至祭から、木材のポールとかハーブの香りといった類の祭りの道具立てのようなものをうまく取り入れているようですが、このお話のテーマらしきものとスウェーデンの伝承とか習慣が関係あるのかどうかは、残念ながらサッパリ分かりませんでした。
で、まったくの思いつき、こじつけ的な読解を試みました。
祝祭と死。
現代に生きる我々にはなかなか結びつけて考えるのが難しいと思いますが、病気や老いからくる衰えや死への恐怖から逃れる医療手段のない時代の人たちにとっては、ムラ全体が高揚感と熱狂に包まれるタイミングに命を断つこと、しかもそれが次の命に生まれ変わると信じられるのであれば、あのシーンも決して荒唐無稽なことではないと思います。
命は繋ぐものであって、いちいち悲しむものではない。
現代といえども、自給自足の中で得られる限られた栄養源しか摂取できない食生活と科学的な医療を施すことができず、ネットもテレビもなく、外の世界と遮断された環境で暮らしていれば、病気や老いの苦しみは昔とさほど変わらないはずです(村人たちがみんな健康そうだったので、そうは見えませんが😅)
しかもあのコミュニティの中では、全員が家族なので、直接的な身内への特段の悲しみ、という概念は薄くなります。
ついにあのムラの人たちと同期したダニー……悲しみや嘆きの咆哮を合唱のように周りの人たちが奏でることで頭よりも先に身体的同化が進んだのだと思います。
ムラの女王がムラの祝祭のクライマックスの炎を眺めながら、恍惚感漂う笑みで応えるのは、当然のことなのでしょう。
カルト映画化!
明るいのに
気分が悪くなる美しい狂気。
特に怖いということはない。
物語が進むに連れて、
村人たちの狂気の世界に引きずり込まれて
いくが、背景が常に青空と気持ちの良い原っぱで
狂気と対極構造が出来ている為
逆に美しさを感じてしまう。
またルーン文字など神話的要素を絡めることで
現実離れしていることを常に意識させられるので
、これがここの常識だと許容さえしてしまう。
映像や人物・音楽など気持ち悪く描かれいるが、
良しとして見れてしまう不思議な映画である。
この映画の最大の魅力が、醜悪を極美にかえてしまう映像手法だろう。
欠点としては物語に爽快感がなくダラダラと進み
あくびをするほど暇な点。
また、意味が明言されないため想像で補完していく必要があり釈然としない点。
伏線があちらこちらに散りばめられているので
想像できるようにはなっているが。。
なんだこれ?という体験がしたい人だけ
見るべき作品。
確かに見たことがないテイストは味わえる。
Happy midsommar. 超カルト!
うーん、何とも言えず気持ち悪かった作品でした。高い評価も理解できる。反面、低い評価も理解できる。そんな感じの希有な作品です。
まぁ、カルトって怖いな~っと思ったのが正直な感想ですね。カルト信者の方には申し訳ないですが、個人的にカルトって苦手です。閉ざされたコミューンで独自の文化が生まれたという設定でも、あの文化にはちょっとついて行けませんでした。ペレさんが友人を祭に呼んだ時点で生け贄要員確定ですし。「悪魔は優しい笑顔でやってくる」を体現しているペレさん。うーん、ろくでもねぇ。後、直接的な描写はなかったのですが、カニバリズムもありますよね?それとあれだけ薬に長けているのならわざわざ飛び降りしなくっても良いような?
あの中にハマってしまえば最後のダニーのように幸せになれるのかも知れませんが・・・だってカルト宗教にハマっちゃう人っていっぱいいますし、自分1人より周りと共感して流されてしまったがよっぽど楽ですしね。でも、あの風習を一番最初に考えた人は頭おかしいと思います。
フローレンス・ピューはスゴく良かったですね!もう本当にパニック障害になってるように見えました。何と言っても最後の笑顔!メイクイーンの話が出た時点でダニーがなるんだろうなぁってのは想像できたのですが、クイーンがよく似合ってたと思います。最後の歩く姿は「花ゴジラ」といった様相でした。
日本人にせよ、アメリカ人にせよ、大半の人は何処だよスウェーデンって?っという感じではないかなと思います。ヨーロッパでも北欧の、特にノルウェー、スウェーデン、フィンランド辺りの順番って馴染みが薄い分わかりにくいですよね。でも、本作観たらスウェーデンには行かなくっていいかなっと思う人が確実に増えるのではないでしょうか?そんな気分になる作品でした。
北欧版グリーンインフェルノ
へレディタリーからアリ アスター監督を知り本作を鑑賞しました。
正直へレディタリーに比べてマンネリした印象だったかな…もっと攻めた演出、話の展開があっても良かったと思う…
舞台は未開の地のジャングル…ではなく北欧の山奥の集落でこれまで誰も取り扱ったことのない白人の土着の風習、ある種のタブーに踏み込んでいる。所々深堀したくなるような興味をそそる部分もあるがまあフィクションなので多少無理があるよな‥と思うような風習の設定だった。(村の老人が崖から飛び降りるのは実際にそういった伝承があったらしいが)欲を言えばもっと心臓を抉ってくるような演出が欲しかった。
パンフレットの装丁も洒落っ気が効いてて映像、舞台設計、衣装制作のクオリティーも高い。話の中身自体は前述したとおりマンネリしたものだったが北欧の民俗学や舞台美術には興味をそそられるものがあるので是非足を運んで観てみてほしい。
全631件中、581~600件目を表示