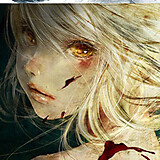ミッドサマーのレビュー・感想・評価
全633件中、381~400件目を表示
好き嫌いが分かれそうな映画です
ホラー系はあまり観ないのですが今回は知人の誘いもあり観てみました
終始不気味な感じで映画は進みなんとも言えない不安がありました
個人的にこう言う謎解きというか伏線が多いの映画は得意ではないので良さがあまりわからなかったのですがそういうのが好きな人なら楽しめると思います
途中までは理解できたのですがだんだんと設定についていけなくなり最後はただただグロテスクな映画という感想です。人生経験が浅いからかカルト的な恐怖もよくわからずまだ早かったかなと思いました
ホルガ村に呑み込まれた。
明るいホラー映画などと言われているが、どうだろう。
個人的に、ホルガ村の風習を順を追って見せられているだけに感じた。
殺された(生贄にされた)人達は、古くから大切にされてきた木に小便をかけたり、書物を勝手に撮ったりと、禁止されている(暗黙のルール)のにも関わらず犯してしまったから殺されたのであり、やり方は残忍ではあるものの、不信感はなかった。
古くからの仕来りだからこそ、生贄に選ばれた者は喜ばしきことであり、宿命である。
だから仕方ない。
と捉えてしまった。
だからこそ、次はどんな風習を見れるのだろうか。
という好奇心で見入ってしまった。
唯一ホラーと思えるところは、エンディングのシーンの時点で、9日間の夏至祭のうちのまだ4日目であるということ。
想像が広がります。
こういう映画だったのね。
2020年 13本目 ★★★★☆「落ち込んだりもしたけれど、わたしは元気です」
スウェーデンの風景の綺麗さと対照的に。。
間違えて観てしまった。
概ね良い映画
映画史上、最も感想に困る映画?
・ゲットアウト的なラストに納得の謎解きがありスッキリ終わる。
・かなりグロく怖い。
・賛否分かれると聞いていたので何か大きな決断がある。
とか思ってたら全く違った。
ホラーというか新しい設定で魅せる主人公の成長物語であり復讐劇のように感じた。
賛否両論になるのは主人公の決断ではなく単純に作風が自分に合うかどうか。ちなみにその作風が独特すぎて自分に合ってるのかすら分からなかった。
そして、まるでスイカ割りの様なシーンなど噂通りの過激描写。しかし今作の見どころの一つである(だよね?)ぼかしシーンは苦笑い。
観終えた直後の正直な感想としては「タランティーノよりもパルプフィクション」って感じだった。(人間としてクズな人を懲らしめただけで後は村の不気味さが永遠と続き結局何も起こらない=壮大なくだらない話だったから)
しかし解説サイトを観てパラサイト顔負けの数々の伏線に感嘆。監督の言う失恋映画、家族映画というのに納得。
スタンリーキューブリック作品のようにこの映画は次世代でやっと理解され、現代では一部にしか理解されない映画なのかもしれない。
物凄く面白い訳でもつまらない訳でもない感想に困る作品だった。
だけど何故かもう一度観たくなる不思議な作品でした。
ラストは厨二病の村人の中で微笑を浮かべるサイコパスクイーン…
一番怖い!
見方で変わる作品
自分は興味本位でみた結果、鑑賞後は不快感や疲労感が残った。まず、興味本位で見る学生とか自分みたいなど素人は全く面白いとは感じないはず。でも、普段からなにかに囚われ辛い日々を送ってる人、やり場のない逃げ場のない追い詰められてる人の立場で考えるとこの映画は「解放」ということを表現してる作品だと思う。自分は作品自体はあまり好みではなかったけれど、決して否定はしない。見る人によって意見が変わる面白い作品だと思う。
素人映画っぼい
絶賛する声、トラウマムービーときいて、
グロもホラーも耐性のあるわたしは喜び勇んでみにいった。
結果からいうと、、不条理系のつまんないやつみたいな感じで、ハズレだった。あまり練られてないシナリオを、いかにも意味ありげ〜に撮ってみた!って感じ。
たいくつなシーンが多すぎる爆睡ムービーでした。
まず、「男の旅行についてきちゃう空気読めない女の子」「いるいるこういう女!」
ってレビューしってたので、さぞかしウザ女がでるんだろなー。って思ってたら、、
その感想のひとたち、、冒頭10分みてないんけ?と呆れた。。
たしかに地味で暗くてメンヘラ気味な彼女だが、ウザいのはどちらかというと子供っぽい男連中じゃん。カレピっぴ大好き♪って感じでついてってねーよ。ダニーの心象風景わからんアスペのレビューなのか、違う映画みてんのかと思った。
んでまあ色々あってしょっぱなからハートが崩壊寸前な、暗い女の子ダニーの心象風景ままに、ストーリーが進む感じ。
「終始光に溢れて明るいシーンで怖さを表現してるのがすごい!」
ってレビューもきいてたんだけど、、これも、どこが??って思ってしまった。
輝度明度でいうなら確かに昼間だったり白夜に近く夜も明るいわな。
でもずーーーっと作中、いやな感じ、いかにも怪しい雰囲気が漂っててとてもアッパーな感じはうけない。
夏至祭はあるけど村入る前からみんなクスリきめてるし、よくわからん遠い地の怪しい儀式?が続いて、におわせもあり、漂うのはダウナーな印象ばかりだ。
ステキな村に優しいひとびと♪たのしいたのしいお祭りだーー♪♪って純粋に楽しんでるキャラもいないしね。
まあそれもいいとして、ウリであろう、衝撃?シーンも、、ふーーん、、その程度?あ、いやもっとみせろ!
って感じで物足りない。。バイオハザードやサイレントヒルの方がよっぽどグロい。
っていうか畳み掛ける展開もないから、時々意識とびかけるほど眠くなる。
主演の女の子の低い声はすきだった。
以上。観て疲れるだけでおもしろくも怖くもなかったー。残念。
予想してた内容と違ったが、それよりGOOD
予告編を見た段階では、
「若者たちがあるコミュニティに入る。最初は快適だったが、次第にその闇・狂気を知り、逃げ出そうとする…」って話だと思った。
(どっかで見た話だな。「ザ・ビーチ」ってこんな感じだっけ?)
良い意味で予想を裏切られた。
このコミュニティはカルト宗教を思わせるが、そういった特殊なモノに限定すべきでなく、(程度の差はあるが)どんな「組織」でも似たようなコトはあるのでは?
国家、会社、地域社会、学校、そして家族。
どんな組織であれ、合理的でない習慣、意味不明な習慣があるが、それに疑問も持たず生きている。
前半の自殺シーンはかなりビビるけど、
日本でもちょい前まで、「切腹」が美徳とされていて、トドメをさす人間もいた。本作とどう違う?
主人公の彼氏は常にラリってる状態だけど
(風景が常にユラユラしてる。お茶にドラッグが混じってる?)
酒だってある意味「ドラッグ」だし、ソマリア(?)のように、そういう植物を日常的に摂取する民族もある。
「自ら生贄にはならないだろう」と言うかもしれない。
でも、「自己犠牲」は最高に尊敬される行動だ。
それは自爆テロだけでなく、戦争はもちろん、子供向けのアニメでも同様(映画「シュガーラッシュ」参照)
女王になったのも、出来レースだったろうし、
彼女に彼氏のSEXを目撃させるのも同様。
SEXに至る過程にしても、「恋愛」が普通とは言えない。日本でもちょい前まで、親同士が決めた相手と結婚するのが普通だったし、今でもそういう国・民族はある。(映画「ビッグ・シック」参照)
主人公は彼らの一員となり、満足そうな笑みを浮かべる。
今まで自らが所属してきた「組織」から浮いていた彼女が初めて受け入れられた瞬間だ。
必要以上にグロい映画だけど、
自分が所属する組織とか、客観的になることとか、いろんな示唆に富む作品だと思う。
何が不快かというと…
いやはや不快感の玉手箱とでもいうべきキテレツ映画であった。
今日からはディレクターズカットも封切りなようだが、もう観る気にはなれない。
映像も、役者の演技も、音響も、とにかくこれでもかこれでもかと観る者の神経を逆撫でする。
鑑賞者の多くは、このような感じ方をしたのではないか。
ただ、鑑賞後、時間を経て熟考してみれば、舞台となった架空の村ホルガの自然観や死生観は、決して奇異でも異常でもないことに思い至る。
しばらく飼われていたであろう檻の中の熊が、終盤で解体されるくだりは、アイヌのイヨマンテの儀式に酷似していた。
死を、魂を現世から解き放ち、次の生につなげる重要な通過儀礼とする解釈も、アイヌほかたくさんの民族に共通する思想が存在している。
やや過激な崖やハンマーの活用場面はあるものの、古くからの因習を大切に保持した、今となってはかなり稀有な民族だと見ることもできる。
ホルガに訪れたダニーたち異国からの訪問者は、村の祝祭で目にするもの全てに対し、嫌悪し、嘔吐し、激怒し、研究材料として搾取し、愚弄する。
彼ら異国からの来訪者のマジョリティ然とした振る舞いが、徹底的にこの村の習慣や人々を異化し、異質性を強調する。
村が一つのカルト集団に見えるのは、観ている側が、異国からの来訪者の視点を取らざるを得ないがためではないか。
マイノリティに対し違和感と不快感の眼鏡を与えたこの作品の視点自体が、実は不快感の源泉だったのだ。
ラストショットのダニーの笑顔は、悲劇的で絶望的にしか感じられなかった家族の死から、このコミュニティの死生観によって解放されたことによる。
それが洗脳の不気味さに見えるのは、よそ者の視点に浸った者の見方である。
と、ここまで考察して、もしかして自分もすっかりあの祝祭の歌声に心奪われ、その残酷だけれど美しく清らかな自然そのものの生き方に洗脳されているのか、とも考える。
全ては夢うつつのことのように思えてならない。まさにそれこそアリ・アスター監督の術中にはまっているのだろうけれども。
期待値より低かった
話題のミッドサマーをみよう!と友達に言われ一緒に見に行きました。
感想としてはTwitterで言われてるほどではない…という感じです。たいしてゴア表現があるわけでもなくカルト宗教紹介PVといったところ…
しかしミッドサマー別にたいしたことではなかったわ笑たいしてエグくないし笑とTwitterで言えばイキリオタク決定ですですのでここに感想を書きます。
前半はなんだか見ていて可愛そうに、というかんじだったのですが友人(ODをよくする鬱病だと思われるが鬱病のカウンセラーはイヤでは?といい精神科に行かない友達)はそこが一番つらいと言っていました。
「ODするとあんな感じなの?」ときくと「失敗するとまんまあれゲロ吐くし」と半ギレしてたのでそうなんだと思います。
私は健康な精神だと思うので特に何も感じませんでした。
九十年に一度ではなさげだと思いましたがどうなんですかね?警察は?とか思いましたが可愛い女の子たちが楽しそうに踊っているのを見るとこっちまで笑顔になりました。あと飯食うのだるいですね
モザイクシーンではそんな同人誌でしか見たことないようなセリフ言うことある?って笑ってしまったり最後のシーンではなんだか北海道のゆるキャラみたいなのが出てきて可愛いじゃんと思ったんですが調べてみたらゆるキャラの方が怖かったです
不穏な空気と狂気性
芸術性がある?いや…ないな
サイコスリラーのカテゴリーか?芸術作品か?まぁ、よくぞここまで作り込んだなと感心はする。
ただ、宗教系とドラックと巻き込まれるる若者を描く王道をいき、そこにグロとエロティシズムを混ぜこぜにした意欲作!と言えば聞こえは良いが、グロ/エロの描写は不快だった。
映像が美しいとの評判もあったが、大自然の山の中で花が溢れ、北欧系のブロンド女性が登場しているだけであって、決して映像が美しい訳ではない。
個人的には上映時間が長いにも関わらず、多くを詰め込みすぎてかなり消化不良かなぁ…
「ヘレディタリー」と逆ベクトルのスリラー
観てよかったと思いました。
というのも、今作を観る前に同監督の「ヘレディタリー/継承」を見て、心が180度ボッキリと折れたように恐怖を感じてるいたからです。
「ミッドサマー」を観て、「ヘレディタリー/継承」の恐怖が、なぜか半分ほど払拭されたように感じました。
「ヘレディタリー」が「呪詛」による死者の為の物語であるなら、今作「ミッドサマー」は「祝福」による生者の為の物語です。
(どちらもスリラー作品であることに変わりはないかもしれませんが…)
また、「家族」という題材を思うと、「ヘレディタリー」が現代社会の中の〈孤立〉を描いているとしたら、「ミッドサマー」は民族社会の中の〈連帯〉を描いている、と言えなくもないように思いました。
個人的には、まるでA面とB面のように…どちらが表か裏か分かりませんが、逆ベクトルで作られた、対のような作品だと思いました。
また個人的な、変な憶測ですが、「ミッドサマー」か「ヘレディタリー」か、どちらか片方だけ観た方が怖いのではないか、と感じました。
両方観てしまうことで、意外と自分は、心のバランスが少し取り戻せたように思います…。
映画そのものの完成度は高く感じられます。
劇中には様々な謎が散りばめられていますが、あまり気にせず、なんとなく観ても楽しめる(スリラーが大丈夫なら…)映画と思います。
どんな映画に似ているか、と問われれば、「楢山節考」のような映画、と思います。
グロテスクなシーンも一瞬ありますが、目を背けても内容はある程度分かるのでは、と感じます。
客層としては、自分が入った時は女性の方が多い印象でした。
見終わった後、どんな内容だったか話し合うのも楽しい映画かもしれません。
コンセプトに賛辞を贈ることができない
結論から言うと面白いと呼べる映画ではなかった。
正直に言えば、あまりにコンセプト・技法ともに全く評価できない。これに絶賛の声を送る方とは、私は価値観を共有できないのだろうな、と考えでしまうほど私はつまらないと感じた。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
本作はアリ・アスター監督によって作成されたホラー映画。
主人公は精神疾患を抱えた大学生のダニー。家族の死をきっかけに精神状態を悪化させてしまうが、そのような状態の彼女を彼氏のクリスチャンは疎ましく思っている。クリスチャンは大学の同期たちとともにスウェーデンの夏至祭に招かれており、そこにいこうと計画しているが、それにダニーも同行することになる。
夏至祭は牧歌的で美しい小さな集落で行われていた。ホルガと呼ばれる集落は緯度の高い位置にあり、夏至は白夜になっている。一日中太陽がカンカン照りで、そこに暮らす村人も歌を歌って、皆が互いを「家族」と呼んで仲良く暮らしている様子である。
夏至祭は全部で9日ある。詳細は割愛するが、ホルガでは老人は72歳まで生きたら自死をする習慣があった。夏至祭序盤で二人の老人が高台から飛び降りて自死をするシーンが非常にゴアな表現で描かれている。そこから楽園に見えたホルガは歪で不気味なものへ変容していく。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「精神衛生に大変悪い」「心がえぐられた」「気持ち悪いのに好きになった」等、レビューがSNSに多数投稿されていたため、気になって劇場で視聴しました。
良い点が1つと、つまらないと感じた点が3つあります。
良い点は非常に美しい映像づくりが意識されていることです。ホルガの暮らしは基本的に明るい色調で色とりどりの花々が美しく飾り付けられています。その暮らしぶりはまさに夢のようで、少なからずあこがれを抱くような世界観でした。
しかし良いと思ったところはここまで。
私がつまらないと感じた点について。
①カット割り、ストーリー展開そのものが冗長。音声効果も古典的で退屈。
特に前半はそうなのだが、見どころが少なく見ていて退屈でした。加えて作品中で一貫して、思わせぶりなシーンの伏線が回収されず、「あそこのシーン何の意味があったんだ」と思うことが多かったです。劇中で学生が殺害される場面で、殺人者の顔が数秒映し出されるシーンがあったのですが、特にその後の展開に全く影響もなく、苛立ちを感じました。弦楽器の重低音や歌声の不協和音でホラー感を演出する手法は非常に古典的で、正直言って手垢のついたやり方に思います。
この内容の映画なら90分で十分かと思いました。
②ゴア表現や不快感を煽ることで話題性を作り出そうとしている印象を受けた。
美しくて明るいビジュアルと対照的に宗教的で不快なストーリーやゴア表現を用いることでホラー要素を浮き彫りにするのはシンプルに面白い試みかと思いましたが、一方で、死体の損壊や臨死時の喘鳴が劇中で登場するし、宗教的儀式として性的描写も長々と登場します。これらの描写で、どんな効果を劇中に求めているのかが不明でした。観客に恐怖体験ではなく、単なる不快感を与えることが目的であるとしか思えず、そのような目的をもって映像作品を制作すること自体に苛立ちを覚えました。
③製作者の文化に対する理解
前述の自死シーンを目にして、クリスチャンは「(自分たちの常識とは大きく異なるけど)彼らの文化に偏見を持ちたくない」と言って、冷静にホルガの文化に対峙しようとします。この態度には私自身も共感します。しかし、劇終盤ではこの文化の狂気性が際立ち、映画全体として、非科学的で宗教的な文化を極めて否定的に感じられる形で描いています。このようなテーマに安易に踏み込み、不快な対象として客集めに使うこと自体がタブー視されるべきものであるように感じられてなりません。
アリアスター監督は本作を『恋愛映画』と呼んでいます。生死さえ関わり、あまつさえパートナーを殺めるような、狂気的な感性が恋愛の本質なのだと監督は考えているのかもしれません。
そのメッセージ性に私は共感できず、映画全体の技術面を含めて面白いと感じる要素に欠いている作品だと思いました。
全633件中、381~400件目を表示