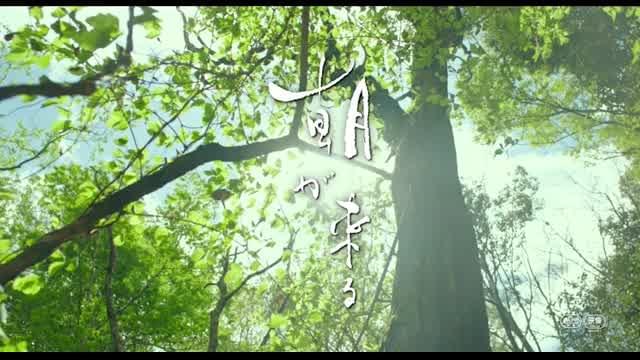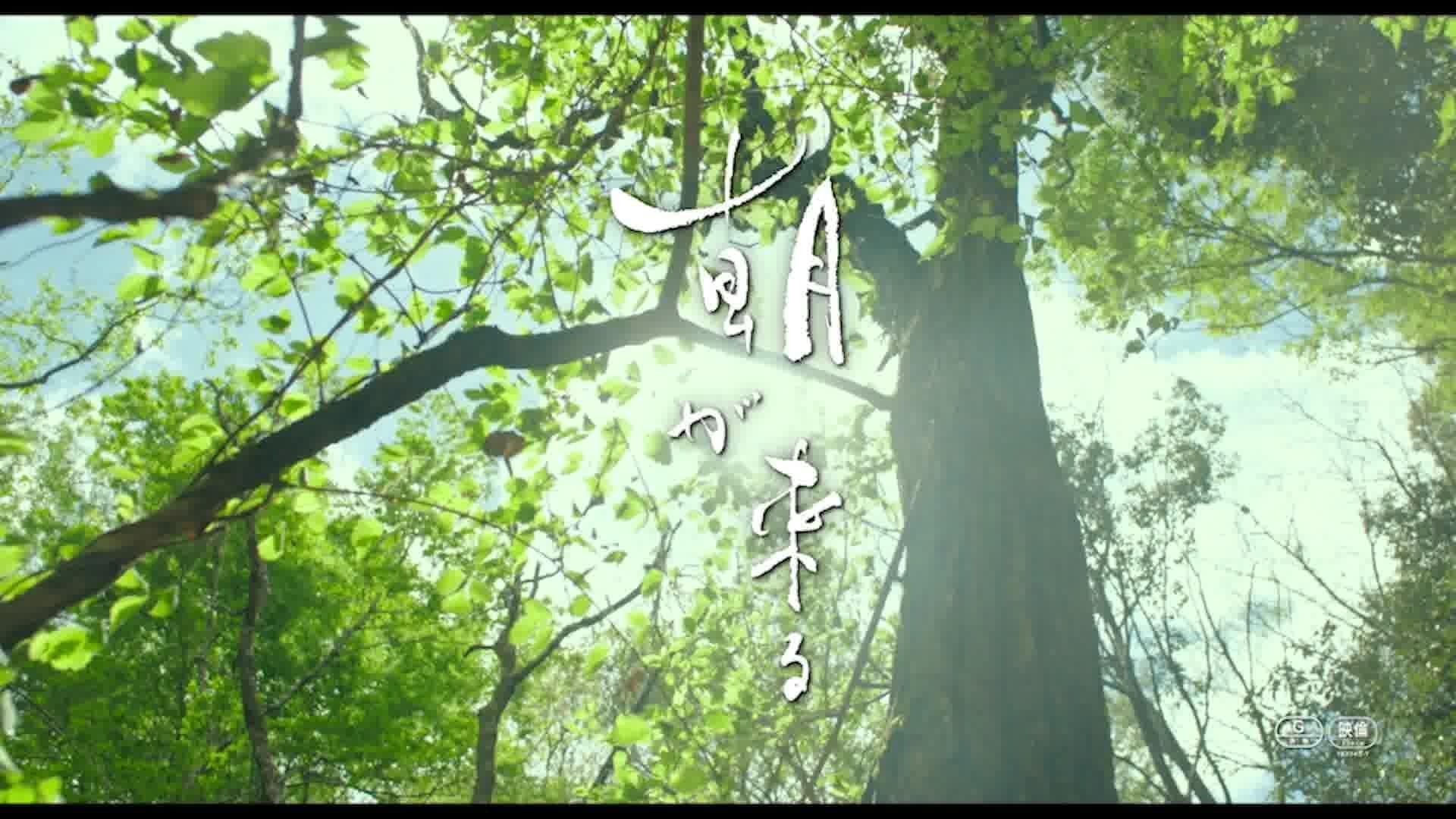朝が来るのレビュー・感想・評価
全212件中、41~60件目を表示
名作ですね、間違いなく。
河瀬直美監督の作品は、おもしろいけど、重い。
そんな印象があります。テンポのいい爽快感のある
作品とは対極に位置する気がします。
う〜ん、と考えさせられるような内容のものが多いので、
見終わった後、すごく疲れるんですよね。
あと、ストーリーの展開があまりなく、静かに時が流れていくような
ドキュメンタリー風の作品ばかり。
そういう映画は、眠くなったり、途中で見るのを辞めたりしたくなるんですが、
この監督の作品は、不思議とそうならない。それが凄さなんじゃないかな
と感じます。
「朝が来る」も、見事に河瀬ワールド。原作は未読ですが、
他の監督がメガホンを取ったら、全然違う雰囲気の作品になると思います。
河瀬監督の作品は苦手だという人にも受け入れられるんじゃないでしょうか。
役者では、永作博美、井浦新という二人が上手いのはわかっていましたが、
蒔田彩珠の才能には驚き。すごい役者になりそう。
なかったことにしないで・・・という抒情詩
会いたかったよ
光
丁寧にしっかりとした作品
原作は未読です。
「特別養子縁組」。それは受け入れた側の戸籍となり、出した(産んだ)側とは縁が切れる。
その双方の話を、時間軸を時に戻しながら進んでいく。
そうなるとわかりにくそうですが。
小説でいうと「第1章:受け入れ側」「第2章:産んだ側」等とメインをチェンジしていく。
なので大丈夫でした。
途中ドキュメンタリー風に進むところもあって。
話にリアリティさを増してました。
時々で受け入れ家庭に、無言電話がかかってきます。
その時の「爪の色」。誰だろう?出した側の女性じゃないよね。でももしや?。
と予測したのですが、そういうことかそれで、ってわかるところは。
出した側の女性の、出産時以降の人生の荒波ぶりを感じたな。
生命の営みとの結果として、命を授かり、生まれる。
その子供がみんなに歓迎される。ばかりじゃないんだよね。
生まれない命もたくさんある。
その難しさを感じました。
重めの内容ではあるけど、見終わった後は「うん」ってうなづける。
140分あっという間でした。
⭐️今日のマーカーワード⭐️
「色々あったね」
一人の人間の命を預かり、育てるという「ミッション」
一つ一つの映像が、どれも美しく、監督の美学が結晶化している。美しいけれど、とても血の通った作品です。この夫婦の人間性が高いので、救われます。そして中学生の二人も本当に純粋に好き合っての縁で。
ただ、つらい状況が続きます。人生には理不尽がいろいろあるね。
自然の情景が、人間の表情と、交互に重ねられていく。
重くエゴの泥沼化しそうな内容も、主人公に感情移入するとか、観客という批評家目線でもなく、不思議な立ち位置で観ました。まるでこの夫婦の友人のような気持ちになっていました。
血のつながりがあっても無くても、
誰かの幸せを願う。それが愛ですね。
でもなかなか足りない、世界には愛が。
愛を乞う人の方が多いから。
周りからはムリゲー扱いされても、中学生が一つの命を産んでくれたからこそ、これだけの「愛する側」になる人が生まれたとも言えます。新しい命は愛を運んで来ましたね。可哀想、とかじゃなく。
迷いのないメッセージ。
一つ大きな論点。
養子縁組の大事な条件が「親のどちらかが、育児に専念できる夫婦」。
一人の女性が質問しました。祖父母もいて、時短勤務もできるのですが、と。縁組仲介者(浅田美代子)が「皆さんにとって、仕事が大事なのはすごくよくわかります。でもそこは譲れない条件です、ご理解ください」とシンプルに、笑顔で、1ミリも揺らがず答えるところ。
世の中の流れ的には、産休育休保育園。女性も男性と互角に仕事人としての活躍が謳われる。一度正社員から外れると、正規雇用復帰は難しい現実。男性一人の稼ぎで一家が食べていくのは難しい時代。
でも本作での設定は専業主婦デフォルトのように捉えられなくもない。それもあえて台詞にして、入れている。ここは議論を呼ぶと承知の上でしょう。
河瀬監督が女性でよかった(男性監督だったら、単に、前時代的な偏見とこき下ろされたかも)。
いいのです、監督が世に問いたいことを描く。
その覚悟こそ映画を作る意味。
母という元型も問うています。
さまざまな母たちが出て来ます。
母になれば愛が自然とうまれる、というのは幻想(不都合な真実)。
いいのです、世の母たちは皆知っているのでは。
外ヅラつい整えたくなる自分たちを。葛藤です。一生かけながら、母も子も(父も)、不測の事態に試されながら、本音で関わり、魂を磨いていくのです、どんな時でも愛せるように。
その覚悟が出来ない親もいる。。。
河瀬監督、美しい映像で、ぐいぐい問うて来ましたね。
その思い切りが、心地よかった。
深い
特別養子縁組を題材に。
この、産みの親と育ての親をめぐる映画作品の中に、
八日目の蝉
夕陽のあと
そしてこの朝が来たが同テーマの三大名作になろうか。
それぞれ、展開と結末は違うがそれぞれに伝えたい何かがしっかりと描かれていて考えさせられる。
辻村深月作品は深い悲しみの中に最後は救いのある結末が多く、本作も河瀬直美監督がどう締めるのかに期待を寄せたが、こんなラストを見せられては誰も文句は言うまい。
素晴らしい!!
いつの時代にも子供を育てられないのにデキてしまうという「することしておいて、無責任な!!」という事が繰り返される。
事情も様々あるが表向きは結局そうだ。
いつも苦しむのは女性側であり、この映画でもワンシーンで象徴的に見せた相手の男の高校通学の姿。
この差がホントに辛い。
ついて離れない産んだ子の行く末。
これが気にならない産みの親はそうそういまい。
若干14歳で産んだこの子もそう描かれてストーリーは進む。
2時間19分の重く長い作品だが、各自の揺れ動きが余すとこなく出ている。
何より、単純な時系列で作品を繋がずに、産みの親、育ての親(夫婦)の展開の過去と今を素晴らしく編集して作品全体をまとめたところに私は感動しました。
これは見逃せない一本となりました。
久々の邦画。演技力に圧倒
透明感と衝撃
奈良学園?
実親と里親とは完全に接触を断つべきではないのか?と引き渡しのシーンで違和感を感じ、それが最後まで続いた。共働きはNGという規定にも疑問があったところ。育休取って良しといった制度にしたいところ。
しかし、養子縁組制度のあり方について論じているようではなさそう。むしろ、寄る方ない少女の救済論のように思える。蒔田彩珠の荒んだ表情と穏やかな表情の落差が良い。おじさんに切れた時の揮発性は思春期らしい演出。びんたで応酬した中島ひろ子も際立つ演技。同じく荒んだ少女役の森田想にも好感。
少し長いが、演出、演技は充実していると思う。しかし、制度的にはそのような着地は無理があるし、True Fatherの方は全く触れないというのも偏りがあるように思える。
何故実在の学校名を使うのか?理由がよく分からぬ。
素晴らしい作品
2本立て2本目。川瀬監督作品、しかも高評価。邦画初勝利の予感。 幼...
2本立て2本目。川瀬監督作品、しかも高評価。邦画初勝利の予感。
幼稚園事件、ありそう、緊張感漂う。
遡って不妊治療から養子縁組へ。うちも不妊治療の子です。養子までは考えなかったなぁ、人様の子を愛せる自信がはなからなかった。
養子を受け取る際、「母親に会いますか」ここで一気に冷めた。米国🇺🇸などでは産む側と育てる側との非接触は常識。浅田美代子が所長だから(笑)では済まされません。
しかもここからドキュメンタリータッチの映像が続き、かえって嘘臭さは増幅するばかり。主人公は産んだ中学生に交代です。永作はどこいった!状態です。
エンディングもまた不思議。金まで要求されたただただ邪魔な産んだ側に理解を示せます?
極め付けはエンドロール最後、ただただ寒かった、怖かった。
私的採点ではここまでのハズレは久しぶりでした。朝ドラモネの妹は素晴らしい演技なのに残念至極。
日韓対決は残念だけど今回も韓国の勝利でした。
全212件中、41~60件目を表示