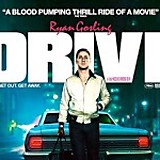燃ゆる女の肖像のレビュー・感想・評価
全169件中、121~140件目を表示
オルフェが振り返らなかった先に光はあったか
過去の思い出とどう付き合っていくか。
2人の選択は、繊細かつ清々しい強さに満ちていたと思う。
観終わったあとの余韻が長く心地良い。
悲しい話と言えばそうかもしれないけど、個人的にはむしろポジティブな生命力を感じる幸せな映画だった。
あとたぶんこの映画でポップコーンを食べるのは至難の業です。
音で感動させられました。
映像は綺麗ですが中盤まで展開がほとんどなく飽きてきましたが、後半にかけてドキドキさせられました
音で心揺さぶられました。
焚き火で歌うところはミッドサマーを思い出したw
ところどころホラーっぽい演出(そこまで怖くないけど)
白いドレス?を着た女性はもしかして死んだ姉かな?
双子とは言ってなかったから微妙だけど
コロナの2020年にこんないい作品に出会えるとは
尊くて美しい
激情をこれでもかと見せるラストに涙が溢れた
舞台は18世紀のフランス。男尊女卑の時代ゆえか同じ画家である父の名前で絵を描き、女性のみに絵を教える女性画家・マリアンヌ。彼女の回想というかたちで物語がスタートした。
孤島の屋敷で暮らす貴族の娘・エロイーズの肖像画を依頼されたマリアンヌ。当時の富裕層にとって肖像画は見合い写真のようなものだったのですね。
見知らぬ相手との結婚に不安を抱くエロイーズには肖像画を描かれることに抵抗があったのだろうが、マリアンヌに心を許しモデルとなった。
美しい島で二人が過ごす濃密な時間。邪魔するものは何もなかった。苦手なジャンルだと危惧していたが心配は無用だった。二人の恋が十分腑に落ちた。強い説得力があった。
それにしてもこのラストシーンはいったい。
マリアンヌが知ることのないエロイーズの激情を我々にこれでもかと見せるアップの長回し。激しく感動した。涙が噴き出した。語られなかった別れてからの時間が頭の中を駆け巡った。
『情感』を堪能。
振り返ってよ
たぶん、永い失恋の話なんじゃないかな。
冒頭の絵、タイトルである燃ゆる女の肖像。
緑のドレスの女は、後ろ姿で描かれている。
最後の劇場で、視線に気付いているのに決して目を合わせようとしないエロイーズのよう。
その後ろ姿をみて、マリアンヌはまだどうしても、願ってしまうんじゃないだろうか。
「振り返ってよ」
でもじゃあ、絵の女のドレスの後ろについた火は、どっちの情念?
マリアンヌの?
エロイーズの?
エロイーズは、あの日二人の思い出の音楽を聴きに、あの日劇場に来た。そして泣いていた。
それでも、たぶんもうエロイーズがもうボロボロになっているであろうあの本の28ページ目を開くことは、ないんじゃないかな。
きっと燃ゆる女の肖像は、劇場から帰ったマリアンヌが描いた絵。
まだ情熱を心に燻らせながら、振り返ってよって、何度も願いながら。
とても良かったです。
静かで荘厳な作品だった。 BGMを殆ど使用しておらず、波や風の音、...
夏
芸術的な映画が綴る儚き日々と愛の行方、眠気を取ってから観るべき
芸術的なアプローチから作られた切なく儚いいつかの日々。長く暗いトンネルを抜けると眩しく美しいラストにたどり着くこの作品に、過程を耐えられなかった私にはあまり良く映らなかった。
とことん突き詰められた、アーティスティックなテンポ。焚き火の木々が割れる音、波のさざなみがBGMとなり、淡々と日々を綴っていく。そのなかで芽生える二人の感情は、長いトンネルのように続き、行く先が分からない。平穏でありながら、新しい発見と感情が芽生える過程は確かに美しい。そこを迎合出来なかった私には、ラストまで息苦しかった。眠気もあったかもしれないが、なかなか好感を持てはしなかった。
変わらない日々を感情のみで描くため、ロケーションがあまり変わらないことが意味を成してゆく。優しく進む日々と変化に、屈託を覚えたことが大きい。難しさが際立っていた。
女3人の温かな火
とても良かったので星5つです!今年ベスト級。
女性2人の関係性が主題だと思ったのですが、もちろんそれはありつつ、使用人ソフィも混じった3人の描写がとても素晴らしかった!中盤、3人が対等に(完全に対等かはわかりませんが私には友人同士のように思えた)暮らし、料理を作り合い、ムキになってゲームをし、手を差し伸べ合い、歌い踊る描写は本当に輝かしい日々で泣けてしまいました。どうかこの先も共に幸せに生きて欲しかったけれど、短くとも輝かしい日々に灯した火は彼女たちのその後の人生を温めたでしょう。
予告編からは勝手に重たく辛い物語という印象を受け取っていたのですが、予想を裏切り軽やかで暖かく、その中で生きる女性たちの切実さを描いた物語でした。とてもおすすめです。もう一回観に行きたい。
女性視点の女性たち
予告では寝そうな映画と思った。実際、始まりはうつらうつらだったが…出演している女性の表情、仕草、肌の質感までもが全て美しく撮れていて目が離せなくなる。また、(絶妙ではなく)微妙なアングルで彼女たちを捉え、それがハッとするほど美しい。演出、セリフ、間のどれもが、彼女たちを引き立たせる、息遣いさえ美しい。この監督、さすがです!音楽というか音による演出が殆どないので、映像の良し悪しがこの映画の全てを決めています。
最後にオペラか音楽会で彼女を見かけるシーンがあるが、絵かきの女性が”彼女は私を観なかった”と言ったが、観ていないのは絵かきの女性の方だろう。
恋の先に
近くの映画館でかかってないので、舞浜までやって来た。夜の上映なので、帰りはちょうどランドから流れてきた人で、駅は混んでた。若者は、どんな状況でも、遊びたいんだね。君たちは感染しても軽いんだろうなー。うらやましいっす。中高年は本当に注意します!
危険を犯してまで観に来たよ。良かったよ。満足した。いい時間をありがとう!
まず、海がすごい。色といい波といい、世間から切り離された感がある。次に音。波の音、雨の音、暖炉の薪が爆ぜる音、木炭の音、筆の音、落ち葉を踏みしめる音。人が動いて出るものや自然のものなど、これがすごくいい。音楽つけなくても、充分にドラマティック。で、ここぞとばかりに、夜の焚き火を囲んで、不協和音から始まるアカペラコーラス。背筋がゾワっとした。さらにヴィヴァルディ「四季」の夏! 主人公たちは若く、まさに人生においても夏の時期。くー、洒落てる!監督、あなたのシモベにしてください!
最後のシーンのコンサートで演奏された「夏」、音が重くなくてはじけた感じがする。どこの楽団が演奏したのか、クレジットで確認したかったけど、字が小さくて読めなかった。帰ってから調べたら、エイドリアン・チャンドラーというイギリス出身のバイオリニストで、古楽器のアンサンブルグループで活動してるそうだ。音源が欲しくなってきた。
妻を振り返ってしまったオルフェに対する考察。「ヤング・アンド・シンプル」なソフィー。人間の感情を理由とするエロイーズ。マリアンヌは表現者の観点から見る。この時、エロイーズは、芸術家の性を知ったのかもしれない。それでソフィーを描かせようとしたのでは。男性が描けない、思いつきもしない題材、女性ならではの視点。見事なアシストだと思う。
見つめて見つめて、見られて見られて、いつの間にか落ちた恋。お互いに好きだけど、恋だけではどうにもならない。別々に歩むしかない。でも、恋の先に何かがあるかもしれない。時間が経っても、会わずとも、心の深いところに居続ける想い。ソウルメイトだ。そんな人に出会えるって、世の中にそうない。
本筋と関係ないことが気になるタチなので、つい書いてしまう。キャンバスって海水で濡れたらマズいんじゃないの? 真水で洗ったのだろうか。あと、意外に絵の具はちびちび使うのね。やっぱり高価なのか? 風が強い日用の薄いスカーフ、ねじって頭に絡める、あの方法が知りたい。カードゲームのルールはどんなんだ。…わからなくてもいいことだけど(笑)
静かできれいな、美術館のような作品だった。自分はとても好き。
女という性の本質
表現するということは、対象について観察し、考察し、寄り添おうとする事だろう。【形】の把握から、【本質】の理解まで。本当の美しさも、醜悪さも、深入りしなければ解らない。近寄り、共感し、愛で、時に憎む。対象に自己が混じり合い、その落とし子であるかのようにひとつの作品となっていく。そう考えれば、全ての芸術は、恋愛によく似たものであるかもしれない。
「この肖像画は私に似ていない」と娘は言い放つ。本質を突かれて画家は憤る。互いの誇りのぶつかり合い。形をなぞる視線が、内を探る視線に。隠れ見る眼差しが、見つめ合う眼差しに。
【愛とは何か】。言葉でなど語れるものか。感情を揺り動かし、身体を突き動かし、嵐のように呑み込み、波のように去り行くもの。芸術もまた同じ。音楽も、絵画も。わけなど判じる間もなく、心を高みに投げ上げる。
光、陰、色彩。吹き荒ぶ風の冷たさ、暖炉の火の熱、砂の感触。荒々しく響く波音、一心不乱なデッサン音、密かな衣擦れ。濡れた唇、乱れた髪、蝋燭の灯りに浮かび上がる肌の艶かしさ。論理で説くのではなく、表現は極めて感覚的、叙情的。台詞は少なく、けれど鋭く。
情感一杯にロマンスを詠い上げながら、一方で、観察する画家の目のように冷静に。女性の冷遇、自由の抑圧、と、ともすれば社会的倫理的な主張に偏りがちの所を、監督は、女性達を可哀想な被害者ではなく、自立し、逞しく強くしなやかなものとして描く。男達がどうあろうと、女は女として存在し続けるのだと。
画家は信念をもって芸術の道を選ぶ。女主人は、遠方の縁談を選んだのは退屈しないためと豪語する。侍女は赤子に手を握られながら堕胎し、男の裸体を画く事を許されない女画家がその堕胎を描く。女達は夜の帳の下朗々と自由に歌い上げる。そして、画家に啓示を与え、芸術となって永遠を得た娘は、潰えた恋の思い出に慟哭しながら、それでも恍惚と笑みを浮かべるのだ。振り向く事はせず。
女性という性が持つ業、身体と感情、苦しみと喜び。【女】という対象物を、いとおしむ眼差しで見事に描き出した肖像画。
成る程、これは女性監督にしか成し得まい。
油絵
スルメのような作品とでも言うのだろうか?噛めば噛む程味が出る的な。
ただ、キャラクターの内面に寄り添うような構成なのかカットが長い…と言うか深い。なのでその辺に惹きつけられなければ「緩やか」だとの印象が拭えない。
俺は若干、寝た。
なかなかに手厳しい話なのだ。
女性が自らの意思で生き方を選べなかった時代の話で…そこに同性愛の話も乗っかってくる。
結ばれる未来などないのだ。
別離しかない恋情なのだ。
けれども惹かれ合う気持ちは止められない。相手に惹かれれば惹かれる程、悲劇の度合が増すのだ。
それを最後の最後まで秘めていたのは、その刹那を濁したくないとの想いからなのだろうか?
ラストの交わらない視線…アレは偶然の産物なのだろうか?機会は偶然だったとしても「被写体に戻る」って意思が痛烈に伝わってくる絵だった。
鑑賞途中に思うのは「色彩」だった。
衣装やメークは世界観なので当時が反映されてて当たり前なのだけど、動く油絵を目指したと言わんばかりの質感だった。
それに伴い表現されるものは勿論あって…色々と小難しい事を考える。
美術品以外の側面から見た時の油絵とでも言うのだろうか…固定とか、非干渉とか、普遍の価値観とか、色褪せないとか。ノスタルジーな事だけではないのだろうなと思う。そして登場人物達が絶妙に18世紀。油絵の被写体が抜け出てきたのかと思う。
さすがはフランス。
相変わらずのお家芸は健在だった。
■追記
talismanさんのレビューが素敵!
ラストの考察に至極納得。
写真もない時代に肖像を描くということ
予備知識ほとんどなく観賞
こういうフランス映画もたまにはいいじゃないか的ノリです
感想としては
・シンプルでテーマは絞りやすい構成
・音楽がほぼなく集中力維持が大変
・目力ある女優さんの演技に惹き込まれる
・凝ったカメラワーク
色々賞をもらったというほどのインパクトは
感じないもののなかなか印象的な作品でした
18世紀のフランスで婚約の肖像画を任され
孤島にやってきた女流画家マリアンヌ
自殺した姉にもショックを受けている令嬢エロイーズに
最初は目的を悟られぬよう接しながら
少しずつ肖像画を描き上げますが肝心の本人に
出来を認めてもらえず
もう一度描き直す中でエロイーズは肖像画を描く
事を了承します
エロイーズは婚約を望んでおらず状況を少しずつ
理解しながら交流を進め距離を縮めるごとに二人は
(当時としては)禁断の愛に目覚めていきます
エロイーズがそもそも婚姻を嫌がっている理由が
それだったかは定かではありませんが
肖像画を描くという行為が相手を知りどんな人物かを
理解し一枚の絵から人物像が浮き出るよう描き上げる事で
それがきっかけで愛が芽生えてしまったわけです
マリアンヌの製作は捗りますが徐々に花嫁姿の
エロイーズが浮かんでは消えその絵の完成が
何を意味するかをマリアンヌも感じ取っていきます
そして自他ともに納得のいく肖像画が完成したところで
マリアンヌはエロイーズが嫁いで別れなければ
ならない事がつらいとつい吐露してしまいますが
エロイーズは突き放すマリアンヌに失望し
悲しみにくれますがやはり状況的にかなわぬ恋
途中出てきた有名なギリシャ神話のオルフェウスの
冥府下りになぞらえ別れ際の「振り返ってはいけない」
約束に対しマリアンヌはやはり振り返り
花嫁衣裳のエロイーズを一瞬視界に入れ
それ以降しばらく会うことはなくなります
その後マリアンヌは一度目は子供と一緒に絵画として
出会うことになりますがエロイーズの手には
自分の絵を残した本のページが記されており
もう一度オペラで会ったときには目も合わせることは
ありませんでしたがその眼には一筋の涙が伝うのでした
LGBTがどうとかといった話は一切抜きにして
素直にストレートな純愛ストーリーだったと思います
写真のない時代の肖像画というものの意味
音楽がほとんどなく集中力というか眠気が襲ってくる
部分もあるにはありますが頑張って観てみると
色々感じ取れていい作品でした
全169件中、121~140件目を表示