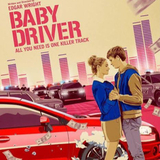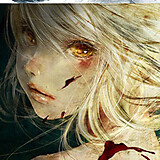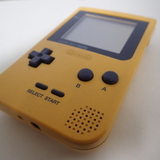燃ゆる女の肖像のレビュー・感想・評価
全169件中、101~120件目を表示
(^_^) 久々の見応えある映画、激しく推奨。
激しく推奨!!!
久々の見応えある映画。
孤島に住む母と娘。娘エロイーズは歳の頃30歳前半、完全に婚期を逃して世間を何も知らず島に閉じこもる。姉がいたようだが自殺。
この娘の結婚の話がありお見合い用の肖像画を描きにパリから女性の肖像画家マリアンヌが訪れる。2人は惹かれ、愛しあい、別れ、そして再会を、、、、。
美しすぎる。同性を愛する話であるがノーマルな人が見てもグッとくるはず。
愛し合う2人は本当に美しく見えます。
ラストとラスト手前は感動しました。
ラスト手前は別れて数年後マリアンヌがエロイーズの肖像画を偶然絵画展で見つけるんですけどエロイーズはマリアンヌを忘れていなかったことが絵画を見ただけでわかります。ハッとされました。
そしてラスト、オーケストラのコンサート会場で会場のトイ面でマリアンヌはエロイーズを見つけます。マリアンヌはエロイーズは私を見つけていないと言いますが、、、、、。感動的な曲とともにエロイーズの涙を浮かべた顔のアップ。私はエロイーズがマリアンヌの方を向くんじゃないか?向くんじゃないか?向くんじゃないか?と思いつつ映画はそこで終わります。完全作者の術中にハマってしまいました。
完全ネタバレ スンマソン。
あの終わり方、、、、さすがフランス映画。日本人と通じる物を持っていらっしゃる。
〝万引き家族〟同様、ラストは視聴者に託されています。
ちゃんと睡眠を取ってから見た方がいい。
.
婚約を控えた貴族の娘の肖像画を描くために、フランスのある島の館にやってきた女性画家の話。
.
この話すごく『君の名前で僕を呼んで』に似てるなと思った。ひと夏の恋、男同士、舞台はイタリア、ラストはエリオが泣いているのを正面からくつして終わる(音無し)。
.
これを全部逆にすると『燃ゆる女の肖像』の話になると思った。ひと冬の恋、女同士、舞台はフランス、ラストはエロイーズがそっぽを向いて泣いているのをうつして終わる(大音量のオペラ)。
.
あとは、毒蛇から妻を救うために地上に戻る際、絶対に妻の方に振り向くなと言われていたのに振り向いてしまい永久に妻を失ったオルフェウスの神話が出てくるんだけど、これ『窮鼠はチーズの夢を見る』でも出てきてる。
.
今ケ瀬が見ていた映画はこのオルフェウス神話を元にした『オルフェ』という映画で、だから『窮鼠』の2人は向き合うと上手くいかなくなるのよね。
.
こういうのを考えると最近のLGBTQ映画の流れって全部同じ流れの中にあるのかなと面白かった。
.
思えば初めて2人が対面する時も先を歩くエロイーズが振り向いていて、だからこそマリアンヌは彼女の顔を見れて絵を描くことができる。でも絵が完成するとエロイーズは嫁ぎに行ってしまう。
.
この映画の中で振り向く行為を肯定してるマリアンヌは、いずれ別れなければいけないと決まっていても、見つめ合って絵を描くという一瞬の大きな幸せを掴んだのかな。そして最後エロイーズが一度も顔を向けてくれないのに繋がってきて悲しい。
.
なんか途中めっちゃ眠たくてそんなハマってないなとか思ったけど、これ書いてるうちにすごい良い映画だったんだと実感している(笑)
【"緋色と翡翠色"の二人の女性の禁断の恋" 18世紀フランスの離島を舞台に、気品溢れるエロティシズムな映像でその様を描いた作品。鑑賞後の僥倖感にじっくり浸れる作品でもある。】
■特に素晴らしき点
・肖像画家のマリアンヌ(ノエミ・メルラン)と、伯爵夫人の次女エロイーズ(アデル・エレル)の笑顔なき出会いから、徐々に打ち解けて行く過程を彩るフランスの離島の海岸の荒々しくも、美しい風景。
- この海岸の様々な風景が、二人の関係性の変遷と、重なって見える・・。-
・マリアンヌは、住込みの少女ソフィーと徐々に心を通わせ、伯爵夫人が島に戻るまで、彼女達(途中から、エロイーズも)が一緒に食事を食べるシーン。及び少女の堕胎のシーン。
- イロイロな事を語っていると思ったシーンである。
当時は貴族と女中が共に食事をすることはなかった筈であるし、堕胎も・・。-
・二人が愛し合った後に、マリアンヌが、エロイーズにあげた本に、エロイーズの横臥の裸体を描くシーン。
そして、数年後、展覧会でマリアンヌが、エロイーズとその幼き子供の肖像画を見るシーン。エロイーズが持つ本のページが描かれている事にマリアンヌが、気付くシーン。
- 見事である。唸らされた。-
◆マリアンヌが書き上げた「燃ゆる女の肖像画」が、マリアンヌと、エロイーズの二人の顔が合わされているように描かれたように、私には見えた・・。
・ギリシャ神話の”オルフェウスの冥府下り”のシーンを、”今までにないオルフェウスの妻が夫の目の前で”冥府”に引き戻される姿”を描いたマリアンヌの意図。
- 分かりやすいが、オルフェイスはマリアンヌ、オルフェスの妻はエロイーズであろう。ー
・マリアンヌが、エロイーズに様々な感情を拙いピアノで伝える序盤のシーンと、ラストの「ヴィヴァルディの四季/夏の第二楽章からの嵐」が、激しく奏でられる関連性。
オペラ座で、二人が遠目に再会しながら、エロイーズが一切、マリアンヌの方を見ずに、毅然とした態度を崩さない中、涙を流す横顔。
-今年の、個人的に激しく魂を揺さぶられたシーンである。見事である。-
・18世紀の貴族の衣装、住んでいた館の意匠の美しさも、この作品に深みを与えている。
<素晴らしき作品に出会えた事に、心から感謝である。>
深いような。
人って狭い所で生きてると、色々偏りができてしまうもの。
2人が別れた後のエロイーズとエロイーズの子供の肖像画を目にしたマリアンヌ。マリアンヌはエロイーズを片時も忘れてなかったように思えた。だから切ない。
エロイーズの手にしている本の28ページを見て、報われたのかな?
それでも切ないな。
だって、自分は独身なんだもん。
って思ってしまった。
3人とも素晴らしい演技でした。
永遠の愛の獲得と喪失を同時に表現した巧みな脚本
画家のマリアンヌは離島の貴族から娘、エロイーズの肖像画を描いてほしいと依頼される。
写真もない時代。
女性の肖像画を送り、相手が気に入れば婚姻が成立する、というのが当時の習わし。
エロイーズの母もまた、送った肖像画を気に入られて、この家に嫁いで来たのだった。
しかし、姉の死により、本土の修道院での暮らしを楽しんでいたところを呼び戻されたエロイーズは、結婚を望んでおらず、不機嫌だ。
マリアンヌの前に依頼された画家は、肖像画を描かずに帰った。エロイーズが、画家に、まったく顔を見せなかったのだ。
そこでマリアンヌは画家であることを隠し、“散歩の相手”として、エロイーズと接し始める。
マリアンヌは当初、怒りで心を閉ざしていた。しかし、エロイーズと徐々に打ち解け、信頼し合うようになり、やがて恋に落ちる。
この過程で、2人がどんどん美しくなっていくのが見事だ。
だが、肖像画が完成すれば、マリアンヌは島を去らなければならない。そしてエロイーズは結婚に向かうことになる。
映画の中の愛は、いつでも「時間限定」だ。
「スピード」のキアヌ・リーブスとサンドラ・ブラックが、事件が終わったあとも長く付き合っているかどうかを問うのは野暮である。
「スター・ウォーズ」のシークエル・トリロジーで描かれたハン・ソロとレイア姫の“その後”は、現代的なリアリティはあるが、苦い。
それでも映画は、描いた愛の強さを伝えるために、愛の永遠を表現しようとする。
本作では常に、「見る」「見られる」関係が意識される。
画家のマリアンヌは肖像画を描くためにエロイーズを観察する。つまり本作ではマリアンヌが「見る側」、エロイーズが「見られる側」にある。
マリアンヌが島を去るシークエンスは、劇中に登場するギリシャ神話のオルフェが伏線になっている。
オルフェは死んだ最愛の妻を取り戻すため、死者の国に下り、そこで妻を連れ帰ることが許される。
ただし、条件があった。
死者の国から地上に戻るまで、後ろを歩く妻のことを一度も振り返ってはいけないのだ。
ところが途中でオルフェは振り返ってしまい、妻は再び死者の国に落ちていってしまう。
オルフェが振り返ったのは妻を愛するがゆえである。そして、永遠に妻を喪うのだ。
島を去る場面。
マリアンヌは、エロイーズと短い抱擁を交わしただけで、足早に屋敷を出ようと階段を降る。追いかけるエロイーズは「振り返ってよ!」と叫ぶ。
マリアンヌが振り返って見たのは、踊り場に立つウェディングドレスを着たエロイーズ。
その姿は、マリアンヌが2度も見た幻と同じ姿である。その幻を見るシーンも、マリアンヌは「振り返って」見ている。
マリアンヌは「見る」、エロイーズは「見られる」。
これが2人の愛の関係である。
オルフェは愛の物語だ。
オルフェの深い愛と、と同時に、その愛が喪われることを表している。
マリアンヌはなぜ、振り返ることなく足早にエロイーズの元を去ろうとしたのか。
それはオルフェの物語が頭にあったからではないか。振り返ってしまい、エロイーズと永遠に会えなくなることを恐れたからではないか。そしてマリアンヌが2度も幻を見てしまったのもまた、その「恐れ」の深さゆえなのではないか。
と同時に、愛するがゆえ、その後のエロイーズの幸せを願ったからではないか。オルフェが振り返ったことで、妻は死者の国に落ちた。エロイーズの結婚が、彼女にとって「死者の国」にならぬよう、マリアンヌは振り返ろうとはしなかったのだろう。
ラストに入る後日譚が秀逸である。
後年マリアンヌは、絵の品評会にいる。彼女はギリシャ神話のオルフェを題材にした絵を出展していた。
そしてマリアンヌはそこで、エロイーズが描かれた肖像画を見る。エロイーズの手には1冊の本、そして28ページが開かれている。
そのページは、余白にマリアンヌが自画像を描いたページだ。
肖像画には、その人の価値観や大切にしているものを一緒に描く。マリアンヌは、エロイーズの愛の永遠を知る。
そして、ここでもマリアンヌは「見る」、エロイーズは「見られる」側だ。
さらに、その後、マリアンヌは音楽会でエロイーズを見かける。エロイーズは口を開けて、感情をたかぶらせ、涙を流しながら音楽を聴いている。
曲はヴィヴァルディの「夏」。それは、かつてマリアンヌがピアノで、エロイーズに弾いて聴かせた曲だった。
そして本作の最後のシーンでマリアンヌは、こう語る。「エロイーズは私を“見なかった”」。
そう、マリアンヌは「見る」側で、エロイーズは「見られる」側。これが2人の愛の関係である。島にいたときと変わってはいない。だから、確かに、ここに永遠の愛は存在している。
しかし、愛はあっても、2人はもう会うことはない。それは、オルフェと同じく。
ここに、愛の喪失がある。
この愛の永遠性と同時に喪失を表す、素晴らしいラスト。
喪われてもなお、残り火のように熱を持つ愛。2人の想いの深さと切なさに打たれる。
「28ページ」、ヴィヴァルディの「夏」、そして「オルフェ」。親密になっていく過程で語りあった音楽や文学が、すべて伏線となり、島を去るシーンと後日譚に意味を持つ。見事な脚本である。
それらが生み出す、観終わったあとに心に刻まれる余韻の深さ。それが心を掴んで、しばらく離さない。
傑作だ。
♪僕にパスをください あゞ藤井ノンパス藤井ノン
画と音の圧倒的な美
燃ゆる女の肖像-今年ベスト級の映画に出会ってしまった。全てのシーンが絵画のように美しい圧倒的な画の力…(冒頭の暖炉の前で煙草をふかすシーンから一瞬で虜にさせられる)そこに与えられる甘美な音の表現がまた凄い。キャンバスをはしる筆の音、暖炉で薪が燃える音、家具や床の軋み、蝋燭や煙草を灯す音、パンとワインを食する音、刺繍の針と糸が布を通る音、風や波の畝り、息遣い、瞬きの音すら聞こえてきそう…そんな静けさの中に響く無数の音に誘われ没入していく。それらの音が音楽へと変わる限られた場面では彼女達の感情の隠微が現れ、二人の心が燃え上がる瞬間に流れ出す歌はそれまでの静寂を打ち破る、緩急という言葉ではおよそ片付けられない鮮烈な、鳥肌が立つシーンだった。そして彼女らの眼差しとスクリーン越しに目が合う瞬間、じわりと身体の奥底が熱くなるのを感じた。息をのむエンディングはcall me by your nameのそれと並び称したい。大げさじゃなく全人類に見て欲しい傑作。
2020年ベストムービー!⭐️⭐️⭐️⭐️✨
村の祭り?(村の集会?)のシーン、エロイーズの服に一瞬火が燃え移り、美しく燃え上がります…とても官能的な場面でした。そして、まるでホラー映画みたいなコーラスから(笑)、美しい歌声へと変わっていくシーンは、ちょっと鳥肌ものでした(オリジナル音楽だそうです)。
監督の細かい演出…息遣いや表情の変化など、心理描写が上手く、なかなかドキドキさせられました。
とても印象深い作品でした…オススメです!
画は綺麗で尤もらしいが。
日常の音を再認識した
一瞬一秒、息も出来ぬ圧倒的な美しさ
「ため息も出る美しさ」という表現があるが、この作品はため息すら許さない美しさ。
・2人の気まずい沈黙の空気から手の届かない官能的な空気感。
・登場人物を観察するかのような長回しカメラワーク。
・島の風景とその空間の撮り方。
・波の音、民族音楽、オーケストラ(ヴィヴァルディ)など映画館の音響を引き出すサラウンド。
その全てが研磨かれた圧倒的な美しさ。
この映画はとても淡々な展開し、とてもあっさりと幕を閉じる。
観客側としてはこの映画が創り出す「手の届かぬ儚さ」という美しさにもっと浸っていたかったのだが、とてもあっさりと終わってしまうのだ。
展開だってそう。
全てはこのシーンの為に!という普通ならベタ演出で観客を泣かせるような大切なシーンもなんの飾っけもなく淡々としている。泣かせる気もない。
しかし、そこにこの作品ならではの「美しさ」がある。
暗闇の劇場の大スクリーンで映画を観るという行為に付きまとう虚しげな感情。
ーすぐそこにあるのに手が届かない
この悶絶にも似た感情を観客に爆発させる美しさと官能。
そして、追い討ちをかけるのがこの「あっさりと終わる」だ。
『バードマン 或いは…(略)』でも表現されていたあくまでも日常の延長線上にあるストーリーで現実味が増すし、感情移入もしやすい。
この映画鑑賞の副産物とも言える感情を引き出すように創られた繊細で綿密な脚本でした。
カンヌ国際映画祭脚本賞も納得。
最初は「燃ゆる女の肖像の美しさに萌えた!」みたいな感想を書こうとしたけど、正直な感覚とは違ったのでやめた。
萌えなかったし。でもこの映画を生み出した監督の才能に対する嫉妬心は燃え上がりました。
ああ…
この映画はこれからもっと観ていきたい。(見事、作品の罠にハマってる)
取り残されました。
恋愛映画に惹かれたことはなかったが
映画史に残るクライマックス
今年のベストワン。さまざまな暗喩に満ちた神話の世界。表層的には肖像画家が貴族令嬢の結婚用肖像画を描く仕事を通じて恋愛に発展、絵の完成とともに別れが来るという時限的な残酷な愛の悲しみ、という本筋。しかしその裏側に監督が仕掛けた裏テーマをどう読み取っていくか。ハリウッド映画ではまず不可能な、鑑賞後に仲間と解釈の意見を戦わせることができる久しぶりの「討論用の映画」でもある(「ミッドサマー」以来かな)。
ともあれ、物語の舞台をどう解釈するかから始まる。一枚の絵の登場で回想に入って、本筋が始まる。メインの物語はすべて過去を回想しているもの、という前提を忘れてはいけない。
画材とともに海を小舟でわたり、絶海の孤島にある貴族の館へ向かう画家。途中、海に落としたキャンパスを冷たい海に飛び込んで拾い上げる彼女のエピソードは何を暗喩しているのだろう。途中語られるオルフェの物語、小間使いの堕胎、村の女性たちの祭での歌声、姉の死の真相、ヒロインの母へのルーティン行動、唯一ラスト間際に食堂で男が食事をしている描写、すべてに意味をもたせているような描き方。現世にいる画家、海を渡ることによって彼岸へ行き、肖像画を描き、そのモデルを愛し、しかし完成とともに再び海を渡って現世へ戻る。そんな解釈をさせる象徴的なシーンが館を去る時にヒロインが画家を呼び止め振り向かせるくだり。あたかもオルフェのクライマックスのように。
スクリーンに映されるのは、静かな平坦このうえないドラマが粛々と進んでいくように見える作品だが、そこには膨大な情報=意味が詰め込まれて、観客を圧倒していく。
その後の出会い、一回目の再会の静かな感動に観客は溜息をもらすだろう。そして二回目にして最後の再会は映画史に残るクライマックスだと断言できる。そこではヒロインのアップが数分間長回しされる。その圧倒的な演技に、ここまで見続けた観客の心を締め付け、息を止めさせ、うちのめす。
終始、美しさに息をのむ。
絵画を映像にした芸術映画
女たちのものがたり
全169件中、101~120件目を表示