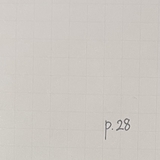燃ゆる女の肖像のレビュー・感想・評価
全171件中、1~20件目を表示
私は振り向かずにいられるだろうか
ミニマムな舞台設定で、よくぞここまで描ききったなと感嘆する。
18世紀のフランスの辺鄙な田舎の館は、登場人物が身につけているコルセットと同じように彼女たちを閉じ込める。
自然の音以外で唯一耳に聴こえてくるヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲。「夏」だろうか。まさに二人の人生の短い夏を象徴するかのように時に気だるく、時に激しい。
本作は二人とも女性であるし、その必然性は理解できる。しかし、二人がいかなる性別の組み合わせであったとしても…。いや、二人ともが女性であることがメッセージとして大切なのだ。
これをきちんと言語化できないことがもどかしい。
描くこと、振り返ること=想い起こすこと
セリーヌ・シアマ監督作品。
18世紀後半のフランス。女性画家のマリアンヌは、伯爵令嬢のエロイーズの肖像画を依頼される。肖像画を描くのはエロイーズが結婚をするからである。姉の自死が運命づけるエロイーズの未来。二人は「肖像画」を描くことで接近していく。
本作では「描くこと」と「振り返ること=想い起こすこと」が象徴的に描かれている。
描くことは本作のマリアンヌの職業であることは言わずもがなである。ただし描くこと、特に肖像画であれば、対象≒他者をみつめ、「線」を引かなければ不可能なのである。〈私〉が〈他者〉をみつめることで、好意を寄せたり、理解をすること。そのことが「描くこと」に表象されているのである。しかしそれは「死」も意味してしまう。描いてしまうことは、他者や好意を過去に追いやる。それは決して現在に継起しない死するモノである。そしてこのことは「振り返ること=想い起こすこと」とも関係する。「振り返ること=想い起こすこと」は、オルフェウスが冥府から妻のエウリュディケーを連れ戻す際に不安で振り返り、死んでしまったことに言及され、意味づけされる。つまり「振り返ること=想い起こすこと」は、現在に他者が存在しないことが不安であるためにされることである。振り返った途端、他者は過去になり、死へと向かう。このように「描くこと」と「振り返ること=想い起こすこと」は死に近接する事象である。
しかし私はこの事象のラディカルな価値を本作では示していると思うのである。
他者としての女をみつめることや描くことは、18世紀のフランスでも現在の日本ー西欧化される世界ーでは男の領分にされている。さらに女、特にヌードを描くことは宗教的な大義名分や芸術の崇高さによって正当化されてきたが、そこには性的な搾取が多分に含まれてきた。
そんな社会の中で、本作の「描くこと」はラディカルである。女のマリアンヌが女のエロイーズを描き、またマリアンヌの肖像画をエロイーズに渡す相互性、マリエンヌのヌード描写をヘテロセクシュアルな恋愛の文脈から逸脱させることは上述の常識とは違うのである。
常識は社会規範や法によって形作られる。本作は法=社会規範=常識を逸脱させながら彼女らを描いていくのである。
「法」の逸脱は、ソフィの中絶でも象徴的である。中絶が違法とされた時代、中絶を遂行することは彼女らが文字通り死を賭けた行為であった。それは同性愛も然りである。しかしこの死を賭けた行為は、マリエンヌやソフィ、エロイーズにとって、セクシュアリティや階級を超えて、女の連帯を可能にさせるのである。
彼女らは「法」に立ち向かい、逸脱しようともエロイーズの肖像画は完成し、エロイーズは結婚してしまう。
エロイーズは悲劇的な結末を迎えたが、最愛の人に肖像画を描いてもらったから幸せだった。
そんなことを私は言えないし、言ってはいけないと思う。男によって構成させる「法」は依然として存在しているからだ。この「法」が変わらない限り彼女の死を美化させてはいけないのである。「法」は変革可能である。それは中絶が容認されたように、同性愛が社会的承認を受けるように。しかしそれは今なお政治闘争のさなかにある。それなら私たちは、対象≒他者をみつめ、他者や「法」を描き続けなければならないのではないだろうか。そのためには「描くこと」や「振り返ること=想い起こすこと」が必要だ。それは死に近接している。しかしそれは死するモノを現在に回帰させ、未来を想像/創造することも可能にするのではないだろうか。それが「描くこと」と「振り返ること=想い起こすこと」のラディカルな価値ではないだろうか。
「燃ゆる女の肖像」。それはマリアンヌがエロイーズをみつめ愛が発現した瞬間だ。と同時に女は燃えている。今も燃えている。「燃ゆる女の肖像」をみつめる私たちは、何を描き、振り返り、想い起こすのだろうか。本作もまた私たちをみつめている。
完璧かよ。
正直、語りづらい映画だと思った。というのも、どこの瞬間を切り取っても完璧にしか見えなくて、もはや付け入るスキがない。もう、伝えるべきことはすべてそこにあるので、観てくださいしか言いようがない。一応ライターという名目で仕事をしてる者として、かなりの敗北と言わざるをえない。
かといって、説明的なのではない。むしろ説明は極力省き、なんなら登場人物も極力絞り、人物や物語の背景に関する情報も最小限に留められている。静かに、淡々と進むようで、とても熱い。そして、静けさを一気に打ち破るのが、炎と、人海戦術による歌声というあまりにもダイレクトなぶっ込みであり、「繊細かつ大胆」みたいなあまりにも陳腐な言葉をついつい書いてしまう。やはりこれほどの敗北感を味わう映画にはなかなか出会えない。完璧か。
🔥🔥
憤怒に満ちた愛の讃歌が観客に与える不思議な感情
18世紀のブルターニュの孤島で暮らす貴族の娘、エロイーズは不機嫌極まりない。母親が気の進まない結婚をゴリ押しする上に、お見合いのための肖像画を先方に送らなければならないからだ。なぜ、当時の女性たちは相手の顔も知らないのに自分だけ肖像画を差し出さなければいけなかったのか?ヒロイン一家に仕えるメイドが置かれた状況も含めて、甚だしい女性蔑視に対する押し殺した怒りが背後に横たわっていることは確かだ。しかし、そんな重々しい背景を凌駕して、エロイーズと肖像画家マリアンヌの恋が、孤島という閉ざされた空間を舞台に堂々と燃え盛っていく。たとえ人々に広く告知され、祝福されなくても、否、だからこそ秘めた思いは強く、エロチックな香りを放つもの。監督がエロイーズを演じるかつての恋人に捧げたという物語は、無駄なカットを極力削ぎ落として、憤怒に満ちた愛の讃歌を観客に向けて奏で続ける。だからだろうか、見終わった後、なにかに憑かれたような気持ちになるのは。
「見る」という行為
画家とモデル=見る側と見られる側という記号的な関係性は、これまでの幾度となく映画の題材として用いられてきた。対象をつぶさに観察し、その心情まで読み取って筆に伝えようとする画家の行為は、一方的な求愛にもよく似ている。そこが恋愛物語の語り部たちの想像力を刺激するのだろう。
「見る」という行為は、何にも増して禁断的で、潜在的な欲望そのものなのかもしれない。
思えば、日常生活において誰かのことを「見る」とは、とても限定された条件のもとで行われている。一定の秒数以上ずっと相手のことを見続ければ、それはすぐさま特別な感情や事情に紐付けられてしまう。
映画の舞台となった18世紀のフランスでは、女性同士がお互いを「見る」行為は、いま以上に社会的な束縛を課せられていたはずだ。だからこそ2人の行為はスリリングで、ゆえに絵画のように美しい輝きを放つ。
また、この映画はさらに、「見られる」側の心情にも踏み込んでいく。画家により一方的な求愛を受ける側は、どんな気持ちでこれを受け入れるのか。劇中、ギリシア神話のオルフェとユリディスの物語を引用し、「見られる」側の心情に独自の解釈を忍ばせるあたりに、この映画のオリジナリティがある。
こうした伏線をこれ以上ないかたちで回収するラストシーンがとにかく素晴らしい。われわれ観客もまた「見る」側となるのだが、それは、スクリーンの向こう側から覗く視線とは全く別物の、主人公と一体化した主観の視線にほかならない。その視線でわれわれは、「見られる」側の心情に寄り添い、禁断の愉悦に身を浸すことを許されるのだ。
Another Worthy Artifact in the Gallery of Painting Films
Portrait is certainly a modern social issue film that addresses abortion and female homosexuality. It hangs high on the easel for its deep literary presence equal to that of a fabulous oil painting, so much so its profound nature sings in shots of the artist's fundamental sketch marks. Costumes drape the actresses with the same mystery of classical paintings. A quiet film pleasant to gaze upon.
そのままでも愛すべき好作。背景を知るほど傑作の感を強くする
女性の人権や自由が男性より低く見られていた18世紀末のフランス。伯爵家の娘エロイーズは親に縁談を決められる。画家の父親と同じ職についたマリアンヌは慣例にならい父の名で作品を発表している。そんな2人が、見合い用肖像画の制作を通じて出会い、芸術を愛し自由を渇望する互いの魂に触れ、恋に落ちる。
監督・脚本のセリーヌ・シアマは、やはり女性同士の恋愛を扱ったデビュー作「水の中のつぼみ」のヒロインにアデル・エネルを起用。シアマはエネルと一時期パートナーだったが、友好的に別れた後、エネル(仏映画界でのMeToo運動の牽引役でもある)に新境地を拓いてもらいたいとエロイーズ役をあて書きしたという。監督の心情がマリアンヌに投影されたと知れば、ラストシーンでエロイーズを見つめるマリアンヌの眼差しから伝わる切なさが一層増し、彼女らの絆に感動も一段と深まるはず。音楽の使い方も絶妙で、焚火シーンの劇中歌は鳥肌もの!
スローだが、先が読めない展開にただただ驚く
完璧な・・・
エンディングでも流れていた、火を囲むシーンの、声の音楽素晴らしい。
映画館で観たかった🥲
油絵の具の匂いでバレるのではないかと思ったけれど・・・匂わない絵の具とオイルってあるの?
「映像」と「ラストシーン」が絶妙
本作の予告編を観るかぎりあまり触手が動かなかったが、第92回アカデミー賞国際長編映画賞ノミネートは逃したもののその他数々の映画賞受賞とのことで鑑賞。
ストーリーとしては想定内で特筆する点はないかも知れないが、「映像」と「ラストシーン」は目を観張るものがある。
映像的には赤いドレスと緑のドレス、黒髪と髪金のコントラストが実に美しい。
ラストシーンは今までのまったりムードから一転して一気に盛り上がり、3分近く続くエロイーズの複雑な表情を撮らえたアップからのエンドロール。この盛り上がりは予期していなかっただけにインパクト大。個人的には「歴代名ラストシーン」にランクイン。
その他「28ページ」へのこだわりや、本作タイトルの起源も絶妙。
本作を特に気に入ったというわけではないのだが、美しい映像と記憶に残る鮮烈なワンシーン、この2点があれば個人的には合格点といったところでしょうか。
あいをこんなにも美しくこんなにもイヤらしく・・
この作品の登場人物たちの間に湧き上がる感情を「愛」と書いてしまうと違うものになる。またエロティックなシーンもあるが、それもエロティックと言う程ドライでなくポップでもない。それは多少の湿り気を伴う纏わりつくような気配である。言葉にすると少し違うような気はするが、やはり「いやらしい」という言葉が最もフィットする。あとこの映画の卑怯な点はフランス映画である点だ。フランス語と言うのはそれだけで十分芸術的で音楽的である。視覚的な芸術性と聴覚に届く芸術性を兼ね備えたこの作品は非常に高潔でかつ美しく尊厳を以って毅然とそこに佇む。中でもモデルと画家と侍女が揃ったシーンはとても絵画的で息をのむ美しさがある。こうしてみるとこの映画を鑑賞すると言う事はまるで自分たちが美術館の名画を愛でながら回遊してるかのような錯覚に陥る。そんな不思議で美しく充足感に包まれる映画であるのだ。
こっち系のはあまり好きではないがなんかすごい
エロイーズお嬢様の見合いの肖像画を依頼された画家のマリアンヌと絵を完成させるまでの5日間の女同士の恋。
あまり感情移入できなかったけど私だけを見て描いて欲しいというエロイーズの気持ちとあなたの全てを見て描いてるわというマリアンヌの気持ちがジリジリ伝わってくる。始まりから物音とセリフだけで静かなのに感情が爆発するシーンになると女達のアカペラやオーケストラ出てきて音楽の効果絶大。
強い愛は個々の中に潜む
セリーヌ
"28ページ"
感想
この映画は最高で素晴らしかった
シンプルで美しい映像
理解を深めると完璧だったことに気づいた
でも最初はただ彼女たちをみて感じた
それで充分
しばらくしてから検索してみると理解が深まり解像度が上がった
監督や役者のインタビューを少しと海外のファンのコメントは興味深く 漁るのが楽しい
特別好きな作品になった
⚫︎見て所々感じたこと
エロイーズが振り向いた時、思っていたより大人っぽいと思った
儚いお嬢さんだと思っていたのだ
私の先入観とそれくらい前情報なしで見た
静かに進む物語 でも彼女たちの視線が魅力的で引き寄せられる
静かに怒っていたエロイーズ
海に入ったあとの彼女は子供に見えた
表情に幼い感じが少し出て
彼女らしさがだんだん見えてくる
なぜ散歩の友が来たのかわかって怒りとかがっかりの感情が見えてくる
カードゲームしてるとこ みんなかわいい
目で好意がわかる
途中、顔がよく映り、しゃべらなくても気持ちが伝わる
彼女たちが仲良くなっていくのがうれしい
ちょっと面白さもある
エロイーズのキリッとした表情で幼さがあるのが魅力に感じた
ちょっとユーモア担当
面白いと感じるとこについて話してる人見ないけど…
映像がすてき 色とかなんか色々演出とか美しい
この映画には男性がほぼ出てこない
でも彼女たちの人生に影響を与える支配力を持ってるのは男性だ
絵を取りにきた男達によって
ここにある平等も自由も終わったのがわかる
対等だった彼女たちは外では違う
当時の常識やルールが彼女たちをしばる
最後のシーンは圧巻
全171件中、1~20件目を表示