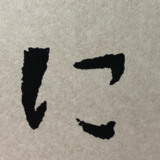グレース・オブ・ゴッド 告発の時のレビュー・感想・評価
全49件中、21~40件目を表示
淡々と描く素晴らしさ
小児性愛者の司教によって少年時代に深い心の傷を負った主人公たちが、司教及び、知っていてもほとんど何もしなかった教会を訴えていく話。
最初はそのことから30年経ち、ようやく妻に語れるようになった一人の男が、行動を起こす。行動し続けるうちに、同じ経験を持つ人たちが、一人二人と同調を示し、徐々にだが大きな動きになっていく。
冒頭から、ど真ん中のストレート。主人公が、子供時代の自分に起きたことを、妻ばかりか子供達にまで話し、訴えを始めていく。
ただ映画は、淡々と事実を描いていく。そこには、映画にありそうな大逆転や、思いもよらぬ裏切りといった
"劇的な要素" は、全くない。強大な妨害勢力が現れる訳でも無ければ、メンバー一同が契りを交わして一糸乱れず行動する訳でもない。だんだん人が増え、考えていることは少しずつ違うが、進めていく。その姿を、ただ淡々と描いていく。
しかし、それが実は、彼ら一人一人の苦悩を生々しく描くことにつながっている。訴えが届くかどうかは、もちろん大切なファクターだが、もっと大切なことは、彼らの苦悩を我々観客が肌で感じることなのだろう。
観ている私が感じるべきことは、「訴えが通った、あ〜気持ちいい」ではないのだ。被害者である彼らの苦悩を、気持ちを、少しでも感じとることなのだろう。
そんなことを感じながらの137分は、あっという間にすぎさっていた。被害者にも、様々な人がいる。しかし、誰でも苦しんでいる。苦しみ続けている。
終盤、息子が主人公に聞く「パパ、今も、神を信じる?」という問いかけには、明確な答えはなかった。あれだけ、「棄教すべきではない。内部から、教会をより正しく変えていくべきだ」と言い続けてきた主人公が、だ。被害者は、苦しみ続けている。
切り口
カトリック教の司教の犯罪と、それを隠す枢機卿は、語弊があるけど、いつの時代も、どこの国でも組織が違えど起きる事で…特にキリスト教を知らなくても、この物語に理解は出来た。立件までのストーリーがオムニバスではないが、なかなか、興味深い流れで感心した。
被害者もそうだが、被害者の関係者までもが、センシティブな内容に目を瞑るのは、きっと、フランスでも日本でも同じだし、勇気を持つこと、仲間がいる事で生きる希望が見える事もフランスでも日本でも同じだと思った。
正統派のオゾンも悪くない
これまでエロティックかつミステリアスな作品で魅了し続けてきたフランソワ・オゾン。しかし今作にエロさは微塵にもない。カトリック教会の神父による児童への性的虐待事件をストレートに描いた。
自らを病気だと認めなからも行為を続ける神父とそれを知りつつ黙認する教会。
大人になった三人の被害者たちがバトンをつないだ。彼らの負った傷と告発までの過程をじっくりと捉えた。彼らの苦悩を十分に納得した。
う〜〜ん、正統派のオゾンも悪くないなぁ。
説得力のある秀作でありました。
しかしエロいのもお願いしたいものです。
ちなみに同じテーマを扱った作品としてはマスコミによる糾弾を描いた『スポットライト 世紀のスクープ』のほうが好きかな。あの作品の展開と高揚感は凄かった。
苛立ちの釣瓶打ちに窒息寸前
長くかかった告発
二つの闘い
長年小児性愛者である事を隠されていた神父を
告発して裁判になっている事実を映画化している。
人類愛を説き、信者からは崇められている神父が、愛はアイでも幼きモノへの性愛だとは、ホントにぶったまげてしまうが、怖いのは、その事実を、知っていた上層部の者達の隠匿、訴えた子どもの声をきちんと聞かなかった大人それも家族であったことの驚きと怖さである。
見たく無いもの、聞きたくないものに真摯に向き合わず我慢を強いらせ、無かった事にしてしまおうとする体制や同調圧力、人々の沈黙の怖さ。
皆、敬虔なカトリック信者で、正直であれ、清く正しく生きよとの教えを学んでいても、権威や理不尽な事へ異を唱える事の難しさ、勇気を出す事の難しさ。
カトリックでなくても
己の心のあり方が問われている様に思えた。さすがオゾン監督👍
「被害を沈黙させられた」様々な被害者たちに見て頂きたい映画
当方、キリスト教会でモラハラ被害を受けた元牧師です。
この、フランスカトリック教会における司祭の児童性虐待事件を描いた「グレース・オブ・ゴッド 告発の時」を、大きな期待と密かな恐れを持ってを見に行きました。
「大きな期待」とは自分自身の感情の整理と未だ十分に言語化できない痛んだ心を誰かの言葉で表現して欲しいという思い。自分自身が少しでも癒されたいという渇き。
「密かな恐れ」とは描かれる加害者や周囲の心ない人たちの批判が、少しばかり似た境遇の私にも突き刺さりはしないかという恐れでした。
結論から述べますが、見て本当に良かったです。涙し、励まされ、こういう言葉をかけてくれる人が自分の周りにいたらどんなに心が楽になっただろうと思いました。
私にとってのハイライトは、二人目の主人公フランソワが警察から尋ねられるシーンです。多くの被害者たちがプレナ神父からの性虐待被害を沈黙せざるを得ませんでした。彼もまた大人になり無神論者になり、そして今までの生活が変わってしまうことを恐れ被害者であることを公にしようとはしませんでした。
多くの被害者たちにとって性虐待被害を言葉にするには20年-30年の月日が必要でした。ところが時効が成立してしまったケースもあり、プレナ神父は未だ法的に裁かれず子どもたちに聖書を教え続けていました。フランソワはそのことを知り、自分の約25年前の被害を警察に相談します。
「あなたは時効前です。告訴しますか?」と尋ねる警察に「告訴します。」とはっきりと言い切るフランソワ。彼の勇気ある告発が新たな被害を防ぎ、沈黙させられてきた被害者たちを癒し始めたのです。
私は自分が言ってほしかった言葉をフランソワにかけようと思います。
「よく言った。どれほどの勇気が必要だっただろう。どれほど苦しんだだろう。どれほど周囲の目が怖かっただろう。あなたの勇気ある告発によって新たな被害が生まれなくなった。」
一方、加害者のプレナ神父は被害者に対し「自分も子どものころ神父から性被害を受けた」と告白します。作中ではこの発言は、「同情を買うための詭弁だ」と表現されていました。ですが、私は映画を見る前から、事件の記事等を見てプレナ神父もかつて被害者だった可能性もあると考えていました。
プレナ神父の発言の真偽はともかく、作中で描かれる性被害を受けた男性たちは様々な苦悩を抱えています。家族関係、性的劣等感、社会への不適応など・・・それをオゾン監督は「性的虐待被害者を時限爆弾のように描いた」と表現しています。オゾン監督は被害者たちを「時間が経って爆発する爆弾を抱えさせられた」と理解しました。そして、これがオゾン監督が表現したかったことなのだと思います。被害者たちの様々な葛藤は本当に考えさせられます。
しかし、こう言うこともできるのではないでしょうか。「プレナ神父も時限爆弾を押し付けられた被害者だった可能性がある」と。
私はこのレビューのタイトルに、「被害を沈黙させられた」様々な被害者たちに見て頂きたい映画、と書きました。
これは第一に被害の癒しのためです。共感し、自分ができなかったこと、してもらえなかったことを映画で見るだけも癒される部分があります。
そして第二に、自分自身にはいつ爆発するかわからない時限爆弾が押し付けられていることを覚えておく必要があると思うからです。被害者の心は痛んでいます。身体ですら傷があれば自身の動きに影響が出ます。心をズタズタにされれば自身の言動に様々な影響が出てしまうことは避けられません。「時限爆弾を押し付けられた」という認識が必要なのではないかと思うのです。必要な助けを求め、新たな被害者、傷の連鎖を生み出さないためにも。
最後に、興味を持ってここまで見てくださったクリスチャンの方に。
隠蔽は神の義を軽んじた結果起こります。罪を矮小化するのは、神の義が軽んじられているからです。また、赦しとは罪を曖昧にし大目に見ることではありません。罪の深刻さを明らかにし、そんな罪人の私(あなた)だからイエスの十字架なくして生きていけないのですと十字架にすがる行為が、赦しを受け取るということです。
キリスト教会が罪を明らかにしないということは罪人を十字架から遠ざけることです(そして作中でも描かれるように、教会の罪も隠すために個人の罪を隠している)。社会的地位、プライド、信用、時として長年通った教会、そんなもの全部失った方が、裸の本当の惨めな自分で十字架に近づけるのではないかと思うのです。
私は主の最善だけが為されると心から信じています。被害に遭われた方々に主イエス・キリストの慰めと癒しがありますように。
犯罪として。
オゾン作品
フランス映画の佳作🌟
重いテーマのため、今まで迷っていましたが、「僕を葬る」でのオゾン監督とメルヴィル・プポーのファンなので観に行きました。
結果、やはり観て良かったです。
近年はヨーロッパ映画を観る機会が少なくなり、ハリウッド映画の「いかにも作りあげたゴージャス感」に慣れていた自分には、フランス映画特有のウェットな感覚・・・被害者たちが現在住む家、濃密な家族の在り方など・・・の描き方がとても心に染み入りました。
被害者の1人ひとりに丁寧に光を当てて描いていて、実はその妻のほうも性的被害を受けていた過去があったり、今まで息子の苦しみに気が付かないふりをしていた母親が、時を経て一所懸命に力になろうとしているところにもグッときました。
個人的に、リヨンを観光した時のフェルヴィエール教会などの景色も懐かしかったのですが、アレクサンドルが家族で祝うクリスマスのシーンは本当に美しくて・・・
息子達がカトリックの学校に通っていたり、日々の生活と宗教が切っても切れない環境にあって、それでも告発せずにはいられなかった苦しみがいかに深いものかを考えさせられずにはいられない映画でした。
静かな作品を見たい時にオススメします。
赦しより勇気
実話ということで、いつものオゾン風味は、やや抑え気味な気はしましたが、
とても丁寧に、実在の被害者たち、その家族や関係者に敬意をもって創られた作品だと思いました。
また、3人の被害者が順に描かれていき、同じ場所に集うまでが自然で、
面白いストーリ展開で、その辺りも、さすがのオゾン、
抑え気味ではあるけれど、やはり、彼が創る映像美や脚本や演出は素晴らしく、
さらに、今回、非常に音楽の効果が印象に残りました。
この事件のことは、この作品から知ったので良く解らないのですが、
信仰って難しい...。
アレクサンドルとプレナ神父とレジーナの面談の最後に手を繋いで赦しをこうシーンも、
違和感しか感じなかったし、
エマニュエルと面談して去るときの神父の笑顔にもゾッとしました。
「赦し」って何?
神の代わりを人間が出来るわけないのに、信仰により神格化みたいになっている気がして、
ただ、それも宗派によりそれぞれだろうし、そこまで詳しくないし...。
ただ、神父の行為は犯罪だし、隠した人たちも同罪だし、きちんと罰して、
被害者たちの心が少しでも平穏を得られることを祈るしかない...神を信じて...。
フランソワ・オゾンの新境地は、やはりさすがだった。
男性ゆえの苦しみ
騒ぎ立てない
いまだ戦いは続いている
予告で興味を持って観賞
カトリック神父の性的虐待を告発した人々の実話の映画化
なんかワールドニュースで見た覚えがある話でもありました
この映画の主人公は3人います
まず銀行マンの敬虔なクリスチャンのアレクサンドル
5人の子供も成長し長男が洗礼を受けようかという時期に
ふと幼少期自分が受けたプレナ神父からの性的虐待を思い返し
いまだ少年達と関わりを持つ神父から子供達を守るために
教会を通じてそれを認めるかどうかのために行動します
妻は積極的に協力してくれますが
両親はそんな時間の経ったことを今更と言う反応
教会もプレナ神父と会わせれば済むだろうという程度にしか
取り合わず神父も自身のペドフィリアは認めるも病気だから
仕方がないという他人事な対応でアレクサンドルは
怒りを通り越し落胆します
アレクサンドルはそこで他の性的虐待事件において
断固追及すると宣言した教皇の文言を引用し
バルバラン枢機卿にかけ合いますが神父の行為は
許せないが聖職を解くことはないと信じられない
返答をされついにアレクサンドルは教会を告発する
決断をします
…そして次の主人公フランソワ
性的虐待で告発されたプレナ神父の話を母から聞き
自身の虐待の経験から無神論者になっていたフランソワは
思い出したくないかのように関与を最初は拒否しますが
娘の寝顔を見るにいまだに少年達と関わりを持つプレナの現状に
怒りが爆発し神父と教会関係者もろとも罪を認めるよう
被害者の会を立ち上げ同じく虐待を受けた外科医のジルなど
協力者を募るとどんどん集まってきます
そしてそして最後の主人公エマニュエル
虐待による強いPTSDで身体や性格に支障をきたし
前述の2名に対し仕事も生活もうまくいっていなかったが
被害者の会設立を知り自身の体験を打ち明けます
この3人の主人公の違いはもちろんそれぞれの暮らし
体験や家庭環境がありますが何より大きいのは
告発自体の捉え方です
アレクサンドルは敬虔な信徒ですし家族が教会関係の
教師をしているのもあり教会主導による穏便な解決を
望んでいますが結局それがかなわず告発したのです
フランソワは無神論者になったし子供への危険をなくす事が
目的ですからなるべく世間にセンセーショナルに
伝わることが必要だと思って過激なアピールを画策し
あまりメンバーの賛同を得られていません
エマニュエルは前述の通り生活が上手くいって
おらず精神的にこの件に関与するとけいれん発作を起こして
しまう恐怖と向き合えずにいるところもありました
こんな調子ですから被害者の会のメンバーも数は
揃いつつも意見の相違がありなかなか方針が
決まらなかったり日常生活への回帰を望み協力を打ち切る
メンバーが出るなどしそんなんで強大なカトリック教会の
大組織とやり合えるかは不安しか残らないのでした
ただ被害者達に共通していたのは
苦しみを打ち明けるまでに何十年もの時間を要したことでした
その会合が終わりアレクサンドルは帰宅した長男に
「父さんはこれでも神を信じるのか」と
聞かれすぐ返答できず言葉に詰まったまま
終わっていくラストは印象的でした
そして衝撃的なのはその後のテロップ
この告発事件の裁判は未だに続いており
虐待行為を続けたプレナ神父を役職に起き続けた
枢機卿は無罪となるなど必ずしも被害者の会の意向に
沿った展開となっていないのです
決してハッピーエンドではないのです
こういった立場ある人間の性的虐待のニュースは
あちこち今でも見かけますが
反対運動が政治利用に使われたり
プライバシーを侵害したりうまくいっていない
現実がありますからこうした作品を観て
それぞれ考えてみるのも必要に思いました
おすすめしたいです
神父による性的児童虐待事件を被害者側から描く力作
仏国リヨンで妻と5人の子どもたちと暮らす金融マンのアレクサンドル(メルヴィル・プポー)。
敬虔なカトリック教徒の彼は、少年期にひとりの神父から静的虐待を受けていた。
そして、こともあろうか、件の神父プレナが、いまも子どもたちを教えていることを知る。
教会を通じて対面したプレナ神父は、アレクサンドルへの性的虐待の事実は認めたものの謝罪の言葉はなく、神父の上位者である枢機卿とも面談するが教会側の態度は煮え切らない。
思い余ったアレクサンドルは、プレナ神父を告発するが・・・
といったところからはじまる物語で、フランス中を震撼させた「プレナ神父事件」と名で知られるカトリック教会の児童への性的虐待事件を描いています。
丁々発止の裁判劇を期待していたが、本事件、現在も係争中というで、そのような場面はありません。
また、メルヴィル・プポーが演じるアレクサンドルを中心に映画が進展するのかとも思っていましたが、その後、フランソワ(ドゥニ・メノーシェ)、エマニュエル(スワン・アルロー)と別のふたりの被害者の物語へと引き継がれて、映画は多層構造を持っていきます。
この構造は、序破急の三部構成といえるでしょう。
序にあたるアレクサンドルの部で、事件を明るみに出し、
破にあたるフランソワの部では、被害者の会が結成されます。
当初、温和で大人しい人物にみえたフランソワが、会のリーダーになっていく過程で、過激で攻撃的な面を表に出していくあたりも興深いです。
急にあたるエマニュエルの部では、事件が明るみに出、会が活動する中で、救われ、新しい人生が始まろうとする様子も描かれます。
そして、特筆すべきは、アレクサンドルの立ち位置で、事件を明るみに出し、教会を糾弾するもの、カトリックへの信仰心は喪いません。
教会と信仰は別、というあたりが興味深いです。
実話を基にした社会派ドラマということで、フランソワ・オゾン監督の演出も正攻法なのですが、アレクサンドルの部は、彼と教会との間でやり取りされるメールをモノローグとして用い、書簡小説のように演出するあたりは、やはり非凡といえるでしょう。
それにしても、神父による児童性的虐待・・・
被害者のトラウマ、PTSDが凄まじいことが、この映画で伺えます。
本当にひどい・・・
虐待の加害者プレナも酷いのですが、それを知っていながら隠蔽し続けた教会組織の方が、より罪が重いと感じました。
なお、この事件が、『2人のローマ教皇』で描かれた、ベネディクト教皇からフランシスコ教皇に代わったきっかけになった事件ですね。
オゾンらしくないけど素晴らしい
被害者は数百人いるんじゃないかとも思われたプレナ神父の性的児童虐待。彼の被害にあった男子は何年もの間、被害を口にすることも出来ず、また親に伝えたものの軽くあしらわれたりして事件は表ざたにならなかった。そもそも親からすれば、敬虔な神父様がそんなことをするはずがないという固定観念によって、虐待の事実は闇に葬り去られていたのだ。
幸せな家庭を築いていたアレクサンドルが発端だった。未だに子供たちを教えている司祭となったプレナ神父に憤りを感じて、謝罪をしてもらうつもりで面会に応じるのだが、事実は認めるものの謝罪の言葉がなかった。バルバラン枢機卿にしても、教会としての罪を巧みにかわそうとするだけだったので、刑事告発するに至る。
一方で、時効が成立している匿名の被害者が告訴したことを受け、被害者の会を立ち上げたフランソワ。カブスカウトの名簿から同じように被害者を探し出して、皆で告発しようという目的だ。外科医の仲間や多数の被害者を見つけ、定期的に会合を開くようになる。
スカウトの子たちはほとんど裕福な家庭の子だったが、エマニュエルはそんな中でも両親の離婚により苦難の道を歩む。IQ140という頭の良さ(ゼブラと言ってた)が逆にあだとなり、友達もできない、仕事も恋愛もうまくいかなくなるという運のない人生を強いられてきた。プレナの名前を見るだけで痙攣発作を起こすという症状も痛々しい。
神父の贖罪、対する“赦し”を問う内容かと思ってたのに、全く違っていた。被害に遭った男子たちがカトリックの権威ともいうべき神父について沈黙を守らざるをえない状況。それを打ち破るための結束の物語。一人の神父とそれを擁護しようとする教会側との戦いでもあり、彼らのトラウマや人生の大半を台無しにされたことを世間に知らしめるものだった。
教会内の荘厳さを映し出していたりしているし、カトリック教会を非難したり糾弾するノンフィクションでもあるけど、宗教そのものを否定する作品でもない。教会の自浄作用、組織を正しく導くための訴えだと思う。中には信仰を止めるという者もいたけど、その時のアレクサンドルは結婚指輪を外そうか外すまいかと悩む姿を映し出していたし、キリストの教えは尊重しているのです。逆に会見でバルバラン枢機卿が不謹慎な発言をしたり、記者の痛烈な質問の方が的を射たりしていたのも面白いところ。
日本人にとっては馴染みの薄いところではあるけど、権威・権力によって性的虐待を受けることは親からの虐待事件と何ら変わりがない。親だから逆らえない。上司だから逆らえない。世間体、友人からは白い目、訴えれば逆にハニートラップだとして非難する輩もいる。有無を言わせぬ権力によって隠蔽工作する奴もいる。そんな世の中の暗部を真摯に描いたフランソワ・オゾンを称えたい。
3人の視点が良かった
フランスで、長年数百人にも及ぶ未就学男児への性的虐待を続けてきた神父に関する訴訟、「プレナ神父事件」を映画化。
ドキュメンタリーではなく、訴訟記録や証言から、再現フィルムのように作られた作品。
被害者は支えてくれる人の存在があって、言う勇気がでるのだなと。
そして恐怖と嫌悪感から身を守るためと、世間の好奇の目や仕事を喪う恐怖から、「なかったことにしたい」と思って沈黙する道を選ぶことが多いのだなと。
沈黙は更なる被害者を増やし、犯罪に加担することであると気づくまでに、人々は2~30年かかるという現実。
3人の視点で描いたのがよかった。
敬虔なキリスト教徒ゆえに、自分の子供たちを守りたい気持ちと、教会を変えたいという思いで訴訟という形で告発した「0から1にした」アレクサンドル。
棄教し、怒りからマスコミを使って世界に発信し、被害者の会を作った「1を100にした」フランソワ。
トラウマから、パニックを起こして失神を起こす障害を抱え、仕事も家族も持てなくなった「100の中の1」エマニュエル。
3人がそれぞれ、告発の<葛藤>、社会や家族との軋轢という<代償>、告発によって生まれた<希望>を表していたように思う。
そして浮かび上がらせたのは、犯人のプレナ神父は、自分が小児性愛者で、レイプ依存症であることを自覚していて、隠していなかったこと。
プレナは告発されるたび認め、子供に触れられないように、解任を(企業で言えば上司に当たる)地区教会の歴代枢機卿に訴えてきた。
しかし、組織を守るためと、プレナが信者と寄付金を集める才能に長けていたため、教会はずっと事件を隠蔽。
被害者の家族に「子供に触れさせない場所へ異動させた」と嘘をつき、町を変えただけで、プレナに同じ聖歌隊やボーイスカウトで子供に教える仕事を続けさせていた。
これ、完全に教会および枢機卿による、隠蔽と犯罪拡大(幇助)。
なのに、悪びれず「神が試練を与えた」「時効は神の祝福で罪を逃れられてよかった」と言い続ける枢機卿に、一番の怒りを抱きました。
別の事件ではあるが、神父の性的事件を告発するに至るまでのマスコミの苦闘を描いた『スポットライト 世紀のスクープ』と併せて見ると深みが出ると思います。
映画作品では『スポットライト ~』のように、訴訟に持ち込んだ人達の正義感の達成で完結することが多いと思うのですが、本作は訴訟が起きるまで言えなかった、普通の映画であれば「モブの一人」の心に至るまで、多角的・多面的に切り込んだところに意義があると思います。
時間的に、少々長すぎるのが難ですが。
2020年7月時点で未だ係争中ゆえ、この結末は今後も見守っていきたいと思いました。
主人公のスイッチがお見事
ノンフィクション物。
カトリック教会の性犯罪をテーマにしたものは「スポットライト」なり「二人の教皇」なり数多くあるが、きなり被害者側の視点になって具体的に映画化されていた。なので普通に勉強になる。
また特にアレクサンドル→フランソワ→エマニュエルと被害者となった主人公がスムーズに作品のなかてま移動していく。レベルの低い作品にありがちな「画面ブラックアウト白文字でチャプター○○」とならずに、それぞれの個性ある俳優に切り替わっていくところに感心した。
しかし、バチカンの上空に絵を描こうと空想したり、独走が目立つぽっちゃりメガネさんには感情移入できなかった。笑
信教と棄教
中学と大学の7年間をミッションスクールで過ごした自分でも理解しがたい「世界」だ。
「無宗教」である日本人には、ほとんど共感できない内容かもしれない。
児童への性的虐待を重ねてきた神父への謝罪を求める主人公のアレクサンドルは、神父と監督者である枢軸卿を糾弾するも、事件を隠蔽してきた教会や信教そのものを否定することに躊躇する彼の姿を丁寧に描いている。
フランスの敬虔な信者にとって、カソリックは生きる世界そのものなのであろう。信教を否定することは、生きることそのものを否定しかねない。(神の存在を信じない国民と)どちらが正しいか否かの問題ではなく、みえている「世界」が全く違うだけなのだろう。
重いテーマをドラマチックに展開するのではなく、淡々と確りと進めていく、フランスらしい良作。
全49件中、21~40件目を表示