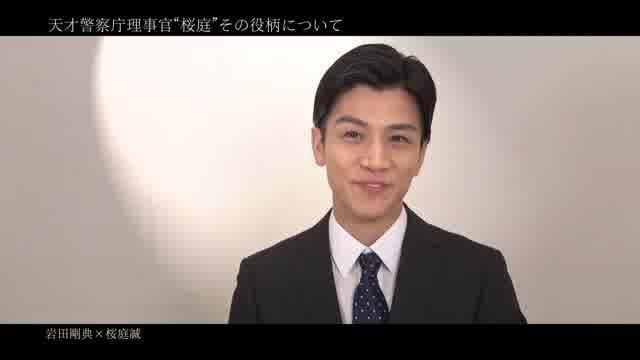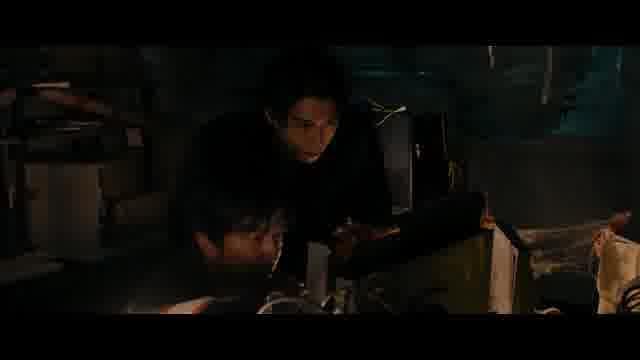「技術的な設定が穴だらけで入り込めない」AI崩壊 アラカンさんの映画レビュー(感想・評価)
技術的な設定が穴だらけで入り込めない
原作はなく、監督のオリジナル脚本だそうである。AI の専門家に取材を重ね、自ら人工知能学会に入会して知見を広めたという。しかし、この完成版を見る限り、肝心な部分の科学的リアリティがかなり欠如しているのではないかと思われてならなかった。
時代設定は今の 10 年後になっており、少子化が更に進んだ世の中のあり方や、自動運転車やネットワークなどの技術の進展はなかなかリアルに描写してあったと思う。今までなかった技術を世の中があっという間に受け入れ、やがてなくてはならないものに変化していく過程は、既にスマホなどで経験済みなので、映画の導入はよく出来ていると感心させられた。
だが、システムを作り上げた主人公が開発の現場の一線を離れて 10 年のブランクがありながら、最先端のシステムにソースレベルで関われるという話にはかなり疑問を感じた。今の世の中で、ネットや AI の開発現場にいた者が 10 年も現場を離れれば、使っている OS から開発言語までまるっきり変わってしまうはずである。それが苦もなく復帰できてしまうところにまず違和感を感じてしまった。
次に、仮に AI が人類一人一人を選別して生きる価値のある者かどうか判別したとして、殺害すると決めた人間に対して積極的に行動を起こせる人は非常に限られているはずであり、投薬などを一切行なっていない人には手が出せないはずである。そもそも、判別終了までの時間をわざわざ人間に向かって表示する必要はない。
設定としては面白いが、町中の監視カメラや車載のドライブレコーダーが全てネットに繋がっているというのもあり得ない話であり、更に警察の要請もなく動画や静止画のデータを提供するなどという話は、密告制度が徹底されているチンペー国や豚朝鮮などならともかく、日本では想定が困難な設定であると言わざるを得ない。
そもそもこの脚本は、機械学習というものを誤解しているとしか思えない。学習とは、与えられたデータに依存して分類境界を書き換えるなどの機能を言うのであって、プログラム自体には一切の変更を行わないのに対し、プログラムのハッキングは実行形式のカーネルの一部を書き換えることであり、この両者は全くの別物である。また、テキスト形式のソースプログラムを実行させるにはプログラムのコンパイルが必要であり、稼働中のプログラムを停止させずに上書きすることは出来ない。
コンピュータのプログラムを一度でもやったことがあれば常識的なこうしたことが、脚本では非常にいい加減に扱われているのにかなり面食らってしまった。コンピュータ関連の技術に関する描写は穴だらけというべきである。文系の人が考えた脚本なのが丸わかりである。このため、非常に技術的なリアリティを欠くことになってしまい、問題の解決のための行動がかなり釈然としないものになってしまったのが残念であった。
出てくる警察官が非常に安易に銃を使用して被疑者に肉体的なダメージを与えようとするのも全く釈然としなかった。爆発物を持ち歩いているテロリストを相手にしているわけではないのだから、被疑者を殺害してしまえば解決するというような事件ではないのに、あんなに簡単に被疑者の生命を危うくするような行動を起こしてしまっては、問題の解決を遅らせるばかりであり、最悪の場合は解決が不可能な事態に陥るだけである。
また、最終的な手段もテキスト形式のソースプログラムに依存したものであったが、仮に百歩譲ってあの方法が有効だったとしても、それをコンピュータに見せたければ、映像の全てをカメラのレンズ内に入れなくてはならないのに、大部分がレンズの外に漏れていたのには頭を抱えた。あれではソースプログラムのほんの一部を虫眼鏡で拡大して見たというだけになってしまう。
逃亡劇はそれなりに見応えがあり、協力者が出てくる理由も納得できるのだが、あらゆるプログラムが容易にハッキングされて上書きされるという話にはどうにも付いていけないものを感じてしまった。犯人らが行おうとしたことも実に馬鹿げた話であり、少子高齢化の対策に更に人口を減らそうというのであるから、もう何を言ってるのかというレベルの話になってしまっていたのが残念であった。
(映像5+脚本3+役者3+音楽3+演出3)×4= 68 点。