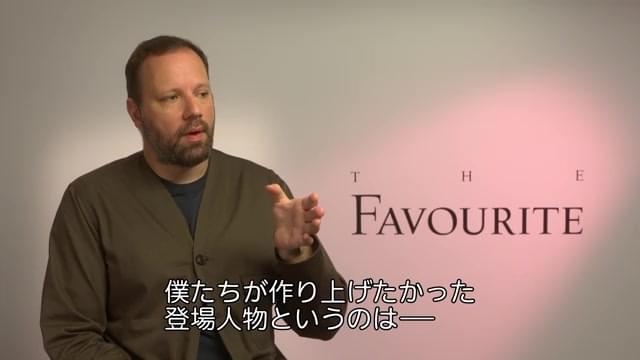「格調高くてお下劣な歴史コメディ」女王陛下のお気に入り ケンイチさんの映画レビュー(感想・評価)
格調高くてお下劣な歴史コメディ
すごく面白くて、毎日この作品ばっかり見ちゃいました。私は吹替派なのですが、セリフに乗せられた感情まで全部知りたくなって、両方交互に見ましたよ。
ということで基本情報。
監督:ヨルゴス・ランティモス(1973年生、公開時45歳)
脚本:デボラ・デイヴィス
トニー・マクナマラ(1967年生、公開時52歳)
制作国:イギリス、アイルランド、アメリカ
製作会社:フォックス・サーチライト・ピクチャーズ 他
配給:20世紀フォックス
出演
オリヴィア・コールマン(1974年生、公開時44歳)
エマ・ストーン(1988年生、公開時30歳)
レイチェル・ワイズ(1970年生、公開時48歳)
歴史劇ですし、きっとイギリス人ならきっと学校で習う内容でしょうから、歴史的事実も確認。
・アン女王(1665〜1714、享年49歳、在位1702〜1714、劇中37〜45歳)
・アビゲイル・メイシャム(1670〜1734、享年64歳、劇中32〜40歳)
・サラ・ジェニングス(1660〜1744、享年84歳、劇中42〜50歳)
・国務大臣ロバート・ハーレー(1661〜1724、享年62歳、劇中41〜51歳)
・大蔵卿(首相)シドニー・ゴドルフイン(1645〜1712、享年67歳、劇中57〜65歳)
・マールバラ侯爵ジョン・チャーチル(1650〜1722、享年72歳、劇中52〜60歳):サラの夫、軍最高司令官
・マサム男爵サミュエル・マサム大佐(1679〜1758、享年79歳、劇中23〜31歳):アン女王の小姓・侍従、アビゲイルの夫となる
この映画で描いているのは1702〜1710年、およそ8年間の出来事のようですが、時間経過をモヤッとさせている作品ですし、当時の人たちは生没年月日が曖昧な場合も多いので、厳密な年齢表記ではありません。
それからイギリスという国は島国ではあっても日本と違って単一民族国家ではなく「連合王国」という何とも微妙な国家形態で、その歴史もゴチャゴチャややこしい所があるので、歴史背景の理解も多少複雑です。
あくまで私の個人的な理解、超乱暴で超ザックリなイギリスの歴史ですが…
①イングランド成立
②イングランド + ウェールズ = イングランド
③イングランド + スコットランド = グレートブリテン
④グレートブリテン + アイルランド = 大英帝国
⑤大英帝国 - 南アイルランド = イギリス
って感じ。
①は西暦1000年頃?で漫画『ヴィンランド・サガ』の時代。
②は1300年頃?イングランドが勢力拡大。
③は正味1600年頃?、正式には1700年頃?
④が1800年頃?
⑤は第一次世界大戦の後。「狂乱の20年代」の出来事
③の少し前からイギリスの歴史は面白くなりますね。絶倫王ヘンリー8世以降、娘のエリザベス1世の時代まで、何度も映画化されるようなドラマチックなエピソードが続きます。そして結局、子供のいないエリザベス女王が崩御して、遠い親戚であるスコットランドの王様がイングランド王も兼ねるようになります。1人の王様が2国を治め、劇的な歴史ドラマは一区切り。
ここでイングランド王 兼 スコットランド王となったのがジェームズ1世。そのひ孫が本作の主人公アン女王。
ただしイングランドとスコットランドは宗教とか政治の派閥争いで色々とモメまして、なかなか合併できません。およそ100年かけてようやくアン女王の時代に正式合併してグレートブリテン王国になります。
その後、ヨーロッパは帝国主義、アメリカ独立、フランス革命、ナポレオン戦争、産業革命…等々、激動の展開を迎えるんですが、時代のうねりに耐えうる国力をキープするため半植民地のアイルランドを吸収して④大英帝国に。
ここから先、アイルランドではジャガイモ飢饉がありますが、大英帝国全体で見ればヴィクトリア女王の統治下「パクス・ブリタニカ」を謳歌して世界一強い国になって行きます。
やがて第一次世界大戦が勃発。大英帝国の中でもアイルランドではジャガイモ飢饉からずっと悪影響が尾を引いており人々の不満が溜まっていたのですが、国際的な戦争が終わって世界が平和になり「狂乱の20年代」を迎えると、せいせいと仲間割れができるようになりましたね…ということで、南アイルランドがイギリスと喧嘩別れ⑤。
そこから先は世界恐慌、ファシズムの台頭、第二次世界大戦、アメリカの台頭、ソ連の台頭、アイルランド紛争、冷戦終結、EU拡大、ブレグジットで今に至る…って感じ?
そんなイギリスの歴史ですが、本作は多分に政治劇の要素があります。
当時の政治状況も確認しておくと、アン女王のひいお爺さんであるジェームズ1世のときに歴史が一区切りしてますが、その後イギリスは宗教と王位後継者の問題で清教徒革命とか名誉革命とかゴチャゴチャ揉め続けます。
そんなこんなの成り行きで王様の権力はだんだん制限され、議会の力が無視できなくなって行きます。議会では穏健右翼のトーリー党と、穏健左翼のホイッグ党という二大政党制が成り立って行きます。
トーリー党はどちらかと言えば王様重視、ホイッグ党はどちらかというと議会重視。宗教的にはどちらもプロテスタントですが、トーリー党の方が厳格で、ホイッグ党の方は寛容。トーリー党は現在の保守党、ホイッグ党は現在の自由民主党。
ややこしいのは、両党員とも考え方がスパッと白黒分かれている訳ではなく、人によって微妙なスタンスを採るんです。
本作の登場人物でも、ゴドルフィン大蔵卿はトーリー党だけど案件個別な動向を示すし、ハーレー北部担当国務大臣はもともとホイッグ党だけどアン女王の治世にはトーリー党に転向してます。政治的には無所属のはずの軍人マールバラ公爵は、交友面ではゴドルフィン大蔵卿と仲良しで、政策面ではかなりホイッグ党寄りです。
さてさてそんな中、おバカちゃんでも愛嬌のあるお姫様だったアン王女は、王位継承順位がそれほど高かった訳ではなく、子供の頃にメイドのサラと超仲良しになります。サラは厳密には貴族の血筋ではなく、いわば豪族の家柄で、やがて若き没落貴族の軍人ジョン・チャーチルと結婚。アン王女もデンマークの王子様ジョージを婿に取ります。
イギリスでは宗教問題と王位継承問題がこじれてクーデター起きて王様が追放されたりします。アン王女の王位継承順位はどんどん上がって行き、とうとう37歳の時、女王に即位。アン女王に従うメイドのサラと夫のジョンも立場や家格を上げていき、アンが女王に即位した時、サラは10歳年下の従姉妹アビゲイルを宮廷の女官を斡旋します…というあたりから本作のストーリーが始まっています。
さて本作はヨルゴス・ランティモス監督の作品でも、脚本家がこれまでと違います。
デボラ・デイヴィスさんというのは、あんまり情報が見つからなかったのですが、ネットで見つけた写真を見ると60歳くらいかなぁ…。主業は弁護士・批評家だそうですが、若い頃には脚本の勉強をなさり1998年に本作の原作『バランス・オブ・パワー』という脚本を著してラジオドラマになったりしたそうです。非常に博学・多才な人ですね〜。
その原作を映画用に仕上げたのが監督さん(脚本家としてはノンクレジット)とトニー・マクナマラさん。トニーさんはオーストリア人で、TVドラマや映画の脚本家からキャリアをスタートしてました。
また、見事な衣装が印象的だったので確認したところ、サンディ・パウエル(1960年生、公開時59歳)さんという方が担当。この方は超大御所でした。納得。
それから、効果音というかBGMというか場のムードを程よく緊迫させ、同時に脱力させる絶妙な音楽を担当したのは、ジャースキン・フェンドリックス(1995年生、23歳)さん。何という若さ!彼の才能も凄いけど、この才能を発掘したことも凄いし、それを躊躇なく起用したのも凄い!
ヨルゴス・ランディモス監督、役者に淡々と棒読みをさせる演出がほとんどなくなりましたね。そのせいかシュールなムードがずいぶん減りました。
本作は基本的にイギリス映画ですが、ヨルゴス・ランティモス監督の作品としてはとうとうハリウッドメジャーのフォックス社がメインで製作・配給をしています。監督の作品、どんどん規模が大きくなってます。
実際いかにもお金がかかっていそうで凄く贅沢な映像でした。こんなに格調高くて豪華な美術なのに、こんなにしょっちゅうお下劣なことする歴史コメディ映画は見たことない!
脚本家が変わったためか、監督さんの変態趣味もかなり抑えられた印象。ただし、変な踊り、容赦のない動物殺し、手コキ、自傷シーンはもはや監督さんのフェイバリット・ホールドですね〜。
インパクト重視のエグいシーンに度肝を抜かれますが、本作の主軸は権力や親愛の情を巡る人間ドラマです。
そこはきっと原作脚本が実に上手くできているのでしょう。史実では当然もっと多くの人物がアン女王に関わって大きな影響を与えていますし、本作で描かれている時代にはもっと重要な出来事が沢山ありました。それをドラマチックな仕上がりになるよう巧みに取捨選択し、時間経過を見事に圧縮して、完成度の高い1本の物語として仕上げられています。
初見時、この作品の主人公はアビゲイルだと思い込んでいました。平民出身の女中がタイトルどおり「女王陛下のお気に入り」に成り上がって行く話だと。
しかしやがて、アン王女、サラ、アビゲイルの3人が主人公だという理解に。
そして繰り返しこの作品を見て、ストーリーの背景まで調べたら、一番思い入れのある主人公はアン女王になりました。
史実では(本作でも)、アン女王は何度も何度も妊娠してますが、子供たちは全員死産・流産・早逝し、合計17人の子供を失っています。また仲の良かった夫にもアン女王が43歳の時に先立たれています。
さらに、当時は「王権神授説」という考え方があって王様たちは現人神みたいな扱いをされていました。王様が触るとケガや病気が治るという「ロイヤル・タッチ」という奇跡の儀式みたいなことをアン女王もやらされたそうです。
アン女王自身は、そんな神通力ありゃしないと自覚していたでしょう。しかしロイヤル・タッチに限らず、国王の職責に抗い切れないことは山ほどあったに違いありません。
愛する家族を失い、政治・宗教・職責に翻弄される孤独な立場の最高権力者のアン女王と、そのお気に入りの女官たち。この映画の本質は正統派の人間ドラマでした。