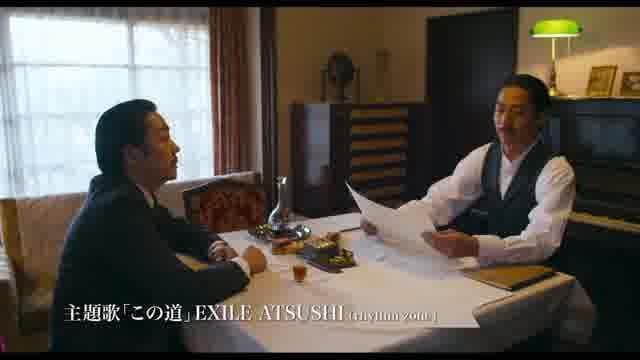「詩に遊んだ白秋の自由な魂」この道 耶馬英彦さんの映画レビュー(感想・評価)
詩に遊んだ白秋の自由な魂
北原白秋のイメージは、一言で言えばお坊ちゃんである。「あめふり」の詞に「きみきみ、この傘さしたまえ」とあるのを見てそう思っていた。こんなふうな言葉遣いをする子供は、ちびまる子ちゃんの花輪くんくらいしか思い浮かばない。少なくとも現実に逢ったことは一度もない。凡百の我々には、聞いたことのない詞を書くのは不可能だ。間違っても「さしたまえ」という詞は書けない。だからこの詞が書けるということは、北原白秋という人物がそういう言葉遣いをするお坊ちゃんに違いないと考えたのだ。
しかし当方のそんな浅はかなバイアスは、本作品によって見事に打ち砕かれた。北原白秋という人は浮世離れした人ではなく、頗る即物的であり、地を駆け風を切り水に遊ぶ詩人であった。五感をそのまま表現するかのような言葉のひとつひとつは、実は計算され尽くし選び抜かれている。一度も聞いたことのない言葉さえ、自由に紡ぎ出す。
しかし日本中に盛り上がる軍国主義の波は、白秋の詩から自由を奪い取ってしまう。詩人にとって使う言葉を制限されることは、手足の自由を奪われるに等しい。走ることも飛ぶこともできず、筆の運びさえままならない。美しいものを美しいと書けず、楽しいことを楽しいと書けないで、なんのための詩人か。戦時下の白秋の忸怩たる思いに強く共感する。
たしか中上健次だったか、溢れ出すように文章を書きたいと言った作家がいた。文章を書くのは楽しいと同時に苦しいことでもある。言葉が溢れ出してくれればどれだけ楽しいことか。白秋はまさに、溢れ出すように詩を書いた。それは彼の天性の成せる業(わざ)である。文章ではなく詩だからこそそれができる。詩人は現実的には常に不遇であるが、およそ言葉とのかかわり合いにおいては、作家よりも遥かに恵まれている。
大森南朋は名演であった。熱血漢の山田耕筰を演じたエグザイルのアキラもよかった。明治から昭和にしてはスマートすぎる二人だが、平成に上映するには多少のデフォルメも必要だ。与謝野晶子と鉄幹の夫妻といい、有名な詩人を一同に集めてしまうのが史実に合っているのかどうかは不明だが、朔太郎や犀星、啄木らが如何にも言いそうなセリフを言うところがいい。
陰陽道では人生を四つに分けて、青春、朱夏、白秋、玄冬などというが、白秋は遂に玄冬を迎えることなく生涯を終えた。それが残念だったのか、それともそれでよかったのか、答えはない。詩人は時に夭折し、時に長い孤独に生き延びる。詩に遊んだ白秋の自由な魂が、彼の童謡を歌うたびに永遠に蘇る。