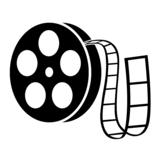ロープ 戦場の生命線のレビュー・感想・評価
全57件中、21~40件目を表示
A Perfect Day
ままならなさ
ベニチオデルトロに惹かれて鑑賞。
オープニングの演出が良く、わくわくしました。
本作は戦争による被害やそれに関わる人の心情を描いています。ドキュメンタリー調で、リアリティが感じられました。それなのにコメディチックなチグハグ感がおもしろかったです。
ロープがなかなか手に入らないところなんかはおもしろくはあるのですが、全体的に展開がゆっくりなので、退屈に思う人もいるかもしれません。このままならなさも本作のメッセージと捉えられるかもしれません。
キャラとしてはティムロビンス演じるビーが愉快な性格で好きでしたね。
ベニチオデルトロはいつも通り格好いいのですが、『ボーダーライン』に比べると輝きは控えめに感じました。
感情移入したのはメラニーティエリー演じるソフィーでした。
停戦中の話ということもあり、戦争の悲惨さはダイレクトには描かれていません。しかし、考えさせられる演出がされています。ラストはストーリー展開はもちろん、曲も良かったです。
ベニチオ・デル・トロがシンプルに好き、っていうのもありますが。
乱暴に言うと「1本のロープを求めて探し回る」映画。…なのだけれど、その行為が「紛争地帯」で行われるだけで、こうも困難な事なのかと思い知らされる。
けれど決して暗い雰囲気の映画ではなく、監督も言っていったが「パンク」な精神で描いている。それは、映像がぶっ飛んでいるわけでもなく、紛争地帯で活動する支援活動家の「志」がパンクということ。ルールに則り、ルールに抗い、敵を見定め、他者が自分が、どうすれば「生き残れる」かを軸に活動している。すごく見やすい映画。センセーショナルな場面も多く、ショッキングな描写もあるが、現実として映画として受け入れられる範疇だと思います。
オチも素敵。観ると(…でもそういうことよね)と、「自分のできることを精一杯する」ことで物事がどうなるかが、わかる。わからせてくれる。素晴らしい映画。
原題は皮肉ったタイトルなのか。邦題も微妙
キャストに比べると地味な小品
ブラックコメディとしてみればいいのか?
一見不毛かと思われる国際援助活動
国連軍の役立たず感は他の映画でもよく出てくるが本当にこんな感じなのかな
ラストの奇跡が救いに
エンディングテーマはマレーネデートリッヒが歌う「花はどこへ行った」有名な反戦歌との事。本編で流れるのは似つかわしくないゴリゴリロック
ティムロビンスがあまりやらない役どころ。
女癖が悪い設定はデルトロっぽいが彼の役柄もまた珍しいかも。
フランス人女優が新人感を出してていい。
オルガキュリレンコが野ションする。
1995年、ユーゴスラビア紛争停戦直後の「バルカン半島のどこか」。途中でボスニア言うた。
地雷原
意外と軽妙なコメディ
先のことは分からない
牛の死体と地雷
「これが戦争だ」。いや、戦争は和平条約によって停戦が結ばれたはず・・・なのに、現場は違っていたのだ。国連が中立を守るというのも理解できるが、だからこそ色んな法律が邪魔をして、何も出来ない状況に追いやられる矛盾が感じられる。
冒頭の井戸でのローアングル映像。緊迫感漂わせておいて、ロープが切れてからはジョークの連発が続き、どこで笑っていいのかもわからなくなる。とにかくロープを探すためにマンブルゥ(デル・トロ)とビー(ロビンス)のチーム。山道で牛の死体が置かれている状況ではどこかに地雷があるんだと力説するビーだったが、新人活動家ソフィー(メラニー・ティエリー)は冗談だと思って真剣に取っていない。いや映画を観ている者でさえティム・ロビンスのジョークだと思ったはずだ。「国家なき水と衛生管理団」の日常も多分にやりきれないほどの汚物や死体を見ているはずで、ジョークで気を紛らわすしかないのだと感じられる。
ショップでは主人に「売り物のロープに触るな」とか「首吊り用のロープだからダメだ」とか言われ、これもどこまでがジョークかわからないほど。大体、通訳のダミール(フェジャ・ストゥカン)にしてもちゃんと通訳してるのか心配になるほどジョークに満ちているのだ。
一人の少年ニコルと出会ったマンブルゥチームはロープのついでにサッカーボールも見つけなければならなくなり、彼の自宅へと向かう。そこでは犬が繋がれたロープもあったが、狂犬だからと説明を受けうまくいかない。さらにニコルの両親は安全なところにいると信じ込まされたいたが、庭先には首吊り死体が・・・。もう伏線がすべて繋がっていくブラックユーモア。
マンブルゥの元カノ・カティヤ(オルガ・キュリエンコ)がやってきて、彼の浮気度合なんて話はあまり笑えなかったのに、カティヤがみんなの前で野外おしっこする羽目になった。笑えない。彼女はこのためだけに配役されたのかとも思ってしまうくらいでした。
「これが戦争だ!」という言葉は強烈。明らかに捕虜を捕まえていた地元軍に対しても何もできないし、全ては国連軍の指示と法律を遵守しなければボランティアさえ出来ない状況なのだ。結局井戸の死体には触れないと言われ、ほったらかし。そんな終盤に次の仕事が入ってきた。難民キャンプのトイレが詰まってしまった・・・。これも戦争なんですね・・・
その終盤に流れてくる曲が「花はどこへ行った」。反戦歌の代表曲として知られるこの曲の歌詞がしみじみ伝わってくるのですが、クレジットを見るとマレーネ・デートリッヒが歌ってるバージョンだった。最後に、原題タイトルがバーンと出てきたとき、すんごい皮肉ったタイトルだったんだな~と、オチとともに評価が上がってしまった。
私には難しかった‼︎
観終えた後にこの作品の意図をインターネットから読んだのですが、私には難しかった…あと、ちょこちょこティム・ロビンスがブッ込んでくるブラックユーモアがイマイチ理解出来ないというか、クスッと笑えなくて。残念。
井戸に死体を投げ入れた人達も雨が降れば水面が上がって自然の摂理で解決しちゃう事も見越しての短期ビジネスだった、っていうのは分かったし、結局はマンブルゥ達部外者はあんまり内部の事はわかるはずもなく。
周囲がロープ1つにどんちゃん騒いでもあんまり意味は無いのです、その国にはそこの風土があり、人があるのです…というちょっと切な寂しいメッセージ性は痛かった。
あとはカティヤが最高にうざかった。あんな地雷まみれの戦地で男の事ばっか考えてピーピーうるさくて、ホントああいう役柄最近見るのも嫌だ〜!!
ディア・ハンターのように1つのロープを通し実情を描く
文化レベルの違いなのか
正直、見る前はタイトルから戦争物のちょっと説教くさい話なのかなと思っていたがそんなことは全くなく良い意味で期待を裏切られた。
原題の「A PERFECT DAY」の方が内容に合ってるし、何故変えた?
政治思想の低い人間にとっては中東?ヨーロッパ?でずっと内戦とかやってるな、なんとかならんもんなのかな、と多少の反戦意識は持ってるが、IS壊滅作戦の映画とか見せられても正直何処かの国のプロパガンダの「勧善懲悪」物にしか見えなくて、本当の意味の戦争が伝わってこなかったりするのだが、この映画は派手な戦争描写は一切なく、地雷に怯えて暮らす人々や、日々の飲み水を確保するために奔走するボランティアを主軸にしたことでよりリアルな戦争が遠い異国の僕にも伝わってきた。
シリアスになりすぎず、ユーモアを交えたこの作品のバランス感覚は凄く好きだし、ここ最近の邦画(お子様ランチのように思えてしまう)と比べると文化レベルの違いに嫉妬する。
デルトロのいぶし銀具合がサイコー。
あの「ショーシャンク」のティム・ロビンスだったんだって解説見てビックリ‼️
紛争国に対し周辺国ができることとは
面白かったなぁ〜
久しぶりに観たティム・ロビンスのボケ担が良かったなぁ
紛争地帯だからこそ、笑いが必要なんだと思わせてくれるキャラクターだった
1995年のバルカン半島で起きていた紛争に停戦協定が結ばれる
そのとき、ある村の井戸に殺された男の死体が投げ込まれていて、腐敗し始めていたため
NGO団体の「国境なき水と衛生管理団」が死体の除去に向かうが
死体を引き上げている最中にロープが切れてしまう
人間は水がないと生きていけない
だから、上水道がない国々の人にとって、井戸とは「命の源」である
その井戸の汚染を除去するということは、その地域の人々の命を救うことになる
そのために、そのNGOでは、プエルトリコ、アメリカ、フランスなどいろんな国の技術者が集まって、試行錯誤しながら汚染を取り除こうとするのだが
様々なところから、想定外の妨害が起きてうまく取り除くことができない
なぜなら、この紛争の根っこにある民族間の対立は
井戸に投げ込まれた死体のように肥大化し、腐敗しており
他国から来た人たちが必死になって、その差別や偏見を取り除こうとしても
上から井戸を覗き込むような
ただの高みの見物でしかない
それでも、様々な障害を乗り越え、人の命の犠牲の上で、ようやく手に入れた希望の命綱をたらし
あと少しで汚染を取り除くことができると思っても
その命綱は、彼らの目の前で無残にも切り取られてしまう
それも、国連軍の手によって
かと言って、周り国々の善意が紛争地帯に対して全く何もできないわけではない
時には不当に捕虜にされた人たちを救い、詰まった下水を直す日もある
それだけでも、彼らにとっては「素晴らしき日」なのである
そして、奥底の深いところで腐ってしまった人種間の対立も、いつか彼ら自身が自分たちの力を合わせ、取り除くことができる日がやってる
周りの国々は、その日が来るのを辛抱強く待つしかない
面白かったのは、国連軍は邪魔者でしかなく、分析官は何もできない役立たずでしかなかったところ
現地の人たちが求めているのは、軍事力よりも、技術力なのである
紛争地帯の話とかニュースでしかわからないし…。
他の方のレビューを見て再考。
2018年度ベストムービー!
原題は"A Perfect Day"。停戦中のボスニア?で活動するNGOのお話。2018年2月時点において、今年暫定No. 1の映画である。これを観ずして何を観る!?(笑)
*国際協力の仕事に関わった事がある方には、興味深い作品かも知れませんね。異文化に対する理解や距離感、そして何が起こるか分からない状況…うんざり続きの1日に「今日って、完璧!」と皮肉も言いたくなる。
全57件中、21~40件目を表示