映画レビュー
【哀しみを抱えた三つの家族を描いたアンソロジー。三つの物語が連関しており、三つの家族に仄かな希望が刺す展開も人間性全肯定をベースにした傑作、秀作を今作後、世に出し続ける中野量太監督らしい作品である。】
<Caution!内容に触れています>
1.【神田家】
両親から離婚を告げられたマヤとカナの高校生姉妹。
どちらと暮らすかは、任せると母に言われ、マヤとカナは悩む。
マヤは母に願い、恋人と会うが、母に”あの人、私を性の対象にとして観ているよ。”と告げる。
吃音のあるカナは、スーパーで万引きをしてしまうが、両親はナカナカ迎えに来ない。
そんなカナに、優しく接する店長は、3H待ったカナにプリンを上げて、更にはお土産まで持たせてくれて返してあげるのである。
2.【相模家】
スズカは、軽い気持ちで父に迎えを頼む。だが、父は途中で交通事故に遭い、帰らぬ人になる。自責の念に駆られたスズカは父の末期の病を患う伯父の元に通い、彼を彼女なりに励ます。そして、スズカは万引きしていたスーパーの店長に”万引きしていました。”と言い、二万円を渡し、戸惑う親友のツルミと共に帰る。
スズカはいつも、伯父に”お父さんに会ったら・・。”と頼みごとをしていたが、伯父はスズカの前で、笑顔で川に飛び込む。その後、スズカは伯父が遺した手紙を読む。
3.【最上家】
スーパーの店長は、ゴーグルを掛けてボンヤリ川を眺めている妻の元に来る。そして言う。”もう、良いじゃないか。帰ろう。”と言って妻の手を取る。
<ご存じのように、中野量太監督は、今作を含めた多数の短編を発表した後、2016年に傑作「湯を沸かすほどの熱い愛」を総なめにし、且つ邦画でも貴重なオリジナル作品で勝負し、結果を残して来た映画監督である。
今作には、中野監督ならではの人間性全肯定の姿勢が仄かに描かれ、傷ついた三つの家族が徐々に再生していく様が、巧に連関した構成で描かれている。
このような作品を作り続けた結果、「湯を沸かすほどの熱い愛」「長いお別れ」「浅田家!」というヒューマンドラマの秀作、傑作が産み出された事を考えると、意義深い作品であるし、中野監督の確かなる才能を感じさせる作品でもある。>
タイトルなし(ネタバレ)
3つの家族なんだなぁって思った。
作られた社会的に不幸な人々ではないとは思う。
全て贖っても逆らう事に出来ない運命の様なものに翻弄される人間模様だと思う。
見終わって、暫くは呆然となっていたが、泣けてきた。どんな映画を見てもこんな偽善的な事では泣けなかったが、自分が嫌になる位泣けてきた。
まだまだ
修行が足りない!!!
クサすぎる不遇
この監督はしぬしぬで日本中を熱狂させた湯を沸かすほどの熱い愛のひと。しぬしぬドラマの構造はシンプルでありながら、日本国民を入れ食いにできる。構造つっても露命を主役に置くだけなんだが。釣れる釣れる。とはいえ、日本人にしかウケないので日本にしかない。わたしは腹を抱えて笑い転げた。
お涙頂戴な演出は、わが国の映画やドラマの定番。
今はお涙頂戴ではなく、感動ポルノという言い方が定着している。とにかくなにがなんでも積極的に泣かそうとする演出で、近年実写でもっとも露骨なそれは、前述のとおり湯を沸かすほどの熱い愛(2016)だった。
テーマは「かわいそうな境遇」。主人公双葉は薄命、娘の安澄はいじめられっ子、探偵さんは亡妻の子連れ、拓海くんは継親から逃げ出したヒッチハイカー、酒巻さんは唖者。右も左も不遇の免罪符しょっている人物だらけ。かれらが不幸自慢を繰り広げる様子はモンティパイソンの4人のヨークシャー男も顔負けで、エジプト行きたいを伏線とする人間ピラミッドなんか、全身鳥肌の恥ずかしさだったが、映画サイトは軒並み異様な高得点をつけた。つまり大多数の人々を支持を得ていた。
日本にお涙頂戴な演出が多いのは、日本人がそれがすきだから。
映画のレビューサイトでは「泣けた」が褒め言葉として常用されている。てことは「泣けなかった」はとうぜんサムズダウン。ばあいによっては、泣けたか泣けなかったかが、映画を良し悪しの判断材料ですらある。
個人、一般庶民は、みんなに映画の魅力を伝えたいと考えるより、映画に泣ける自分の感性をアピールしようと考える。それがSNS。
むかしのフィルマはSNSの形態を持っていなかった。だからSNS的偏差値(フォロワーの数とか、アクティビティの頻度とか、コミュニケーションなど)について、警戒する必要がなかった。だがSNS形式になり、ポピュラリティが競争化されたので、じぶんのポジション、あるいは「フィルマの住人らしさ」みたいなもの──について、まがりなりにも警戒しなきゃならなくなった。
SNSが映画の魅力を伝えるよりも自己アピールが目的のツールならば「良かった」よりも「泣けた」のほうが効果的。
けっきょくネットワーク内での自己主張がレビューの主目的になったため「泣けた」が合意・不合意のキーワードと化した。すなわち「泣けた」とは映画の感想ではなく、レビューの読み手に宛てた共感促進の会釈。そこへいいねをすることで挨拶が成り立つ。
が、泣けたから泣けたと言っていけないことはない。わたしとて小市民。泣くことは、庶民、労働者にとって身近なストレス発散方法。サクッと泣いて眠りに就く──のは、健全な消費生活だと思う。
ただし、こんにち泣けたか泣けなかったかが、映画の判断材料になってしまっているのなら「泣けた」発言は、寄るか去るかの他者の判断材料にもなりえる。
つまり「泣けた」との批評に寄ってくる人々もいるが、同時に「へえ、これに泣けちゃうんだ」と去る人も生じさせる──というはなし。
湯を沸かすほどの熱い愛に並んだ高評価だらけレビューをながめたとき、わたしは強烈な疎外感を感じた。「泣けた」「泣けた」「泣けた」「泣けた」「泣けた」「泣けた」「泣けた」「泣けた」「泣けた」「泣けた」が居並ぶその渦中へ「爆笑しました」で突撃するのは気が引けたから。が、「朗報!この国フランダースの犬の最終回で天下取れっぞ!」とは言ってやったぜ。
私見だがお涙頂戴=感動ポルノの主目的は人とお金を集めること。映画のプペルや、24時間テレビがこの手法をもっていることをご存じだと思う。それがいけないとは思わない。人とお金を集める手法を使って人とお金を集めているだけのこと。ちっともわるくない。
ただ感動ポルノではないものが、感動ポルノに負けるならば、この国にまっとうな映画/ドラマができる地盤(リテラシー)なんか無いんじゃなかろうかとは思う──というはなし。
本編はその中野量太監督の初期作で、やはり「かわいそうな境遇」で釣ってくる。誤解しないでほしいが「かわいそうな境遇」はシンパシーをあつめるプリミティブな方法。「かわいそうな境遇」を使わなければ映画ができない。が、クサいのとクサくないのがある。たとえばあの夏、いちばん静かな海(1991)のふたりは聾唖。かんぜんに「かいわいそうな境遇」で釣る映画だった。ただしクサくなかった。ただ君だけ(2011)のヒョジュは盲だった。ジソプは落ちぶれたアウトサイダーだった。ただしクサくなかった。弱者や虐げられた者で釣りたいならば、巧くやろう──というはなし。ザ日本映画業界には巧いひとがいない。にしてもクサすぎ。0点。
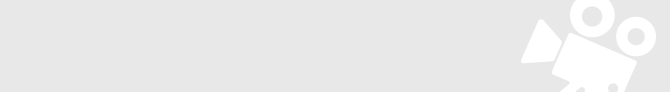




 チチを撮りに
チチを撮りに 想影
想影 湯を沸かすほどの熱い愛
湯を沸かすほどの熱い愛 浅田家!
浅田家! 長いお別れ
長いお別れ ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド


