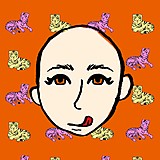ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラのレビュー・感想・評価
全12件を表示
【”住宅は人を包み込む殻”近代建築の巨匠、ル・コルビュジエとアイリーン・グレイとの出会いと相克と、一方で実は相手への尊敬を持つ姿をドキュメンタリータッチで描いた作品。】
■天才建築家のル・コルビュジエは、気鋭の家具デザイナー、アイリーン・グレイと出会う。
アイリーンが恋人で建築家兼評論家のジャン・バドヴィッチと共に手掛けた海辺のヴィラ「E.1027」を絶賛するコルビュジエ。
彼は所有欲のないアイリーン・グレイが居ないどの家に入り浸り、その思いは徐々に嫉妬へと変化し、彼女に無断で家にそぐわないフラスコ画を描いて行く。
◆感想
・ル・コルビュジエは知っていても、アイリーン・グレイを知っている人は、余りいないのではないかと思われる。
・故に今作は、アイリーン・グレイに”家”に対する考えと、ル・コルビュジエが彼女の才能にまるで嫉妬しているような、描写が面白い。
・映画としては、淡々と描かれており、ル・コルビュジエとアイリーン・グレイとの出会いから、グレイの死までを描いている作品である。
<今作は、近代建築の巨匠、ル・コルビュジエとアイリーン・グレイとの相克と相手への尊敬を持つ姿とをドキュメンタリータッチで描いた作品であり、アイリーン・グレイという、現代では忘れられた建築家、デザイナーを知る入門的な作品である。>
100年前とは思えないほどモダンな世界
建築界は完全に専門外だが、フランスのリゾート風景と独特なモダンさに惹かれて鑑賞。
観始めてすぐメイン舞台が1920年代と知ってびっくり。えっ、100年以上前でこんなに近代的だったの!? モダンな建物にモダンな家具、そしてモダンなファッションを身に纏ったモダンな感性の登場人物たち。まさにモダンのオンパレード。室内を真横からまっすぐ撮り続ける映像は、特にモダンに映り印象深い。この撮り方が、全くジャンル違いで私だけかもだが、少し「2001年宇宙の旅」チックな雰囲気を感じられたのがふいに面白い。
また、登場人物が劇中でカメラ目線で自ら色々と解説してくれているのもなかなかユニークだ。
ただし、やはり建築に興味が薄いと、ストーリーや映像的に刺さる点が少なく、全体的に物足りなさを感じるかも知れない。
そういえば 「ロダン カミーユと永遠のアトリエ」でも、弟子カミーユの作品に師ロダンが合格点を出し、カミーユの作品に《Rodin》とサインを揮毫するシーンがあった
【ロンシャンの礼拝堂】
憧れの建造物だ。
ぜひいつか行ってみたいと思っている。
・サヴォイ邸
・国立西洋美術館
・ラ・トゥーレット修道院 等々、
直線一本槍だったル・コルビュジエが
なぜに最晩年に及んで、直角や平行線を排したミロの絵のような礼拝堂を建てたのか。
ピロティも窓も無く、装飾を拒む頑丈な厚い壁に閉ざされていて、無限拡張の逆を行き
彼はなぜご自慢の「5原則」を離れたのか。
それは大変不思議なことだ。
アイリーンとの関わりが、彼の中に何かの変容を引き起こしたのだろうか。
ロンシャンの緑の丘の上、
あの褐色の屋根は、まるでアララト山の白い巨石の上に止まった箱舟のようだ。反り返ったその屋根の裏側は、下から仰いだ船の腹のように見える。
あの礼拝堂は山の頂に堂々と着地をしており、そして光のスリットを介してわずかに浮かんでいる。
重力と無重力が同居している。
東北の津波の際、白いビルの屋上に巨大な船舶が取り残されたままになっていたが、あれはこのロンシャンの礼拝堂を思わせる光景だった。
恐らく、当地で現物を見れば、その内部は20人ぶんほどのピュイ(長椅子)しか置けないサイズゆえ、
想像よりも意外にも小さくて、僕の中で膨らみ過ぎていた期待をしぼませてしまうかもしれないのだが。
でも、
映画を鑑賞し終わって、一人の男の情けなさ、その体たらくを突きつけられて、僕の心の中の巨匠=ル・コルビュジエへの尊崇も幻滅。
ポシャってしまったのだが。
・・・・・・・・・・・・・
【三人のアーティスト】
映画は、アイリーンを愛し、アイリーンを踏み台にしたジャン。
名士コルビュジエと、彼を嫉妬させ、苛立たせて撹乱させた女性、アイリーンについての物語。
自分と愛人ジャンのために海辺の邸宅をデザインすることにしたアイリーンだが、
そのイメージの世界に遊びながらゆったりとワルツを踊る姿が大変良かった。
⇒ 家具デザイナーが建築に目覚めていくいいシーンだ。
自信と満足に満ちた目、次の構想への意欲に燃えるアイリーンの眼差しが素晴らしい。
僕も自宅の設計をしたことがある。
もちろん図面は専門家に引いてもらったのだが、一切は僕の夢の具現。
たくさんの家を意識的に見てきた甲斐があり、自画自賛だが素晴らしい家が完成した。
礼拝堂のスケッチも構想した経験がある。
だから建築関係の映画には、ついつい手が伸びてしまう。
アイリーンならずとも、建築はワクワクドキドキで寝食を忘れる一時なのだ。
・・・・・・・・・・・・・
【映画の造り】
アイリーンと、ジャンと、コルビュジエ。
三人の創造作業のための、《建築の前段階でのイマジネーションの風景》、
•・あれはまだ形にはなっていない渾沌の世界だ。
本作の画面においては、おのおのの「横顔」と「光」と「音楽」によってしか、彼らの心中は伝えることはなされない。
建屋に求めるスピリットとしては
①住む者たちを守る“生命の殻”を目指すアイリーン。
②かたやコルビュジエは自然と屋内の調和を具現する“機械”として建造物を据え、居住する人間たちをコルビュジエ理論に屈伏させる意向。
③ジャンは?といえば業界の有能なライターではあるが、アイリーンとコルビュジエという巨人の間で右往左往する根無し草だ。
感覚を重んじるアイリーンと
理論を信奉するコルビュジエと。
そしてアイリーンの才能に寄生するジャン。
・・・・・・・・・・・・・
【映画の演出技法】
◆撮り方の工夫としては
どうしても先述の「イメージ画像」の尺が長いので、こういう作風が肌に合わない方には、緊張を持続してスクリーンに向かうのはくたびれるかもしれないが、
時折、「目指すものの相違」という確執の中で、それぞれ登場人物の中で言葉化され明確になっていく三人の「ポリシー表明」が光る。
発見された「ポリシー」が本人たちの口から、映画の進行中にコメントとして直接に挟み込まれている。
それが鑑賞者のための道しるべとなるから、その発される言葉に眠い目が醒めてハッとさせられるかもしれない。
アイリーンのセンシティブでシリアスな独白と
いつも裸の“お山の大将”だったコルビュジエの、カメラを向いてのやんちゃな「独り言コメント」が、双方で対比しているのも仲々ユニーク。
◆時間の進行をゆっくりと撮るかと思えば、まったくのその逆もある。
仏独の「 開戦〜戦中〜戦後」を1カットずつの、たった1分でのコマ送りの早送りにしたり、
ジャンの「ガンの告知から死までの数ヶ月」が、枕辺でのノーカットの優れた1シーンで撮られていたり。
斬新な監督のアイデアだ。
◆そして、
長調・短調にかかわらずいつも後ろに流れ続けているのが作曲家ブライアン・バーンの
「三拍子のワルツ」というところが、また“この三人の絡み”を象徴するようで、恐らく意識的な、旨い当て書き作曲であったと思う。
アイリーンと女友だちの避暑も三人のシーンであった。
・・・・・・・・・・・・・
【残るものと 残らないもの】
僕はオルガンの演奏をしていた。
「音楽」は、録音を残しておかないならば、その場その時だけで、はかなくどこかに消えてしまう一瞬のものだ。
「音楽」には、つまり形が無いのだ。
演奏は、失敗すれば舌を噛み切りたいほど恥ずかしく悔しいものだが、その失態を知る人々の記憶から消えていく幸運をも持っている。
しかし「建築」は違う。
友人には幾人かの建築設計士や公共工事の施工管理者がいるけれど、彼らに「作品」と後年再会する時の、作者としての気分を訊くのは面白い。
「嬉しいかい?」
「後悔は?」
「どんなふうに使われているか関心は?」
「崩壊してないか心配にならないかい?」
高層ビルや長大なトンネルの作者だ。
消えてしまう音楽の演奏とは真逆だ。
固形体・ソリッドとして長く残る物を造る人間たちの、叡智や技術、そして名を残す勇気と責任感は大したものだ。
僕が建てた家は賃貸に出した。
その後いろいろな階層の人たちがそれなりのけっこうな家賃で住んでくれており、お陰でローンもペイ出来たのだが、
当初そこに暮らし、一生をそこで過ごすものと思われていた最初のカップルは、残念ながらもうそこにはおらず、
外壁は断りなく塗り替えられて、
遠景からたまにその方角を眺めることはあっても、(コルビュジエの世界文化遺産17件とは異なって)近寄りたくもない負の遺産となってしまったが。
だから、形が残る建造物は、容赦がなく、告発的で、時に残酷だ。
・・・・・・・・・・・・・
【男性性=俺が壁画を描いてやるよの傲慢、笑】
映画の冒頭、「このE.1027を守りたい。俺の壁画だけでも守りたい」と臆面もなくぶち上げる恥知らずの男が、カメラ目線で得意げなのだ。
見終わって判明したのは、ル・コルビュジエの「5原則」は、実は+プラスもう1個の「6原則」だったという種明かしではないか。
「『家』は男の側が力の象徴として用意すべき物なのであり、そこに か弱い女を迎えてやるべきなのだ」とするコルビュジエ風の、そして愛人ジャンなりの、それまでの男社会の常識が壊れていく様相、
その「変革期」を、建築に於いて、そしてジェンダーに於いて、語って見せようとした映画であったと思う。
男尊女卑の醜態。
「E.1027」の名義は盗られ、鍵は隠され、美しい壁は凌辱されて、女は黙して耐えることを強いられる。コルビュジエとジャンに利用され、虐待されていたアイリーンなのだ。
聖家族の“落書き”に銃弾が撃ち込まれたのが象徴的だ、
窓があってももうそこに人はおらず、
ピロティにも外壁にも愛する家族がいない始末だ。
コルビュジエ先生には言いたいが、HOMEに生命が宿るのでなければ、それはHOUSE=廃墟に過ぎないのだと、
僕は痛みと反省を込めて、男の自分の経験からもそう思った。
監督は完全にアイリーンの肩を持っている。
女は「嫁」ではないと主張する。
ル・コルビュジエは最低の男だったことを暴露する。
それが今現在ル・コルビュジエの作品に住むハイソサエティたちの怒りを買おうとも、だ。
自信過剰の男二人が先に死に、アイリーンが長らえたのもちょっとウフフかな?
監督がやったのは 敵討ちですよ。
姉妹作「アイリーン・グレイ 孤高のデザイナー」もぜひ観てみたい。
思ってたのと違ったけど。
コルビュジエのこういう姿は知りたくなかった。
視点がどこに、誰にあるのかがわかりにくい作りに思えました。
後半の駆け足なのも気になります。前半の非常に細かく描写される人間関係は素晴らしいものがありました。突然事切れたかのようにアップテンポの展開。
ただ、全然嫌いじゃない作品です。
愛と理論の結晶
巨匠の執着
グレイは 家具、インテリア、プロダクトデザインから 建築へと 手を拡げてきたデザイナーである
ヒューマンスケールを熟知しており 家具などは作り直したものもある
(実験 あるいはカイゼンか… 愛の深さか… )
そして トータルで完成度の高い〈E 1027〉を作りあげた
彼女に建築を教えた バドウィッチが、この開放感あふれる別荘に〈個室〉を主張した意味は 後でわかる
コルビュジエは 彼女とコラボしたかったに違いない… 何故 (二流の)バドウィッチと組むのか?
女性、著作権、所有権… と問題は多々生まれたが、 一時 愛は感じたし、彼に才能が無いからこそ主張も弱く、彼女の思い通りに出来たのではないだろうか
この家に〈壁画〉を描くように勧めたのも彼で、そのセンス、感性が理解出来ない
それに乗ったコルビュジエも どうしたのか?
(当時 壁画が流行していた)
大戦時に この家を占領したドイツ兵が〈壁画〉を撃ってしまったのも、その違和感が気持ち悪かったからだろう
また、オナシスがちゃんと理解していたのが 興味深かった
グレイが 裕福で、芸術家肌で 繊細なのも
バドウィッチと〈E 1027〉を潔く捨てて、出て行ってしまう要因になり、問題をややこしくした
そして後世で 二人の男の人間性を 浮かび上がらせてしまった (笑)
〈神が細部に宿った〉この別荘に対するコルビュジエの執着は 理解は出来る
彼の心のうちは判らないが、政治、マスメディア活用が巧みなことから 疑惑も感じられる
そして その執着が グレイの家具の値段 (評価) をべらぼうなものにしてしまう《運命の不思議》
グレイを演じる オーラ・ブレイディの いつも問いかけている様な瞳が、美しかった
邦題に惑わされないように
観終わった後はピンと来ませんでしたが、E1027の解説を読んで理解...
物作りの創造者と使用者の確執から観てみました。
観客6名と言う静かな鑑賞でした。
エネルギッシュな男どもと静謐な女性との確執かな。
五原則で作られる彼の作品にはどうしても越えられないものがある。
それは設計者としての心だろうか?
彼が提唱した五原則をみごとに具現化し、そしてそれに余りある作品に触れたとき使用者であり続けることが創造者として当然の傲慢な行使だ。
それをしたくなる作品とは、設計者が愛する人にプレゼントして、二人で愛を育む愛の館ということではないだろうか。
そう彼の作品は無機質なのだ。
しかし、彼女が設計施工した館は、彼が提唱した設計理念の完璧な完成品なのだ。
そんな館に自己を潜めたときの安堵感、そんな館に何物にも変えられなく思わず自己の表現として落書きを残したくなるコルビジェ。
テロップではその館の浜辺で亡くなったそうだ。
清々しいほどの愛と固執
デザイナーであり建築家としても高く評価されたアイリーン・グレイ。彼女が恋人のジャン・バドヴィッチと共に住むため、彼にプレゼントした海辺の邸宅《E1027》に、同じく建築家として名高いル・コルビュジエが惚れ込んだうえ、固執しまくるお話です。
見る前はアイリーンとコルビュジエの関係性についてドラマが語られるのかと思っていましたが、アイリーンの目線は仕事とジャンに専ら注がれており、コルビュジエの完全な横恋慕になっています。《E1027》に壁画を書いたり、裏に自分の建築物を建てたり、本来なら嫌悪感すら感じる所業だと思うのですが、アイリーン本人ではなく《E1027》という建築物に対しての固執であること、コルビュジエ役のヴァンサン・ペレーズの飄々とした独白に味がある事などから、彼をあまり憎めないフィルムに仕上がっていました。アイリーン・グレイを演じたオーラ・ブラディも眼で語るお芝居が素晴らしく、台詞以上に多くのイマジネーションを想起させます。彼女が度々見せる、得も言われぬ表情の数々が、天才と言われつつも、必ずしもアイリーンの人生は幸福なものでは無かったのかも・・という印象を抱かせ、色々と考えさせられました。
芸術家同士の物語という事で、あまり前衛的に仕上がっていたら楽しめないかも・・と思っていましたが、杞憂でした。淡々とした語り口のためドラマティックではありませんが、芸術家としての模索と、他者への愛と、嫉妬と、固執と、諦念をバランス良く描いています。コルビュジエだけではなく、アイリーンとジャン・バドヴィッチの関係性にもちゃんと尺を取っていたのも良かったですね。
全12件を表示