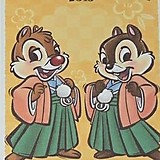92歳のパリジェンヌのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
【”自らの死を、自らの意志で、自ら決める。”フランス元首相の母の実話から生まれた重いテーマの物語をユーモアを交えながら描いた作品。だが、ラストは様々な事が頭を過る作品でもある。】
■92歳の誕生日に「2カ月後に私は逝きます」と家族に告げたマドレーヌ。
体の自由が利かなくなったら自ら人生を終わらせたいと考えていた元活動家で、恋多き人生を送って来た彼女は、荷物の整理を進めるが、娘・ディアーヌは戸惑い、息子・ピエールは猛反対する。
だが、信念を曲げない母の姿に娘の心は揺れ始める。
ー ご存じの通り、近年”終活”と言う言葉が飛び交っており、映画でも昨年の仏蘭西映画「すべてうまくいきますように」を始め、”尊厳死”をテーマにした作品が多くなって来た。
尚、人生をどのように終えるかはその人の考え方であるので、若輩者の私が意見を言うつもりはない。
だが、今作は私の様に、通常の生活をしている時には中々考えない”尊厳死”について考えさせてくれる作品であると思う。ー
◆感想<Caution! 内容にやや触れています。>
・今作を観て驚いたのは、マドレーヌの奔放な人生である。
夫亡き92歳になっても、恋人ジュルジュが居たり、元活動家であったり。
ー ジュルジュに会えないと思っていたマドレーヌをディアーヌが車で連れて行き再会させるシーンなどは、文化の違いを感じる。
個人的には素敵なシーンだったと思う。
そして、マドレーヌはジュルジュに家族に言った事を話すのである。驚きつつも手を振って別れるジュルジュ。-
・”このテーマの解を出すのは難しいな。”と思ったのはマドレーヌの宣言により息子ピエールや娘ディアーヌ、孫のマックスが戸惑い、怒り、悲しむシーンが多数描かれているからである。
ー 誰も悪くないからこそ、”尊厳死”という重いテーマに安易に解を出すのは難しいと思ったのである。
私は”安楽死”についての考えは持ってはいるが、”尊厳死”をどう考えるかは難しい。-
<今作は、フランス元首相の母の実話から生まれたそうだが、改めて”死を自らの意思で決め、実行する。”という事の重さを考えさせられる映画である。>
私たちの社会と、一人ひとりの生き方を問いかける物語り
『ヨーロッパには寝たきり老人はいない』という本がある。
あちらでは、ヘルパー制度や老人ホームなどを使い、子供を頼らず一人で生活を積極的に楽しもうと努力する。モノが食べられなくなったら特別な治療はせず自然と亡くなるのを選ぶ。そういう生き方をすることが「彼らの誇り」であるという。
日本の老人ホームでは、本人についての措置・判断でさえ本人抜きで子供と担当者で決めるのがふつう。若いときから「まるくおさまるのがなにより大事」と思って自分の考えを言わないで生きているうちに、いつしか「老いたら子に従え」になり、無感動のつらい日々が続いたあと寝たきりになる。認知症にならなければ怖くて苦しくて生きていけないのではないだろうか。
この映画では、老いと闘いながらも人間らしく自立して生きられる時まで生きようと、パリのアパートで独り暮らしをするマドレーヌを、家族は遠巻きに支援する。黒人ヘルパーも対等の関係(「契約関係を結んだ友人」という感じ)でのマドレーヌの相談相手であり協力者である。
マドレーヌが尊厳死の意思を家族に宣言したあと、家族は驚き、とまどい、怒り、嘆きながら、しかし最後はマドレーヌ(母)の意思を理解し尊重してその日にむけて協力する。
特にマドレーヌへの娘の情愛(生きていてほしい!)という願いと母の意思を尊重してあげたいとの間を心が揺れ続け、最期の日を迎えるまでのプロセスは、こちらもハラハラしつらくなる。
しかし、すべてが終わった後、家族にも我々にも静かなさわやかささえ感じさせる。
1年でも、1日でも長く生きさえすれば幸せであるとは限らない。自分の最期までを自分で決めることの大切さについて、私たち日本の社会と、一人ひとりの生き方を問いかける物語りである。
家族みんなで観るのにちょうど良い
「最強のふたり」を思い出しました。共にフランス映画です。
本作は女性編ですが、2つの映画とも移民のヘルパーにどれだけか、ユニークに心身共に、支えられたかというストーリー。
自立した女はフランス映画の鑑。
ヘルパーのヴィクトリアが、信頼できてごっつ魅力的!とかく煮詰まってしまう家族の中にいつも彼女が新風を吹き込んでくれる。
まさに「救いは外からくる」ですね。
「終活」のイメージトレーニングに、この映画はとてもいい教材じゃないかな?
家族のリアルな慌てぶりは、我がこととして勉強=予行演習になるので。
母親の“決意”にうろたえる息子と、娘と、孫とお婿さんと。彼ら家族全員のショックと成長が、その年代別に、そしてその立場ごとに、丁寧に描かれていてとてもいい。
・・・・・・・・・・・・
みんないつかは、自分も家族も100%死にますよね。
そうだと知っているのに、看取りも、自身の死も、みんな嘘のように覚悟なし。
こんなに大きな課題なのに、僕ら無責任だったなぁと改めて教えられました。
ほら、
来週の計画を手帳に書き込むように、ちゃんとスケジュールを立てなくちゃね。
(あと、部屋のお掃除とかも、笑)。
むかし特別養護老人ホームに勤めていた僕なのですが、失禁の始まったお年寄りへのフォローは、とても大事な役割でした。
「気にしない気にしない、大丈夫大丈夫、何度でも何度でも、笑顔と、ハグ、
・・安心して僕を呼んでね」。
そんなホームでの生活を久しぶりに思い出しました。
母親の“決意”に苦しむディアーヌを、その気持ちを察して訪ねてきてくれる看護助手の青年。
一緒に走るスタジアム。
寄り添うって、これだよね。素晴らしいシーンです。
そしてもうひとつ、
母子の珠玉の会話です
私が手を離さないかと怖がっていた
今でも怖いわ
落ちそう
大丈夫よ
離さないでね
離さないわ
怖い
怖くないわ
お母さんがむかし娘に約束した言葉を、今は娘が母に語ります。
本当に宝石のような会話です。
・・・・・・・・・・・・
安楽死やら、もうすぐ訪れる僕の両親の終わりの日々についても、新しい情報や心準備のために、いろいろと知識の“上書き”もしてもらえたとても良い作品でした。
家族みんなで、リビングで観るとか◎だと思います。
タイトルなし
生きる気力が無くなり自分で出来る事が少なくなっていく高齢者が死を選...
そんなに遠くない、自分。
尊厳死
老いることもまた、人としての尊厳を失うことなのだろうか?
尊厳死というものは、今後世界で多く議論されることになる題材の一つだろう。不治の病や大怪我だけでなく、老いて正常な生活が送れなくなったりした時、尊厳死は生き方の選択肢の中に浮上する。もちろんそれには様々な意見や議論があるし、私自身が、あるいは私の身近な人が、と考えれば、とても簡単な結論が出せないものでもある。この「92歳のパリジェンヌ」はそのお洒落ぶった邦題とは別に、老齢からくる生活の不自由を感じた時に選択する尊厳死と、その周囲の人々の心模様に問いかけをする映画だった。
私は、尊厳死も一つの生き方の選択肢であると考えているが、正直なことを言うと、私にはこの映画の主人公マドレーヌを好意的に見ることは出来なかった。私はまだ若いので、老いによって生活の質が低下していく恐怖や、今後自身の肉体がますます不自由になっていくことの恐怖などは確かにいくら想像を巡らせても計り知れないだろうし、マドレーヌのQOLが当然守られてしかるべきものだと断言する。しかしながら、マドレーヌが死の決断にまで思い至るほど葛藤し苦悩したその考察がこの映画からは感じられず、彼女の「気力のある今のうちに死にたい」という希望を鵜呑みにして共感してあげられるほど私は優しくはなれなかった。誤解を恐れずに、ひどく意地の悪い言い方をしてしまえば、これは尊厳死という概念を利用して周囲を散々振り回した挙句の自殺、に見えてしまった。「これは私の人生よ!」は万事の免罪符となる魔法の言葉ではない。
死の宣告をすれば、家族が動転し動揺し困惑するのは目に見えていることなのに、わざわざ死の2か月前の誕生日パーティーの席という芝居がかったやり方でそれを宣言する気持ちも私には理解してあげられないし、2か月という猶予によって家族が救われるとも思えない。この「尊厳死までの2か月」というところに映画的な作為が感じられて逆に共感を妨げたような気がするし、全体的に見てもちょっとこの映画は尊厳死を美化し過ぎではないか?という気さえしてしまう。
一方で、家族から突然死の決断を聞かされた者たちのそれぞれの受け入れ方、という点では娘、息子、孫、ヘルパーなどのそれぞれ違った視点から、それぞれ違った経路で死の決断を受け入れていくその様子はなかなか興味深く見られた。ただの分からず屋にしか見えなかった息子ピエールのことも、しかし誰が彼を責められるだろうか?家族の死を受け入れるのに辿るルートは人それぞれで、それぞれの苦しみ方とその癒し方があるのだということをこの映画に感じた。
自分の祖父母のことを想った
自分もこうありたいと
極めて実存的なテーマ
自らの尊厳死を望む老婆の物語だ。
健康寿命という言葉がある。何をもって健康とするのか議論の分かれるところではあるが、簡単に割り切る考え方がある。それは食事とトイレと入浴の三つをひとりでできるかである。生活の基本動作だ。
自動車の運転が下手になったら、運転するのをやめればいい。運転をやめたからといって、すぐに介護が必要になる訳ではない。ところが基本動作がどれかひとつでもできなくなったら、誰かのお世話にならないといけなくなる。それは長いこと自立して生きてきた人間にとって、堪え難い屈辱だ。人間としての尊厳の危機である。
歳を取ると身体が思っているように動かなくなるだけではなく、制御も利かなくなる。寝ているときの失禁つまりおねしょは、老いを迎える人間にはショッキングな出来事である。筋力が弱って立ち上がれなくなったときの絶望は計り知れない。
人間は悲しみや苦しみ、苦痛や不安や恐怖で自殺するのではない。明日という日に何の希望も期待も抱けなくなったら、躊躇うことなく自殺するのだ。今日が酷い一日だったとしても、明日はいい日になると思えば自殺することはない。明日は今日よりももっと酷い一日になるだろうとしか思えなければ、自殺以外に道はない。いじめ自殺の心理的な構造も同じである。
現実世界にはおいしいシャンパンや贅沢な食べ物や人との楽しいかかわりもあるが、それらを全部底に沈めてしまう大きな絶望がある。年老いた主人公はそんな絶望をひとりで受けとめ、ひとりで決着をつける決意をするのだ。
そしてそんな状況でも母としての優しさを失うことはない。息子の、死にたいのは老いるのが怖いんだろう、鬱だから薬を飲めば治るという愚かな言葉にも何も反論せず、ただ悲しみの涙を流すのだ。
フランス映画らしく極めて実存的なテーマを真正面から描いている。宗教的な価値観の介在する余地はない。自殺が禁忌とされているのは宗教的な価値観ではなく、大勢が自殺してしまうと共同体の存続が危うくなるからだ。人を殺してはいけないとされているのと同じ理由である。
だから主人公は共同体の禁忌や法律と折り合いをつける。家族が共同体による禁忌の束縛から離れ、尊厳死を選択する実存としての自分を理解してくれるように努める。見事な生き方、立派な生き方だ。
こういう映画がきちんと評価されるところに、フランスの精神的な健全性がある。フランス語の原題は、そのまま翻訳すると「最後の授業」となり、別の映画のタイトルになってしまうので、今回の邦題はいいタイトルだと思う。
おばあちゃん
11/1 92歳のパリジェンヌ銀座
女の人は強い。
男の人はいざとなると弱い。
うちの家族だけかと思っていたけど、
共感する人は多いのかな?
おじいちゃんが笑顔になるように、
実家帰って孝行したいなって思った。
尊厳死ー
死にたいのは体が弱ったのではなく、
自分の死を自分で決めたい
ーと言う考え方があることを知った。
夜に対する考え方ー
歌うためや、誰かと愛を育むため
寝るためにあるんじゃない。
ーに共感した。
女の人は強い。
自分の意思を貫き通す。
男の人はいざというとき弱い。
自分勝手で幼い。
怒鳴り逃げ後で後悔をする。
父を見ているようだった。
死なないで、とは言えない。
96歳のおじいちゃんを想いながら
この作品を観ていました。
おじいさんが笑顔になるように、
安心して死ねるように、
自分も変えて行こう。
人生の最期を自分で
等身大の物語
フランスの元首相リオネル・ジョスパンの母の実話を原案にした映画。原案となった本を書いたのは、リオネルの妹であり作家のノエル・シャトレ。フランス映画祭2016で最高賞の観客賞を受賞。
フランスの元首相を描くのが目的ではないので、現実の世界ではその位置にあたると思われるピエールの職業は政治家ではありません。でも、この行動はおそらくこの作品で描かれたような、「母の主張を受け入れることは出来ない」と言う事だったんじゃないでしょうかね。そんな気がします。
ちょっとピエールの職業に脱線しますが、何やら中国と取引のある職業の模様。ハリウッド映画のみならず、フランス映画でも中国は避けて通ることは出来ないものなんですね。
映画の話に戻ります。こう言う作品の場合、みんなハッピーになって幸せになるというなんかキレイな物語になりがちですが、この作品はそうではありません。等身大の人々、現実の出来事として描かれています。そう言う意味で、見ている側も、リアルな出来事として捉える事がしやすかったと思います。逆にそれが故に、生々しいと言う気にもなりましたが。
高齢化が止まらないいま現在の日本にも当てはまるリアルな物語でした。
なにおもう
昼前の回での観賞
24人の観客
自分が最年少だったのでは?くらいシニア層の方ばかりでした
介護を仕事にしているものとしては
リハビリパンツ(一般的には紙パンツ?)をオムツとして悲しむ姿は
あぁ自分の感覚が麻痺してるんだな~と考えさせられました
どこを最期にするか、選べる、選べない…自分の意思より家族の意思が尊重されたり
家族内でのいざこざもあるし
とても難しいです
お兄さんの最後の立ち位置が とても悲しくて
グッと締め付けられました
尊厳死を扱った映画が増えてきたけど、
これが1番 かと
全23件中、1~20件目を表示