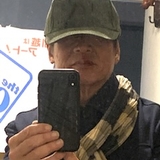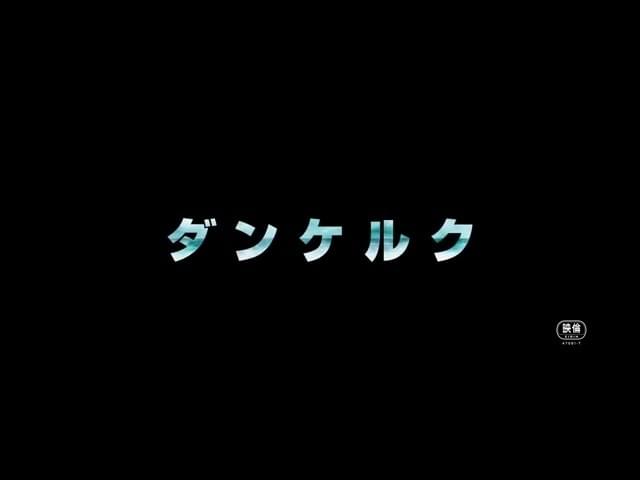ダンケルクのレビュー・感想・評価
全745件中、101~120件目を表示
ダンケルク
ジャムパンがうまそう
脚本家が逃げたんだろうか?
正直言ってしまうと、映画になってない。こんな作品初めて見る
戦場の雰囲気や迫力は非常に良かった。3つの話を絡ませるのも面白かった。でも各ストーリーの整合性が全然合ってない。迫真度を求める為に、時系列の異なるシーンを交差して緊張度を高めてるけど、改めてそのシーンの整合性を別のシーンから見ると疑問が湧いてきて、そこに気を取られる事が何度もあった。そうこうしてるうちに各視点でのシーンが一つに重なって盛り上げようとするんだけど、それより前のシーンの方が派手な演出が何度もあったので、3つの物語が繋がっても何も感じない。そもそもストーリー的に盛り上げようともしていない。でも映画として納めるためにそれらのストーリー達が凄かった、と後付けで演出する事でなんとか映画っぽく見せて終わらせてる。うーん、なんか変な映画を見てしまった
しかし、レビューを書こうとここに来て、この作品がアカデミーで凄い評価されててちょっと驚いた。一体どこがそこまで評価されたんだろう
4Dで見たけれど、飛行機のシーンで揺れる事が多くてちょっと酔った。4Dらしさを感じるには良い作品かもしれない
IMAXフルサイズで見なければ・・・
こんな戦地から早く逃げたい
4DX上映で見ました。
前知識ゼロ状態で見たので、状況も敵もよくわからないとこから「英仏」「チャーチル」あたりでボンヤリと状況を把握。
しかし敵は一向に顔も姿も見えず、耳をつんざくような敵機の音がしたと思ったら、爆撃の嵐ですぐ横にいた人が吹っ飛んで倒れていく…。
こんなところからスタートして、場面は陸海空と三箇所がほぼシームレスに切り替わり、どこも安全な所は無く、どこかが危険に陥れば別のところでもまたピンチに…。
すぐ横にいる人の名前も事情も知らないけれど、一刻も早く危険な戦場を脱したいという同じ気持ちになってきます。
後半、船室から顔を出して故国の陸地を見ようとする兵士の気持ちもよくわかりました。
4DXでは銃撃や爆撃のたびに激しい振動や頭の横を風がすり抜けていくのを感じられました。船上や飛行機のシーンでは常にグラグラガタガタと揺れちょっとしたアトラクションに乗っている気分です。
その分、最後にようやっと故国に着いた時にはスン…と静かになって兵士と一緒に一息つくことができた気がします。
最後にはチャーチル首相の言葉が読み上げられますが、撤退という不名誉にうなだれる兵士を労う言葉でありながらも、この戦争がまだまだ続くということが述べられていて、穏やかでいっとき明るい画面と音楽とは裏腹に私個人はやや暗い気持ちを抱えてエンディングのスタッフロールを見つめることとなりました…。
他のレビューを見ると、人間ドラマやアクション面で物足りなさを感じて退屈という意見もあり、確かにそういった感動やスペクタクルを求めて見る人には物足りないかもしれません。
IMAXとDolby Cinemaを体感するための作品
クリストファー・ノーランといえばIMAX。話題作「TENET」の前宣伝を兼ねて再上映されているので鑑賞。
ドイツ軍の包囲網からの命からがらの撤退戦なのに肝心のドイツ軍の姿が全く映らないという実録戦争映画としては奇抜で斬新な試みだが、代わって戦闘の緊迫感を音で伝えようとしているのが本作の特徴。
アカデミー賞で音響部門の賞を複数取っただけあって腹の底からズンズンと響いてくるような戦闘音などは、その辺のスペクタクル映画とは一線を画す。
映像的には、燃料が尽きたスピットファイアが黄昏時の海岸線をゆっくりと滑空している様が美しくて印象的だった。
終盤、帰還した兵士達に毛布を配っている盲目の老人が一人だけ顔に触れて自分の息子かどうかを確認していたシーンも「戦争とは何ぞや?」を問い掛ける、なかなか示唆に富んだ深いメッセージ。
キャストの中では、ボルトン中佐(ケネス・ブラナー)が切迫した場面でも常に大局観を見失わないリーダー然としていてカッコ良かった。
ただ、陸海空それぞれの作戦がごちゃごちゃになった展開は見づらいし、分かりにくいのがマイナスかな。
初IMAX
IMAXは、ノーランのキャンバス
初見は2017年にスウェーデンを旅行した時に、日本より早く上映していた現地の映画館で鑑賞して、それなりの好印象を受けていたが、普通な環境設備での鑑賞だったので、見逃していたIMAXレーザー版が、再公開されているので再見しました。
結論から先に言ってしまうと、「最高!」でした。(IMAX環境に限る)
それはフィルムに拘る映像作家クリストファー・ノーランの覚悟を感じたからである。
映像は全編に渡って素晴らしいが、特にラストのスピットファイヤの滑空が画面一杯に映される場面での映像の美しさは、映画史上に残る素晴らしさで最高!
戦争映画大作の定番だと複数のキャストと役柄のグランドホテル形式で描くのだが、登場人物の立ち位置を大まかに3組に分けて時間軸を交差させながら、同じシュチュエーションをそれぞれの目線で描く手法は、一見混乱し易いが、実はシンプルな反芻て成り立っている物語。
シンプルなのは、背景に現れていて、30万人規模の撤退作戦にしては、人や船や飛行機の数も明らかに少なくないが、緻密に配置してから画面構成をしているので、あまり気にならない。
以前からいわゆるCGやデジタル撮影に頼らないで、コントロールの難しいフィルム撮影にこだわってきたスタンスは、フィルム特有の色・質感などの再現性と独特の空気感スクリーンに映し出されている。
もちろん上映方式は、デジタルではなくデジタルデータに落とし込むのだが、IMAXレーザーの先鋭度に寄ってポジフィルムと遜色無い再現性があるのではと思う。
IMAX専用音響の強烈さも上々で、カチカチとアナログ時計の音で緊張感を煽る音楽と共に、銃弾や爆撃やか風切る航空機のエンジン音と臨場感が溢れ終始、緊張感を持続させる。
気になるところは、切り返しカットで特に人物の照明の光の方向や調子がチョイチョイと変わったり、色温度やカラーバランスに違いが見受けられる場面があるが、前者は、スケジュール都合によって生じるので仕方ないが、後者はプリントやデジタル変換時に補正可能だと思う。ただ監督のノーランはそれも含めてのフイルム撮影の特徴をスクリーンに刻みたいと思っているのかもしれない。
デジタル映画撮影についてのドキュメンタリー『サイド・バイ・サイド フィルムからデジタルシネマへ』でもノーランは、使える限りフイルム撮影に拘りたいと発言していた。逆に10才近く年上のデビッド・フィンチャーは、もうフイルム撮影に何もメリットがないと言っていたのとは対象的だった。
ともかく、今作はIMAX環境に限ると思うのは、映像と音響の効果が最大限に発揮できる環境を推奨している体感性の強い作品だから。
自宅でホームシアターを組んでも、映画館自体の広さも含めた物理的な理想空間は個人的では、とても再現が難しいと思う。
凄い迫力ある
何を目的としてつくられたものか、事前事後の考察が大事
この作品をノーラン監督がどのような意図で制作したのか、事前に、そして観賞後に考察することが必要では。そうしないと、何を観ているのか全く分からなくなる可能性がある。
内容は、英国がナチスドイツと戦うために大陸に派兵したが、ドイツに追いつめられダンケルクで孤立した約33万人の英仏兵を救出する実話をベースにしている。救出には多くの民間船が「出動」し多大な貢献をしたと伝えられている。
本作は、決して戦争翼賛の作品ではなく、かといって戦争反対のテーマ設定でもない。戦争という非常事態において、この救出作戦(ダイナモ作戦)を英国と英国民はどう捉えていたかを「救出現場」を通して描かれている。
同様な状況下に日本が置かれたとき、決死の覚悟で小型船をもって海を越えて自国兵を救出にいく市民がどれだけいるだろうか。
残念ながら皆無だろう(実際、太平洋戦争時にそのような話を聞いたことはない)。日本には政治や国防を、政治家や官僚、軍人任せではなく、市民が自分ごととして捉えることができる機会が歴史的になかった点は不幸なことだと思う。
自由や民主主義を自分たちの力で守ってきた欧州の歴史を理解せずに漠然と鑑賞すると、本作は戦争を肯定するかのような見方に陥ってしまう。海外の映画(特に歴史もの)を観るうえで、制作者の意図や制作国の文化や背景を理解することが大事だとあらためて感じる。
本作はまさにノーラン監督がいう、「体験」する映画。IMAXでこそ、その意味が十二分に理解できる。
「1917」では全編ワンカット(のように作られたもの)というイノベーティブな切り口を提示していたが、本作はTriptych(もとは三連祭壇画という意味)という三つの画がバラバラで進行し最終的に組み合わせていく手法で作られている。
半端ない臨場感、ビビりの方にはオススメ出来ません(笑)
IMAXとマッチした作品
ノーラン作品らしい映像体験を楽しめる作品としてIMAXで観るにはとてもマッチしていて迫力がありとても良かったように思う。とくに銃弾の音は迫力があり自分が戦場にまでいるような感覚になり作品に没入する事ができる。作品自体初鑑賞だった為IMAXかDolbyかで迷ったが、今から見るのであればDolbyの方を選択すれば、さらに作品を楽しめるような気がした。
台詞が殆どない為いかにこの作品に没入し、自分が一人一人の兵士の視点になりきったような見方をすると非常に楽しめたようにも思えた。ただ若干中だるみは感じてしまった。
似たような作品で今年1917があったが、個人的には1917の方が見易く楽しく思えた。まぁこの辺は好みの差か。
ノーラン作品は頭や心を使い時には見疲れする作品も多いが、そういう意味ではこの作品はラフに見られるような作品に個人的には思う。
もちろん深く見ればもっと味が出て深みのある作品なのかもしれないが、個人的には戦場体験ムービーとして楽しませてもらい、それなりに楽しむことはできた。
ただ見るならやはりIMAXなりDolbyが良いように思う。大音響の中見るのと自宅で見るのではかなり印象が変わる作品に思える。
独自視点の戦争映画
海岸で帰還を待つ夥しい数の英兵。
乗船に奔走する在英外国人。
作戦ダイナモに参加した何隻もの民間船のなかの一隻。
たった三機で制空を担うスピットファイア。
海の彼方を見つめ、佇む指揮官。
車両で桟橋を設営する残留部隊。
それらが、無作為のように入れ替わりながら描写される。
その背景には、メロディをなさない弦楽奏が反復している。
そして恢恢のシーナリー。
どこまでも拡がる海、海岸に並ぶ英軍の列、真っ青な空。
乱暴な言い方をすると、心象描写ぬきのテレンスマリックのような美しい構図が続く。
いうなれば、もっとも美しい戦争映画で展開される人間のドラマ。
圧倒的な緊張感。
白眉は、水平線に何十艘もの民間船(帆船・ヨット・はしけ・モータボート)が見えたとき。
What do you see?
Home!
スクリーン上のケネスブラナーと同時に目頭があつくなった。
独兵がひとりも出てこない。
帰還船・桟橋への爆撃や、爆撃機・戦闘機との空中戦はあるが、ドイツ軍の描写がまったくない。
完全に無かった。
この戦線で、憎々しいナチスを可視化しないのは異例ではなかろうか。映画には相手国への敵視が感じられない。
戦争だから、戦っている。
いたずらに英国を賛美してもいない。
きわめてフェアな戦争映画だと思った。
覚えているのは銃声
全745件中、101~120件目を表示