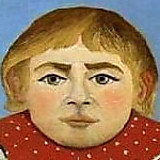ディーパンの闘いのレビュー・感想・評価
全50件中、21~40件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
スリランカから家族を偽装してパリ郊外に逃れてきた人々の生活が淡々と描かれる映画、途中まではそう。随所に挟まれるゾウのアップがまた郷愁をそそってたまらない。が、途中からものすごいアクション映画に様変わりしてディーパンの最強っぷりに歓喜。サイコー!
ウィーラセタクンとイニャリトゥとリーアム・ニーソンのいいとこ取りって感じで永遠に観ていたい映画でした。
異国でのサバイバル
移民社会のジェンダー
内戦のスリランカを脱け出した元反政府ゲリラの男ディーパンと、女ヤリニ、少女イラヤルの三人。三人とも家族は内戦で失ってしまっている。この三人で疑似家族となり、フランスへと移住するのだ。
いきなり外国へ来て、まず苦労するのはお金と言葉の問題。しかし、まだ子供であるイラヤルが言葉の問題を一番早く乗り越える。当初は引きこもりがちだったヤリニも、仕事を通じて存在が認められるようになると、自分を取り巻く社会を理解し溶け込もうと努力する。
ディーパンはと言うと、必要にかられて仕事を懸命にするものの、周囲に溶け込むことは全く考えない。
ディーパンにとっては、スリランカにいたときと同様に、フランスでの生活もサバイバルに他ならないのだ。しかし、一緒に来たヤリニとイラヤルという女性二人にとっては、その社会で生きるということは、自分がその文化を受容し、自らもまたその社会に受容されることを意味する。
ジェンダーや年齢が、移民の社会への浸透に格差を生み出すという視点が興味深かった。
怒らせてはいけない男
静謐と爆発。
パルムドールに期待をせずに観たら、ものすごい形で裏切られた一本。
血も繋がらないディーパン一家の異国フランスでの生活を通して、男女・家族・民族・貧富等々多すぎるほどの各種の「溝」で織り成す物語。
そこには希望も明日も無く、あるのは過去とただ今を生きるための惰性の現実。
それらをすべて飲み込む最後に訪れるカタルシスの凶暴な清々しさがとにかく圧倒的で素晴しかった。
前半の淡々とした描写が無ければ、このカタルシスは生まれないし。
後半の爆発が無ければただの鬱々とした所謂「カンヌらしい」作品でしかなかっただろう。
この構成の妙はさすが監督、と言うべきなのだろうか。
万人にお勧めはしない社会問題の縮図、だが少しでも関心があるならば観て絶対損はしない作品。
なかなか味わい深い
力あるね。
正直、前半の疑似家族くだりはきつかった。何となく後半への期待が見えなくて。が、ラストのディーパンの怒りの爆発が良かった。もしかして前半の悶々もこのための布石だったように思えるけど、まさか?
ターミネーター
それでも夢をみる
最後の「夢」のシーンで泣きそうになった。
こんな状況なのにまだ夢をみてるのか、将来への希望を捨ててないのか、バカじゃないの?ほんとバカじゃないの?ディーパンの愚直さに泣きそうになった。
この映画は、ペキンパーの『わらの犬』を下敷きにしているという。『わらの犬』のあらすじ(物騒なアメリカを逃れイギリスに移り住んだ若夫婦。だがそこも牧歌的な風景と裏腹にゲスな暴力がはびこる場所だった…)と本作は似ている。が、ラストは全く違う。
『わらの犬』のラストは、主人公のダスティン・ホフマンが虚無的な眼をして去っていく。夢も希望もへったくれもないシニカルなラストだ。
ディーパンの置かれた状況は、『わらの犬』よりも更に酷い。
本作は、それでも夢をみる、男の物語だ。
希望など持てる状況でないのに、それでも家族との未来を夢みた男の物語だ。
—
私は正直『わらの犬』のラストの方が、今の現実に近いのではないかと思う。シニカルになって当然のような気もする。だが、映画が現実を追ってどうする?
本作は、内戦、難民、フランスの下流といった現在を、リアルに作り込まれた映像で、ドキュメンタリーかのように描いている。日本人にとって身近な題材でないにもかかわらず、切実に感じてしまう。ディーパンという男が実在したのではないかというほどの熱がある。
それはキツい現実を知らしめるためというよりも、そんな状況にあっても、人を愛してしまった、希望を捨てきれなかった人間を、出来る限りの迫真をもって描きたかったからではないかと思う。
それはキレイゴトなのかもしれない。嘘くさいことなのかもしれない。虚無が本当なのかもしれない。でも、ディーパンみたいな男がいたって良いじゃないか、そんな祈りが、リアルとノワールが交差するこの映画になったのではないかと思う。
———————
<追記1>……三つの賛美歌
私たちは何も考えずに難民とひとまとめにするが、各々習慣が違う。こだわりが違う。この映画では、その違いをさりげなく描いていたと思う。
偽装家族として一つ屋根の下に暮らす他人。
片方は食事の前には祈り、片方は信仰に重きをおかない。
片方は食事はスプーンで。片方は手で掬って食べる。
兵士のディーパンにしてみれば、同胞を救うための内戦だったが、女にしてみれば、その内戦で祖国を捨てるしかなかった訳でディーパンもまた加害者である。
異国で、異質なバックグラウンドの者が分かりあえるのか。それを象徴するかのように、この映画には、三つの異質な賛美歌、祈りが流れる。
冒頭の、賛美歌「主は愛するものに眠りを与えたもう」。
二つ目、ディーパンが酔っ払って歌う唄。信条を歌ったこれは、元兵士にとっての聖歌だ。
そして、三つ目、ディーパンの疑似妻ヤリニが信仰する寺院で流れる読経。
三つの異質な祈り、文化は溶け合うのか。乗り越えられるのか。本当の家族になれるのか。それを映画は丹念に追っていたと思う。
—
<追記2>……四つの夢
ディーパンは、異なるバックグラウンドの女を愛しはじめる。
そして元兵士という自分のバックグラウンドを捨てようとする。
途中、ディーパンは内戦の上官にしたたかに蹴られる夢をみる。過去と決別する自分を罰するような夢をみる。闘いにすべてを捧げてきた元兵士の深い葛藤がある。
それでも、ディーパンが選ぼうとしたのは、新しい家族であり新しい生活だったのだと思う。
(この映画にはディーパンのみた四つの夢が入っている。ディーパンが寝ているor意識が途切れた後に夢を差し込んでいて、そういう所が律儀だなあと思う。)
—
<追記3>……二つの疑似家族
ディーパンと対照的な男が出てくる。
団地に住み着く麻薬ディーラー、ブラヒム。その名前から推測するに彼もまた移民の子なのではないか。
ブラヒムとヤリニのやり取りは、言葉が通じないにもかかわらず、いや言葉が通じない気安さからか、どこか静かな共鳴がある。ヤリニと彼もまた疑似家族のようにも見えてくる。
ディーパンは疑似家族を本物にしようとしたが、ブラヒムはそんなに他人に期待していない。
ブラヒムはチンピラのボスではあるが、自分は所詮捨て駒であり、この世界から抜け出せず死んでいくんだろうなと、うっすら自覚している。世間に何も期待してない。誰も助けてくれないことを知っている。彼の諦観もまた、この映画の中で切なく響く。
家族を守る闘い。
2015年・第68回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した作品。
主人公ディーパンを演じたアントニーターサン・ジェスターサン
は実際にスリランカ内戦時には青年兵士、その後フランスに亡命。
決してイケメンではない彼の(失礼!)静かな表情や振舞いに却って
心が波立つ。平和に暮らすことだけを願いパリ郊外の集合団地に
越してきた彼と若い女と親を亡くした娘の偽家族3人だったが…。
高倉健の映画に似てるなど感想をお持ちの中高年の皆様の気持ち
がすごく分かる、静かであればあるほどいつそれが噴出するかと
気が気でない。彼がいい夫でいい管理人でいい人間であればある
ほど、あぁどうか、この幸せを壊さないで欲しい…と祈るばかり。
母国で家族を亡くし、もう銃撃なんか見たくないと怯える若妻の
気持ちも、学校に置き去りにされるんじゃないかと後を追う娘の
不安も、難民になったことのない自分には分かるはずもないのに
怖すぎて泣きたくなるのだ。この国は安全?なはずだったのに…。
別の移民達が起こす暴力や抗争が巻き込まれたくない人間を勢い
巻き込んで恐怖へ突き落とす。彼らとの優しい時間や会話があれ
ばこそ、後半の悲劇はどこへ逃げようが難民の闘いは終わらない
ことを指し示す。英国に行けば安全?いやそういうものでもない
だろうにと思うのだが、ディーパンの初笑顔には泣けてしまった。
(負けるなディーパン!暴力に屈せず、家族と平和を守り通せ!)
家族のカタチ。
フランスの低所得者用団地って…
人の夢と、書いて…
テレビで見るフランスは、いつもおしゃれですね。そしてスクリーンに映るおしゃれな街では、ちょっと皮肉の隠し味が効いた、ロマンスが。そんなビジターの思いを、余す処なく粉砕する逸品です。昔、「ウィンターズボーン」で、地球の歩き方に、掲載されないアメリカに、驚愕したものです。でも、やはりそれは、何処にでもあるんですね。しかも、難民、移民問題という、隠しきれない隠し味が、メガ盛りなので、すっかりお腹いっぱい。そして、怒涛のアクションの後に訪れる、この世のものとは、思えないラストと、エンドロールの歌声。あれは、多分…。たちの悪い冗談に、付き合わされた気分です。これがカンヌの味わいでしょうか。深いコクと、芳醇なはかなさに、気を失いそうでした。
よかった
見ている最中はドキュメンタリータッチの地味な作風でけっこう退屈してしまったのだが、後から後からやっぱりすごくよかったような気がして今はもう一度見返したくてしかたがない。
無関係な3人の難民が家族として暮らすところは自分にとって重要なテーマだった。
ディーパンが小さくて見てくれが悪く、どんくさい人物に見えるのだが、意外と腹が座っていてかっこいい。そんな風に思っていたら軍隊仕込で圧倒的な戦闘力を備えていることが分かっていてびっくりした。
女の子の出番が少なかったのでもっと見たかった。
戦場、生きる、そして家族
先の読めない展開、観る価値あり
圧巻の銃撃戦
開巻、スリランカの場面にまずは衝撃を受ける。死んだ戦士たちをまとめて焼いている。
戦争下の町や貧民窟を描写した映画はたくさんあるが、それらを観るたびに日本の平和と治安に安堵する。
女が避難民のキャンプで手当たり次第に訊ねて回っている。「この子はあなたの子?」
やがて、親を亡くした少女を見つけると、その子を連れて主人公のもとへ。
元兵士の主人公と、件の女と少女。
家族を偽装して難民として国外へ出るのだが、少女を説き伏せる場面もなく、暗黙のうちにお互いの利害一致が了解されているのだろうか。
果たして、送り込まれたフランスのとある高層アパート。
これが、戦火のスリランカと変わらない危険な臭いがする怪しい場所だ。
少女を地元の学校に入れるが、逃げ出して主人公にすがりつく。「一緒に帰りたい」
他人同士の偽装家族に芽生える絆の兆しだ。
この映画で心を打つ最初の場面。
夜、主人公の部屋に「一緒にいていい?」と、少女が入って来る場面もある。
母親役の女とうまくいっていない。
女も20代の若い娘である。子供をもった経験はない。
窓越しに同世代のフランスの娘たちを見つめ、何を思っていたのだろうか。
主人公は、女が入浴していると気になってしょうがない。
そりゃあそうだろう。
だが、なにもしはしない。
主人公も女も、勤勉さが周囲に認められはするが、そこは麻薬密売組織の巣窟だった。
危険な環境であることは、母国と変わらない。
少女が「優しくして」と女に懇願し、二人は打ち解ける。
女と主人公も結ばれる。
全編通じてほんの一瞬、幸せな空気が流れる。
3人は、お互いを家族として生きていくしかない。
ならば、女は少女に死んだ弟と同じように接すれば、擬似母子になれる。
男と寝てしまえば夫婦になれる。
関係を進捗させたのは、女なんだなぁ。
しかし、それも束の間。
麻薬密売ギャングたちの抗争が表面化し、たちまち危険にさらされる。
主人公たちには容赦のない物語展開だ。
が、ここからがこの映画の見せどころ。
主人公は、一人で逃げ出そうとする女を咎める。が、少女と二人で逃がしてやろうとする。
女は主人公の優しさを改めて知る。
女を助けるためにギャングたちの抗争の直中に突入する主人公。
銃撃戦の激しい描写は、リアルだ。
本当に銃弾が飛んでいるような迫力。
フランスには実際にあんな場所があるのだろうか。
警察の手も届かない無法地帯のようだった。
戦場からやって来た主人公は、正義のためではなく女のために戦う。
カッコいいじゃないか!
眠くならないパルムドール作品
全50件中、21~40件目を表示