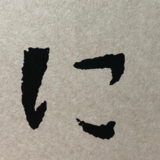ヒトラーの忘れもののレビュー・感想・評価
全26件中、1~20件目を表示
戦争の遺産 悪魔が蒔いた種
戦争が終結しても埋められた膨大な数の地雷はその後も死の花を咲かせる種となってその場に居座り続ける。
第二次大戦で連合国と戦ったドイツ、イタリア、日本の三カ国は悪の枢軸国と呼ばれた。ファシズムの下で侵略行為を行い周辺国に多大な被害を与えたとして。
その中でも特にドイツはナチスによるホロコーストなどもあり、敗戦後も連合国から憎悪感情の対象とされた。
彼らドイツ兵は敗戦後連合国側の様々な捕虜収容所に入れられ過酷な運命をたどることとなる。本作のような非人道的な強制労働をさせられた者や、あるいはドイツが行ったわけでもない戦争犯罪の加害者に仕立て上げられて代わりに処刑される者までいたという。しかし彼ら捕虜がたどった運命が広く世界に知られることはなかった。
当時の西ドイツ政府捕虜史委員会は捕虜であった帰還兵から多くの聞き取り調査を行い、彼らの受けた様々な悲惨な体験を報告書としてまとめたが、それを当時の西独政府は国際的に公にはしたがらなかった。
ナチスドイツの加害責任と自国の捕虜たちが受けた被害との相殺を目論んでいると勘繰られるのを恐れたからである。当時のドイツには周辺国からの信頼を取り戻すことが最優先され自国の兵士が受けた被害を主張することなどありえなかった。そうして捕虜たちの悲惨な末路は歴史の闇に葬られることとなった。
しかしこの度、デンマークの歴史家による暴露で少年兵を含む未経験者を使った地雷撤去強制作業という事実が明るみになり、そのあまりに非人道的な行為がデンマーク国内で物議をかもし、本作が製作されることとなった。
このデンマークで行われた捕虜を使っての地雷撤去の詳細を記した書物はそう多くないが、やはり前述の西独政府捕虜史委員会の資料によるとフランスで同じように地雷撤去を強制された元捕虜の証言がある。本来それは専門の兵士にやらせるものを未経験の捕虜にやらせて多くが犠牲になったという。中には少年兵も混じっていてその点もまさに本作の内容と合致する。地雷撤去後の一帯を歩かされたという記述もある。
だが当時の捕虜たちは帰国を餌にされて進んで地雷撤去を行ったという。彼らにとって帰国を成し遂げる手段はそれしかなかったのだ。毎日仲間が一人また一人と爆死してゆく中でも彼らは帰国を信じて作業を続けたという。
そんなジュネーブ条約に反する行為が当時のナチス兵捕虜に対しては横行していた。戦後の混乱期でもあり戦勝国とはいえ国土は破壊され復興のめども立たない中で敵国の捕虜を手厚く扱うなどできはしなかった。食料も不足していて捕虜には十分な食事も当たらなかった。
敗戦直前期、日本同様当時のドイツはもはや疲弊の極みに達しており兵隊の数は不足して16歳未満の子供でさえ戦場に送らざるを得なかった。そうして戦場に送られ敗戦を迎えて捕虜となったのが本作で描かれたような少年兵たちである。
はたして彼らに罪はあるのだろうか。もちろんヒトラーを信奉し、捕虜になる前に敵兵の命を殺めてきた者もいるかもしれない。しかし、彼らが当時のドイツに生まれてその国を支配するナチスに逆らうことなどできるはずもない。それは当時の大日本帝国に生まれた少年たちも同じだ。自国のすることが正しいと信じて皆が戦った。それは連合国側にしても悪の枢軸国と言われた側の国の人間もみな同じだ。
戦争は殺し合いだ。敵同士が戦争で殺し合うのは当たり前だろう。しかし戦争が終わってもいまだ敵同士なのか。戦争が終わればもはや戦う必要はない。相手は武器も持たない。それはもう敵ではないはずだ。確かに家族や仲間を殺した敵国の人間として恨みがあるかもしれないがそれはお互い様だ。しかし当時の終戦直後いまだ感情が冷めやらぬ時期を考えればそのような冷静な判断を期待するのは無理からぬことなのかもしれない。
戦後80年が過ぎてようやく当時の忘れ去られた戦争の犠牲者たちの遺跡がこれから掘り起こされてゆくのかもしれない。
本作もそういう忘れ去られた戦争の犠牲者たちの声に耳を傾ける作品になっている。とともに、たとえ加害国だとしてもその国の人間をここまで非人道的な扱いをすることに果たして正当性を見出せるのか。本作はそれも問うている。
まだまだあどけない若者である少年兵たち。彼らが戦場に送られてきた事情は自分たちの立場と照らし合わせれば容易に理解できるはずだし、彼らを憎むよりも憐れに思うのが本当ではないだろうか。しかし食事も与えられず家畜のエサで食中毒になって苦しむ彼らの姿を見て農家の主婦はいい気味と笑顔見せる。さすがにナチスを憎む軍曹でさえその態度にカチンとくる。
しかし軍曹も同じだった。彼も少年兵たちを憐れに思い情けをかけることもあったが、愛犬が爆死したことから態度を豹変させて彼らに砂浜を歩かせるのだ。これはどんなに彼らを同情して彼らと心を通わせようとしたとしてもけして許される行為ではなかった。
彼らに小便をかけて侮辱した兵隊たちよりも軍曹がしたことは酷い行為だった。目の前で一人また一人と少年兵が地雷で犠牲になる光景を見てきたはずなのに、それを見て自分たちが彼らにしてることはナチスと変わらないと感じていたはずなのに彼は少年たちを砂浜に歩かせたのだ。
憎しみがいかに人間を変えてしまうのか、あるいは憎しみによって元から持つ本性がさらけ出されるのか。
彼ら少年兵たちにとってはこの地はアウシュビッツ収容所とまさに同じだった。憎しみの心が人間をナチスに変えてしまう。誰もが憎しみの心によってナチスのような残虐行為を行えてしまう。
相手がナチスに加担したから、自分もナチスと同じことをしていいという理屈は所詮は自分たちも同じナチだと認めることになる。ナチスには何をしても許されるという考えはユダヤ人には何をしても許されるという考えと同じだろう。たとえ憎いナチスであろうとも自分たちは同じことはしない。人間であり続けたいと願うべきなのだ。
本作自体は史実を基にしたフィクションであり、ラストは救いが感じられる結末になっている。しかし当時のドイツ人捕虜たちの末路は本作で描かれた以上に悲惨だっただろう。そんな声なき犠牲者たちの声を声高々に主張するには世界はまだまだ未熟なのかもしれない。
本作はなかなか知られることのない加害国側の捕虜の悲劇を通して戦争の不条理を描いた衝撃的な作品であり、また少年兵たちとデンマーク人軍曹との心の交流を描いた佳作だが、脚本的に軍曹のキャラクターの描写が失敗している点が残念だった。彼がたとえ愛犬を失ってもあの場面で怒りを抑えることが出来なければ結局彼は少年たちのと交流を通して何も進歩してなかったことになる。そのあとに彼らを逃がす行為の説明がつかなくなってしまったのが残念。あの脚本のミスがなければ満点に近い作品だった。
辛すぎる。
地雷なんて物を考えついて発明する人がいることに、本当に人間の残酷な一面を見せつけられる。
150万個の地雷を2000人の少年兵で撤去したらしい。計算すると、1人ざっと750個。
映画だとわかっていても、地雷のある場所に少年達がいて、ひとつずつ触っているのも目を背けたいくらいで観てられなくて辛過ぎた。
最後、4人を国に帰してあげてくれた事が本当に救い。ありがとう。
国境まで走っていく時にも地雷で爆発して死ぬってオチじゃないよね??とドキドキハラハラしてしまった。
もう地雷の撤去は人がやるのはやめてください。今の時代は機械があるから、そちらでお願いします。
あと、ロシアもこれ以上地雷とか埋めたり、戦争続けるのやめてください。
知るべき戦争現実の名作
ヒトラーの罪は深い。戦時中だけではなかった。war is not over、という状況。
ナチスドイツによってデンマークの海岸地帯に埋められた地雷原を、戦敗国であるナチスのデンマークに取り残された少年兵らが駆り出されて命がけで除去してゆくストーリー。
10代の若者らが理不尽な仕打ちを受け続ける訳だが、同時代の日本を思い起こせば予科練出身の神風特攻隊や回天を思い出す。洋の東西を問わず、しょうもない大人らに翻弄された少年たちの悲劇。本作では結局のところ、ヒトラーの作戦の後始末をさせられている訳である。少年兵に対するデンマーク兵の軍曹の気持ちも分からんでもないが、それにしても、とも思う。憎むべきは少年兵ではなく、ヒトラー含めたナチス上層部である。しょうもない荒くれ者のヤンキーが、街で子犬の頭をちょっと撫でれば「実はとてもいい人」と思われてしまう風潮があるが、それは違う。騙されてはいけない。少年兵らへのひどい態度のあと、多少は自責の念からちょっと食事を差し入れたり、一緒に遊んだり、となるが、結局自分の犬が爆死すれば、また少年兵らのせいにするしょうもない大人な訳だ。ま、流石に自責の念に駆られて最後に彼らを逃がしてやるという相当に重い決断をした訳だが、それをもってして、人として合格点、とは思えない。
しかしこのような世界中のほとんどの人々が知らなかった重大な残酷な史実を知らせてくれる映画は非常に貴重であり、こういうのは中学、高校の授業で流すといいと思うんですよね。歴史の教科書を普通に読むよりずっとためになると思います。★5つ。
戦争の残滓
1945年5月、ドイツが無条件降伏し、デンマークにはドイツ軍の少年兵たちが残された。少年たちはナチスがデンマークの海岸に仕掛けた無数の地雷を撤去することを強要される。エンディングでもテロップが出るけれど、これは実話らしく、かなりの数のドイツ兵が死亡したらしい。
映画のポスターには「少年たちが見つけるのは、憎しみか明日への希望か」とあり、あどけない顔した少年が海岸に横たわっている。タイトルが「ヒトラーの忘れもの」。ほんわかしたヒューマンドラマなのかと思ったら、うぅむ、これは、ちょっと見るのが辛くて、胸が詰まって涙が出そうになりました。
まだ、お尻が青いような少年らが、こわごわ、素手で砂をかきわけて地雷を撤去していくとは。下手に扱うと一触即発で命が吹っ飛ぶ。食事もろくにもらっておらず、寝る時間は決められて、逃げ出さないようにドアに錠を下ろされて。
鬼のような軍曹は当然、ドイツへの憎しみがあるけれど、任務と立場と正義の葛藤の中で心が氷塊していき人間らしさを取り戻していきます。最後に、軍曹は約束どおり、少年たち4人を母国へ帰します。少年たちは家に帰れたんだ。最後はせめてもの救いでした
史実に基づいた話
実話らしい。
軍曹は最初嫌な人だったけど、ドイツ人少年に寄り添うようになって1番好きになった。
ドイツ人少年たちの顔が覚えられず、誰が誰だか最後まで分からなかった。。
解説を見てなるほど、って思うところが多々あった。
軍曹と仲良くなったセバスチャンと、色々問題児のヘルムートがリーダー格で対立しているというのを理解すると色々見えてきた。
軍曹と少年兵が打ち解け、ビーチでサッカーをしているシーンは泣きそうになった。
愛犬が亡くなったのはつらい、、
双子のヴェルナーが死んだことにショックを受け、エルンストも自ら地雷を踏みに行ったシーンは泣いた。
最後ドイツに帰国かと思いきや、次の地雷作業場に連れていかれた時は少年兵4人が諦めの表情になっていて辛くなったが、軍曹が帰してくれて良かった。。
あそこも実話なのかなぁ、、。
色々残酷だけどオススメしたい映画。
忘れものを届けに来ましたよ〜!
原題"Under sandet"は「砂の下」。「ヒトラーの忘れ物」が邦題。
「砂の下」に取り残された地雷。敵地に取り残された少年兵。邦題には、この二つの意味が掛けられていると言います。もう一つあるんじゃない?
ラスムスン軍曹とセバスチャンの間には、親子の様な心情が芽生えていました。ミッションをやり遂げて生き残ったのに、約束は守られず別の地雷原に移動させられる少年たちを、ラスムスンは国境まで500mの場所で解放します。ヒトラーが少年時代に忘れて来たものって「人への愛情」だよね。
そもそも原題の意図は。
砂の下にあったのはナチへの復讐心。地雷が除去されて行き、復讐は少年達への愛へと変化して行く。子供達に戦争のツケを払わせてはならない。壊れた国を再建してもらわなくてはならないのだから。
邦題も悪くないけど、原題の意図と少し違う事ないでしょうか?ってのは気になりました。
いずれにせよ、ささくれた心に滲みてしまう映画でした。何回も泣けたのは、お家だったせいかもしれんけど。
良かった。とっても。
人類の教訓
常に緊迫感があり、心が休まる暇がなかった。
今日本で平和に暮らしているので、本当にこんなことがあったのかと毎回戦争映画を見て驚く。
この映画でも、地雷をまずこんなにも埋めるのにも相当な危険があるし、そこまでやるのかと思った。
撤去も途方もない作業で約半数が死んだと最後にあったが意味がわからない。
この時代に生まれていたら自分はどう過ごしていただろう、自分も戦争によって今とは全く違う人間になっていると思う。
戦争はどんなことがあっても絶対に起こしてはならない。
いろんな方にこの映画を見て感じて欲しい。
良い作品ではある
導入からいきなりドイツ兵をなじり、もういいだろうというくらいしばき倒す主人公のラスムスン軍曹。
戦争は終結しても、まだその熱に浮かされ敵はゴミ以下の扱いよう。そんな彼の下に戦後処理の実行隊として、ようやく鼻の下にうっすら髭が生えてきたくらいのドイツ軍少年兵達が派遣される。
軍曹はファーストコンタクトで「なんだ?子供じゃないか?!」と面食らうも、憎き敵国の兵士と割り切り、厳しくあたる。
地べたに這いつくばり、ただただ地道に地雷を処理していく少年兵たち。ゴールなどあって無いようなものと思いつつ、「処理が終わったら家に帰れる」という軍曹の言葉に一縷の望みを託しながら。
そうした姿、また処理に失敗して死んでいく彼らを見て、一人の人間としての自分と軍人の矜恃の狭間で苦しむラスムスン。
地雷の処理シーンでは、このシーンは爆発しないなとわかっていつつも、いちいちハラハラさせられる。この子役達は本当に素人なんだろうか?本当に見入ってしまったし、双子の兄貴が死んだ直後、弟が「砂浜に戻って兄を探さないなきゃ!」とうなされるようにベッドで喋っているのを、「明日必ず探そう」となだめ、涙を堪える軍曹のシーンはヤバかったですね。
全編において、緊張とやるせなさに支配され、気を抜けない。
ただ、ラストが…個人的には、ちょっと。
良かったとも思う反面、バッドエンドにしてもらいたかった気持ちもあります。リアル体験はしていませんが、戦争は惨いものでしょ?
「理不尽でバカげた救いのない戦争を身体全面で受け止める」のが、戦争を知らない世代には必要かと。
辛い
タイトルはなんだが可愛らしい雰囲気だが、中身は全然。邦題を恨むよ。
わずかな時間、サッカーを楽しむ少年兵達。
帰ったら〇〇するんだ!という話を楽しげにする彼ら。
そんな明るいシーンは本当に短く、少なくて。
目を覆いたくなるシーンばかりが続いて、正直辛かった。
せめて帰国出来た少年達が幸せな人生だったと思いたい。
目をそらしてはいけないこと
反戦映画。
重たい。やり切れない悲しい気持ち。怖い。
こんな歴史があったんですね。
いろいろ考えさせられました。
自分が軍曹だったら…
自分が少年兵だったら…
ラストは…映画やな…思いました。
(ホッと一安心やけど…その後…想像したら…複雑やわ…)
観て良かったです。
こんな映画を作れるなんて凄いですね!
戦争は絶対にやってはいけない!
ラストが秀逸
砂に埋まった無数の地雷を
一つ一つ手で除去して行く少年兵たち
彼らはまだ子どもであり、
夢があり、腹が減り、
よく遊び、よく眠る歳なのだ
ひとり、またひとりと命を落とす彼らに
感情移入しすぎて終始辛い映画だった
映画のキーパーソンは軍曹
どちらも人であり、国民であり、感情があるんだなぁ、と感じた。彼は誰かの親だったのかもしれない。戦争は彼から何か大切なものを奪ったのかもしれない
双子の兄が死んだとき「兄を許してください、わかってやってください」「ドイツで左官をします、ドイツは今瓦礫だけなんです」と虚ろな目で軍曹に伝えるシーンが印象的だった。優しく撫でる軍曹の後ろ姿が寂しくも美しい。どちらも失ったものが大きすぎる両国のどちらにも寄らない映画での描き方が心にしみる。
物語の冒頭も印象的
原題の言葉が突き刺さる
僕たちが憎いから爆死しようが餓死しようが関係ないと?
映画「ヒトラーの忘れもの」
(マーチン・ピータ・サンフリト監督)から。
タイトルの意味は、冒頭にサラッと説明される。
「ドイツによる5年間の占領が終わった。
ナチスが西海岸に埋めた地雷は220万になる」
デンマークの海岸沿いに残された無数の地雷こそ、
「ヒトラーの忘れもの」なんだとよくわかる。
その地雷撤去を、敗戦国ドイツ軍の少年兵に強制していた、
その史実も驚いたが、もっと驚いたことは
作品の製作国が「デンマーク・ドイツ合作」だったこと。
第2次世界大戦直後、それほど憎みあっていた両国が、
どちらかの国を美化するのではなく、しっかりと現実を見つめ、
自分の母国がしたことへの反省と、責任を感じて作った、
そんな気がしてならない。
心に刺さる台詞の中から、いつ地雷に吹き飛ばされるか分からない、
食べ物も満足に与えられず、腐ったものを食べて嘔吐下痢を繰り返す、
そんな極限状態で、ドイツ少年兵が、デンマークの人たちに叫んだ、
言葉を選ぶことにした。
「僕たちが憎いから爆死しようが餓死しようが関係ないと?」
人間って、どこまで冷酷になれるんだ・・と怒りが込みあげたが、
それを救ってくれたのが、ホッとして涙腺が緩んだラストシーン。
ハッピーエンドとは言えないけれど、それでも温かい気持ちになった。
日本もこういった映画を作るべきかもなぁ。
善と悪の狭間
「ヒットラーの忘れもの」とは?映画を観てよく理解でき、この邦題は素晴らしいですね。
戦後2000名ものドイツの少年兵がデンマークの捕虜として地雷撤去に駆り出されて居たなんて!こんな事実があっんですね、まずは驚きました。
そしてよくぞこの題材を映画にしてくれましたと頭が下がります。
デンマーク人の軍曹は捕虜として又憎むべきヒットラー率いるドイツ軍の兵士としての扱いを当然として行っていた。
しかしその少年兵達と接している内にふと疑問を感じたのでしよう、こんな若い少年達の命をこんな事で奪っていいのかと。
まずは食べ物を子供達の所へ持っていく(放り投げたけどね)
浜辺でサッカーをしている軍曹と子供達、逃げだせないように大きな木の板を外した時ホッとして緊張がほぐれました。良かったと安堵しましたが、愛犬が地雷で死んだ時、また冷酷な軍曹に逆戻りする。人って間で生きているのだなーと思いましたよ。
地雷撤去が終わり14人いたのに、4人しか残らなかった少年兵を軍曹が救い「国へ走っていけ」言うと後ろを振り返りつつ走っていく少年達は何を思っていたのでしょう。
一刻も早くドイツに帰り国を建て直すと言っていた事を実行すると信じます。こんな過酷な体験と人の善意を知ったのだから。
双子の兄が地雷で死んだ後、弟は錯乱し、軍曹に兄を嫌わないでと懇願するでしょ。その弟が少女を助け、自ら地雷を踏み亡くなるところ切なくて泣けました。
「ソフィの選択」や「サラの鍵」など悲劇的な結末で衝撃を受けましたが、この忘れ物の最後をこのかたちにしたのも、きっと意味があるのでしょう。
軍曹の行為は深い感慨とは思えませんが、それに軍曹のその後は?少年兵が無事に祖国の地に着けるかとか、不安は数々あるけれどこれはこれで良かったと思います。
その前にこんな事実を私は深く受け止めましたから。
デンマーク、ドイツ、サイドを変えてみると善悪の曖昧さ、真実も歪んで見えたりする。
それを映画を観た者が考え見抜いて!と言っているような気がします。
タイトルはこのままでいい
タイトル批判があるが、私はこのままでいいと思う。
地雷の国だの土地だの、地雷と少年兵だのというタイトルだったら、多くの人がこの映画の存在にすら気が付かないで通り過ぎてしまう。
ヒトラーだから人はこの作品を観る。
その名が犯した罪を知るから。
ラストシーンも賛否あるが、私は観る人の心情次第で解釈が変わる良いシーンだと思う。
アレで母国ドイツに帰りハッピーエンドだと信じたい人、国境警備に捕らえられてしまったと考える人。
私は、軍曹の人間らしさを二通り感じた。
何とか救い出してあげたい、母国に返してあげたいという善の気持ち、優しさ。
そして、自分が今後、罪悪感を持って生きることから逃れたい気持ち、よわさ。
そのどちらも間違いではない、人の気持ち。
後者のような脆さ、弱さがあるから肝心なときに人はノーと言えず、ホロコーストを招いてしまった。
間違いではないかと疑問を抱いた人がきっといたのに、誰も声を上げず従い、無感情にあんな歴史を作ってしまったのです。
そんな弱さをどこかに訴える意味も込めてラストシーンはあると、私は感じました。
美しい景色と、少年達の絶望が、残酷なほど見事なコントラストを生み出し、メッセージ以外にも、映像としてもとても素晴らしい作品です。
最後にどうでも良いことですが、ラスムスン軍曹とセバスチャン、イケメンだった…
強い反戦映画
原題:「UNDER SANDET」(砂浜の下)(UNDER THE SAND)
英題:「LAND OF MINE」(地雷の土地)
邦題:「ヒットラーの忘れ物」
デンマーク、ドイツ合作映画
背景
デンマークは現在でもマルグレーデ2世女王が国家元首の立憲君主国家だが、彼女の祖父クリスチャン10世国王の頃、第2次世界大戦では隣国、ナチスドイツに突然先制布告され、戦わずして降伏し、ドイツ軍に侵略された。デンマーク人の中には、志願してドイツ軍に加わる人もいたが、反ナチ活動家となって、レジスタンスの場を提供する者も多かった。駐米大使ヘンリス カウフマンの働きで連合国に接近し、土地をドイツに侵略されながらも連合国扱いされた。
戦争末期、ヨーロッパ戦線の連合軍はフランス、ノルマンデイー上陸を果たし、ドイツ軍を敗退させる。ドイツ軍はノルマンデイーではなく、輸送路が一番短いフランスのカレから、連合軍が侵攻すると考えていた。また同時に、デンマークの西北部の海岸から連合軍が侵攻することも考えていて、阻止するために大量の地雷で、西海岸埋めつくした。
1945年5月、終戦とともにデンマークに進駐していたドイツ軍兵士は捕虜となる。対戦国どうしの捕虜の扱いについては、国際条約ハーグ陸戦条約の規定があるが、ドイツ、デンマーク間は、交戦国ではないため、捕虜虐待禁止や、捕虜の強制労働禁止などの捕虜の扱いに特定の取り決めはなかった。ドイツ軍捕虜たちはデンマーク軍に引き渡され、200万個のドイツ軍が埋めた西海岸の地雷を除去する作業を強制された。従事した捕虜の多くは、戦争末期に非常徴集させられた兵役年齢に達していないテイーンエイジャーだった。
デンマーク人映画監督のマーチン サンドフリットは、地雷撤去に関心があって調べている内に、西海岸に大量のドイツ軍兵士の墓を見つける。どうしてデンマークの海岸沿いで終戦後なのに沢山のドイツ兵が死亡しているのか。調査の結果彼はドイツ軍が埋めた地雷を撤去するためにドイツ軍捕虜が使われた事実を知って、今まで語られることのなかった隠れた歴史を映画にしようと思い至ったという。
映画は、捕虜となったドイツ兵たちが行進してくる。その姿を見て怒りで鼻息荒くなった、ラスムサン軍曹の荒い呼吸音から始まる。
ストーリーは
ラスムサン軍曹は自分の国を侵略していたドイツ軍への怒りを抑えることができない。行進してくる捕虜の中にドイツ国旗を持っている兵を見つけると、飛んでいってぶちのめす。捕虜虐待とか、捕虜の人権とか言ってる場合じゃない。憎きドイツ兵をみて怒り心頭、絶対許せない。彼は12人の捕虜を任された。捕虜たちは、地雷を撤去する作業について訓練を受けた。この12人を生かそうが、殺そうがラスムッセン軍曹次第。3か月で砂浜に埋まった45000個の地雷を撤去してもらおうじゃないか。もともとドイツ兵が埋めた地雷、素手で掘り返して自分の国に持って帰ってくれ。
12人の少年たちは、列を作って砂浜で腹這いになって、棒で砂をつつく。棒に何か当たれば掘り返し、地雷を砂からかき出して信管を抜く。彼らは砂浜での作業以外は、鍵つきの小屋に閉じ込められて、食糧を与えられていない。たまりかねて捕虜の中でリーダー格のセバスチャンが、ラスムサン軍曹に食糧の配給を懇願する。砂浜は、僕たち餓死者で埋まってしまうだろう と。地雷が爆発して、一人の少年の両腕が飛んだ末、死亡した。
軍曹は、少年たちに食糧を配給する。それを見て、エベ大尉は批判的だ。どうして敵に少ない食料を分けなければならないのか。
二人目の被害者が爆破して死んだ。少年たちは空腹に耐えかねて、小屋を抜け出して農家から盗み出したネズミ捕りを知らずに食べ物と思って食べた。軍曹は食べた少年たちに海水を飲ませ、吐しゃさせて救命する。
3人目の被害者は双子の兄だった。弟は錯乱状態になって兄を探そうとする。軍曹は彼にモルヒネを打って鎮まらせ、眠るまで一緒についていてやる。鬼軍曹にも、徐々に少年たちへの優しい感情が芽生えてきている。
基地に出向いたときに、他の隊員達がドイツ兵捕虜に暴力をふるい土下座させたうえ放尿して面白がっている姿をみて、軍曹は虐められている二人の少年を貰い受けてくる。そして今の仕事が終われば国に帰れると、少年たちに約束する。
しかしラスマセン軍曹の大切にしていた唯一の友だった犬が、地雷撤去したはずの浜辺で、地雷を踏んで死んだ。一度は少年たちの父親の様に接し始めていた鬼軍曹は再び態度を硬化する。
そんな矢先、ジープの荷台に集めた数百の地雷を積み込んでいる最中、地雷が大爆発を起こして砂浜にいた4人を除いて全員が死亡する。爆発は強力で、車の残骸さえ残らなかった。残った4人は任務を完了する。終了後は放免されることを約束されていた捕虜たちだったが、地雷除去の熟練者を、軍は放免しない。ラスマセン軍曹の居ないうちに、エベ大尉らは4人の少年を別の地雷撤去の現場に連れ去ってしまう。セバスチャンら4人の捕虜たちは、約束された放免の日のために希望をつないで生きてきたが、ラスマセン軍曹に裏切られたと思い絶望する。
4人は作業の途中で呼ばれて、フードのかかったトラックに乗せられる。どこに行くのか、長いドライブのあとで外に出るように命令された少年たちは、希望を失い仮面のようになった顔で外に出ると、そこに立っていたのはラスマセン軍曹だった。500メートル先はドイツ領だ。走れ、立ち去れ。さっさと帰れ、、、。半信半疑の4人の少年たちは、軍曹の姿を振り返り、振り返りしながら走り去った。
というお話。
鼻息荒く怒っているラスマセン軍曹の顔で始まり、彼の満身の笑顔で映画が終わる。
国境にはデンマーク軍が居るだろう。4人の少年たちが無事に故国に帰れるかどうか疑わしい。軍規に逆らったラスマセン軍曹に待っているのは軍法会議か、厳しい罰則か、全くわからない。映画を観ているものとしては、すべて戦争直後のどさくさの紛れて、なんとかみんな生き延びて欲しいと、切ない希望を託すことができるだけだ。
強力な反戦映画。
砂浜が美しい。地雷撤去したあとの砂浜をはしゃいで走り回る少年たちの姿が、空を舞う天使たちのように美しい。
200万個の地雷。それを撤去するために従事させられた2000人の捕虜たちの映画。まだ兵役年齢に達していない戦争末期に徴発された、貧弱な体をもって腹をすかせた少年たちの姿が哀しい。
ラスマサン軍曹の犬がすごく良い。賢いボーダーコリー。ジープに乗る時も、歩くときもこの犬はいつも軍曹と一緒だ。軍曹が休んでいるとき、犬は幸せそうに全身の重さを軍曹にもたせかけている。演技とは思えない。
ラスマセン軍曹の表情の変化が甚だしい。怒りをたぎらせる鬼軍曹が、少年たちの仲間をかばい合う姿や、いつか家に帰れるという希望を失わず与えられた仕事に励む姿をみて、徐々に硬い表情が緩んでいく。彼とセバスチャンとの会話シーンなど、本当の父と息子のような空気が醸し出されていて、胸を打つ。双子の兄を失った後のエミールが哀しい。兄のオスカーは爆発で肉片さえも吹き飛ばされて何も残らなかった。兄を探して早く見つけ出して家に帰り、父親を助けてレンガを積む仕事をするんだ、と話すのを聞いてエミールが寝付くまで横について居る軍曹の限りなく優しい目。
人間はどんなに憎しみを持っていても、いつまでも鬼ではいられない。ともに飯を食い、同じ空気を呼吸し、同じ光景を見ていれば、人は人を赦すことができる。人は赦す心なしに生きることはできない。
しかし、兵器産業は武器を作り続ける。武器を売るために戦争を作り出している。
地雷ひとつ作るための経費:3ドル
地雷一つ撤去するために必要な経費:200-1000ドル
それでも毎日毎日地雷を作り続ける兵器産業。
米国、ロシア、中国は対人地雷全面禁止条約に署名しようとしない。
カンボジアには米軍が落した600万個の地雷がある。ラオスには、ホーチミンルート補給線をつぶすために米軍が200万トン、8000万発の爆弾を投下し、その30%が不発弾だったため、沢山の地雷撤去ボランテイア組織の活躍にもかかわらず、いまも人々が死んでいる。べtナム戦争は1975年に終了などしていないのだ。
どんな戦争もあってはならないし、起こってはならない。
良い反戦映画は、いつも私達に、自分はどう生きるのかを問いかけてくれる。
最後に「ヒットラーの忘れ物」というタイトルは変。原題はデンマーク語だが、直訳すると「砂の下」、英語の題名は「LAND OF MINE」で「地雷の土地」。どうしてこのまま直訳をタイトルにしなかったのか。忘れ物という言葉は、なにか、間の抜けた「母さん、忘れものだよー。」とか、母親が子供に「忘れ物ない?」と登校前の子に怖い顔で問い質すときなどに常用される言葉で、すぐれた映画のタイトルに合わない。
これまでにも、珍妙なタイトルが多くて、それごとにしつこく文句を言ってきたが、ブログに映画評を書いたので、思い出すだけでもいくつもの映画の例がある。
1)「優しい本泥棒」:「BOOK THIEF」という映画なので、本泥棒で良い。優しい がついて、やさしくて容易いのは泥棒だと言っているのか、泥棒が本だけ持って行ったから優しいのか、本泥棒はみんな優しい人なのか、、、理解不能。ナチによる出版弾圧、思想弾圧、梵書を描いたすぐれた反戦映画なので変なタイトルをつけないで下さい。
2)「ミケランジェロプロジェクト」:「MONUMENT MEN」モニュメント マンと呼ばれた人々が欧米では良く知られていて、ナチが奪った芸術品を取り戻した話なので、そのままのタイトルで良い。ミケランジェロプロジェクトという新語はないし、通じない。
3)「それでも夜が明ける」:「12YEARS SLAVE」苦しくても、夜が明けてハッピーエンドになると、初めからわかっている映画など人は見たくない。12年間奴隷にされた理不尽な人の、本当の話なので、はじめから結果がわかるようなタイトルはつけないで欲しい。
4)「戦禍に光を求めて」:「WATER DIVINER」ウォーターデヴァイナーという水脈を探し出す人で、この言葉は砂漠や荒れ地に住む人しか知らないかもしれないけど、激戦地トルコのガリポリを題材にした反戦映画。大好きな映画なので、奇妙な題をつけられて悲しい。戦禍に光なんかない。
映画の翻訳者には、どんな権限があるのだろう。映画の内容に合わない奇妙な邦題をつけるのは、止めて欲しい。映画監督に失礼ではないか。タイトルまで含めて監督は映画を作る。勝手に翻訳者のセンスでタイトルを「翻訳」してしまって良いのだろうか。これって芸術破壊ではないか。
「ヒットラーの忘れもの」タイトルは悪いが、映画は素晴らしい。見る価値がある。
どう捉えれば良いの?
この映画吹替えで見ました。最初の方はハラハラドキドキで見ていましたがラストは?って感じでした、これはハッピーエンドととらえて良いのかわかりませんでした。最後の軍曹の行為は完全に命令に背いているけどなんであれが出来たのかわからない。それなら少年兵は全員助からなかったってした方が残酷さが出るのではないでしょか?あと登場人物をもう少し丁寧に描いてほしかったです。
心臓を殴られるような思いだった。
心臓を殴られるような思いがした。戦時中、ドイツ軍がデンマークの海岸に残した地雷を、回収する為に招集されたのはドイツの少年兵だった。戦争の爪痕を、まだ幼い少年たちが命を懸けて(そして実際に失われていく命も少なくない)償っていく作業。戦争というものの不毛さを、ありありと見せつける映画で、「胸が締め付けられる」なんて言葉では足りないほど。心臓を殴られるような思いだった。
映画は特別な物語性を付加することなく、実際の少年兵たちの様子を再現するかのように写実的にその様を映し出していく。「軍隊」やら「兵士」たちの、浅ましいまでの従順さや愚かしい程の服従を見せつけながらも、その奥にある少年たちの無邪気さ、軍曹の人間味が顔を出し、しかし戦争の凶器と狂気は、人間がふと息をついた瞬間に、暴音を立ててその衝撃と残酷さを示す。この映画でも、地雷が爆音を立てるのは人間(及び観客含め)がふと気を緩めた瞬間だ。そしてその都度、戦争の恐ろしさ、現実の惨さ、そして戦争にまつわるすべてに対しての愚かしさを感じずにいられなかった。
本当に、この映画を観ていると、戦争がいかに不毛で、徒爾なだけならまだしも、その残骸があまりにも惨たらしいものだということを苦しい程に感じる。この映画には、意図して殺し合う人は出てこない。ましてやまだ幼い少年たち。彼らが、戦争の残り香を嗅いでは次々に死んで逝く姿に、それでも戦争を止めない理由が理解できないと改めて思った。
この映画が描くのは、終戦後の物語だ。でも戦争が終わった後も、まだ戦争は続いている。日本だって、70年前に終戦したけれども、今なお、戦争の残骸は残っている。終戦した後で、いつになったら本当の意味で戦争は終わるのだろう?とこの映画を観ながら思ったし、もし再び戦争を起こしてしまったら、その戦争が(終戦という意味だけでなく本当の意味で)終わるのは何百年後になるんだろう?と思うと、やっぱり戦争なんてするべきではないと、強く思った。
反戦映画ではあるけれどただ反戦を唱えるというよりは、ドイツとデンマークが手を組んで、世界に向けて歴史に向き合った真摯な戦争映画という気がして、そこには「もう二度と同じ歴史を繰り返さないぞ」という両国の強い意志のようなものを感じた。
わかり易く、誰にでも勧められる戦争映画。
軍曹の登場シーンで、恐らく帰還のため行進しているドイツ兵を、怒りに任せて暴行するシーンがあります。
それでまず軍曹がだいっ嫌いになりました。
が、その軍曹が地雷除去のため連れてこられたドイツの少年兵と、ちょっとだけ心を通わせてしまうという話なんです。
あ、デンマークのお話です。デンマークをナチスドイツが占領していたんですね、永い間。
で、ついにナチスが敗れたので、デンマーク開放!去れドイツ!という時点からのお話です。
少年兵が除去させられる地雷は、ドイツ軍が埋めたもの。
それをドイツ兵に除去させるというのは、ある意味当然かもしれません。
ただし、大人でも容易でないその任務を、あどけない子供たちにさせることに、軍曹も観客も悩みます。
また、映画の中では触れられていませんが、捕虜の強制労働はジュネーブ条約違反なんだけど、デンマークとドイツは交戦状態ではなかったから、その隙間で強制労働をさせたということらしいです。HPに載ってました。なので、ほんとは国際的にも道義的にもちょっとしたズルをして、少年兵に危険なことをさせたということなんです。
最終的に、数名(5人かそこら)が、生き残り(みんな死んじゃうんですよ)、
やっとドイツに送り返せると思った矢先、「あいつらは地雷の扱いに長けているから、他の地域で地雷除去を続けさせる」との
軍の意向で、新たな任務地へ連れて行かれてしまいます。
軍曹は、軍にそむいて新たな任務地から少年兵を奪い、ドイツとの国境近くで開放してラストという事になります。
ほんの少しだけこの結末は、見ている観客を救うでしょう。
でも、実際はこうではなかっただろうと思います。
勝っても負けても自分も相手もズタズタに傷つけるんですね。
難しくはありません。
わかりやすいストーリーなので、あまりいろんな映画を見たことがない人にも伝わると思います。
なので、世界の苦しみ・矛盾を学びたいとするならば、いい教材だと思います。
まあ、泣いて終わりの映画になってしまう可能性はありますが。
この映画に関係のないことも色々思いました。
日本だとこういう視点の映画、ないよね、なんでかしらと。
だいたいが、いかに戦渦で市民が虐げられたか、
過酷な環境で兵士は戦ったか(そしてそれは尊い)という視点なので、
日本の戦争映画は正直苦手です。
確かに、戦渦に市民は虐げられたし、兵士も苦しんだでしょうが、
それらと同じ分量で、加害者としての反省をしなきゃならないのではと思います。
でもそういった反省が感じられる映画・物語はあんまり思い出せないですが、何かあるんでしょうかね。
戦メリはそうだったかも・・・
全26件中、1~20件目を表示