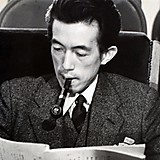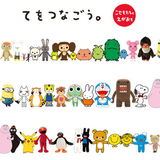この世界の片隅にのレビュー・感想・評価
全158件中、41~60件目を表示
淡々の日常が突如と…
淡々と過ぎる一般的日常が戦争の影響が、ひたひたと押し寄せ、呉の町が戦火に落ち、そして……。
やりきれない変わり果てた日常。
平和教育するよりも、子どもや小学生からみせてあげたい。
今日も明日も
生きていかないけんのですけ。
すべてはこの言葉に集約されてるように思いました。
元々、こうのさんのお話が大好きで、この作品も読んでいました。戦争映画というカテゴリーでありながら、日々を懸命に生きていくすずさんの姿は現代の私たちにも通じるものがあると思います。
存命の祖母が戦中は某軍港に住んでいて、B29が焼夷弾を落としにきた話や防空壕に逃げそびれて側溝で耳を塞いでやり過ごした話など聞いていました。でも、それより驚いたのは空襲の後に普通にヨモギとか食べられる草なんかを採って帰っていたということです。
祖母が、食べていかないけんけねぇ、と言っていたことが思い出されました。
戦争はもちろん悲惨で、二度とあってはならないことですが、そんな中でも懸命に生きていこうした人たちがいて、今の自分があるのだということに改めて気付かされました。
りんさんと周作さんのお話は完全版(長尺版)で描かれるそうなので周作のノートの話や二河公園の花見のシーンなど今から楽しみです。
能年玲奈さんの演技はとても良かったです。
『ほいで、ここはどこねーーー!?』と叫ぶシーンは私的必見シーンです(笑)
戦争の皮を被った青春譚
この作品は「戦争」に本質がある訳ではないらしい。
実はたんなる一田舎娘の青春譚なのでせう。
仮に戦争要素がごっそり抜けていても、普通に物語として成立していたやうに思われる。
この作品には戦争映画特有の切実さがない。
『野火』『永遠の0』『火垂るの墓』『はだしのゲン』などを見て感ずるあの呼吸器が締め付けられる切実感がない。それはやはり距離感の問題であらう。
『この世界の片隅に』はまさに戦争の片隅に位置する人々の話で、戦争映画によく漂う腐臭と吐き気、醜悪さ、絶望、目を背けたくなる感がまるでない。始終、流れるやうな綺麗な筋書きである。だがそれでよい。おかげで何度も観れる。
舞台は第二次世界大戦中の広島。
いかにも虐げられし人々の描写がなされそうだと予感せられる。が、蓋を開けてみるとそんな事は殆どない。普通(とはいかないまでも、それなり)に暮らしは成り立っているやうだった。
その上で勝手な縁談、若い男女が抱く感情、周囲との人間関係、葛藤、ウーマンリヴ精神これだけ素材が揃っていれば別に戦争映画でなくてもよい気がする。だが、ここに戦争といふスパイスが加わることによって我々はある種の感動パターンに嵌められて涙してしまうでせう。
戦争はあくまで付加価値なのかもしらん。
「従来の戦争映画とは違う」というより、「従来の青春譚に戦争要素を染み込ませただけの映画」であらう。
大好きです。
〝感動する〟〝泣ける〟そんな言葉だけで語れる映画ではないと思います。
戦時に生きる人々の日常を淡々と描き、その裏で刻々と悪化する戦況をちらつかせ、観ている観客にはもう嫌でも分かっている、避けられない結末へとカウントダウンしていく残酷さ。ありふれた日常の愛おしさと戦争という非日常の対比。
徐々に困難になってくる日常生活や、繰り返される戦火という理不尽な暴力の中に身を置くと、それに対する疑問や怒りまでも麻痺して戦争というものすら日常になってしまう。生きていくための日々の営みは変わらなくとも、物事の価値観や優先順位は知らないうちに別のものにすり替わっていく。
愛らしい絵でほのぼのと描かれる日常は「戦時中でも小さな幸せを大切にし、笑顔を絶やさず前向きに生活している人達」というよりは、辛い現実の中で「せめて笑おうとしていた」人達の生活だと思う。糸が切れたように突然泣き崩れる登場人物達がそれを物語っているように感じた。
露骨に悲劇的な描写は少ないが、細やかな日常の中にしっかりと悲劇は潜んでいる。
原作を読んだり太平洋戦争史を予習してから観れば劇中に刻まれる日付の意味も深まると思うし、この映画を海外で上映した時の反応も気になる。
個人的にはジブリ作品なんかよりもずっと、後世に遺すべき傑作だと思います。
四コママンガのようだった
観ていて、展開が「四コママンガのようだなあ」と思った。いくつもの話を一つの作品にしたような感じで、構成は「ホーホケキョとなりの山田くん」を思い出しながら観ていた。
しかし、「ホーホケキョとなりの山田くん」には「適当」というテーマがあったのだが、この映画のテーマが何であったのか、それが訴えて来るものが今ひとつ見えてこなかった。それは自分の歴史認識の甘さだったり、考え方の浅さだったりするのかもしれない。
街並みだったり、人物だったり、描きこみの深さはあったと思う。
そして声も良かった。
ラストの展開、束ね方というのも夢うつつのようで、ファンタジーのようなところもあったように感じる。
しかし自分は、戦争はファンタジーでは無いと思っている。
謎めいた作品だったという印象が深い。
子供に見せたい
大好きな絵を描く事も出来ない戦争時代。
生きててよかった。という意味で伝えた ヨカッたという言葉が主人公にはなにがヨカッたのか、、分からないという悲しさ。
何年何月何日、、、と遡る時の映像、印象深い。
知らなかった戦争のことがたくさん知れた映画でした。
これはとてもリアルなのかな?生きていたら、祖父母に聞いて見たかったです。
戦争が奪ったもの
広島で育った少女が呉に嫁ぎ、空爆で色んなものを失っていく。
戦争がなければ、好きな絵をもっと描けただろうか。好きなことだけでなく、小さな命までも奪っていく…。
失った腕が色んなことを伝える気がします。
評判ほどではない。
戦前、戦中、戦後の暮らしが良く描かれていて、映画の画面の中に引き込まれた。この点は高く評価したい。
しかし、戦中での暮らしの中で、主人公が、戦争や、人の死に向き合う姿勢が「平和ボケ主義」的で、違和感を感じた。日本でしか通用しないと思った。この映画は、海外では閑古鳥だろう。
人の死のシーンがあるが、張り詰めた様な緊張感がない事が気になった。私が若い頃、目の前で友人が高所から滑落し、大けがをし、人里離れていたために、救助が間に合わず、目の前で死んで行くのを見た。20年以上過ぎた今でも、鮮明に覚えていて、忘れる事ができない。深い慟哭と、何もできなかった自分への怒り、、様々な感情は、今も忘れる事はできない。
時代は違うが、戦争中、人が死ぬ度に、同様の事があったはずだ。
この映画の中の戦争は、人が命を掛けているのに、緊張感が希薄で戦中暮らしごっこのファンタジーにしか見えなかった。
映画の中で、主人公が手を引いていた子供が死に、自分も右手を失うシーンがある。人の命が掛かった出来事なのに、どこか軽すぎる気がした。悲しみに、現実感がなく、全く涙も出なかった。
子供が爆死するシーンがあるが、その部分は全く描かれず、スリガラスの向こうを見ているように思えた。戦前、戦中、戦後の暮らしを現実的に描くなら、街の爆撃での人の死の具体的描写を加えて欲しかった。但し、街の人の死のシーンを、リアルに入れたら、この映画は作品として成立しないのかもしれない。。
後半の一部のシーンは、作画やストーリー展開の粗雑さを感じた。もし可能なら、予算の制約で取りやめたシーンを加え、監督の思う完成版を見せて欲しいと思った。
また、戦後の暮らしを取り扱った続編が作られれば良いなと思った。
暖かで現実的な戦時の作品
原作のファンで、映画を観に行きました。
時間や予算の関係で、いくつかのシーン(お寺のお悩み相談のところが好きでした)が無い形になっていますが、原作の雰囲気、色彩とアニメーションの動き、声優さん達の演技、どれをとても大変な作品になっています。
漫画の映像化として、一本の映画としてとっても素晴らしいです。
一ファンとして、見に行って心から満足しました。
このお話は、かいつまんだ粗筋だけを辿ると非常に深刻で何とも言えないほどです。
姪を失い、大好きな絵を描く右手を失い、実家とその両親を失い、そして仲の良い妹も恐らくは失われようとしていく。
生まれた街、育った国、嫁いだ先の環境と人々、色々な周囲が絶え間なく変容し、それでも先へと生活は続いていかざるを得ない。
しかし、主人公を始めとするキャラクターと多くの日常表現、人の心の奥で抱えた感情描写が、いわゆる戦争映画に描かれがちであった悲惨さとは明らかに違った雰囲気をこの作品にかもし出しています。
これだけ残酷な話の流れをそこまでと感じさせない作品の力というのは、凄いものだと思います。
勿論、それによってテーマやメッセージが伝わらないのかと言えばそうでなく、むしろありありと伝わってきました。
心があたたまる
すずちゃん可愛い。
キュンとするし、チクチク胸が痛いし、張り裂けそうなほど苦しい と、色んな感情が溢れる映画でした。
はじめは人物の話し方や方言、イントネーションで聞き取りづらく慣れるまで少しだけ時間がかかったけど、逆にそこが集中できる要素にもなった。
のん の声優もとても良かった。
私が知るアニメ映画と違って有名だからという理由での起用ではない気がしました。
しっくりくる配役。
夫婦のあの雰囲気。とても素敵だったし、心温まった。
義理のお姉さんが意地悪なんだけど、可愛いやつでね。
そしてすずのドジでおっとりして可愛い所には何回も笑わされた。
船を絵に描いていて怒られたシーンで、最後に家族で大笑いしていた所は、私がみた映画館の中でも半分の人がつられて笑ってた^_^
空襲の場面ではやっぱり怖くなって泣いてしまった。想像すらつかないあの世界。
見たくないと思いつつもやはり知っていなきゃいけない歴史。
本当に色んな事を感じた映画でした。
君の○はより、断然私は好き!!!!!
またちゃんと見たいな
かなりいいです。
実在した世界だし、リアリティがあった。私の祖母くらいの世代の主人公が、まるで平成の世の女の子のような雰囲気をまといつつ、しっかりあの昭和の時代に生きている。
戦争が進むにつれて、出征があり、食べるものがなくなりといった展開がわずか数分のうちに起こる。
すずは、その設定上、多くのものは望まない。そして、同級生、家族、身体の一部、唯一の趣味、そして故郷を喪う。アニメでありながらこれだけ喪失する物語は珍しいのではないか。いや、最近のはなんでもあるのだろうか。それでも描写は丁寧かつ上品で、新しいジャンルの誕生を感じさせる。
「君の名は」が到達した表現力、エンターテイメント性には及ばないものの、製作者のある想いを丁寧に丁寧に伝えてゆく作りは好感が持てる。
このスタッフの作品をもっと見てみたいという思いでいっぱいになります。この監督のこだわりをもっとたくさん見ていたい。
戦後72年のいまでありながら、当時生きた人々の思いが蘇る。
原爆のシーンには、時が止まった気がした。
戦時とはいうものの、ああいう日常の一瞬に大量の人々の命を一瞬で奪い、または長く苦しめることになる兵器が使われたのだという説得力があった。
能年玲奈だからこそだせるすずのキャラクターにこの作品の成功を感じた。
リアル
戦争を体験してないけど、これが戦争なんだって思えた。
終戦時、すずが「ここにおなごが五人いるけえ!まだ戦えるじゃろ」と発した言葉がこう考えるのだと思った
薄っぺらい言葉だが、戦争時に生きる女性ほどたくましいものはないと考えた。
戦災ではなく人災による悲劇
戦時下の中、日本人がどのように生きていたか、空襲の恐ろしさがどのようなものか、よくわかりました。
全体的にも間延びすることなく、よくまとまっていたと思います。
ただ、とても大人と思えない、障害と思われるほどの主人公の鈍さに、イライラする点が多々ありました。主人公の行動により、事故に巻き込まれた人も多数。
戦災ではなく人災による悲劇には共感できませんでした。
すずちゃん
感動が全く押し付けがましくない。
すずちゃんを巡る様々な、本当に様々なドラマ。
防空壕の場面、怖くて震えました。
「ボーッとしたうちのまま死にたかったなぁ」というすずちゃんの言葉の重み。
言葉にするのが難しいのですが、すずちゃん達には幸せになって欲しいなあ…という気持ち。2時間超と長い作品ですが、それ以上の価値のある映画だと思いました。
うーむ…
別に書かなきゃならない義務もないし、しかしながらせっかく観に行ったんだしパンフまで買ってしまいましたので
パンフ買ったのなんて高校生の時以来じゃないかなあ。
観に行って数日たつけど、どう言ったらいいのかわからない、なんと言っても伝わらない気がするんだけどずっとこの映画のことを考えるし、他のアニメがなんだか軽く思えてしまうくらいの吸引力はあると思う。
うーん、しかしどう判断したらいいのかわからん。少なくとも自分は反戦みたいなメッセージは感じなかったし、これって戦争映画なんかな?と疑問に思う。
当日ちょっと睡眠不足でつまらなかったら寝てしまえ、と思ってたけど
寝るどころか、初盤から引き込まれて最後まで飽きなかった。
二時間以上あってこれはすごい。
では面白かった?と聞かれてもなんともいいがたい。感動できるか?とか泣けるかと言われてもうーん…
すごく異質ななんだか今までにないものをみた気もする。
ただ、はっきりしてるのはすずちゃんが可愛いすぎる。のんさんの声がこれまたいい。これだけで中盤まで引っ張られた気がする。
さらにすずちゃんのめぐる二人の男、旦那と幼なじみ担当声優さんは二人とも大人気の人たちだが、おさえた演技でこれもよかった。
でも、歌はちょっと
好みの問題だけど、私はこういう歌い方するボーカルがあまり好きじゃない。
あと、最大の問題点?
なんかすずちゃんの旦那が浮気してるとか聞いたけどそんな場面ないじゃん?と思ってたら原作にあるらしい。
あのすずちゃんが道に迷った時に道を教えてくれた「こんなとこ来ない方がいい」と言ったおねーさん
らしいけど。えーそこバッサリ切っちゃったのどうなの?さらに言えばこのおねーさん、遊廓で働く女郎らしいがそれもパンフレットに書いてあったからわかった感じ
見落としたかな
※作品の内容および結末、物語の核心に触れる記述が含まれています。未鑑賞の方はご注意ください。
「むかし知っとった人にいま会うたら、夢から覚めるとでも思うんじゃろか、うちは。」
1945年(昭和20年)8月6日午前8時15分、広島市に原子爆弾リトルボーイが投下された。
それは、第33代アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンの7月25日付け大統領令「広島・小倉・長崎のいずれかの都市に8月3日以降の目視爆撃可能な天候の日に特殊爆弾を投下するべし」を受けたB-29(エノラ・ゲイ)によって行われた。
広島市内の中央に位置するT字形の「相生橋」が目標点とされ、投下された原爆は上空600メートルで炸裂。
爆発に伴って熱線と放射線、周囲の大気が瞬間的に膨張して強烈な爆風と衝撃波を巻き起こし、その爆風の風速は音速を超えた。
爆心地付近は鉄やガラスも蒸発するほどの高熱に晒され、強烈な熱線により屋外にいた人は全身の皮膚が炭化し、高熱で内臓組織に至るまで水分が蒸発、水気の無い黒焦げの遺骸が道路などに大量に残され、3.5km離れた場所でも素肌に直接熱線を浴びた人は火傷を負うほどであった。
爆風と衝撃波による被害も甚大で、爆心地から2kmの範囲で木造家屋を含む建物のほとんど全てが吹き飛んだ。
爆発による直接的な放射線被曝の他にも、広島市の北西部に降った「黒い雨」などの放射性降下物(フォールアウト)による被曝被害も発生し、救援や捜索活動のために市内に入った人にも急性障害が多発した。
当時の広島市の人口は約34万人で、爆心地から1.2kmの範囲では当日中に50%の人が死亡し、同年12月末までに更に14万人が死亡したと推定されている。
その後も火傷の後遺症による障害、胎内被曝した出生児の死亡率の上昇、白血病や甲状腺癌の増加なども見られた。
爆発の光線と衝撃波から広島などでは原子爆弾のことを「ピカドン」と呼ぶようになる。
「大事じゃ思うとったあの頃は・・・大事じゃと思えた頃が懐かしいわ。」
本作は戦争映画ではなく、第二次世界大戦中の普通の人たちの普通の日常の物語で、その穏やかな暮らしの背景に、たまたま戦争がある。
ささやかで幸せな生活がずっと続いてほしいという願いは、現代も戦時中も全く同じで、みな日々の生活に追われながらも小さな幸福を見つけ、前向きに生きている。
日々の献立を考えたり、少ない材料の中で調理法を工夫して少しでも美味しくしたり、高台からの眺めに「美しい」と感じたり、それを絵に描いたり、妄想したり、慣れない土地で人間関係に苦労したり、買い物の帰り道で迷ったり、儚い恋をしたり・・・。
現代の日本と違うのは、その小さな幸せがいつ奪われてもおかしくない状況にあり、悲劇がある日簡単に訪れてしまうこと。
やり場のない怒りや悲しみに、誰もが突然に放り込まれる。
生まれてきた時代が数十年違うだけで、平和に暮らしている人々がこんなにも悲劇の連鎖に巻き込まれてしまう。
反戦を訴える手段や言葉は数多くあるが、本作のメッセージは口調が穏やかである分、より心に突き刺さる。
「お前だけは、最後までこの世界で普通でまともでおってくれ・・・。」
徹底したリサーチと時代考証で構築された、アニメーションならではの色彩の世界は、本作の主人公があらゆる情景を美しい絵画で表現した事と同じく、カラフルな絵の具で包まれた夢の様な雰囲気で、だからこそ残酷な現実がより浮き彫りになる。
ナチスドイツ軍によりビスカヤ県のゲルニカが受けた都市無差別爆撃(ゲルニカ爆撃)を主題とした20世紀を象徴する絵画「ゲルニカ」(ピカソ作)と同様、本作は鋭い反戦メッセージが込められた「芸術作品」なのだ。
それは、悲惨な戦場をありのまま切り取った報道写真と、それらをモチーフに描いた絵画の「伝え方の違い」を連想させる。
言葉や文章や映画や絵画など、戦争の恐ろしさや悲惨さを「人に伝える」ための方法は古くからあらゆる手段で行われてきたが「まだこんな方法があったのか」という衝撃を受ける。
悲しみと幸せと希望が入り混じった色々な感情が渦巻き、エンドロールで描かれるエピローグも含めて、鑑賞後は心が震えて立ち上がれなくなる。
「そんなん覚悟の上じゃないんかね。最後のひとりまで戦うんじゃなかったんかね。」
本作は、こうの史代による日本の漫画作品を、宮崎駿の『魔女の宅急便(演出補)』、大友克洋の『MEMORIES/「大砲の街」(演出・技術設計)』、そして『マイマイ新子と千年の魔法』で監督・脚本を手掛けた片渕須直がアニメーション映画化。
インターネットで制作費を募るクラウドファンディングで、国内映画の過去最高額を記録した。
戦争は、人々の幸せな暮らしを一瞬で奪い去る。
楽しい食卓、学校の友達、家族、愛する人、そして多くの人々の「未来」を、突然に奪う。
戦時下の昭和19年に、広島市江波から呉に18歳で嫁いだ主人公すずの日常が幼少の頃から順を追って描かれる中で、細かく年日時が表示される。
我々観客は、昭和20年8月6日に広島で何が起きたのかを知っているので、そこに至るまでの「日付」は悲劇へのカウントダウンにもなっていて、サスペンス的な側面もあり一瞬も気が抜けない。
「海の向こうから来たお米。大豆。そんなもんで出来とるんじゃなぁ、うちは。じゃけえ、暴力にも屈せんとならんのかね。何も考えん、ボーっとしたうちのまま死にたかったなぁ。」
監督の片渕は2010年5月から何度も深夜バスで広島に通い、後知恵を徹底的に排除した上で、多くの写真を集めたり、70年前の毎日の天気から、店の品ぞろえの変化、呉空襲での警報の発令時刻に至るまで、すべて調べ上げて時代考証を重ね、原作の世界にさらなるリアリティを加え本作を完成させた。
例えば、主人公が高台の段々畑から戦艦大和の呉入港を見る場面は、現存する戦艦大和の航行記録で「大和がいつどこで何をしていたか」を全て調べ、昭和19年4月は17日だけ呉に入港していた事が判り、その日付から天気と気温を調べ、実際と全く同じ「昭和19年4月17日の呉」の景色を再現している。
「理念で戦争を描くのではなく実感できる映像にしたかった」と徹底的にディテールにこだわり、劇中で登場する建造物や商店の並び、登場人物たちが歩く道、その周辺の人々、上空を飛ぶ飛行機の種類や正確な時刻、焼夷弾が落とされる場所や日時、そして戦艦大和の艦上での手旗信号の内容までもが解読できるくらいに、限りなく「現実」だけを描いている。
だから、あの時代に、あの日に、この世界の片隅に、今の我々と変わらぬ「小さな幸せ」だけを願い生きていた人々が、間違いなくたくさん居た事を、心から実感できる。
当たり前の様に戦争中にもたくさんの生活があったという事実を、そして今この瞬間も、世界の多くの場所で内戦やテロや飢餓に苦しみながら必死に生きてる人達が大勢いることを、改めて深く考えさせられる。
今までどれほど大きな戦争や事件や災害が起きても、人々は何度も立ち上がってきた。
ささやかで幸せな生活がずっと続いてほしいという願いは、現代も戦時中も全く同じで、みな日々の生活に追われながらも小さな幸福を見つけ、前向きに生きている。
それはこれからも止まる事はなく、我々の生活はこの世界の片隅で脈々と続いていくだろう・・・。
「晴美さんのことは笑って思い出してあげようと思います。この先ずっと、うちは笑顔の器になるんです。」
考えさせられる作品です
前半は戦争の中で生きた昭和の女性ですが、後半からは主人公が腕を失いとても重い暗い戦争の話になってしまい最後まで楽しめる素晴らしい作品だと思います。
作画が細部までこだわっていてアニメを好きな人は絶対見るべきものだと思います。
聲の形に通じるような温かい気持ちになれます。
後からジワジワくる傑作
心の最深部が揺り動かされる作品で、鑑賞中よりも鑑賞後にジワジワと感動の波がやってきました。
この作品は、かけがえのない日常やそれを侵食して破壊していく戦争の無慈悲さ、傷つきながらも愛すべき人々とともに再び日常に戻っていく人間の持つ根源的な強さが描かれているように感じました。
その描写が優しく淡い絵柄で、これ以上ないほど丁寧になされるため、心が弱火でコトコト煮られるように、物語が深く深く染み込んでくるのです。
強火でサッと炒められるハデなやつもスカッとしますが、このじっくり来る感じは格別です。
テンポ良くも淡々とした作風も誠実。すずさんの情動表現を彼女が得意とした絵を用いて行うなどの演出も素晴らしかったです。
そして、すずさんのキャラが最高に可愛らしい。ボーっとするにもほどがあるだろッッ!と思わず突っ込みたくなる。大人の迷子とか、砂糖のくだりとか。のんの声もハマり役でした。
戦災孤児がすずを母と勘違いし、そのまますずの家で育っていくことを示唆するエンディングは、大きな人間愛を感じました。新しい家族となった孤児と過ごす日常が描かれるエンドロールも秀逸。
評判通りの傑作でした。
文句なしの傑作
前評判から期待値は高まっていましたが、それを更に越える傑作でした。
嫌いなところを見つけるのが難しいくらいに!
終戦時の主人公の叫びには、強く共感しました。
絶対ブルーレイ買います(笑)
全158件中、41~60件目を表示