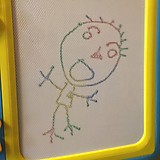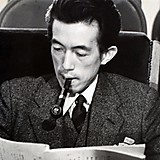この世界の片隅にのレビュー・感想・評価
全1072件中、281~300件目を表示
日常のようで日常ではない
尋常ならざる秀逸さは奇跡
アニメ映画「この世界の片隅に」を観た後のえもいえぬ感動は、過去のすべての映画の概念を覆すものでした。えもいえぬ、つまりコトバで表現することは野暮だと思うほどのものです。私自身還暦となり、これまで観た1000本以上の映画に、この作品に比するものは見当たらない。何故そんな感動が得られるのか、そのコトバを探そうと地元の映画館3館で7度鑑賞しました。一つの作品にそこまで魅せられた事は初めてでした。スクリーンの大きさや音響設備も異なる環境で鑑賞し、その都度発見される小さな事柄にも何故だか凄く喜びを感じ、得した気分を味わい。原作も読み、他のグッズやサウンドトラックもブルーレイも購入し見たり聴いたり、そんな事をしても、私のコトバは陳腐な表現しか思いつきません。この映画は総合芸術の最高位にあると私は感じています。例として挙げるならば長谷川等伯の「松林図屏風」を目の当たりにして、立ち尽くすだけしか出来ないという気分に似ています。これはもはや国宝級だということです。
普遍的価値を持つ芸術作品に理屈はいらないのですね。
海外では「火垂るの墓」と較べられているようですが少なくとも日本人である私にとっては、全く異質な完成度の違いを歴然と感じるのは、この作品の成り立ちを日本人として充分に理解し、その感動を、より多くの人達と末長く共有したいと願うからです。
その為、この映画は毎年一度は大きなスクリーンで鑑賞したいのです。毎年の8月の恒例行事となるよう願ってやみません。
抜けるような青空、コトリンゴさんの歌が流れる。もう涙が出てしまう。この作品に関わった方々に感謝です。ありがとうございます。
淡々の日常が突如と…
淡々と過ぎる一般的日常が戦争の影響が、ひたひたと押し寄せ、呉の町が戦火に落ち、そして……。
やりきれない変わり果てた日常。
平和教育するよりも、子どもや小学生からみせてあげたい。
ちょっとブルーになりました。
今日も明日も
生きていかないけんのですけ。
すべてはこの言葉に集約されてるように思いました。
元々、こうのさんのお話が大好きで、この作品も読んでいました。戦争映画というカテゴリーでありながら、日々を懸命に生きていくすずさんの姿は現代の私たちにも通じるものがあると思います。
存命の祖母が戦中は某軍港に住んでいて、B29が焼夷弾を落としにきた話や防空壕に逃げそびれて側溝で耳を塞いでやり過ごした話など聞いていました。でも、それより驚いたのは空襲の後に普通にヨモギとか食べられる草なんかを採って帰っていたということです。
祖母が、食べていかないけんけねぇ、と言っていたことが思い出されました。
戦争はもちろん悲惨で、二度とあってはならないことですが、そんな中でも懸命に生きていこうした人たちがいて、今の自分があるのだということに改めて気付かされました。
りんさんと周作さんのお話は完全版(長尺版)で描かれるそうなので周作のノートの話や二河公園の花見のシーンなど今から楽しみです。
能年玲奈さんの演技はとても良かったです。
『ほいで、ここはどこねーーー!?』と叫ぶシーンは私的必見シーンです(笑)
等身大の日本人
素敵でした。
新感覚でした。
原爆と言えばマイナスなイメージがあるのに
こんなに明るく(いや決して明るい訳じゃないけど、火垂るの墓などと比べれば)映像化することができるなんて思いませんでした。
たまに挟んでくるリアルな描写に胸がグッときました。
私が見てきた映画の中では回りくどい描写が多いのが普通なのですが、この映画は考察もしやすくわかりやすい映画でした。特に心に残ったのが、「でも全部は食べないようにしよう、また明日も明後日もあるんじゃけぇ」みたいなセリフです。また明日も明後日もある…その言葉に何だか戦争というものに対してイメージが変わりました。
戦争=ダメなもの、としてしまっては、その時代に懸命に生きた人達が何だかなかったことのようになってしまうような気がしました。広島に原爆が落ちても、生き残り、懸命に今日を生きた人がいる…。
最近、北朝鮮がミサイル打ったりして、近々戦争が起こりそうですが、私も1日1日を大切にして生きていこうと思いました。素直に泣きました。
周作とすずの2人が仲良くなっていく過程も素敵だと思いました。すずが「広島に帰る」と言った時に、周作が言った言葉がグッときました。
本当にあっと思わされる映画でした。
優しくて悲しい…
絵柄も話も優しかった
戦争の皮を被った青春譚
この作品は「戦争」に本質がある訳ではないらしい。
実はたんなる一田舎娘の青春譚なのでせう。
仮に戦争要素がごっそり抜けていても、普通に物語として成立していたやうに思われる。
この作品には戦争映画特有の切実さがない。
『野火』『永遠の0』『火垂るの墓』『はだしのゲン』などを見て感ずるあの呼吸器が締め付けられる切実感がない。それはやはり距離感の問題であらう。
『この世界の片隅に』はまさに戦争の片隅に位置する人々の話で、戦争映画によく漂う腐臭と吐き気、醜悪さ、絶望、目を背けたくなる感がまるでない。始終、流れるやうな綺麗な筋書きである。だがそれでよい。おかげで何度も観れる。
舞台は第二次世界大戦中の広島。
いかにも虐げられし人々の描写がなされそうだと予感せられる。が、蓋を開けてみるとそんな事は殆どない。普通(とはいかないまでも、それなり)に暮らしは成り立っているやうだった。
その上で勝手な縁談、若い男女が抱く感情、周囲との人間関係、葛藤、ウーマンリヴ精神これだけ素材が揃っていれば別に戦争映画でなくてもよい気がする。だが、ここに戦争といふスパイスが加わることによって我々はある種の感動パターンに嵌められて涙してしまうでせう。
戦争はあくまで付加価値なのかもしらん。
「従来の戦争映画とは違う」というより、「従来の青春譚に戦争要素を染み込ませただけの映画」であらう。
一番心に残る映画
全1072件中、281~300件目を表示