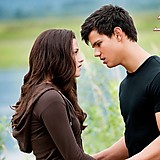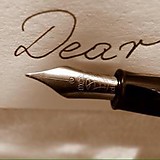ふたつの名前を持つ少年のレビュー・感想・評価
全36件中、1~20件目を表示
【ユダヤ人の名を捨て、ポーランド人の名でナチスの追っ手を掻い潜り、生き抜いた少年の実話の物語。ポーランドのレジスタンスの人達が、命懸けでスルリックを護るシーンは、矢張り心に響くのである。】
■第二次大戦下のポーランド。8歳のユダヤ人少年スルリックは強制居住区ゲットーを逃げ出し、ポーランド人だと身分を偽って放浪する。さまざまな人々や出来事を出会った果てに、ある一家の世話になって安堵するスルリック。だが、ユダヤ人であることがバレてしまう。
◆感想
・私は今まで、何作ナチス・ドイツの映画を観て来たのだろう。50本は観ていると思う。それは、高校時代にヴィクトール・フランクルの名著「夜と霧」を読んだからである。そこには、想像を絶するナチスの強制収容所に囚われた精神科医でもあった主人公が、冷静に収容所で何が起きていたか、何に希望を抱き生き延びたかが記されており、衝撃を受けたからである。
・だが、近年、ナチス・ドイツの蛮行を描いた映画の公開本数は減っている。時代的に仕方がないと思うが、ネオナチ及び極右政党のドイツ国内での台頭を観ていると心配になる。というか、世界全体が右傾化している気がする。
その最も分かり易い国が、アメリカであろう。
・その代わりに、ここ数年増えているのがロシアのウクライナでの蛮行をドキュメンタリー形式で描いた作品である。「マウリポリの20日間」などは、機会があれば観て欲しいモノである。又、イスラエルとパレスチナの状況を描いた映画も公開されている。良い事だと思う。映画は勿論、娯楽だが、世界情勢の危機的状況に対し、警句を発するモノだと思うからである。
<今作も、観ていてキツイシーンが多いが、ポーランドのレジスタンスの人達が、命懸けでスルリックを護るシーンは、矢張り心に響くのである。
だが、今後、出来れば実話に基づく新たな戦争映画が製作されない世界になる事を、切に望むモノである。>
一周回ってポーランド万歳なだけな気もする
第二次世界大戦中のポーランドで、ユダヤ人であることを隠し生き残ろうとする少年を、実話を元に描く。
ドイツ国内ではなくてドイツ占領下のポーランドってところがミソで、軍人が頻繁に出てくることもないし、ナチスに迎合していないポーランド人や、抵抗しているゲリラのポーランド人などが多く登場し、つまり主人公ユレクに対して親切な人の方が多い、生き残りをかけたサバイバルとは少ーし違うところが珍しいと言えば珍しい。
父からユレクへ、父や母のことは忘れてもユダヤ人であることは忘れるなという言葉で物語は始まるが、そうゆうとこだぞユダヤ人、と思わずツッコんでしまった。
だって、どちらかと言えば逆の方が良くないか?ユダヤ人であることは忘れても家族は忘れるなの方が良い。
そのあと、ユレクは親切なポーランド人に匿われ、そこで、これから生き残るための作り話とキリスト教徒の振る舞いを仕込まれる。ユダヤ人であることを徹底的に隠しポーランド人に成りきるために。
ある意味、父の教えに背くような形で生き残り術を身につけていくわけだが、そのあともユレクの危機だったり恐怖に怯える場面で、聖母マリアが何度か登場するのは、ユダヤ教とキリスト教がせめぎあっているようで面白い。
穿った見方をしないならばマリアがユレクを守っているようにも見えるし、ユレクが本当にキリスト教に傾倒していってるようにも見える。
ポーランド人やユダヤ人の宗教に対する考え方はわからないから何とも言えないけれどね。
ついに終戦を迎え、安心して暮らせるようになったユレクの元に、ユダヤ人孤児施設の人間がやってくる。
そこに知らせたのはユレクと同じ村にいたユダヤ人。彼は隠れるように暮らしていたし教会でも黙っていたことから、おそらくこの村に匿われていたユダヤ人だろうと推測できる。
ユダヤ人孤児はユダヤ人全体の未来であるからと無理矢理にユレクを連れていく。
ここで二度目の「そうゆうとこだぞユダヤ人!」が思わず出てしまった。
戦時中はユダヤ人であるからナチスに酷い扱いを受け、戦争が終わったらユダヤ人であるからと本人の意思を無視する。
日本人はほぼ単一のために、その感覚がよく分からないのもあるし、人種が発展するようにコミュニティを作って増やしていくことは多くの○○人が行っているのもあり否定する気はないけど、それってナチスがやろうとしてたことと本質的には同じだよなと思ってしまう。
なんか、ユダヤ人少年の苦労話でありながらアンチユダヤ的な息吹を感じなくもない。
施設の職員の男はユレクが大事にしていたロザリオも返してくれ、ユレクを単なるユダヤ人の少年ではなく、一人の人間として、最後は施設に行くかをユレク本人に選択させた。
父も母も失い一人になっても、最初の父の教えの通り、ユダヤ人であることに戻っていくのは悪くない落としどころだったかもしれない。
昔の家で見たフラッシュバックする家族との思い出がユレクを引き戻したよね。父や母を忘れなかったからユダヤ人に戻っていくのは教えに反したとも言えるし、マリア様の力も及ばない強い家族の力は、全方向に逆張りしているみたいで面白いなと思った。
とはいっても実話だから改編しようもないわけだが。
宗教的対立と融和、人種的対立と融和、その全てがちょっと皮肉っぽい感じて描かれていて面白かったし、結局は本人の選択の問題だというメッセージは良かったと思う。
ただただ可哀想なユダヤ人を見せられるだけの少し前の作品郡とは違って、現代的な風潮に乗った骨太さを感じた。
いつになったら
すごく長く感じた作品。
原題通り、少年が厳寒の中歩く、走る、逃げる…。
少年が安らかになれる時が短かったせいなのか。
いつになったら安心して暮らせるのだろうかと思いながら観ていたので疲れてしまった。
なんとしてでも生き延びようとする利発そうな少年。
冷たい人も多いが、温かく迎入れてくれる家も少なからずあるのが救いである。
少年を助けたばかりに家を焼かれた女性はかわいそうだったなぁ。
割礼が判断基準・・・
42~43年の冬。寒さゆえ、民家でコートを盗もうとして追いかけられるシーンから。森の中で凍えそうになりながらパン職人だった父の言葉を思い出す。両親のことを忘れても、自分の正体を隠してでもユダヤ人であることを忘れるな・・・。8歳の少年にどこまで理解できたのだろう。そして生き抜くことだけを考え、一軒の家にたどり着く。
その半年前、アブルム、ヨサレ、イセックたち孤児の集団に出会い、「ドイツ人はパルチザンを恐れて森に入らない」ことを教えられたスルリック。盗みや生きる術を学んだが、他の孤児たちはみな捕まった。そしてパルチザンの家族を持つヤンチック夫人に架空のポーランド人としての作法を学び、ユレクとしてポーランド人の家族に入る。しかし、ユダヤ人とバレて・・・とてもいい家族だっただけに去るのが辛い。
大農場で働けることになったが、事故により右腕切断。生きる勇気さえ奪われそうになるが、周囲の看護師や病人たちは皆優しいのが救いだった。しかし、苦難の道は続き、SSに追いかけられる運命。ヤンチック婦人から「長居しちゃ駄目よ」と忠告を受けるユレクだったが、森の村もSSによって焼き払われ、少女アリーナのいる農場で静かに暮らすことに。キリスト教の洗礼を受け、一生ここにいたいと願う。しかし・・・
苦難の日々と、執拗に追うナチス。どうして人は残酷になり、優しくなれるのか、人間の本質さえも描こうとしているところがすごい。シオニズム運動も絡んでいるのか、終盤には孤児施設の世話人も登場してユダヤ人の生き方をも描くが、どうもあっさり感じられた。サッカーを教える原作者本人も登場するし、世話になった農場と孤児施設を選択させるなんてのも意味深。父親が撃たれるシーンが重くのしかかるものの、右腕を失ったエピソードやヤンチック夫人の村のほうがつらいものがあった。そんな少年の辛い日々なのに、児童向けであるかのように楽し気な音楽が逆に息苦しくなった。
ユダヤ人として生まれたばかりに・・・
逃げるために名前や宗教も変え、ポーランド人の様に振る舞う少年。一人でナチスからとにかく逃げ、良い家を見つけては働き、匿ってもらい、また逃げる。森に逃げ、生きるために何でも食べ、野で寝る生活。ユダヤ人と分かっていても助けるポーランド人に感動。告げ口し、金を貰う輩は生きるためだが、人でない。片腕を失うのも、ユダヤ人と言うことで、すぐに医者が手術しなかったから。医者としての前に人として失格である。演じる少年の愛くるしい笑顔と、流れる音楽、周囲の人々の温かさに、そこまで悲壮感は感じないが、ラスト片腕のないご本人が孫たちと登場し、実話ベースだということがわかると、想像を絶する思いでした。
すごく、真面目、過酷、きれい
興味ない•••4•好き/並••••5すごい
無••••5社会派/大衆•4•••カルト
よかった/勧める
俺の満足度 80点
作品賞ノミネート可能性 90%
すごく、真面目。
すごく、苛酷。
すごく、きれい。
無茶苦茶に聞こえるかもしれないが、率直な感じ。助かるとはいえ、少年にはひどすぎる経験を疑似体験するのに、見終わった感じにわずかだけれど清涼感が漂うのは、素晴らしい自然描写の中で、あまりに少年が雄々しいからか。映画中では、勇敢と言われていたが、自分が感じたのは、雄々しいという言葉。
誰もが観た方がいい映画。
108分だが、重たいから、長く感じるよ。大切だから。主人公が出会う人たちを見て、自分がどう生きるか考えよう!
社会的な道徳観が映画の倫理観を殺す
冒頭で父が主人公の少年に託した「名前も父も母のことも忘れてもいいからユダヤ人であることを忘れるな」という言葉。
まだ右も左も分からない子供に民族の誇りや宗教を押し付けるのは親のエゴではないかと感じた。
その後、親と別れて一人キリスト教徒になりすまし、ナチス親衛隊から逃れながら、いろんな大人に助けられたり裏切られたりしながら生きていく。
悪い大人にも会ったがたくさんの良い大人にも助けられた。
束の間の幸せを手に入れたりもしたが、それはユダヤ人であることを隠せたからだ。
ユダヤ人として生まれたことを相当恨んだであろうに、最後に少年に迫られた決断を選んだのは民族の誇りからだったのだろうか、それとも父への思いからだったのか。
このような経験を二度としたくない思いでイスラエルという国家を作り上げたシオニストたち。
しかし今度は同じような苦しみをパレスチナ人たちにさせている。
映画の最後にそんなやるせなさを感じた。
こうしたホロコーストを扱った作品はどうも嘘つきユダヤ人がどれだけ傲慢でいやらしい民族かを理解した上で見ると全く感動できないのだが、あくまでも″フィクション″としてなら涙腺に響くものがあった。
ただの″感動作″という括りに入れるだけなら間違いなくオススメできる映画、それが『ふたつの名前を持つ少年』
まぁまぁ
人は心の扉を開けることはできるのか
悲しくなる
うちには男の子の幼児がいるので、彼が成長してこんなつらい目にあったらどうしようと気が気でなく、悲しくて居たたまれない気持ちになった。
ただ、少年があまりに出来すぎないい子で、そうでなければ生き残れなかったのかもしれないが、いい子過ぎて現実感がなかった。もうちょっと彼なりの不出来なところや個性を感じたかった。
アクションシーンがやたらとスリリングで、演出がうまい。
このようなテーマの映画を何度見ても、どうしてユダヤ人が差別されているのかさっぱり理解できない。なんであんなに忌み嫌われているのだろう? クラスのいじめみたいなものなのだろうか。日本でも朝鮮人差別や部落差別があるとは聞いているのだが、身近な問題としては全然ない。キリスト教徒とユダヤ教徒は生活習慣が全然違うのだろうか。仏壇と神棚が同時に家にあり、かつそれほど気にせず普段生活している人間としてはそんなに宗教が熱いことにもあんまりピンと来ない。
割礼、知らなければ調べてみよう。
良作には間違いないんだけれど、いまいち印象に残り難い一本。
演出、子役の演技、枯草色が多い柔らかな画面など良い所は沢山あるのだけれど。
大きな山場も仕掛けもなく、淡々と終わってしまう。
忘れてはいけない、歴史的事実なのは絶対だが。
「歴史実話モノ」の弱味を見事に晒してしまった、と言えば良いだろうか。
しかしながら。
盛りに盛って泣かせれば良いのか、と言えばそうでもないし。
(日本の戦争モノはほぼこの手法を取っているし、ヒットはするけれど、事実がヒトゴトに変わるので)
かと言って事実をただ事実に則って描けば良いのか、と言えばそうでもないし。
(シン・レッドラインみたいな例外はあるが、メッセージが伝わり難いこと多々なので)
内容以上に、そのさじ加減の難しさを考えてしまった作品。
ラストシーン。生きてくれ、という父の願いがいたたまれなくてしょうがなくなる。
逃げろ、逃げろ、とにかく生きろ、生き延びろ。
そんな父の願いが、スルリックを勇気づける。
表情を巧みに使い分ける名演!って感心してたら、なるほど双子か。
1年ぐらい間を置いて感情をリセットして撮っているのかと思った。
それでも、双子の二人の白熱の名演は必見。
第二次大戦下のポーランドで生き延びたユダヤ人少年と、我が身を顧みず彼を助けた大人たちの物語。
最後、父とスルリックが別れたシーンでそんなことが起きてたなんて。それでも、生きようとしたスルリックの姿にただただ涙。
ストーリーをとやかくイジるスキなし。オススメ。
あ、邦題がナンセンスだね。原題「RUN BOY RUN」のほうが全然いい。映画のテーマがぼやける。
ゲットーを脱出した8才のユダヤ人少年が 、最後にお父さんに言われた...
神の問いかけ
全36件中、1~20件目を表示