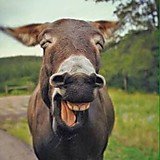あんのレビュー・感想・評価
全257件中、61~80件目を表示
すごい映画でした
樹木さんは満点
隔離からの解放
本編を見るまでは、どら焼き屋さんの話かと思っていました。ところが、それだけではなく差別→偏見→隔離
そして、解放というかなり濃い内容でした。
ハンセン病患者はお墓を作ることも許されない、衝撃の内容でした。酷いかも知れないけど、浅田美代子のような反応が世間の代表なのでしょうね。
料理人を目指していたが、レストランでの修行が辛くて逃げ出した甥っ子の為に店を改装してお好み焼きとどら焼き屋にしようと提案したり、身内には甘々なのに、障害を持った他人には冷たい。
コレが世間の普通の対応かと寂しくなりました。
あえて今取り上げなければならない題材でしょうか。私はむしろこうして...
五感に訴える映画
演技が深い!
だいぶネタバレ含みます。
感想を言うと、めっちゃ面白いです。
それは、エキサイトすると意味ではなく、傷だらけで不完全な登場人物達の人間ドラマとして、日本の実情を切り取る風刺として、そしてエンターテインメントとして他国でリメイク不可能な日本人にしか作れない映画だと感じたからです。
ハンセン病で半世紀も隔離されていた女性が小さなどら焼き屋で働くお話。
甘いものが苦手だけど、訳あってどら焼き屋で働いている永瀬正敏演じる店長が樹木希林演じる女性と出会い、人生を見つめ直していきます。
あんの作り方を学び、本当のどら焼きの美味しさとお店が繁盛する喜びを知った店長と生まれて初めて働く喜びを知った女性。
2人の表情が見る見る明るくなっていく描写はとても心温まります。
しかし、
常連の女の子がうっかり母親に女性の手のこと話した事がきっかけで噂が広まり、パタリと客足が途絶えてしまう。
世間のハンセン病に対する偏見と心ない仕打ちに翻弄され、女性は自ら身を引いてしまう。
どら焼き屋も経営者が業態を変えると言い出し、店長は意見する事も出来ない。
そして、女性は肺炎で亡くなってしまう…
悲しい映画と言ってしまえば其れまでだけど、そこから何を汲み取り感じ取るかは人それぞれな気がします。
少なくとも僕は、店長宛に残した音声を聞く限り、この女性はどら焼き屋で働けて幸せだったと思う。
2時間の映画で終始物静かで厳かな雰囲気ではあるもののついつい見入ってしまいました!
只、あんこを作るシーンであそこまで惹き込まれるとは思いませんでした。
やはり役者さんが素晴らしいですね。
樹木希林さんの演技は本当に凄いです。
とある老人のドキュメンタリーか?と思うくらい自然過ぎる演技に脱帽ですね!
永瀬正敏さんもリアクションが薄い役所であそこまで感情を表現できるのは凄いと思いました。
今回出演されてる樹木希林さんと市原悦子さん共にお亡くなりになったので映画界は大きな損失だと思いました。
今後こうした日本人にしか作れない作品をもっと量産していって欲しいですね!
女性らしい視点の映画
樹木希林は最高です
生きる意味
【今作品は、近年の邦画の中で圧倒的な傑作であると、私は思います。】
河瀬直美監督作。
樹木希林さん主演の”ある重いテーマ”をベースにした圧倒的な傑作。
-ストーリーは”春””初夏””秋”そして、再び迎える”春” と移ろいゆく季節を美しく映し出しながら静かに描かれる。-
永瀬さんの人生を諦めたような諦観の表情を浮かべる千太郎が黙々とどら焼きを作る存在感は稀有であるし、樹木希林さん演じる徳江が小豆に”優しく話しかけながら”あんを作る姿には、崇高さすら漂う。
孤独感を漂わせる女子高生ワカナを演じた内田伽羅さんの透明感。
故市原さん演じる佳子の哀しき過去を背負いながらも、体中から醸し出される、優しき佇まいも、この作品の奥深さを支えている。
必見であると思います。
<全ての人に、毎年、桜の花びらが舞う”季節”の到来を信じたい・・。>
<2015年7月5日 劇場にて鑑賞>
<その後、他媒体で再鑑賞>
■追記
「キネマ旬報ムック 「あん」オフィシャルブック」は、もし手に入れば、一読されることをお勧めしたい。
世間の厳しさと守れなかったことへの内省
数年前から気になっていた作品。河瀬作品をいくつか拝見したが、これが一番伝わってきたし、一番感動した。
ケンカの仲裁で相手に障害を追わせてしまい、借金の肩代わりをした感じ悪い金持ちによって雇われ店長をしている千太郎、元ハンセン病患者で半世紀以上療養所で生活し、世間の冷たい眼をイヤというほど体感してきた徳江、闇を抱える中学生のワカナ、をめぐる話。
ある日バイト候補でやってきた徳江は確かな味で人気のどら焼きになるが、元ハンセン病ということが世間に知られ、バイトも追われ、店自体も経営も悪化していく。
徳江の先入観を持たずに「あん」の美味しさに感動してバイトとして雇うその純粋さを主軸に話が進むが、千太郎に感情移入してはいけないのではないか、と思いながら鑑賞していた。というのも、悲しい・悔しいなど次々にいろいろな感情が千太郎に押し寄せてくるが、千太郎自身も負い目を持つ。その自己内省をしてこそのどら焼き作りではないか。
そう思うと、フラットな状態で見ようと心がけた作品だった。こんなに感情をコントロールしながら見た作品は今までになかったのではないだろうか。
「てんちょさん、美味しいときには笑うのよ」
桜に囲まれたアパート。桜に囲まれたどら焼き屋“どら春”。なぜだか女子中学生が学校の帰り道に立ち寄りやすそうな店。ふらっとやってきた76歳の徳江はアルバイト募集の張り紙を見て、雇ってもらえないかと千太郎に懇願する。二度目に来たときには自家製の粒あんを持ってきて、その味にほれ込んだ千太郎は徳江を雇うことに。
大将の奥さん(浅田美代子)が辞めさせるように忠告するも、穏やかな口調だったためにそのまま徳江を雇っていた。常連で高校進学も諦めかけていたワカナ(内田伽羅)が先輩陽平(太賀)とハンセン病の資料を調べていた。時を同じくして、どら焼き屋の客も遠のいていった。静かに店を去っていった徳江。手紙を受け取った千太郎はワカナとともに徳江の住む療養所を訪れるのだった。
桜の季節から柊の季節を経てまた桜の季節で終わる作品。まるで主人公徳江の生きざまをそのまま季節の流れに乗せたかのような演出。2018年9月に亡くなった樹木希林の人生をも象徴するかのような映画になったのかもしれません。また市原悦子が2019年1月に後を追うかのように亡くなり、この映画の重みが増した。彼女たちが伝えたいことを全て受け止めることはできないにしても、政府がハンセン病患者に対して行った隔離という愚行は十分理解できた。
最近になっても知的障碍者に対する旧優生保護法が行った断種手術など、国内における差別政策が明らかになるのですが、まだまだ隠されたことがありそうです。季節の流れを樹木で表現していましたが、差別用語である「らい病」という言葉も前半は使われていたのに後半はすべて「ハンセン病」と言っていたことも印象に残ります。ワカナたちが興味を持って勉強し、自ら成長したことをも表わしていたかのようでした。
千太郎(永瀬正敏)自身も仲裁から加害者になったという傷害事件を悔いるエピソードも効果的でした。徳江の「陽の当たる社会に出たい」と思う気持ちが彼の中にもあったのです。しかし、徳江が彼の前に現れなければ一生暗い人生を送っていたに違いない。千太郎とワカナの人生に大きく関わったほど、徳江が残した功績、生きてきた証しを残したことに三度涙してしまいました。
演技のぶつかり合い
登場人物が生きている
この映画の良さを長々と説明するのは難しい。
でも、一言で表すなら「登場人物がちゃんと生きてる」からです。
演技が上手なのは当たり前にあって、所作や佇まいがその人物そのものだと思いました。
樹木さん演じる徳江は、あん作りを50年していましたが、そこに違和感が全くなく、むしろ50年やってきたとしか見えない職人芸に魅了されました。
この「あん」やハンセン病に嘘が感じられず、映し出される四季がきれいで、この映画の世界に見入ってしまいました。
この映画は、映画に出てくる「あん」そのものだと思いました。ひとつひとつの過程をきちんと丁寧に作り、あずきの声を聴き、決して手を抜かない。
そうして出来上がった物が、味わい深い物になるのだなと思いました。
簡単にこんなもんだろうと作って出来るのが「業務用のあん」で、今まで業務用のあんのような映画をたくさん観て来ました。
なので、一見地味で単純なストーリーなのに、奥深さが全く違うのを感じました。
余計なものがなく、足りないものがなく、それを自然に作れるのがすごいと思いました。
本物の世界でした。
異質なもの、少数派。
ハンセン病患者は、異質なもの(奇異な症状のため、周囲には恐ろしいという感情が強かっただろう)、少数派として、排除・隔離されてきた。自分の存在が否定される苦しみはどれほどだったろうか。
罪を犯し償ってきた主人公の千太郎には、共感するところが多かったのだろう。
彼への徳江の次の言葉は慰めを与えるものだったと思う。「私たちは、この世を見るために、聞くために生まれてきた。だとすれば、何かになれなくても、私たちには生きる意味があるのよ。」
全257件中、61~80件目を表示