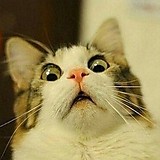家族ゲームのレビュー・感想・評価
全56件中、41~56件目を表示
松田優作がすべて
城南大学なんだから・・・最後はそこに落ち着くのか。とにかく最後の晩餐のシーンは凄かった。松田優作ってのはこういった長回しのパートが得意なんだろうなぁ。
教育問題的には校内暴力が目立っていた頃で、バット殺人など家族の絆が取り沙汰されるバブル前夜の時期だ。スパルタ教育も戸塚ヨットスクールのニュースが毎日流れていたように記憶している。家庭教師の松田優作は、植物図鑑をいつも携えていて、勉強なんて教えない。なにしろ「奥の細道」さえロクに読めない大学生で、ビンタをかまし、恐怖で生徒を押さえつけるタイプなのだ。
ストーリーよりも、淡々とした家族生活をシュールに描き、いつ何が起こってもおかしくない家族。ATGだということもあり、低予算を逆手にとったイメージ。最近の森田監督映画はひどいもんだけど、初心に帰って良作を作ってもらいたいものです。
30年ぶりに観た。カメラワークとか間の取り方なんかそれまでにない新...
不気味な映画
謎な表現が多くて、よくわからないシーンが多いけど
なぜか惹きつけられ最後まで真剣に見てしまいました
見終わった後あれはなんだったのかなどを
考え、調べたりするんですが
明確な答えがあまり出てこないのがいいのか悪いのか…
監督がいろいろ計算して話を作ってるならすごいなー!と思うのですがどうなんだろう
原作を読んだら理解できるんでしょうか…
調べたら原作通りではないみたいですが
ラストの
息子2人と母親がヘリの爆音の中でうたたね?
するシーンがあるせいで余計わかりにくくなった
食事シーンで終わっていたらまだ皮肉なコメディーよりだったのに
あのラストシーンのおかげ?でより難解さ、そして不安感が増す感じがした
お兄ちゃんが占いや星より空手に興味を持ちだしたり、
家庭教師もいなくなったし
なんか暗い未来しか見えない…
なんじゃこりゃー 何をどう見ればいいのか、何がいいたいのか、さっぱ...
やっと見つけた。ここまで大好きだと思える映画。
やっと見つけた。ここまで大好きだと思える映画。
場外ホームラン級に好きです。
ブラックジョークが散りばめられていて、
くすりくすりと笑ってしまう。
最後のカオスな食卓のシーンとか、笑いっぱなし。がははって笑いではないけど。
みんな少しずつズレてる沼田家。そこに、これまた少しズレてる家庭教師がやって来る。
みんなとても自然な演技で、学校の先生なんてセリフかんでたけど、そこがまたリアルで大変良い。
最近の映画は意味のないシーンを雰囲気つくりのために挿入したりしているけど、この映画にはそういった無駄なシーンが一切ない。早送りするタイミングが全くない。退屈することのない、ちょうどいいスピード具合もまた良い。
2011/1/19 @メディラボ
なんだこの異様感…
ラストは父権の不在
バブル時代の家族の危機を予見するかのような、薄ら寒さを感じさせる。誰かのレビューにあった、川島雄三の「しとやかな獣」を想起させる点が確かにある。しかし、あるとすれば物語の舞台が団地ということ以上に、森田芳光と川島に共通するシニカルな現代社会への視線ではなかろうか。
現代社会(川島は言うに及ばず、森田の生きた時代もすでに我々にとっての「現代」というには過ぎ去ったものであるが)を皮肉を込めて描いているが、その中にかすかな希望を見出し、冷めきった人間関係の中にほのかな温かみを感じさせる映画。これが両者に共通するものではなかろうか。
この作品を観たものが必ず感じるラストの不可解さについては、一言述べずにはいられない。
ヘリコプターの音が聞こえる昼下がり。二人の息子は自室で眠り、母親もヘリの音を気にしつつも、趣味の革細工の手を止めてまどろんでいくという幕切れ。
重要なことは、このラストで初めて映し出されるのが夫婦の寝室だということなのだ。それまで映画に出てくるのは、居間兼食堂と子供たちの部屋だけである。そして、映画の最後になってこの問題多き夫婦の居室が初めて出てくるのである。
しかもこの部屋には何もない。ベッドも置かれていない殺風景なこの部屋で、伊丹十三と由紀さおりの夫婦の営みがあるようには見えない。これは単なる観客の推測ではなく、その営みがこの部屋では行われていないことは予め映画では言及されているのだ。
伊丹が「大きな声で話ができるところへ行こう」と由紀を誘い、自家用車の中で親の本音を口にするシークエンスは、夫婦がもはや自宅の中に、一組の男女に戻れる場所を持っていないことを示している。色めき立つ由紀に伊丹が「まさか、いまから化粧をするんじゃないだろうな」というのは、まさにそういう意味であろう。
もはや団地という家屋には核家族の中核である夫婦の居場所がないということ。その夫婦は自分たちの人生を犠牲にして子供を育てる。しかも、ここでの「育てる」ということの意味はより学力の高い学校へ進学をさせるということに他ならない。
伊丹が演じるこの父親は悪びれずに言う。「自分が直接子供に言ったのでは金属バット殺人が起きてしまう。だから、母親や家庭教師に代わりに言わせているのだ。」と。
父親殺しのテーマなど現代社会や受験戦争が生み出したものでも何でもない。ギリシャ神話でも扱われるこのテーマに対して、この父親(他の多くの父親もそうであろう)のとった戦略は、息子と直接向き合わないことで、息子の不満や憎悪の対象となることを免れようとするものだった。
実にこの戦略は成功したかに見えた。ちょっと風変わりだが熱心な家庭教師のおかげで、変わり者の次男は親の希望する学校に合格する。しかし、父親はもはや家族を経済的に支える機能しか果たさず、子供に対してリスクを負う存在ではなくなってしまった。
もしかしたら殺されるかもしれないというリスクを回避する代わりに家族の中の居場所を失う。父権不在の家族の出現。言うなれば新しい「家族ゲーム」の始まりである。
ヘリコプターの音に導かれてベランダへ出る由紀さおりが、自分たち夫婦の寝室を通る。夫婦の寝室を映画のラストで唐突に映し出すには、その部屋に誰かが入る契機が必要だったのだ。
とにかくおもしろい
とにかく面白かった。家庭教師をして子供を高校に合格させる映画であるが、その家族がみんなばらばら、自己中心的な家族、住まいの団地の周りは工場ばかりの殺風景な場所、父は、仕事人間などなど80年代にいろいろと問題になったものがぞろぞろ映画の中に出てくる。監督は森田芳光。彼は本当に独特な感性の持ち主で素晴らしいと思う。他の作品も面白い。見ていない人はぜひ見てほしい作品である。ただ、音楽はいっさい使っていない。音は生活音だけ、特にものを食べの時の音はすごい。何回も見れば見るほど「なるほどなあー」とか「なぜ?」とか話題に尽きない。いままでの映画の中で一番多く見た映画である。30回は見たと思う。
良くも悪くも気持ち悪い
初ATG初森田芳光初松田優作と肩の力が入らずにはいられないシチュエーションで鑑賞。
正面から向き合わない家族。その象徴としての食事シーン。そこに打ち込まれる楔としての松田優作の不気味な存在感。彼の何かが爆発するラスト。ヘリの音が不気味なエンドロール。鑑賞後感…うーん良くも悪くもとにかく気持ち悪い。
強調される咀嚼音とかお母さんの過保護っぷりとか主人公のマザコンぶりお父さんの目玉焼きの食べ方(これがトップ)。どれをとっても気持ち悪い。強烈な個性としての気持ち悪さが僕にはいまいちハマりませんでした。間違いなく今まで見た映画の中で一番気持ち悪い!
家族ゲームは家族ごっこと言い換えることができるのかもしれませんね。
日本映画史に残る傑作
映画館では観てないものの、翌年TVで見たのが最初。
その後も、何回も観たが飽きない。
そして年齢とともに理解度が深まり
最近ようやく横テーブルの意味が解けた。
また現在五十路になったが、自分も生きて過ごした83年当時が
どんな時代だったかを、思い起こせる映画でもある。
当時を知らない若い世代だと、ネタのような場面もあるが
今ほど成熟していない日本の一時代を、そのまま映し出している。
例えば
当時ああいう教師は確かに存在し、既に教師は聖職では無かった。
また学生が今よりずっと多く、受験競争という時代である。
お金はあっても、行きたくても誰しもが大学に行けない時代。
大学の数が今みたいに多く無かった。
お金さえあり大学ブランドに拘らなければ誰でも大学に行ける
今とは違う。
映画に話を戻すと、脚本、キャスティング、演出、カメラワーク
どれをとっても完璧で、ひじょうに完成度の高い作品である。
今思えば森田、松田、伊丹、揃って既に居ない。
日本は優れた才能を失ったものだという思いが
私の中で益々作品の魅力を引き上げてる。
由紀さおりは、当時の一般的な日本の母親を見事に演じきっている。
やっぱり優作は素晴らしい
『失楽園』以来の森田芳光作品鑑賞。内容は、簡単に言えば、松田優作演じる家庭教師がある家庭に入り、掻き乱し、変化をもたらすというものだ。想像していたトーンとは多少異なり、全体的に淡々としていた。監督のメッセージを明確に読み取ることはできないが、「クラスでの順位が一つ上がったら一万円というのはどうだ」という家庭教師に対する父親の言葉から、人間の本質を無視して"生産ロボット"を製造する世の中の親たちを皮肉っていることは理解できる。
それにしても、言うまでもないが、松田優作が素晴らしい。あの独特な話し方には自然と引き込まれてしまう。この役ができる他の俳優を想像するのは相当難しいだろう。
冷めた時代の人間関係
総合:65点
ストーリー: 60
キャスト: 75
演出: 70
ビジュアル: 65
音楽: 0
初めて見たときはわけがわからない映画だと思った。最後のほうの横一列で食べ物を投げたり暴力が出るあり得ない食事の場面、全く理解出来なかった。社会という中、家族という中で生活していくうえで、実際には表面上だけの関係性などを皮肉っているのかと今は解釈している。一緒に生活していてもお互いを本当に理解することもない。物質的には豊かになり先進国として世界に肩を並べた、でも人々の人間関係は希薄で家族はばらばらで、家族同士でバットで殴りあいの殺人事件が起きる時代。そんな虚無感を抱えながらの何か冷めた生き方の描写が、この時代を反映しているのだろう。
物語はあまり意味がない。音楽も全くなく、出てくる場面は団地や学校や工場地帯ばかり。ただひたすらに人々の冷めた人間関係の齟齬が生じていく場面を繋ぎ合わせる。そのような人々の描き方を皮肉をこめて滑稽に映し出す。この独特の雰囲気が醸し出す面白さがこの映画の本質だろうか。
全56件中、41~56件目を表示