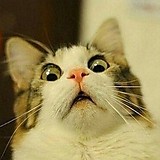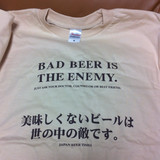アクト・オブ・キリングのレビュー・感想・評価
全61件中、41~60件目を表示
人間の多面性
これを歴史的な虐殺の戒めとして観るなら宇野惟正氏の言うように「全否定」となるのかもしれない。暴力で支配を繰り返してきた国の中心であるアメリカの監督がこの虐殺を安易に否定することは甚だおかしな事で、先ずはお前の国からだろうという話である。
しかし、この作品が残酷なまでに描きだしている「人間の多面性」は驚愕に値するものだ。本作の鑑賞後の感想として「酷い人がいるものね。」となるのか「自分もああなり得る。」となるのかでは全くこの映画の意味は異なるのである。鳥の怪我を心配した後に嬉々として虐殺の内容を自慢気に話す。この様なシーンが本作には何度も意図的に挿入されている。勿論、どちらが本物だ偽物だとかそんな単純な話ではない。どちらも本物であり人間とはそうゆう多面性の生き物だということをそれらのシーンは如実に表している。本作には「勝ったものが正義であって、勝ったものが秩序なのだ。」「お前にとっての地獄は俺にとっての天国だ。」という印象的な言葉が出てくる。その秩序が間違っているとは思いつつも、その現実を否定することは出来ない。事実そうであるのだから。これは他人事ではない。日本が万が一、第二次世界大戦に勝っていたら、自分もあっち側にいたのかもしれないのだ。状況によっては誰しもが無自覚に時代の「歯車」になってしまう。それは、とてつもなく恐ろしいことだ。
どんな極悪非道な人間でも優しい一面はあり、どんな博愛主義者にも醜い一面はある。スクリーンの向こうに映し出される人々を切り離して考えるのか、自分の延長線上に見るのか。安倍政権発足後、その歯車になりうる現実味を帯びてきてしまったこの時代に、大きな指針となる偉大な作品だった。
怖かった
もっとエキサイティングなものを予想していたらけっこう地味で退屈だった。町山智浩さんの解説の方が面白かった。
おじいさんが50年前の自分の罪に気づいて、吐き気を催す場面が本当に苦しそうで迫力があった。
インドネシアの民兵組織の制服がオレンジと黒の迷彩柄という毒々しいもので、特撮ヒーローものだったら絶対に悪の軍団だ。彼らが虐殺の再現をする場面は本当に悪そうだった。
太った男が女装させられたり、完全におもちゃにされていた。彼が調子に乗って選挙に出て落選したのは面白かった。
軍が政権を握るといろいろと良くない感じがした。インドネシアは近年『ザ・レイド』やシラットが注目されているのだが、深い闇を感じた。
衝撃
どこまでが演技でどこからが本音なのかが曖昧、という体裁はユニークではあるが個人的には微妙。
時折挿入されるスタイリッシュで鮮やかな服装の出演者たち。それらはどれも耽美的で過剰なほどに虐殺を行った者たちを美化しているようでもある。彼ら(体制側)の文脈ではあのような世界で生きているのかもしれないが、外から見れば滑稽である。(マツコ似というかそのものにみえるあのオッサンの破壊力はおいといて)
モキュメンタリーのようですらある本作は、語られている歴史的事実が深刻であることさえもあやふやにしている。それは彼らの時に嬉々とした語り口や、ふと自らの残虐性に気づいた際の過剰に見える仕草や振る舞いなどで助長されているのだ。また華僑の義父を惨殺された息子が撮影に立ち会って当時の話を笑いながら(怖れからともとれるが)こと細かく語るシーンなども「これって何なの?」と思わずにはいられない。そしてつまるところそうした違和感や実験的なオリジナリティが本作の魅力なのだろう。
ただ、個人的にはそのアプローチはさほど響かなかったかな。
嫌悪の原因
大量虐殺の加害者は“怪物”ではなく“ヒト”、特別過ぎない卑近な人間でした。
頭グチャグチャになる作品でした。
本作は当時1,000人を手にかけたアンワル・コンゴを中心に話が進みます。
元はダフ屋だったアンワルは当時の時勢に乗り共産主義者と“思しき”人物達を鏖に。
画面に映る現在のアンワルは白髪の一見好々爺という出で立ち。
孫を可愛がる姿は普通の老人という雰囲気。
そのような人物が嬉々として過去の虐殺を語りだし仲間と共に自主映画を作り出す。
後世の人々に自分達の功績を残すため。
『人を殺してはいけない。ましてや殺したことを自慢げに話すなんて』という自身の常識。
一方、アウトロー側の人間とはいえ、姿形や家族を慈しむ感情は同じ存在であること。
その違和感や非現実感に頭グチャグチャになります。
普段目にする映画等での虐殺者は、異形の“怪物”。
見た目からして自らとは異なる存在として捉えることが出来て心理的な距離感があります。
しかし本作を通して見えてくるのは虐殺をする側もされる側も同じ人間であること。
今は周りの見解や雰囲気含めて、その行為を否定することが出来ますが。
時勢等の舞台が揃ってしまえば自分自身もあの立場になってしまうのでは。
彼等が特別過ぎない卑近な存在であるが故に自身の考えや立ち位置の脆さに恐怖を覚えます。
また彼等が作成する自主映画の雑さやチープさに思わず笑ってしまうことも感情を揺さぶられます。
素人が考えた脚本、素人が作った小道具を使って雑な演技を行う。
その間抜けさに思わず笑みが零れるものの、扱っている内容が内容なだけに笑っていいやら悪いやら。
笑うことで彼等の行動を少しでも肯定しているような気すらして変な気持にさせられます。
画面に映る人物達と距離を取りたいにも関わらず、共通点を見つけてしまい違和感を抱く本作。
自主映画の作成を通してアンワル自身にも変化が生じていくのですが。
終盤の或る展開は息をのむ一方で『噓臭い、演技の延長だ』と思ってしまったのは、少しでも彼から距離を取りたかったからかもしれません。
インドネシアで当時起きたことを知る切欠としても良い作品だと思います。
オススメです。
狂っている。
エンドロールが匿名希望って
主人公のアンワルコンゴは若い頃、プレマン(フリーマンが訛ったもの)と呼ばれる街のゴロツキで映画館のダフ屋みたいな事をしていたが、1965年のスカルノ大統領失脚後の共産党狩りで1,000人ほど殺した事で英雄的な扱いを受けている人物。
副大統領や新聞社の社長とも普通に会っているが、そんな偉い人たちもアンワルコンゴを粗末には扱わない。
共産党狩りは彼らが主導した虐殺だからである。
そこが、日本との1番の違いで、彼等プレマンは選挙に出たり、認められた存在であること。そんな彼らが市場の店主をゆすって金を巻き上げている。
強かん、強盗、人の殺し方を自慢げに語る。
そんな彼らが知恵と人脈を結集して映画をつくるという。
まるでドラマの中の様な、あり得ない状況はドキュメンタリーかどうかわからなくなってくる。
ラストシーンの後のアンワルコンゴがどうなったのか知りたい。
革命の恐ろしさを目の当たりにした凄い映画である。 84点
ドキュメンタリーと呼ぶには余りに凄惨な自演劇
正義とは何か
被害者の追随体験という残酷さ
初回立見でいってきた。
インドネシアで行われた250万人といわれる大虐殺の加害者たちは”戦争の勝利”によって罰せられず英雄としてこれまで生きてきた。その真実を今回加害者自身が加害者役or被害者役として演じる。
最初は誇るかのように笑顔で演じていたけれど、次第に「俺たちは残酷だった」と言う。相手の立場になって考えてみる、のショック療法みたいだった。
怖いとか可哀想とか加害者被害者どちらにむけていいのかわからなくなり、ああこれが歴史の作られ方なんだって思う。
演技ではあり得ない衝撃
現代だと思うと
凄いドキュメンタリー
虫けらが人を虫けらのように殺していた実話
軍事クーデターによって樹立された、現インドネシア政府。なんともまあ、彼らは品性の欠片もなく、欲望をさらけ出し、多くの、あまりにも数多くの人(おそらくほとんどが罪のない)を虐殺してきた。それを、うれしそうに再現してみせる。しかも、稚拙なB級ホラーのゾンビのようなお粗末さなメイクと演技で。
彼らは、ただのギャングではないか。こんな国家がいまだ存在することの恐ろしさに震える。
この映画、ドキュメンタリーとして撮影を続けながら、主人公の白髪の老人の心理に変化が現れてくる。
殺される側を演じたあたりから、それまで嬉々として、自分の孫にまで殺人を自慢していた彼の表情が曇りだす。そして、処刑現場でその殺人シーンを解説しながら、突如えずいた。何度も。しかし、吐こうにも、胃の中は空っぽらしい。たぶんもう、ひとりのときに散々吐いているのだ。ようやく、罪の意識が芽生えたわけだ。遅いけど。
その姿をうしろから捕らえ、消えていく。このシーンが、この映画としての救いだった。
無常感
うーん、微妙・・・。
個人的には、今年前半の最大の期待作でした。
しかし、いざ、観終わってみると、なんだか、肩透かしを喰らった感じがします。共産主義者を殲滅させるという名目で大量のインドネシア人を殺し続けた集団の「幹部」とも云える人物(今では白髪の老人)が主人公なのですが、その主人公に殺害の様子を再現させる、というのが、話の骨子なのです。しかし、しかし・・・、その殺害の再現が、なんとも微妙なのです。非常に稚拙なのです。まるで、中学校の文化祭の催事のようで、主人公である殺人の実行者の話にも、私は衝撃を受けませんでした。やはり、このような記録映画を作る際には、当時の実録のフィルムを所々に挿入するのは必須であると思います。当時の加害者と被害者の様子を写したフィルムは必要であると強く感じました。この映画のクライマックスは針金を首に巻いて、何人も殺した現場に立って、当時の状況を語っていた主人公が突然、猛烈な吐き気に襲われ、何度も胃液を吐く場面(多分、このとき、殺された人間の立場に初めて立ったのでしょう)なのですが、劇映画では、人間の遺体を見て、嘔吐するというのは、余りにありふれた場面なので、余り、新鮮さはありませんでした。結局、かつての殺人者が贖罪するという、なんだか、ありふれた結末で、非常に、がっかりしました。所詮、欧米人のキリスト教的な価値観を押し付けられただけの映画である様にも思われました。しかし、決して、悪い映画ではありません。考える余白がたくさん残された映画でもあります。この映画の製作者の高い志は評価できます。週刊新潮では映画評論家のグレゴリー・スターさんが、96点という高い点数を付けていました。そう、悪い映画ではないのですが、なにぶん、こちらの期待値が高過ぎたので、☆は二つ半、と云うことになります。悪しからず。
原一男の「ゆきゆきて、神軍」、小林正樹の「東京裁判」、マイケル・ムーアの「ボウリング・フォー・コロンバイン」、或いはクロード・ランズマンの「ショアー」といった傑作と肩を並べる作品になるか、と期待していたのですが、なんとも残念な結果となりました。
こんな映画観たことない
全61件中、41~60件目を表示