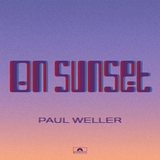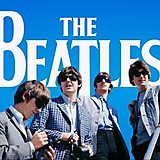フルートベール駅でのレビュー・感想・評価
全39件中、1~20件目を表示
「被害者」ではなく一人の人間としての人生を感じ取ることができる一作
『クリード チャンプを継ぐ男』(2015)、『罪人たち』(2025)など、マイケル・B・ジョーダンとのタッグで様々な名作を手掛けてきたライアン・クーグラー監督による、劇場公開長編映画のデビュー作です。
本作の主演ももちろんマイケル・B・ジョーダンで、彼らの関係がいかに継続しているかを実感することができます。
本作は、2009年の新年を迎えた直後の深夜、米国カリフォルニア州オークランドのフルートベール駅で、オスカー・グラントが警官によって射殺された実際の事件について描いています。作中クーグラー監督の視点は、時に時系列が切り替わりつつも、常にグラントに寄り添い、彼を事件後に生じた大規模な抗議活動の発端となったシンボルとしての「犠牲者」ではなく、ひとりの家族を持つ人間としてどう生きたのか、を語ります。
そこから浮かび上がってくるグラントの姿は、時に失敗し、決して褒められたような言動を繰り返すものの、懸命に立ち直り、家族のために生きようとする一人の人間でした。
事件のその後については結末に簡素な一文を添えているだけですが、それまでの丁寧な描写の積み重ねが、事件の扱いに対するクーグラー監督の怒りを静かに伝えています。
彼がエンターテインメント作品の監督として一流の腕前を持つことは、これまでのフィルモグラフィで証明済みですが、それらの作品作りの根底には、この怒りが原動力としてあるということを強く実感させてくれる一作でした!
スーパードキュメント
冷めた眼も保ちたい
よく覚えている事件
加州オークランド市のBay Area Rapid Transit (BART)バートという電車の駅Fruitvale で22歳のオスカー グラントがバート警察に銃で殺された事件をドキュメンターリー(風?)にしたものだ。オスカーはマイケルジョーダンが演じている。この事件は、今でも記憶にある事件で、また改めてみてみた。この後、Black Lives Matter で 米国の警察の暴力、差別意識、黒人の命を奪う、不平等さに声をあげるものが増えた。
よく聞く話だがアジア人で背が低い(150 cm ぐらいをいう)女はひったくりにあうという。スーツを着ている男と作業服を着ている男とでは、声をかけて道を聞くならスーツの男の方に話しかける。また、黒人と白人があらそっていれば、黒人に問題があるとみる。このような、偏見からこういう事件が起きる。この時の、バート警察は黒人ではなかったから、余計、このような偏見が強くなったと思う。不公平で、理不尽な事件だが、どこでもおきる可能性があるしおきている。このような事件がおきて、また、泣き寝入りしたり、そのままにしておくと、こういう事件はなくならず、次から次へおきるだろう。
実際おきた事件で、数人がビデオどりしているのがネットに載っている。それにまた、おかしなことで、差別や偏見から始まるこのような事件を基本的に理解していないといけない。差別はよくないと言葉でわかっていて、差別という意味の概念を理解していない人がいる。だから他人の目から見て人を差別していると言われてもしていないと答える。それに、良き聞く話だが、私は日本人だから差別されていないという。なぜと聞くと黒人じゃないからと答える人がいる。差別とはなにかと根本に返って、この意味を再検討する必要がある。
インタネットアーカイブでこの映画を探したので再び観た。
被害者は「黒人」というより「ひとりの男性」
【”Black Lives Matter !! " エンドロールで流れたテロップに怒りを禁じえなかった作品。一部のアメリカ白人警官の意識は50年経っても変わっていない事実に愕然とした作品でもある。】
◆今作を観て、直ぐに思い出したのは、キャスリン・ビグロー監督が2017年に発表した「デトロイト」である。
1967年7月に起こったデトロイト暴動を描いたこの作品は、特に白人警官たちが、黒人たちを銃で脅しながら40分にも渡り続く観ているのが非常に精神的にキツイ拷問シーンであった・・。何も罪を犯していない黒人たちを・・。
◆今作の冒頭で、そのシーンは銃声と共に描かれる・・。
その後、その数週間前に時間軸は戻り、度重なる遅刻で店を首になり、恋人ソフィーナとの関係性も危うくなったオスカー(マイケル・D・ジョーダン)が、愛娘タチアナの姿を見て、少しづつ真人間になろうとするシーンが、彼の過去の収監された時のシーンを織り込みながら、描かれる。
ここが、観ていて非常に辛い。
観ている側は、この若き黒人青年の行く末が分かっているからだ・・。
◆彼は、勤めていた店に再就職しようと脚を運ぶ。その際に、恋人の好きな魚のフライの作り方をソフィーナの母に電話で聞いてあげたり、悪友のクスリの誘いも断る。
そして、愛娘タチアナを抱き上げ、可愛がるシーン・・。
◆オスカーは、ソフィーナとの関係性を少し改善し、ママ(オクタヴィア・スペンサー:彼女の存在がこの作品をキチッと締めている。)の誕生日パーティーを楽しんだ後、ソフィーナ達と、サンフランシスコのニューイヤーフェスティバルへ向かう。母の”電車で行きなさい・・”という言葉を受けて・・。
車中で、オスカーは魚のフライの作り方を教えてあげたケイティに声を親し気に声を掛けられるが、オスカーの名を耳にした且つて刑務所が一緒だった男に絡まれ、車中は騒然となる。そのまま、彼らはフルートベール駅で降ろされ、白人警官たちに取り押さえられる・・。何の罪も犯していないのに・・。
そして、愚かしき警官の拳銃から・・。
<エンドロールで警官や駅関係者への処分が流れる。
当時の状況は多くの客が動画で撮影しており、発砲した警官は逮捕される。
だが、彼の抗弁により、懲役2年!僅か11カ月で出所したというテロップが流れる。
”アメリカの司法制度はどうなっているのだ!警官の制服を身に着けた、殺人者が、11カ月で出所だと?”
オスカーを追悼するシーンで大きくなったタチアナの俯く姿に涙を禁じ得ない。
この事件の後も、1992年のスピード違反をした黒人男性、ロドニー・キングさんを袋叩きにする白人警官たちの姿が拡散し、ロス暴動を引き起こした事も記憶に新しい。
民主主義国家アメリカは、いつになったら、真の民主主義国家になるのであろうか・・。暗澹とした気分になった作品。
私たちは、犠牲になったオスカーが”愛娘を抱く姿”を忘れてはいけない‥、と心から思う。>
テンポがほしい
2009年、一人の男の死は歴史ではない
Ryan Coogler
現在はハリウッドでもブロックバスター作品を手掛ける、新鋭監督ライアン・クーグラー監督の長編1作目。
この作品は、2014年サンダンス映画祭でグランプリを受賞した最高のデビュー作。
映画というのは人を動かす。心を動かすという意味でもそうですが、その心が動いてから行動に移させるほどの力を持ってると私は思います。
この作品なんかもそう。ニュースで連日取り上げられた2009年1月1日の事件ですが、この事実を来世に残すという意味、そしてもっと多くの人に知ってほしいという意味でこの映画は人を動かしたと思います。
個人的にいうと、この映画を観た後には、映画を作らなければならない。という気持ちに駆られました。それほどまでにパワーのある作品。
16mmフィルムで撮影された本作には、日常を表す表現がたくさんありました。
まず16mmフィルムというフォーマット。現在多くの作品が35mmフィルムやデジタルフォーマット、65mmで撮影しているところを、デビュー作ということで低予算映画ということを逆手に取り、16mmで撮影することにより、少し解像度の落ちたフィルムのグレインを感じる映像を実現していました。それは、我々が馴染みのある8mmの家庭用ムービーに似たような、日常を感じさせるテイストを観客に与えます。
そして、ハンドヘルドでの撮影。ワイドレンズを使い、常にキャラクターの近くにカメラを置くことで、観客がその家庭だったり、コミュニティだったりに一緒にいるような感覚を感じ取ることができます。それが、キャラクターを描く一つの方法にもなっており、観客が一つのキャラクターになるというような、映画の世界の中に視点を置くテクニックをつかっていました。
そして、編集もまたハンドヘルドのリズムと、家族の中の会話、キャラクターの感情などを編集へのリズムに反映させ、ワイドのエスタブリッシュショットでリズムを落としたり、サスペンス的要素を視覚的に表現するようなカットの粘りがありました。ほとんど無駄のない編集と、編集でストーリーに縦軸をもたらすテクニックは見事だったんじゃないかなと思います。
このように、すべてが一流のタレントをもった人が作り上げたわけではないけど、それらが一貫性を持っており、相互に編み込まれているからこそ、大きな感情を生み出すことができ、観客を動かすことができるのだと思います。
結局は映画もアートであり、何を伝えたいのかということが明確であり、そこを軸にどこまで観客を参加させられるかということが重要であるということがこの作品からよくわかりました。
軸がぶれたり、細かったり、ましてや軸がなかったりする映画はどんだけタレントを持った人々が作ったとしても観客を動かすことはできない。たとえ、観客を楽しませることができたとしても。
映画はそれだけの力を持っているのだから、それだけの力を持たせてあげるのがフィルメーカーの役割であり、義務であると私は思いますし、私はそれを作り上げたい。
こういう映画が作られる意味
重い。(重厚という意味で)
この監督のことはBlack Pantherでも褒めちぎったが、そんな彼のデビュー作。
新進気鋭の若手監督と言えばNeill Blomkampが浮かぶが、
Neillが奇をてらった新鮮な作品を作る若手だとすれば、
本作の監督であるRyan Cooglerは、真面目にとことんスタンダードなことをやる、といった印象か。
実際に起こった事件を基にしているため、ストーリーは決まっているからこそ難しい。
必要以上にお涙頂戴風にすることもなく、しかし淡々ともし過ぎず、
なんとバランスのとれたことか。
学校で観せても良さそうなくらい真面目な創りなのに、かと言って退屈もしない。
実際の事件であり、日本人には予想も付かないほど複雑な人種問題が絡んでいるだけに
真面目すぎて退屈になるか、オスカーを善人に描きすぎて押し付けがましいかのどちらかに偏ってもおかしくない。
しかしどちらに偏ることもなく、ひたすら考えさせられる。良い意味で、重い。
この若さにして、3作目にしていきなり、MCUシリーズの一本を任せられるだけのことはある。
黒人(当事者)である監督が、こうも冷静に人種問題を描いた点も評価されるべきだし、
なんてことだろうか、良い点しか見付からない。
作品の舞台になったオークランド周辺には何度か行ったことがあるが、
確かにいかにも治安が良くない。昼間でも、そういう空気がある。
さすがにアメリカの刑務所を訪れたことはないが、全編を通して、舞台となった街の空気感まで伝わってくるようだった。
デビュー作からこれはすごい。かなりの良作。
観るべき映画
後半、あまりの悔しさや悲しさで涙が止まらなかった。
映画は他人に強制されて観るものではないけれど、この作品は観るべき映画だと言い切りたい。
自分自身、この事件がニュースで報じられていた事を覚えているけれど、それはあくまでも遠い国で起きた理不尽な事件であって、当然憤りは覚えたものの結局のところその時の僕にとっては単なる「情報」だった。
ライアン・クーグラー監督はマイケル・B・ジョーダンを始めとする素晴らしい役者陣と共にドキュメンタリータッチの撮影を行う事で、オスカー・グラント3世の「生」を見事に浮き彫りにしたと思う。
オスカーの人柄や周囲の家族や仲間達との関係を丁寧に描き、2009年1月1日に彼が確かに存在し、そして理不尽にも命を落としたという事実を「リアル」なレベルに表出させた。
本当に素晴らしい、忘れてはならない映画だと思う。
2017年、同様の事件がアメリカで多発した。
そんな時にこそ、この映画は観られるべきだと思う。
二度と起きてほしくない事件
冒頭から実際に携帯などで撮られた事件の一部始終が流れ、余りに衝撃的過ぎてそのままあっという間に映像に引き込まれてしまいました。
家族のある一人の黒人男性の1日を映像化した作品で、85分という尺ながら彼の人となりがしっかりと伝わってくる内容になっており、冒頭で「死」という結末をすでに示されているだけに何とも居たたまれない感情で見続けることになります。
そしてラストもこの事件後の記録映像を流し、しっかりとメッセージとして締めくくっており、アメリカの抱える銃や人種差別などの社会問題を考えさせられ、見終えた後にずっしりと重たさが残る作品でした。
映画としてもキレイにまとまっていますが、やはり記憶に留めておくべき内容なのでいろんな人の目に触れるといいと思います。
何と言ってよいか
全39件中、1~20件目を表示