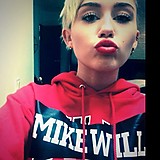許されざる者のレビュー・感想・評価
全55件中、21~40件目を表示
流石ベテラン陣な映画
オリジナルに忠実でありながらも、キャラクターの外見的な設定と、舞台の置き換えが素晴らしくてあきない。
この作品の元は、イーストウッド氏の監督としての出世作。
オリジナルは大好きで、何度も見ていて、先日もテレビで放送していたので、また見てしまった。
何度見てもあきない素晴らしい作品で、個人的には、生涯でもベスト10には入る映画です。(あまりにもベタなので、レビュー等は書いていない)
それを日本でリメイクするというので、それだけでうれしくなって見に行った。
予想では、オリジナルがあまりにも素晴らしい作品なので、ここがダメ、あそこがダメ、ということになって、結局つまらなかった、ということになるだろうと思ったが、それでもいいと思っていた。
でも、予想に反してすごく面白かった。
ストーリーや台詞は、設定の説明的な部分の他は、内容的にほぼ同じで、バカ正直なくらい変えていない。
演出的なところも、ちょっとだけ違うけれどもほぼ同じで、期待を裏切らない。
それではオリジナルには勝てないからつまらないのか?というとそうでもない。
違うのは、キャラクターの外面的な設定と舞台設定なのだけれども、これは比べれば、比べるほど、面白くなってくる。
舞台が、開拓時代のアメリカ西部→明治初期の北海道
主人公のマニ―やネッドが、昔のならず者→旧幕府軍の残党
キッドが、近眼のカウボーイ→アイヌと和人の混血の若者
こんな感じで、置き換えがすごくうまくて、味があり、興味深い。
特にイングリッシュ・ボブのくだりは最高だった。
イギリスが長州藩になっていたのには思わずうなった。
それから、武器をさしだすところが、小銃が小刀になっていたのもすごい。
最後の銃身のひん曲った拳銃が、折れ曲がった刀になっていたのには笑った。
こんな感じで、何度も見ていて、細かいところまでつい比べてしまう人には、キャラクターの外面的な設定や、舞台設定等を比べると面白くなるようになっていて、この映画で初めて見る人には、オリジナルに忠実なストーリーや演出で、名作テイストが味わえるようになっていました。(昔一度だけ見た、という人はつまらないかも・・・?)
ただ、最後の酒場でのガンファイトの置き換えと、結びでオリジナルのテーマを少しはずしたような感じになっていたのが残念だったけど、全体的にはかなり成功しているリメイク作品だと思います。
リメイクの必要性は感じないけど…
ん?
やっと観れました
心に染みました。
無法者達の伝説が聞こえる
ついオリジナルと比べてしまいますが、西部劇を開拓時代の北海道の雪原に翻訳したのは大成功。猛者や無法者達の伝説がまことしやかに聞こえてくる舞台にはうってつけで、見応えがありました。
主人公・釜田十兵衛と行動を共にする青年・沢田五郎が印象深かったです。
五郎の身の置き所ない孤独、十兵衛が、彼だからこそ感情を動かされるのはとても自然なことに思えました。柳楽優弥が熱演でした。
村を牛耳る大石一蔵はオリジナルでジーン・ハックマン演じる保安官にあたる役どころ。一番注目していたのですが、だいぶ厭世的で大人っぽくちょっと残念、保安官の稚気を含んだような所が魅力だったと思います。
渡辺謙にはどうも多湿なイメージがあるので西部劇は合わないんじゃないかと思ってましたが、低温多湿な雪原にはピッタリで良かったです。
許せる!
けっこうよかった
これぞ映画の一級品
久々に出来の良い邦画を観た。
キャスト・ストーリーに違和感が
中身のない映画
道具立てやキャストには力が入っているが、ともかくプロットが悪い。
主人公の十兵衛は、子供のことを考えて行動を開始するが、自分の行いが、どんな結末をもたらすかも考えず、最後には自暴自棄に陥るような人格で、『論語』でいう下愚とは、このような存在かと思わせる。子供が父親と会えなくなる悲しさを理解できない男なのだから。いくら金を渡しても子供の心は癒えない。非常に単純な人格なのである。
こうした人格を見せられても反面教師にすらならず、何も学ぶことがない。
さらに一蔵は、傷害事件を馬で肩代わりさせる理不尽な男で(あるいは女郎屋のオヤジから賄賂を取ったのかもしれない)、またお金で殺人を依頼した女郎たちに裁きを下さない。公平な立場になら、お梶も金吾と並んで拷問を受けているのが筋だろう(これにも裏があるのか?)。法の番人たるべき一蔵は、公平さもない悪人だが、十兵衛よりは複雑な人間かも知れない。
女郎に憐れんで(感情移入して)プロット展開を考えたのだと思う。その気持ちは分かる。可愛い「なつめ(女郎)」を傷つけた奴を許さんぞ。それは分かる。ただ、その情念に流されて他の事が見えなくなり、平板なプロットになってしまった気がする。へたをすると学生が自己満足で作った映画のようになってしまう。
エンターテイナーは、自分の描きたい世界を描く自由を持っている。それと同時に、お金を出して見に来てくれる観客に学びと満足を与える使命もある。もちろん、これは人それぞれの感想であるから、この映画について断定するつもりはないが、個人的には学ぶことは何もなかった。
こういう作風は、かつてデカダンを標榜する映画にも見られたが、
最近は少なくなり、日本映画が隆盛を取り戻しつつある。だが、意味なき芸術主義がはびこると、再び冬の時代が来ると危惧する者である。
全55件中、21~40件目を表示