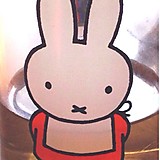どん底(1936)のレビュー・感想・評価
全3件を表示
木賃宿の人々の群像劇
ロシア文学で有名な戯曲「どん底」、原作は読んだことないけれども、貧困層のプロレタリアート!みたいな暗い作品だと思い込んでましたが、意外にも、木賃宿の人たちはお酒や歌で毎日が楽しそうでありました。
男爵(ルイ・ジューベ)が賭け事で公金を使い込み、そのおたずねのシーンが冒頭に来ますが、この男爵、ペペル(ジャン・ギャバン)の次の主人公といってもいいぐらい、キャラクターが魅力的で存在感がありました。賭けでお金を使い込んだあげく、最後の賭けにも挑戦。しかしここでも破れてどん底へと落ちるのですが、その後、ぺぺルと友情で結ばれ木賃宿に住むようになります。宿の人たちにまじってゲームなどしてすぐに馴染んでいました。
ペペルは家主コスティリョフの妻、ワシリーサと恋仲でもあるようなのですが、ワシリーサの妹ナターシャに惚れるようになります。ラストはナターシャと新しい生活をスタートするような予感が漂ってました。
ぺぺルがワシリーサと別れ話するシーン。ワシリーサに「きれいだ。色気がある。でも心ときめいたことがない。愛おしいと思ったことがない。やさしさがない」と言い放つところが印象的。動物を手なづけるように包み込んでくれる女性を望んでいるという。なのに、ペペルが選んだナターシャには、柔らかさ、優しさがあまりないのでちょっと違和感ありました。
ジャン・ギャバンが若くてかっこいいです。32歳の時だそうですが、貫禄はありますね。
賭場で女性が歌います。世相を表しています。
♪♪♪
ブルジョワは羽布団にくるまり
ネズミは通りをうろつき
強盗は仕事に出かける
銃やナイフを忍ばせ、こっそりと
どんな仕事にも適した時間がある
犯罪に生き、盗みを糧に生きるのは
楽しくないことよ
憐れな男たち
♪♪♪
何と豊かな窮乏か
ルノワールの独特な思想が貧しい人々を見守る『どん底』に、ルイ・ジューヴェの名演
ジャン・ルノワールの非常に豊かな精神性に守られたシリアスドラマである。ゴーリキーの原作未読の為断言できないが、ここに描かれたルノワールの世界より遥かに悲惨な社会背景ではないだろうか。しかし、今この映画を観るにあたって、そのことは余り問題ではない。それは、ルノワールの「どん底」がゴーリーキーの骨組みのみを利用したに過ぎなく、ゴーリキーのテーマとルノワールが描きたかったことは違うと思われるからである。
何故それが言えるかと云えば、貧民たちの打ちひしがれた生活描写を観ていても、社会に対する不満や批判といったプロレタリア文学の特徴が感じられないからだ。あらゆる状況下において、人間は精神に余裕を持ち生きるべきで、人生はその意味で幸せに過ごせるものなのだという思想が、全編を覆う。木賃宿に住む種々雑多な男たちの言動を観ても、飢えた生活に絶望した様子は窺えない。これには驚きを持った。例えばチャップリンが喜劇の要素として貧しい人々を題材にするのとは違って、ルノワールはリアリズムで表現しながら厳しい境遇と人間を対比させている。これがとてもユニークであり、ジャン・ルノワール独自の世界観と云えるだろう。
この映画で一際異彩を放つ人物は、文句なくルイ・ジューヴェが演じた男爵である。賭博にハマり全財産を失い、屋敷を出て泥棒のペペルのいる木賃宿に住む男爵は、身を滅ぼす人間の典型的な例である。それがルイ・ジューヴェによって、何と魅力的に毅然と演じられていることか。この名優の演技には感服しかない。それと、ジャン・ギャバンのペペルと男爵の友情が美しい。フランス映画の特徴の一つに、他の国と比較して男の友情を扱う題材の多さとその描写の繊細さがある。この二人の友情も、フランス映画の中で特筆すべきものであろう。それから、ルイ・ジューヴェの男爵が何故身の破滅を自ら導いたかが、単に賭博に目が眩んだ結果だけではないことが分かる。ここにルノワールの意図がある。物語は、ペペルが木賃宿で働くナターシャと結ばれ、新しい人生を求めて旅に出る。チャップリンとクレールを思い起こすラスト・シーンで結んでいた。作劇としては、ペペルが悪徳の主人ユスティレフを殺害するも、程なく釈放されて悲劇には転化していない。全ては、ルノワールの救済の愛の豊かさで登場人物は生きて行く、生命感溢れる「どん底」であった。ただ一人、役者の夢が破れた男だけが自殺するエピソードは、ルノワールの自省的皮肉と見えなくもない。
1980年 2月28日 フィルムセンター
全3件を表示