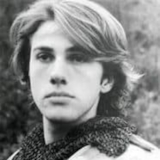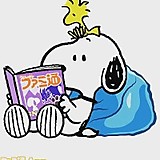J・エドガーのレビュー・感想・評価
全74件中、21~40件目を表示
いったい何を言いたいのだろう、この映画は。
FBIの創設者であり、約半世紀にわたってアメリカの権力の頂点に君臨し続けた男、フーバー長官の記録です。
彼が副長官とホモ関係であることも、大統領たちの恥部を握って脅迫して権力を維持し続けていたことも、有名な事実ではありますが、知らない人はまったく知らない話でしょう。
なにせ昔の人の話ですからねぇ……。
そこで、知ってる人にも知らない人にもストーリーを楽しませようとして、イーストウッド監督は、それはそれは苦労しています。
監督のご苦労は認めます。
ですが、その苦労のために貴重な上映時間をかなり浪費してしまっており、彼がFBIを掌握した部分も、FBIを通して米国の権力を裏側から完全に牛耳っていたという点も、あるいは彼を止めようとして動いていたケネディー大統領兄弟との対決というドラマも、まったく食い足りません。
FBIってのは、全米あわせて1万人規模の人員を擁するきわめて強力な捜査機関のはずですが、映画からは数十人規模の組織じみた貧弱感が漂って来て、チープな感じが否めませんでした。
従ってストーリーだけなら1点でも不思議ではない作品でした。
この映画で評価できる点は、特殊メークです。
人間の半世紀分をそれぞれ同一の俳優が演じるのですが、老人になってもまったく違和感を感じさせないメークが施されています。
どアップにしても、なお違和感がないのです。
この特殊メーク術は、これぞハリウッドの底力と感じました。
というわけで、長尺の映画ですが、特殊メークの勉強をしたい人と、よほど時間を潰す必要がある人以外にはお勧めできません。
ラブストーリーでした
権力の保持
殴り合いの告白
人柄も功績も賛否両論ある人物を主人公に据えると、一体どんな作品になるのだろうと思って観ました。
タイトルに”Hoover”を入れていないのも、「あの」Hoover長官ではなく、孤独なひとりの人間として描こうとしたのだと思います。純粋な愛国心溢れる貢献者なのか、それとも権力者達を影で操る独裁者なのか。謎に包まれた私生活も作品の通りかは分かりませんが、本人を含めごく数人しか真実を知らないのですから、断定を避けつつ、公平な推測に基づいて表現するのは苦労したことでしょう…。全体的には少々地味な作品でした。
万人に愛される人ではなかったけれど、それでも最愛の人はずっと側にいた(*´∇`*)。
ゲイの脚本家だから書けたロマンチックな同性愛。
“I need you, Clyde. Do you understand? I need you.”
“On one condition: Good day or bad, whether we agree or disagree, we never miss a lunch or a dinner together.”
ケンカとセックスは同じ
レビューするのが難しい。フーバーと言う人を知ってる人なら、また違う視点で描かれてたりして、なるほどと思うのかもしれないが、無知な僕からするとFBIを作った人はこういう人だったんだ…で終わってしまう。
たぶんフーバーと言う人の認識は傲慢で権力を振りかざし、人を下に見るような偉そうな人なんだと思うけど、その裏では母親しか信用できる人がおらず、孤独で自分に自信がない裏の顔もあったとと言う事なのだろう。
自伝が偽りと作り話で出来てたというのが人生を表しているというか、悲哀に満ちててなんとも言えなかった。
インタビューを取りながら偽りの派手な人生を見せると言う見せ方がよかった。
映画や物語の表現において、セックスとケンカは一緒なんだなと思った。
トルソンがいて良かったね。
タイトルなし(ネタバレ)
映画では 悪者が多い フーバー長官 ディカプリオという事で見てみた FBI設立前の1910年代は実際 共産主義革命が起き アメリカにもテロが多発してた歴史を知る フーバー側からの視点の映画はなかったので 楽しめた
だが 後半はゲイのプラトニックラブ話へ
ビックリの展開だが フーバーがなぜ これほど 「取り締まり」に執着したか…に納得
また マスコミを用いての宣伝戦略や情報を集中して握る事で権力を持ち やがて 腐敗していくのは どこの国も同じ
まさか 結婚されてるけど 子供がいない 日本のあの人も…
楽しめた(*^^*)
宣伝には「FBIを作った男」観た後「ホモ映画」
アーミー・ハマー
ディカプリオがやりたかったことの集大成、たぶん
FBIはだれでも知っているが、その創始者フーパーについて知る人は、日本にはほとんどいないだろう。もちろん自分も含めてだが。
そのフーパーの人となりというのだろうか、映画を観るにつれて思ったのは、ここに描かれているフーパー像は、おそらくディカプリオがこれまでに映画でやりたかったことの集大成に違いない。
(ほぼ)同年代ということもあり、デビュー当時からずっと応援してきたディカプリオ。彼はこの映画で、これまでやりたかったことをきっとほぼすべてやり遂げることができたに違いない。そう思ってつい「泣ける」にチェックを入れてしまったが、フツーにこの映画を観て「泣く」ことはまずない。たぶん。
昔から老け役(というか役の晩年とか)を自分でやるのが好きだったディカプリオ。かつては、ただ付け髭を付けただけで童顔がよけいに目立ってしまったとかずさんな仕事ぶりが多かったが、今回の老けメイクにまるで違和感がなかったのは彼が年取って自前で老けてきたからなのか、それともメイク技術が格段に向上したからなのか……そう思うとまた目頭が熱くなる。
しかし泣く子も黙る「FBI」の権力者なんて、はたから見たら超絶エリートで近寄れんはずだが、やっぱり人っていろいろあるのね~、天は二物三物与えても必ず一つは奪うのね~などとしみじみ思ってしまう。最初らへんのナオミ・ワッツ扮する秘書(最後までナオミだと気が付かなかった)との最初のデートでいきなりひざまずいてプロポーズし、こっぱみじんに断られるシーンは妙に哀れを誘い、また泣けてしまった。
エリートも屈折してんだな~、エリートって完璧じゃないんだね……そうだ、人って完全無欠じゃなくっていいんだ、弱みがあってもいいんだ……とこの映画はきっと勇気を与えてくれる。んなわけないか。
でも最後は、フーパーが心から分かり合えるパートナーに出会えて本当によかった。床に倒れているディカプリオの腹のたるみ具合が、別の意味でまた涙を誘ったが。
「FBIはじめて物語」
FBI初代長官の話。今までほとんど知らなかった。途中からは「FBIはじめて物語」「FBIを作りあげた男」というサブタイトルを自分で勝手につけて観るようにすると入り込めた。無理やり日本のイメージで言えば、警察がなかったころに警察庁という組織を作り上げたようなもの。「8人の大統領が恐れた男」は、3. のことを言っているのだろうけれど、大統領全員との生々しいやりとりが描かれているわけではないので(そうするといろいろ問題があるのかもしれない)、ちょっとずれたコピーだなと感じる。
1. 国会図書館のすべての資料に対応した目録カードをつくり、管理できるようにした(無整理情報のデータベース化)
2. 犯罪現場の指紋をとるなどまったくされていなかった時代から、それを重要視するようにした(指紋のデータベース化)
3. FBIとして "公式の" 人物データベースを公称して行うと同時に、政治家個人のスキャンダルを(過去までさかのぼって)別の極秘ファイルに集めて、いざというときのカードにしていた(公的権力+フィクサーという2本柱、または飛車+角)
主人公のレオナルド・ディカプリオが議会で朗々と語るシーンが何度かある。特に、リンドバーグ法を成立させるために、冷静でよどみのない、演説のような証言シーンに2分くらい使っていた。字幕翻訳の人も大変だったろうなと思いつつ、ここは聞き応えがある。また、最初のほう、国会図書館の室内を真上から見下ろすカットもなかなか。本物なのかはわからないけれど、「SP 革命編」の国会議事堂(よく見ると惜しくも作り物とわかってしまう)に比べると、かなり "本物感" があった。
ただ、特に前半、いい意味でいえば「抑えた色調」なのだけれど、全体の色味が地味なために、視覚に訴える起伏が少なくてちょっと退屈だった。たとえば、捜査員のコートはグレーか黒、せいぜい濃い茶色。自動車や建物は、もう少し明るい色調のものも絶対にあったはずなのに、出てこない。しかしこれも、口ひげがあるだけで捜査員を解雇したとか、華美な服装を極力排した、というエドガーの厳しいポリシーを示していたのかもしれない。
全74件中、21~40件目を表示