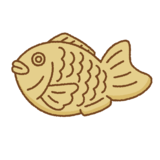バグダッド・カフェ 4Kレストア版のレビュー・感想・評価
全28件中、1~20件目を表示
個性的な登場人物
登場人物がそれぞれ個性を持ち、かつ、自分に正直な感じが良かったです。
当初のブレンダは最悪のコンディションでした。常にイライラしており周囲の人間に当たり散らしていましたが、ヤスミンと関わる中で元の性格を取り戻して行またように感じます。
元は音楽好きの陽気な女性だったのかな。
全体を通して、ヤスミンの人柄でモーテルの利用者が噛み合いハマっていく過程が見ていて楽しかったです。
ただ彫り師女性だけは別でしたね。彼女は居場所や家族ではなく、程よい距離感の人間関係とある程度の仕事を求めてモーテルにいたのかな、と思います。
皆んなが仲良く楽しくを望むわけではなく、そうではない人間もいる、というところが現実味あって良かったです。
また、モーテル周辺の風景がとても絵になり、ふと切り取られたシーンが美しかったです。
荻上直子系
めっちゃチルいと思ったらカムバックしてきた時にめがね(もたいまさこ)の絵が浮かんだ
カムバックしたとこで切らずにちゃんとハグしてその後日談まで描くのは日本とハリウッド(?)の差だなーとは思います
鑑賞動機:そりゃ当然名前は知ってるけど見る機会がなかった10割
それこそむかーし、劇場で売られていたポストカードで存在は知っていたが、こんな話だったのか。
こちらのコンディション悪目で、前半苦労したけど、ジャスミンが周りに受け入れられ出したあたりから復調して、楽しく見ることができた。何から何まで気に食わなかったのが、するすると反転して、実に爽やか。
カタコトの英語もちょっと可愛らしく見えてきて、あらあらまあまあなシーンもちょっと微笑ましく思えた。
不思議な感覚と共に訪れる満足感・幸福感
4Kリマスターで再上映されると聞いたので有名な作品との認識はあったけど殆ど予備知識なしで鑑賞。
「かもめ食堂」とか「めがね」っぽい印象(こっちの方が先に公開されてるからむしろ逆なんだろう)。
クスッとさせらたり、ハッとさせられたりしながらあっという間の時間だった。フライヤーや予告編の印象よりも面白かった。
アングル?カメラワーク?や色の使い方が独特な気がするけど、小気味がいいリズムを生んでて鑑賞中はずっと「なんかいいな」って思ってた。
ストーリーは分かりやすくて登場人物はみんな愛おしい。変わり映えがなくてなんか上手くいかない日常にイレギュラーな主人公が現れて、最初は警戒してるけどいろんなキッカケで関わりながら良い方向に変わっていく既視感あるストーリー(メリー・ポピンズ的な?)。登場人物の心情と一緒に荒れ果てたカフェが変わっていく感じとか、主人公も周りの影響を受けて変わっていくのとか好きだった。
ちょっとよく分からないシーンがいくつかあったのと、え?まだ続くのと思ってしまったけど終わり方は好き。
作中で流れるCalling Youがとても良くてお気に入りの一曲になった。
中だるみしそうだったけどセーフ
展開がゆっくりで、途中飽きてしまいそうになったが、ギリギリのところで少しずつ場面に変化があった。コミュニティーに1人別の人が入ることで変化が生まれ、カフェが活気付いていく。そのストーリー展開はほっこりして良かったなと思った。しかし、なぜモーテルの女店主はあそこまでイライラしているのか。ずっと何かに対して怒鳴っているが、動悸がはっきりしなかった。ただ、説明をしすぎる映画もつまらないので、余白を楽しみたいと思う。
マツコ…
ジャスミンがわがままボディでマツコにしか見えない…。
なんか色々もやっとする映画だったなあ。
世間の評価は高いみたいだけど。
ジャスミンはなんでケンカ別れしたのか(ついでに言うと旦那はそれっきり。ブレンダは旦那とよりを戻したのに)。
最後のプロポーズもちょっと年齢考えると不釣り合いかなぁ。それに対するジャスミンの返答もなんかなぁ…。彼のトレードマークを入れ墨にしておいてそりゃない。
荒涼とした砂漠、夕陽で真っ赤に染まる空は綺麗でした。
晴々と生きる
ヤスミンに心無い言葉を言ってしまったことから、カフェの主であるブレンダは、これまで周囲に当たり散らしてきた自分の態度を省みる。
そこから育まれていくヤスミンとブレンダの友情は、見ていてとても幸せな気持ちになった。
サロモの子供の母親はいなくなったのか、ヤスミンは夫と別れたのか、そうなんだろうなと思わせつつ、映画は一人一人の事情を細かく描くわけではない。でもそれが良いなと思う。何を抱えようが彼らはそこにいるというのが。
ヤスミンのビザが切れて帰国を余儀なくされたとき、映画はここで終わるのだと思った。
ブレンダの横暴な態度に家を出たものの、ずっと見守っていた夫が代わりに帰ってくるのかなと。
でも先に帰ってきたのはなんとヤスミン。再会したブレンダもヤスミンも晴々としていて、依存し合うわけでもなく、自分が好きなようにありのまま生きている感じがした。
ヤスミンの最後のセリフ、ああふたりは本当に友達なんだなあという実感があってよかった。
トップレスの方がセクシーよ
小説か何かでタイトルは覚えがあり、気になって鑑賞。
よく分からない夫婦喧嘩×2から始まり、不機嫌な人間とマイペースな人間しか出てこない。
ちょっとした誤解から警察呼ばれたりコミカルさはあるが、序盤は退屈。
明確に流れが変わったのはヤスミンが本格的に掃除をはじめたあたりから。
ここで今までとまったく違うBGMが流れて分かり易い。
ヤスミンのおおらかな人柄が、少しずつ周囲の人間を包みこんでいく。
正直、市販のセットで学んだマジックで盛り上がるのは他に娯楽のないあの場所だからだろう。
ただそれだけでなく、“ヤスミンだから”だという説得力があるのは見事。
良くも悪くも彼女のキャラクター頼りのため、映画的なエピソードが無いのは評価を分けるところか。
ビザ切れで帰国してから戻ってくるのが早すぎるし、途中の電話も活かされないのは気になる。
ヤスミンの旦那にも言及されないし。
男どもが揃いも揃って仕事してない(カヘンガ除く)し、サルはずっとどうやって暮らしていたのか。
タトゥーイストの美女だけ去ったのは何を示す?
脱ぐ必要性と、コックス(COX=Cocks?)の名前の関連性を勘繰ってしまう。
最後のマジックショーの雰囲気は素敵だが、サスガに長いのでエンドロールと被せてほしかった。
砂漠の乾いた色彩の中に、青空と衣装の黄色が映える画面は好き。
唐突に断片的なカットが入ったり、色々と考察要素はあるけど、今観て新鮮かというと…
全体で観て、ヤスミンの性格が旦那と喧嘩別れするところだけ浮いてるように感じてしまう。
魔法瓶で始まりマジックで終わる、魔法と奇跡、癒しと救済の現代の御伽噺。
20年ぶりくらいに観たけど、やっぱり良い映画だ。
記憶にあった以上に、御伽噺のようにメルヘンチック。
田舎町に舞い降りた「聖者」が起こす、
魔法と奇跡、癒しと救済の物語。
何度か観たことのある映画だし、わざわざ無理して行かなくても良いかな、と思っていたのだが、『どうすればよかったか?』と『きみといた世界』のあいだの時間つぶしにちょうどよかったので、シネ・リーブル池袋で観た。
結果的に、とても幸せな気分になれたので、行ってほんとうによかった。
パーシー・アドロンの映画はこれくらいしか観た記憶がないが、『バグダッド・カフェ』に限って言えば、僕の若いころはシネマ・ライズ公開だったこともあってか、「渋谷系」のイメージが間違いなくあった。でも今見直しても、別にオシャレな映画でもなんでもないよね(笑)。
むしろ、人種や出身を超えて友情を結ぶ大切さを問う本作は、今の時代にこそ真にふさわしいともいえる。
なぜ僕がこの映画を大学時代に初めて観たかというと、
実は大学で僕は奇術愛好会に属していたのだ(笑)。
本当は京大ミステリ研やワセミスみたいなミステリ・クラブにあこがれていたのだが、母校に本格ミステリ研究をメインとするサークルがなく、やむなく入ったのが奇術愛好会だった。
奇術愛好会といっても実態は結構本格的な体育会系のノリで、年三回のステージショーを通じて、そこそこ力の入ったステージを披露していた。僕は大変エキサイティングな青春をこのサークルで過ごした。
というわけで、かつての僕は『バグダッド・カフェ』を渋谷系映画としてではなく、「マジック映画」として観たのだった。
― ― ― ―
ここでいきなりだが、僕のマジック映画ベスト10をあげておく(時代順)。
『魔術の恋』(53)(トニー・カーチス主演のフーディニの伝記映画)
『魔術師』(58)(イングマール・ベルイマン監督による魔術一座の物語)
『ヨーロッパの夜』(61)(チャニング・ポロックの鳩出しが見られることで有名)
『テラートレイン』(81)(デイヴィッド・カッパーフィールド出演のホラー)
『バグダッド・カフェ』(87)(本作)
『プレステージ』(06)(マジック監修はデイヴィッド・カッパーフィールド)
『幻影師アイゼンハイム』(06)(奇術演出はCGが多くてイマイチだが、良設定)
『イリュージョニスト』(10)(ジャック・タチ執筆脚本のアニメーション)
『俺たちスーパーマジシャン』(13)(デイヴィッド・カッパーフィールド出演)
『ナイトメア・アリー』(21)(元映画の『悪魔の往く町』にもマジシャン登場)
何度も名前の出てくるデイヴィッド・カッパーフィールドというのは、アメリカを代表するマジシャンで、ちょうど僕が大学で現役マジシャンだったころの「絶対的ヒーロー」だった。僕は有楽町の東京国際フォーラムで、彼の「フライング」の実演に触れて、文字通りむせび泣いたものだった。
『バグダッド・カフェ』で演じられるマジックは、本人が市販のマジック・セットを持ち出して独学で練習しはじめるくだりがあることからもわかるとおり、学生マジックレヴェルでもよく実演されるような、比較的オーソドックスなものばかりである。
多少、「カメラからは耐えているが、カフェにいる客の視点からは耐えていない(耐える耐えないというのは、隠しているものが見える見えないをさす奇術用語)のではないか」と思われるスライハンド(手先の器用さを用いたマジック)や、その照明では種が隠せないのではないかと思われる演技(とくにダンケン=ダンシング・ケーンのシーン)もあるが、基本的に1カット、カメラ・トリックなしで「本当に舞台上で実演するとおりのマジック」を実際にやっているので、大変フェアで気持ちがいい。
ざっと思い出すだけで、シルク、カップ&ボール、フラワー、コイン、腕切断イリュージョン、ダンケン、あとはクラッカーを出したり、卵を出したり。
いずれも古典的で有名なトリックではあるが、結構な練習を必要とするものばかりで、彼女たちが師匠もなしに短期間で人に見せられるレヴェルで習得するのは非現実的だし、一般の観客に毛花を渡してしまうのもどうかと思う。その後のステージ・ショーに関しても、とても素人レヴェルではない演出と衣装が導入されていて、実際はいろいろ嘘くさいところがある。
ただ、そんな些細なことはどうでもよくなるくらいに、本作は「マジックの効用」をうまくつかんでいる。
英語で、奇術と魔法は同じ「マジック」。
奇術は小さな魔法だ。
さびれたカフェに火をともす魔法。
疲れた人々の心に火をともす魔法。
人と人を結び付けて幸せにする魔法。
ここでは、マジックがそういうものとして位置づけられている。
奇術って、「タネ」と「知識」と「訓練」さえあれば、だれでも「ステージ側に立たせてくれる」少し特別な演芸なんだよね。
僕みたいに、舞台経験もなければ眉目秀麗でもない人間であっても、練習さえすれば、「人に見てもらえて」「人に喜んでもらう」ことができる。ちょっと「着ぐるみ」に近い、魅力増量の特殊効果が、マジックには間違いなくある。
マジックするよってだけで、お客さんは最初からわくわくしてくれるから。
演技者以上に、タネと手先に集中してくれるから。
『バグダッド・カフェ』は、そういうマジックの本質を物語にうまく取り入れている。
肥った異邦人の女が、砂漠の最果てにあるカフェで、マジックを通じてお客さんに「小さな不思議」と「小さな幸せ」を与え、それが人と人の縁を結び、やがてみんなを大きな幸せで包んでいく。
マジックは魔法。誰でも奇跡は起こせる。
そんな御伽噺を、ドイツ人がアメリカを舞台に撮った。
それが日本で単館ロングランの記録をつくるような大ヒットを巻き起こす。
マジック愛好家の僕にとって、『バグダッド・カフェ』はやはり特別な映画である。
― ― ― ―
『バグダッド・カフェ』は今考えると、
ずいぶんと時代を先取りするような映画だった。
黒人と白人とインディアンが手を取り合って仲良しになっていく、ボーダーレスな映画であり、「移民」や「流れ者」が地元住民に受け入れられていく幸福な映画でもある。
それぞれの夫に置き去りにされた女ふたりがカフェを再興させる、シスターフッドの映画であり、「女性版のブロマンス映画」のはしりともいえる。
それらの要素が、まったくの押しつけがましさやうさん臭さを感じさせず、アンチポリコレの僕ですらすんなり受け入れられるくらいの自然さで、物語として巧みに組まれている。
結果的に、地元民も、流れ者も、カラードも、白人も、みんなが幸せになれるある種の楽園としてバグダッド・カフェは成立し、ドイツから来たディヴァインみたいな肥った女は、ある種の「市井の聖女」として位置づけられる(息子の弾くピアノを聴くヤスミンの背後からは後光がさし、老画家の描くヤスミンの肖像には常に頭光が描き込まれる)。
砂漠にそそりたつ黄色い給水塔。
常に手元に戻って来るブーメラン。
こわれたコーヒーメイカー。
ドイツコーヒーの入った魔法瓶(マジック・ジャー)。
名曲「コーリング・ユー」。
幾多の「象徴物」に彩られて、『バグダッド・カフェ』は「伝説」となった。
― ― ― ―
●パーシー・アドロン自身は、ニュー・ジャーマン・シネマの監督たちとはかかわりもなかったし、さしたる影響も受けていないとインタビューで答えている。ただ、ヴィム・ヴェンダースの『パリ、テキサス』(84)を彼が知らないとはちょっと思いにくいし、『パリテキ』でも見られた「異邦人の眼差しでとらえた幻想の国アメリカ」というテーマを、アドロン流に敷衍したものが本作だとはいってかまわない気がする。
●本作の場合、補色を強調した強烈な色彩美(監督いわく、色彩感覚についてはサルバドール・ダリの絵を意識したらしい。魔法瓶や給水塔に共通する「黄色」は「優しさ」の色とのこと)と、主題歌「コーリング・ユー」のけだるい響きによって、「幻想のアメリカ」を強調している点は見逃せない。
●「コーリング・ユー」は、今ではスタンダード・ナンバーとして歌い継がれている名曲だが、もともと「この映画のために」つくられた楽曲であり、前からある曲の流用ではない。監督の依頼では、ガーシュインの『ポーギーとベス』に出てくるアリア「サマータイム」のような曲を、という要請だったらしい(まさに異邦人から見た「アメリカ」だ)。
●「コーリング・ユー」と並んで本作を彩るのが、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」だ。カフェのピアノでブレンダの息子が弾き続けている楽曲。壁にはバッハの肖像画がかけられている。ドイツつながりの部分で、アメリカの片田舎でドイツ人女性が受け入れられていく「土壌」として、バッハ受容が描かれているのかもしれない。
単なる騒音扱いされていたピアノの練習が、ヤスミンを触媒として、美しい旋律として「化ける」瞬間の演出は本当にすばらしい。
あのとき彼は、はじめて自分のためではなく、聴いてくれる誰かのために弾いたのだ。
●旧弊を打ち払い、すべてを新しく始めることの象徴として、「掃除」が出てくるのも今風といえば今風な気がする。考えてみると、つぶれかけたレストランとかショップとかを再興させる話ってのは、『タンポポ』とか『王様のレストラン』とか山ほどあるけど(みのもんたの『愛の貧乏脱出大作戦』みたいなやつ)、『バグダッド・カフェ』もまさにその定型に乗っかってはいるんだな。
一度、劇的なまでに賑やかに変化した日常が、変化をもたらした当事者がいったん去ることで元の木阿弥に、という展開も、『サウンド・オブ・ミュージック』のマリアや、『美女と野獣』のベルなどでもおなじみの王道演出。
●実は、前から似た設定だなと思っているのが、シドニー・ポワチエ主演の『野のユリ』(63)。『バグダッド・カフェ』の舞台はモハーヴェ砂漠だが、こちらの舞台もアリゾナの砂漠地帯で、「東ドイツからの移民である5人の修道女」を、「車の故障でたどりついた黒人の青年」が助けて、礼拝堂を建設するまでを描く。シドニー・ポワチエは「神から遣わされた人物」として修道女たちに扱われ、冒頭は「井戸の水」から話が始まり、彼らはいっしょに歌を歌い、屋根にのぼり、礼拝堂の建築が進むにつれて、多くの地元民が援軍にかけつけてくれる……ね、いろいろよく似てるでしょ?
人種も出身も関係ないという思想や、流れ者が止まっていた時間を動かすきっかけになる流れ、登場人物全員が善意の人である点なども含めて、両作の共通点は多い。
●映画の顔としては、ヤスミン役のマリアンネ・ゼーゲブレヒトの特異な魅力と体当たりの演技(ちょっと春川ますみみたい)、それから、常にいらだっているブレンダ役のCCH・パウンダーのキャラクターが立っているわけだが、個人的にはジャック・パランスの老画家が素晴らしかった。映画のなかでも「銀幕のスター」扱いされる内輪ネタが出てくるが、まさかあのジャック・パランスがこんな役で復活するなんてね。
その他、寝てばかりのぐうたらウエイター、無口なタトゥーアーティスト、長期キャンプ中のブーメラン使い、インディアン保安官、トラッカーたちが登場する。
●画家がヤスミンを描き続けるうちに(何枚目かは裏のナンバリングでわかる)、だんだん持っているフルーツの形状がエロティックに変容し、それに合わせてヤスミンの服が脱げていく(ヤスミンが服を脱いでいく)流れは、いわゆる「天丼ギャグ」というやつでなかなか楽しかった。ただし、大変個人的な意見で恐縮だが、ゼーゲブレヒトの裸は必ずしも見たいとは思わなかったし、より正直にいえば、あんまり見たくなかった(笑)。
なんか、ヤスミンにセクシーな恰好させたり脱がせたりってのは、この映画で「是が非でもやらないといけないこと」みたいな真剣度で取り組まれているけど、このあたり、「肥っている/痩せているなんかで女性の魅力は決定されないんだ」といった強い意見表明でもあるんでしょうかね?
不思議な感覚
すみません。序盤、自分はあんまり好きじゃないかも…と思って観てました。
だけど、ブレンダがヤスミンに部屋で謝った所あたりからだんだん面白くなってきて最後のマジックショーはとても解放的な気持ちで観れました。
さらに観終わって時間が経つにつれ、良い映画だったなぁと思えました。
キャラクター達も観ていくうちにどんどん好きになっていきました。
今思い返してもとても良い映画でした。
じんわり感動😌
物語はそんなに派手な事が起きる事もなく、ゆったりとしている。
バグダッド・カフェの女主人、ブレンダがすごく良かった!
物語の最初、彼女は自分の環境にウンザリしていて、表情、仕草、言葉使い全てがストレスの塊みたいになっている。
それがヤスミンと出会い、少しずつ自分の良い部分を取り戻していく。終盤のバグダッド・カフェでのマジックショーでブレンダは別人のように生き生きしていた。そして歌も上手い!
良い映画だった😊
溜め息が出る程良い作品
ブレンダがあまりにヒステリックなので、最初の数十分間はしんどいなぁと思いつつ観ていたが…
情景が好みなのと、ヤスミンが丁度良い感じに控えめな性格でいてくれて、時折子供たちに見せる笑顔が可愛くて…
ザワついていた心も穏やかになれた
ヤスミンの存在が、乾き切っていた人たちの心を少しずつ潤わせて、繋げて、豊かにしていく過程が本当に美しかった…
再会のシーンは涙が出た
ショーシャンクが思い浮かんだ
4Kじゃなくて残念だと思ってたけど、むしろ良かった
映画館でまた観たいので、次は4Kにしてみよう
ピンク色のマジックアワーはアメリカ大陸ならではなのかな
生で見たいと思うほど綺麗だった
ヤスミンが徐々にはだけていく過程は可愛くて可笑しかった
彼女のちょっとした心情(襟を戻して又折り返したり、部屋に彼が尋ねてきた時に服を着る時間をわざととったり…)が垣間見えるシーンも凄く好き
絵、ブーメラン、タトゥー、手品…
ゲームもスマホもAIも知らない世界で、気に食わない人がいて、たとえ憎しみを感じたとしても、人は人を信じれるし繋がれる素晴らしさを改めて思い知らされた
良い映画に出会えて幸せだと感じた
Jasmin’s Magic
オリジナル版は昔観ていたがテーマ曲のCalling You以外は記憶の彼方だから殆ど初見に近い。
バグダッドといえばイラクの首都の方が有名だが映画のバグダッドはカリフォルニア州ニューベリースプリング、ルート66沿いに昔、実在した街のことです。
主人公はデブのドイツ人のおばさん、ヤスミン、旅行中に夫婦喧嘩でハイウェイに取り残されてしまった。行くあても無く街道沿いのガソリンスタンド兼カフェ兼モーテルのバグダッド・カフェに居ついてしまう。カフェの女主人ブレンダは多忙の為か常にヒステリー状態、夫も追い出されるところはヤスミンの境遇と似ていなくもない。ドイツの主婦は勤勉で綺麗好きが多いと聞くがヤスミンもまたしかり、最初は迷惑がっていたブレンダだがヤスミンの優しく健気な人柄に惹かれてゆく。
なんと唐突なのだがヤスミンは手品の名手、店で披露していたら評判となり店は大盛況、いまでは欠かせない存在になるが・・・。
出てくる人は善人ばかりだが個性豊か、劇中歌で「人生をローギアに入れてトラジック(悲劇)とはお別れ、マジックが世界を救う~♪」と唄うがまさにローギアでのんびり生きることがテーマのようなほのぼのとした名作でした。
タイトルなし(ネタバレ)
今でもTSUTAYAなどで「映画通が選ぶ100本」に選出されるほどの名画らしいし、名作!最高!と本作をあげる人も多いらしいけど私は何が起きたんかよく分からんかった
いや、なんも起きてないんか
自分の視野が足りてないんだど鑑賞後、
色々なレビューを見たり評論を検索したけど
おぉ!なるほど!とは納得出来ず、
最後のブレンダに相談のセリフも何の意味が込められてるのか…
全部ひっくるめてよく分からん
タイトルなし(ネタバレ)
パッケージや序盤の雰囲気から勝手にシリアスな作品だと思っていたので、中盤以降の展開はかなり驚いた。こんなに癒される作品だとは思わなかった。
ブレンダのキャラクターが最初はなかなかキツかったけど、終盤は作品に良い味をもたらしていた。モーテルに住む家族達が徐々にジャスミンへ心を開く様が自然と笑顔を誘われた。
ジャスミンのマジックがあのオモチャのようなもので身につけたのだとしたら、怖いレベル。プロ顔負けの腕前だったので元々上手いと思いたい。
主題歌のCalling youが多くの場面でかかるので耳に残った。終盤の展開には少し切なさを強く感じる曲でマッチしていなかった気もする。途中弾かれたバッハがピッタリだったこともある。もちろん序盤にかかった時は作風に合っていた。
「ブレンダに相談してみるわ」の意味
結婚すればグリーンカードを持たなくてもずっとバグダッドカフェにいられるよ、というプロポーズらしき言葉。
好きだ!結婚しよう!みたいな単純明快な言葉じゃない、まわりくどいプロポーズ。
それに対するジャスミンの答えが「ブレンダに相談してみるわ」。
バグダッドカフェの主人であるブレンダにここでずっと働いてもいいか確認してみるね。
みたいな意味合いの返し?
偽装結婚の合意形成みたいな会話の下に流れる、2人にしか分からない暗号みたいな愛情のやり取りを表現してるのかな。
私はそんなふうに読み取りました。
このシーンは人によって全然解釈が違いそうなので、興味深いです。
砂漠のオアシス
クールなテーマ曲や画面とは対照的に、主人公のキャラが純朴でほっこりできる物語。
広大なモハヴェ砂漠の中にある打ち捨てられたようなガソリンスタンド兼モーテル兼カフェに、ドイツからロサンゼルスに行く旅の途中の車で運転する夫と口喧嘩になりはぐれてしまった主人公の一人、ジャスミンが逗留することから話が始まる。
同じ頃、喧嘩の末に夫が出て行ってしまい一人で店を切り盛りするブレンダは常に疲れてイライラしており、みんなを笑顔にしようと色々と立ち働くジャスミンのことも怪しんで激しく責める。けれど、そんな彼女に同情しているジャスミンは穏やかに自分の気持ちを告げ、二人は家族同様のバディになり、ブレンダも店も一変する。
どんなひどい場所だってジャスミンのような人がいれば砂漠のオアシスになる。そんな感じの映画ラストの二人のショータイムも良かった。
幸せな気分になれる
序盤のクセがすごい。ジャスミンがヒッピーに囲まれたドラム缶風呂から出てくるシーン、あれマジでなんなん(笑)
ブレンダのカリカリした行動・表情が、徐々に柔らかくなっていくのが本当によくわかる。ジャスミンの不思議な魅力がよく伝わる。コックスの絵は、ジャスミンをマリア像みたいに描いてたけど、うん、そう見えるのがわかる気がする。体型のせいもあるのか?笑
殺伐としてたバグダッド・カフェが、ジャスミンが加わることでイキイキしだす。この移り変わりが、なんとも見てて幸せな気分になる。
ラストのマジックショー、ブレンダの歌唱力に驚愕。めちゃくちゃ上手いやん。このマジックショーに、カタルシスが詰め込まれてる。
好き嫌いは別れる映画なのは間違いないけど、俺は好きだな。
あ、でもラストの謎のプロポーズシーン、あれは要らないんじゃないかな〜(笑)
女性向けカラフル映画
最初の1時間弱は、話が見えず、少しモヤッとするが、段々と話が展開するに連れて、惹かれていく作品でした。
調べて知るまで、ドイツ映画と気づきませんでした。
色彩が鮮やかで、登場人物の心が晴れてくると共に、その映像も色鮮やかになっていく感じがしました。
女性にぜひ観て欲しい作品。
全28件中、1~20件目を表示