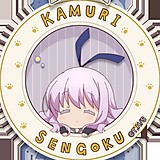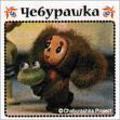真夏のオリオンのレビュー・感想・評価
全60件中、21~40件目を表示
悪い意味で美しい映画。
少し前に観ました。
私は戦争映画を娯楽として観れない部分があります。
個人的に、モヤモヤしました。
美しいです。悪い意味で。
北川景子も玉木宏もすごく綺麗です。
美しい役者に涙を誘う美しいストーリー。
そこそこ広めな潜水艦にイケメン達。
奇跡のような美しい結末。
本当に爽やかで美しい映画でした。
戦争映画とは思えないくらい。
暗いけれど悲壮感は無くて「戦争って、そんなに悪いもんでもないんじゃない?」みたいな声も聞こえてきそうです。
美しいものを創りたいなら戦争を題材にしなくても。。。と思ってしまいました。
もう一息
どうして、潜水艦乗りを選んだんですか?
映画「真夏のオリオン」(篠原哲雄監督)から。
同じ「太平洋戦争」の海軍の話なのに、
艦隊(船)、ゼロ戦(飛行機)とはまた一味違う、
潜水艦が舞台とあって、またまた違った視点で戦争を眺められた。
私が興味をもったのは、潜水艦長に若い医師が訊ねるシーン。
「どうして、潜水艦乗りを選んだんですか?」
「自由なんですよ」「自由?」
「潜水艦は、いったん海に出てしまえば、
自分の判断だけで行動ができるんです」
そうか、潜水艦の居場所が敵にわかってしまっては、
話にならないから、極力、本部とは連絡を取らないし、
そういう意味では、戦争中は上官の司令は絶対という、
軍隊ならではの縦の規律もあまり届かない世界と言えそうだ。
逆に言うと「全て自分の判断」がものをいうこととなる。
「艦長、潜航してから35時間です」という台詞は、
空気があと僅かしかありません、を意味し、
行動は自由だけれど、空気が吸えなくなる危険性もある。
戦争時の配属先って、どうやって決まるのだろうか。
もう少し、調べてみようかなぁ。
潜水艦ものにはずれなしというけれど
総合:45点
ストーリー: 45
キャスト: 40
演出: 30
ビジュアル: 65
音楽: 60
もう潜水艦のこととか海軍のこととか、本当に全然わかっていない人が脚本書いているんでしょう。設定や技術・時代背景の描写が現実無視して無茶苦茶でした。
・坊主頭が基本の日本海軍の兵士なのに、何故かみんな髪が長い。潜水艦なんか乗っていると汗だくになってシラミだらけになりますよ。
・自動追尾魚雷もなくて水上艦艇しか攻撃できない時代に、何故か潜行中の潜水艦同士が魚雷の打ち合いをする。
・最初の戦闘(最後の主な戦闘ではない)で何故か敵駆逐艦の目前で堂々と浮上し、敵は救助活動をしているから攻撃してこないと断言し、実際攻撃されない。
・アメリカ側が日本の潜水艦を見ただけで、それがたくさんある他の同型艦ではなく具体的にどの潜水艦か名前まで特定ができるだけでなく、その艦がどのような戦果をあげたのかまで実によく知っている(イ77が13隻沈めたと知っていた)。隠密兵器の潜水艦なのに、なんでそんなことがわかるの?
・戦闘状態の緊迫した状態で音を出せば発見されてしまうのに、何故か船員は大声を出したり音を出しっぱなし。
・何時間もお互い相手の位置を見失ったこう着状態なのに、何故かアクティブソナーが使用されっぱなしでピンガーの音が鳴り続けて自分の位置を暴露しているのに、それでも不思議とお互いを発見出来ない。
・爆雷を投下されているのに、何故か艦長は平気でソナーのヘッドセットを耳につけたまま。鼓膜破れるでしょう。
・一発当たれば駆逐艦など沈めてしまう強力な潜水艦搭載用魚雷を直撃されたアメリカ駆逐艦が、何故か沈むどころかまだ戦闘能力すら維持している。
ここまで無茶苦茶なことが次々に出てくると、こんなことがあるわけないだろうと呆れてしまい、見ていてどうも面白くありません。だからもう何もかもが嘘に見えてしまう。
それに攻撃されている命の危険のある恐怖状態において、何故か乗員たちに死線を彷徨う緊迫感がない。攻撃されて死を感じたときでも本来は敵のソナーに捕捉されないように声が出せないはずだが、そんな場面でもただ大声で叫びっぱなしによってそれを表そうとする。演技も下手な人が多い。君たち死ぬかもしれないんだぞという雰囲気がなくて、なんとなく平和な感じがする。せいぜいクラス対抗のサッカーの試合をやってるけど負けそうです、くらいの緊迫感しかない。これはもう演技の素人の芸人とかを配役したことの失敗でしょう。
艦長の決断といった物語性をとにかく重視しているのか、そのために戦闘や技術的な現実を無視して都合のいい話を無理やり作り上げている。
映画では潜水艦ものにはずれなしという格言があります。それは潜水艦がどういうものか、戦闘とはどういうものか、そのときの乗組員の心理はどういうものかを非常に現実的に描いているからです。この作品にはそれがない。まるでサッカーボールの代わりにバレーボールを使用して、手をつかってもハンドにならず、相手を殴ってもファールにならないサッカーの試合を、吹奏楽部の部員が演じている映画を見ているようなもの。だから例えば潜水艦映画の傑作「Uボート」とは全く比較になりません。
眼下の敵Part2
ナショジオで実際、似たような出来事があったことを知りました。
もし自分が同様の立場で艦に乗っていたら・・・主人公と同じように少しでもひろく判断できるかどうか・・・自分の感性に忠実に生きれるかどうか・・考えさせられました。そう生きたいが・・・なかなか修行が足りなくって。
終戦記念日には最高の映画の贈り物となりました。
個人的に潜水艦大好き人間でパッシブソナー音に痺れます。携帯も呼び出し音にしています。
φ(・_・。 )フムフム
太平洋戦争
海軍
と言えば玉砕と連想する映画が多い中
少し異色な感じがする作品でした
太平洋戦争末期の軍人と言えば
いかに散り花を咲かせるか
という勝手な印象があるのですが
あの時代にこのような「戦争」があったのだとしたら
まだ少しは救われたのかなぁなんて
思ったり 思わなかったり
テレビで放映されて見ました
戦争映画の転換期。
観る前までは、それほど期待していない作品だったので^^;
これはまだあとで良いか。なんて、先延ばしにしていた。
玉木宏を使っているあたりからして、ん?アイドル映画?
あるいは…コメディ?じゃないな、潜水艦映画だから…など
色々な憶測を持ったが、観終えてこれは私の好きなタイプだと
(出ている役者自体タイプですが)素直に観て良かったと思った。
まぁ洋画の…傑作「眼下の敵」とか「Uボート」などには、
(それを引き合いに出しては可哀相)叶わずとも健闘している。
なんで戦中映画なのに、みんなしてロン毛なのさ??という
(キムタクが決して髪型を変えずドラマに出るような)不具合を
指摘する旨もあるが、当時の乗組員たちはボサボサのロン毛。
とても散髪をする余裕などなかったそうだ。でも確かに、
潜水艦vs駆逐艦映画には、スッキリとした髪型の俳優が出る。
とりあえず今回は、私には目に余るほどの、ではなかった。
それともう一つ。
玉木君が艦長ってのは…ちょっと若すぎやしないかい?
という心配だったのだが、これがまたなかなかいい感じだった。
実社会でも、歳若い上司と年配の部下。というのは当たり前に
存在するし、優秀な人材が常に上に立つのは決して珍しくない。
(まぁ凄味には欠けるんだけど…)
そんなことよりも、常に艦長を信頼して従う部下と、部下を労う
艦長の人間性に清々しいものを感じたし、常に「飯にしよう」と
まるで永谷園のCMのように食べまくる豪快さに笑いが毀れた。
とはいえ、戦略となれば抜群の勘と指導力、一寸外せば、命に
かかわるという決断をする…という重要な立場をよく演じていた。
彼を取り巻く部下たちも好演していて、みんな素晴らしく、
なんか「男の仕事場」を見せてもらいました。という感じだった。
地上でのやり取りや、恋愛云々を出来るだけ排したのも良い。
せめて「真夏のオリオン」だけ、ロマンチックに掲げたのだろうか。
映画初出演の堂珍嘉邦、若手ベテランの平岡祐太・黄川田将也、
中年勢の吉田栄作、吹越満、益岡徹に加え、敵駆逐艦長の
D・ウィニングという俳優の目が良かった。艦長の頭脳攻略戦が
期せずして「終戦」を迎えた洋上でのラストシーン…。
戦争という凄まじい男の仕事を終えたあとの、男同士の視線の
交わし合いに、やっと終わったのだ。と安堵の気持ちが訪れた。
確かに戦争映画としては、キレイに描かれすぎ感が強いものの、
何をか云わんや。語ろうとすることはどの映画も同じなのである。
(回天の悲劇に対する「もったいない」には尊い意味があったのね)
日本の戦争映画の転機か?
日本映画における夏の風物詩ともいえる戦争映画だが、一貫したテーマは軍政府の愚かさだった。ところがこの作品、ある作戦行動に的を絞り、海上と海底を舞台にした駆け引きに焦点を当てている。史実に捕われない作品を作り上げた勇気がいい。これを機会に、もっと割り切った娯楽作品が生まれることを期待する。戦争の愚かさは、見る側が悟ればいい話。そろそろお仕着せはやめてほしい。
VFXはしょぼいが、作品としては見応えがあり、スコープ・サイズに意気込みを感じる。
カレーライスがうまそうだった。「おい、飯にしよう!」って食えるものがあると生きるための戦いにもなるが、食えるものがないとどこかの国みたいに自虐的な行動に出るんだな、きっと。
細かく見たら文句があるけど・・・
まったく期待せずに観たので予想外に良作だった。
戦争映画だと思うと、いかがかと思うし、艦長たちはもっと年配の方が、もしくは、
がっちりした俳優の方が内容的にいいような気もするし、
ヒロインはなんだか感情表現が乏しい気もしたし、細かい部分を言い出したらきりがない。
しかし、特に何の情報もなく、期待もせず観たためか、
一つの物語として、感動することが出来た。
また、観た後の余韻も心地よく、良い意味でじわじわと気持ちが暖かくなった。
脇役がすばらしい。
潜水艦って、重いんじゃないの?
全体的にスケールが小さく、ちまちましている。
玉木宏が潜水艦の艦長って、設定に無理があるような気がします。
若すぎて・・・。
太平洋戦争末期という設定になっていますが、「戦争をしている」という切迫感、悲壮感、緊張感がまったく伝わってこない。
細かいことですが、当時の海軍なんて言ったら、それこそ規律が厳しくて
上官にむかって話す時は「~であります!」と直立不動で答えるんじゃないの?命令されたら必ず「復唱」するんじゃないの?
艦長自ら「みんな、ありがとう」なんて軽い言葉吐くわけ?兵隊たちは、皆、坊主頭なんじゃないの?カレンダーに西暦なんて載せちゃっていいわけ?
この作品のどこにも琴線がくすぶられる部分はありませんでした。
SFX、ヴィジュアルエフェクト、船(潜水艦、敵艦等)のミニチュアの出来もお粗末。
撮影が、拙いセット内で行われているのがありあり・・・。
「オリオンよ・・・」のキーワードは一体誰に対して言っているの???
せっかくの映像化なのに・・・もったいない
何となく戦争ではなく、魚雷戦ゲームの印象
タンカー撃沈後、護衛艦の目の前で浮上する潜水艦があるのか。
しかも回天搭載艦。
タンカー乗員を救助中だから、こちらは撃たれないとする根拠がわからない。
船団の護衛艦が単艦で行動しているのも不思議ですが。
ピンポイントで伊77潜と爆雷攻撃による機関故障で海中に潜航したままの僚艦とモールス信号での交信はU-571のパクリ?これもあり得ないような気が・・・
潜水艦長の手記などによれば、潜望鏡の操作も迅速に上げ下げしないと潜望鏡の波きりで見つかるそうですが、そのような緊張感もなく、じっくり潜望鏡をのぞいていたりしていて、何とも緩慢な印象です。
原作は重巡洋艦インディアナポリス撃沈(日本海軍最後の大型艦撃沈戦果)に由来しているそうですが、普通にインディアナポリス撃沈話で良かったと思います。
実話でも、回天搭乗員の出撃希望の催促を無視して通常魚雷で撃沈しているそうで、映画でもそのようなシーンがあるものの、緊迫感がなく残念です。
実話の文章だけでも緊迫感が味わえるのに、せっかくの映像化でこの出来栄え。
伊77潜艦長の言葉にありますが実に「もったいない」。
大部分が潜水艦と駆逐艦のバトルになっている以上、もっと緊迫感が欲しかった。
ミッドウェイ海戦での伊168潜による空母ヨークタウン撃沈、魚雷攻撃後、相当な爆雷攻撃を受け、蓄電池の硫酸ガス発生などで修理後、決死の覚悟で浮上、命からがら逃げて来ている話もあることから、潜水艦が敵護衛艦の目前に浮上する演出は度し難い(悪天候下で潜るに潜れずという話もあったようですが)。
細かいことはあげつらいたくないですが、映画でも妙に細かい演出があったりしてますので、細部にこだわるなら徹底してもらいたかった。
最後に魚雷を命中させているのに、敵駆逐艦の損害軽微というのも納得いきません。
本来なら艦尾が吹き飛ぶほどの大破か撃沈のはず・・・・
全体的にファンタジックな戦争映画の印象です。
邦画ならしょうがないか・・・・
映画とは関係ないですが、佐藤和正著「艦長たちの太平洋戦争・艦長たちの太平洋戦争(続編)」の潜水艦長の話の方が当然リアルで緊迫感を感じます(インディアナポリス撃沈の伊58潜艦長の話も収録)。生死を分けて戦い、日本駆逐艦長宛に(日本側が)撃沈したと思っていた米潜水艦の艦長から手紙が届いたというエピソードもあったりして、いくらでもネタはありそうなもの・・・・
(映画の構成はこのエピソードに類似してますね)
真夏のオリオン
池上司氏の原作、また映画原作「真夏のオリオン」を読み、とても感動したので映像化を期待していましたが、なんか不完全燃焼でした。キャストにさほど問題はありませんでしたが、駆逐艦パーシバル、イー77の対決のシークエンスがなんか間延びして「手に汗にぎる」感じがしませんでた。名作「眼下の敵」を再現したかったようですが、ちょっと及びません。むしろ同じ福井作品なら前のローレライの樋口監督の演出のほうが良かったと思います。メキシコ海軍の実物駆逐艦を使用したのなら、ミニチュア、CGのパーシバルも使用しイー77との駆け引きにもっとスピード感と迫力をもってきたほうが良かったと思います。CGの爆雷攻撃のもっと迫力出せたと思います。回天を囮に使うのもなんか・・・間延びで、「してやったり」みたいな感じはしませんでした。こんなことなら原作通り敵は重巡インデアナポリスでも良かったかもしれませんね。キャストは良かったけど、とにかく戦闘シーンが不完全燃焼。これは演出と編集の問題なんでしょうか?まだプスプスして面白くないので一言書かせていただきました。
艦長と呼ぼう
玉木宏の艦長がカッコよかったです。主人は、艦長はもっと年配の落ち着いた役どころを期待していたみたいですが、逆に戦争末期のあの時期なら若い艦長になりますよね。
戦争映画の「男たちの大和」が動なら、「真夏のオリオン」は靜という感じがしました。一人一人が責任と誇りを持って行動していることに感動しました。戦争映画にありがちな、理不尽な命令や、やらされている感がなくて、命がけで働いているという感じ。「わたしは貝になりたい」のストーリーとすごくギャップを感じました。一方は、夫を助けたい一身で署名を集め、あだとなって処刑され、一方はたった一枚の楽譜が皆の命を救った。戦争の招くうねりのようなものを感じる。
戦争映画を観るたび、悲劇は繰り返してほしくないと思うし、今の平和に感謝したい気持ちになります。こんな気持ちを忘れないためにも、このような映画は残り続けるべきと思います。
戦争を全く知らない人たちのための戦争映画
いい意味でもよくない意味でも、
「戦争は遠くなったなぁ」と感じさせられた映画でした。
いまの60歳くらいの人たちが若いころ
「戦争を知らないこどもたち」といわれましたが、
30歳というのは、そのさらに子どもたちの世代
これは「戦争を全く知らない世代」を対象に書かれたドラマなのだ!
ということを確信した次第。
北川景子演じる倉本いずみは、祖父の倉本艦長(玉木宏)あてに届けられた
一枚の楽譜の意味を知りたくて、唯一の生き残りである
鈴木水雷員のもとを訪ねるところからこの物語ははじまります。
祖父の倉本艦長は激しい戦闘を生き残り、戦後も商船のしごとにつき、
祖母もいずみが小さい時は存命だった・・・なのに
いずみには、祖父の足跡がちょっとも知らされていなかったのです。
本篇にいく以前の時点で、
うーん・・と考え込んでしまいました。
戦争末期の日本不利な状況のなかで、なんと
13隻ものアメリカの軍艦を沈没させた軍功高き軍人だったのに、
そういうことって、たとえば父(倉本艦長の息子)をとおして、とか、
自分でしらべてみたりとか(資料はたくさんあるはず!)してもよさそうなのに、
楽譜がおくられてきてはじめて、祖父のことを知るなんて、
「おかしい」と思う反面、
「いやいや、こんなものなのかもね」とも思いなおしました。
太平洋末期の人間魚雷を搭載した潜水艦の映画は、
最近だけでも、「ローレライ」「出口のない海」と二本観ましたが、
潜水艦は、(セリフにもあったように)
そのつど指令を待たずに単独での判断ができる「自由」があること。
仲間をつぎつぎに失う、ということのないかわりに
作戦が失敗すれば、「一蓮托生」で、ともに命を失うこと。
など、閉鎖された空間の中での
シチュエーションドラマにつくりやすい設定なのですが、
この作品では、潜水艦の「外側」の映像も多かったです。
倉本艦長と米海軍駆逐艦スチュワート艦長との
おたがい相手の棋譜を読み合うような頭脳戦、
相手の裏をかく攻撃、人間魚雷回天の驚くべき使い方、など、
もともと戦略重視の原作でしたから、
船の位置や進路が重要になってくるわけです。
そのあたりはざすがに本を読むよりは分かりやすかったです。
イマドキの映画だから仕方ないんでしょうが、
戦争を経験した高齢者や
「戦争映画はこうでなきゃ」と思い込んでいる人にとっては
「ありえない映画」だと思います。
人間魚雷なんて究極の「自爆テロ」みたいなものですが、
当時だって人の命は大切だった、でもそれ以上に大切な
守るべきものがあると思っていたから
やむを得ず「回天」とか「特攻隊」が存在したわけです。
死ぬのも怖いし、死なれるのも辛いから、
美しさ潔さの装飾をして、「気持ちよく」送り出したわけです。
でも、このドラマでは、人間魚雷は「野蛮な兵器」で
(たしかにそうなんだけど)
倉本艦長はついに最後まで出撃命令をだすことはありませんでした。
今の感覚では、とってもまともです。
とにかく「戦争はよくない」メッセージが
現代の私たちの感覚で繰り返されています。
これからの戦争映画はみんなこうなっていくんでしょうか・・・
当時の艦長は、たいてい30歳前後と聞きますから、
キャストの実年齢とも近くけっして若すぎるキャスティングではないのですが、
さらさらヘアーの草食系男子ばかりのキャスティングにも違和感あり。
原作とは何もかもが違うので、いちいち指摘はしませんが、
つっこみどころはあちこちあって・・・
楽譜が敵艦の艦長の手にわたったのは「奇跡」だからいいとして、
海底何百メートルの潜水艦内のハーモニカの音が海上まできこえたり、
モールス信号や発光信号で伝わる情報多すぎっ!!
特に敵艦からの発光なんて、たぶん英語なのに、
「オリオンよ 愛する人を導け
帰り道を見失わないように・・」
なんて、光をピカピカするだけで、しゃべるスピードで伝わるなんて
なんなんでしょう・・・!?
私のメール打つ速さよりずっとずっと速いです。
敵といえどもお互いに敬意を払い、
終戦でノーサイドになったわけで、
攻撃をする必要もなくなった。
そこへもってきて、「真夏のオリオン」の詩は
このシーンにぴったりで、感動するポイントなんでしょうが、
あまりにご都合主義で、ちょっと冷静になっちゃいました。
全体的に、この映画、とても「おススメ」とは言えないのですが、
観終わってみると、玉木宏の倉本艦長像は、
むしろリアルかも?という気になりました。
たとえば「硫黄島からの手紙」の
栗林忠道中将も、(いろいろな資料でみるかぎり)
かなりおだやかな癒し系の人のようで、
渡辺謙のイメージじゃないんですよね。
食事の時間を大切にしたり、
極限状態でのおだやかな笑顔など、
有能な指揮官は、意外と玉木宏みたいな
ソフトな感じなのかもしれません。
玉木宏ファンなのに・・・
戦争映画は基本的に苦手である。だいたい観ようともしないことが多い。
でも、予告に惹かれて、「好きな玉木宏やし♪」と劇場へ。
予想以上に、頭は切れるは、人情には厚いわ、完璧な”いいひと”を いやみなく←ここポイント 好演してた宏さん。
堂珍さんに関しては、確かに演技うまくなかったけど、不器用そうなイメージもあったし、好演してるやん!と、思いました。それを言うなら北川景子、相変わらず、う~んだなぁ。ちょっとしか出てないにもかかわらず。イマイチ
機関士長の吉田栄作!!若い頃、イキっとたし、はっきりいって大嫌いだったのに(ハリウッド進出失敗当然!と思っていた。)
今回、むっちゃ良かった!!いぶし銀って感じの演技で、艦長に全幅の信頼を置く実直な技術屋を好演!ちょっと好きになってしまった。
彼も苦労して演技の幅が広がった!?
↑相変わらずな上から目線でした~それでも何回かほろっときて泣いてたりしてたんだけどね。いい映画でしたよん。
全60件中、21~40件目を表示