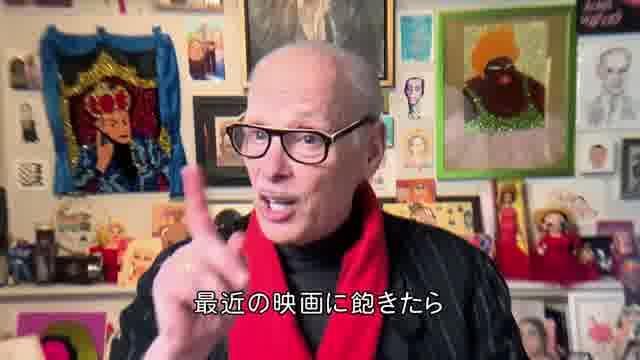「令和6年9月28日 新文芸坐「倒錯するカルト映画の世界」にて鑑賞②」マルチプル・マニアックス モアイさんの映画レビュー(感想・評価)
令和6年9月28日 新文芸坐「倒錯するカルト映画の世界」にて鑑賞②
令和6年9月28日 新文芸坐「倒錯するカルト映画の世界」の2本目。
この企画の上映作品は4作品。
「イレイザーヘッド」(77年)
「マルチプル・マニアックス」(70年)
「リキッド・スカイ」(82年)
「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」(68年)
本作の監督、ジョン・ウォーターズと彼の代表作「ピンク・フラミンゴ」(72年)の名前は知っていましたが実際に観た事はありません。過去に「セシル・B ザ・シネマ・ウォーズ」(00年)を見たハズですがもう内容も覚えていません。なので実質はじめて観るジョン・ウォーターズ監督作品です。
オープニングのスタッフロールが下から上へと流れていきます。ところがその流れるテンポがいささかイビツです。ほどなく、長い紙に書かれたスタッフロールをカメラか紙かを手で動かして撮影したものなのだろうと察します。誤字を修正するため上から貼り付けた紙に正しい綴りが書かれている箇所も散見されるのです…。
私もそれなりの数の低予算映画を観てきましたが本作はオープニングからその“低予算振り”の格の違いを見せつけきますので、緊張が高まります。
しかしこの映画はまごうことなきアメリカン・ニューシネマの一つです。保守的で排他的な既存社会に対してアダをなす主人公が悲劇的な結末を迎えるという様式に違いはありません。ただいくらアメリカン・ニューシネマが基本低予算だったとはいえ、本作の低予算振りは底抜けです。メインキャストはまだしもエキストラへの衣装や小道具含む演技指導のユルさを見るに若干開き直ってるフシまで感じるほど、あからさまに低予算です。
この作品の挑発的な姿勢や反骨精神を真に理解するためにはキリスト教文化圏で生まれ育った経験が必要なのだろうなという気がします。キリスト教的価値観で構成された社会特有の空気感を知らなければこの作品はイキリ中学生の露悪的な悪ふざけを見せつけられているという風にも受け取れるのです。
本作の主人公であるレディ・ディヴァインが教会でキリストの磔刑のくだりを暗唱しながらロザリオを用いての性交渉に悶えるシーンでは客席から笑いも起こりましたが、キリスト教社会の根底にある価値観にツバを吐いてみせるこの映画の破壊的なインパクトは、八百万の神々に囲まれて一本筋の通った教義もなく、都合のいい時に都合のいい神様を拝んでいるような のほほん とした宗教観の私のような一日本人には到底 真に感じ得ないものなのだろうと思うのです。
しかしそれでも主演のディヴァインの不思議な魅力が作品への興味を惹き付けます。
ルノワールの裸婦像の様な豊満な肢体を有するレディ・ディヴァイン。本作がモノクロ映画である事も相まって光を浴びる彼女の白い肌は美しく輝いています。そして大袈裟な演技と大仰な台詞を朗々と口にする様子が妙に印象に残るのです。
そんなディヴァインが率いる“変態一座”は自分たちのマイノリティな性的指向(嗜好)等を見世物として、人の出歯亀根性を刺激しながら集客し、集まった観客から金品を強奪して暮らしています。彼女らは犯罪者ですが、その行為は自分たちを排斥した既存社会に対する復讐行為なのかもしれません。
しかしその怒りに満ちた復讐行為はどんどんエスカレートしていき、映画の冒頭でディヴァインは観客の一人を銃殺してしまうのです。ディヴァインたちの話を聞くに、この冒頭の殺人以前にも既にいくつかの殺人を犯している事、ディヴァイン自身が次第にヒステリックに、過激になってきている事が伺えます。
殺人を犯してもなお苛立ちを募らせるディヴァインは恋人にもその苛立ちをぶつけます。もちろんディヴァインの恋人はそんな彼女に嫌気がさしており二人の口論は絶えません。しかしこの恋人は過去に犯した女優殺しの件でディヴァインに弱味を握られているためディヴァインから離れられません。やがて浮気相手と共謀してディヴァインの殺害を企てる恋人ですが、一方のディヴァインも恋人の浮気を知り、恋人を殺してやろうと怒りに燃えるのです。
ただディヴァインは浮気をされた怒りよりも殺しの口実が出来た事に喜び、高揚している様にも見えます。
たぶんディヴァインの怒りの起源は自身を理解せず排斥した既存社会であったろうにその怒りの矛先はいつの間にか身近な人間へと向けられているのです。あいつの態度が、言いぐさが、顔つきが気に入らない!という風に…。悲しいかな人が安寧と暮らすためには他人と形成する社会が必要なのに、人が抱くストレスの多くは他人に起因するのです。
行き当たりばったりの計画と加速する狂気により連鎖する殺人は、ディヴァイン自身の手により彼女がこの社会で生きる為の拠り所であったはずの自身の小さなコミュニティを崩壊させます。
己が心の内から湧きあがる怒りの赴くままに身内という名の他人を排斥したディヴァインは狂気の境地に至ったことを喜びます。怪物となった者だけが味わえる充足感と孤独を噛みしめるディヴァインの前に何の脈絡もなく現れる巨大な○○○○ーには面喰らいますが、もしかしたらそれは人が他人と生きていくために当然備え持つべき社会性の一切をかなぐり捨てて怪物と成ったディヴァインへ洗礼を施しに来た使者だったのかもしれません。
怪物と化したディヴァインは人間が文明と倫理観と協調性で作り上げた街へ繰り出し暴れまわります。究極にまで自己を優先するディヴァインという怪物を許容できるような社会は、当時はもちろん、今もなお存在しません。物語は至極当然な結末へと至ります―。
1960年代に愛と平和とを旗印にフリーセックス、フリードラッグをキめて既存の社会体制へ挑戦したヒッピーカルチャー。その終焉を象徴する事象の一つと言われるマンソンファミリーの連続殺人事件をこの映画はモチーフとしているそうです。マンソンファミリーの事件についてはそんな事がかつてあった程度にしか知らない私ですが、この映画はそういった制作当時の時代背景を越えてもっと普遍的な自己と他者(社会)との関係のジレンマを見せてくれている気がします。
開き直った低予算振り、悪ふざけが過ぎる演出に目先を囚われてしまいますが意外と社会性のある作品だと感じるのです。