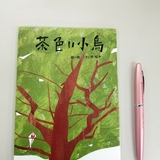ひまわり(1970)のレビュー・感想・評価
全111件中、1~20件目を表示
デ・シーカの故郷への思いが宿るメロドラマ
ナポリの海岸で奔放に愛し合うジョバンナとアントニオだったが、アントニオが戦争に奪われたことで暗転。そこから始まるドラマは、ロシアに従軍したまま戻らない夫を探して、イタリアから現地へと向かうジョバンナの過酷なロードに追随する。製作されたのは冷戦時代真っ只中の1970年。本作は史上初めて西側の撮影クルーが鉄のカーテンを潜って旧ソビエト連邦に分け入った作品として記録されている。つまり、多くの人々にとっては未知の大国だったソ連の赤の広場や、奈落の底へと続きそうな長く深いエスカレーターが、スクリーンを介して初めて眼前に現れるのだ。そして、モチーフとなる広大なひまわり畑は、ウクライナに実在する。ジョバンナとアントニオのような戦争に引き裂かれた人々を、太陽に向かって懸命に伸びようとするひまわりに擬えた、これは反戦のドラマ。しかし、社会の劇的な変化に翻弄される庶民に暖かい眼差しを向けるそのタッチは、監督のビットリオ・デ・シーカが初期に発表したイタリアン・ネオリアリズムと根底で繋がる。故郷へと思いが迸るが如く。そして、戦争を超えていこうとするジョバンナとアントニオは、コロナ禍から這い出し、新たな日常を模索する我々の仲間でもあるのだ。
曲だけはGood.
世界の片隅のジョバンナ
この音楽!
「終戦80年の8月15日に①〜ウクライナのひまわり畑」【追記あり】
毎年夏になると、お花屋さんの店頭にひまわりが並びます。
品種改良された「ゴッホのひまわり」や「モネのひまわり」という名前の、名画ソックリの小さなカワイイ花が楽しみです。
映画の『ひまわり』は、いつどこで観たか憶えていないのですが、どこまでも広がるひまわり畑、ソフィア・ローレンの瞳が哀しみを映す表情、そして美し過ぎるヘンリー・マンシーニの音楽が、切なく悲しかった記憶があります。
NHKの「映像の世紀 バタフライ・エフェクト」で、第二次世界大戦の独ソ戦の戦場になったウクライナを見ました。
両軍に繰り返し街を破壊され、食糧の穀物を最後の一粒まで強奪され、多くの戦死者や餓死者が出ていたことを知りました。
2022年2月にロシアのウクライナ侵攻が始まってから、映画のひまわり畑が実際にあることを知りました。
3年半が経った今年の夏も、あのひまわり畑には満開の美しいひまわりの花が咲いているのでしょうか…
8月15日の夜、地上波(関東ローカル)の放送で再鑑賞しました。
ひまわり畑の下に、ドイツ軍の命令でソ連兵やイタリア兵の遺体が埋められている場面があり、美しい映像と音楽の記憶に埋もれていた、戦争の描写に気付かされました。
※ひまわりの花言葉は「あなただけを見つめる」「何度生まれ変わってもあなたを愛する」。
✎____________
終戦80年の今年、戦争をテーマにした映画の公開が続きます。
『木の上の軍隊』『長崎 閃光の影で』『この世界の片隅に(再上映)』『雪風 YUKIKAZE』、『太陽の子(特別版)』『遠い山なみの光』『宝島』『ペリリュー 楽園のゲルニカ』、『あの星が降る丘で、また君と出会いたい。』…
8月15日にレビューを残しておきたいと思い、旧作から戦争映画の名作2本を選びました。
P.S.
靖国神社のそばに、「遊就館」という戦争記念館のような施設があります。
明治維新、日清・日露戦争、第二次世界大戦までの歴史、日本が開戦という選択肢を選ばざるを得なかった経緯が伝えられています。
銃弾や血痕の跡が残る軍服や装備品、零戦や回天、特攻兵の写真や手紙、展示の前で立ち尽くし語る言葉を失くします。
政治信条や思想とは別に、東京に来られる機会があれば足を運んでほしい場所です。
現代の価値観で歴史を裁くことは、愚かなことかもしれないと考えることもあります。
それでも毎年8月15日という日には、体験したことの無い「戦争」を振り返りたいと思います。
✎____________
映画館で鑑賞
BS・地上波で鑑賞
8月15日地上波で鑑賞
8月15日★★★★★評価
8月15日レビュー投稿
8月18日レビュータイトル編集
8月19日レビュー※追記
名作と名画
映画を物悲しさが包んでしまう
タイトルなし
第三回 新・午前十時の映画祭(2015/5/17)
午前十時の映画祭14(2024/12/21)
にて。
戦争が人にもたらす悲劇には人の数だけ様々な形があるのだと、この映画を観るたびに思う。
戦地に赴いた夫が戻らず、生死も分からない。単身でロシアの地に夫を探しに行くジョバンナ(ソフィア・ローレン)の執念に近い愛。
夫アントニオ(マルチェロ・マストロヤンニ)は、極寒の戦地で生死の境にいたところを現地の女マーシャ(リュドミラ・サベーリエワ)に救われ、終戦後もマーシャとその娘と暮らしていた。
当事者は誰も悪くない。戦争が引き起こした悲劇が、ときに人の心に邪気をもたらす。
戻らない息子を待つ老母。息子の痕跡を消そうとする嫁に憤るが、嫁から息子の現状を聞かされたとき、嫁への謝罪の思いよりも息子が生きていたことの安堵の方が強くても、責めることはできない。
アントニオはもう戻ってこないかもしれないと知りつつ、故郷へ送り出したマーシャの思いにも身がつまされる。
今この映画を観たときに、あの戦争が終わって平穏が訪れた当時のウクライナ地方のひまわり畑の風景に、現在はどんな状況なのだろうと、思いを馳せずにはいられない。
ソ連が全面協力して製作された本作(イタリア・ソ連・アメリカ・フランスの合作)だが、当然のようにソ連側の様々な要求や制約があり、揉め事もあったようだ。
とはいえ、ロケが行われた現地では、イタリアの世界的スターを迎えて歓迎ムードに盛り上がる中で撮影が行われたという。
映画(スター)には、イデオロギーの対立を封印させる力があるのだ。
余談…
ミラノ中央駅のホームから見える看板は「Olivetti」ではないだろうか。当時はイタリアの代表的な企業だった。一時期は日本法人もあり、アップルに引けを取らない美しいパソコンを発売していた。
さらなる余談…
ソフィア・ローレンは日本でも認知度は高かく人気もあったが、この映画が公開されたときの日本では、リュドミラ・サベーリエワが話題をさらったらしい。
ロシア人女性の透き通るような美しさに、当時の日本男子が魅了されたことは想像に難くない。
エロシーン要らないな
激しく強く愛した二人
ソフィア‼️❓ローレンローレンローレン‼️❓
2024年ラスト
面白かった
ソ連ロケ部分がもの凄い。厳しい監視や制限の中で撮ったのだろうが、都市と自然、そしてものすごい数の人、人、人が画面に溢れる映像に圧倒された。初見をスクリーンで見られてよかった。
あらすじはザ・メロドラマで、かなりざっくりと豪快に展開していくので随所にツッコミを入れつつ見ていくことになる。二人の俳優、特にソフィア・ローレンの、表情一発で説得力を生む演技があればこそ、このスケールで2時間未満という現代映画では到底不可能な短尺に収まっていると言える。余計な説明がなくとも背後の感情の機微を感じさせるスタアの力というか。マストロヤンニの前半、隠そうともしないスケベ男っぷりからの後半の落差も素晴らしい。
戦争とは、、、という重たい部分もありながら、王道のすれ違いモノをパーティームービー的に楽しむ見方が相応しいのでは、と思ってしまった。今のご時世では不謹慎だが。
一面に広がる墓地と、一面に広がるひまわりの対比が印象的。 お決まり...
ひまわりは墓標 行方不明者を訪ねてロシアまで行った一人の女のはなし。
ひまわりは墓標だ。
死ななかったアントニオ=マルチェロ・マストロヤンニも
この凍土に立つ卒塔婆の根元に、かつての結婚を生き埋めに葬ったのだと思う。
けれどひまわりは戦火を超えて、永遠に太陽を見つめてその顔を上げるのではないか。
ソフィア・ローレンがひまわりだ。
短くしか映らないが、「スチール写真」として我々の目に焼き付けられているあの写真 =駅での女たちの顔。真ん中で写真を持つジョバンナ。
屍の大地で、そしてミラノの駅で、負けじと咲く女たちの花が、
その顔・顔・顔 が、
引き裂かれた者の悲しみをば胸元に掲げて、そこに咲いているのだと思う。
・・・・・・・・・・・・・
WWⅡにおける、ソ連での軍民の戦死者数は、最多の2,700万人。
そこにはロシア国内で戦死した外国からの兵士の数は含まれていない。
日本と、イタリアと、ナチスドイツは
三国同盟を結んで全世界=連合国側と戦争をした。
その第二次大戦では、総勢で 5,500万人が死んだのだそうだが、
イメージが沸かないこの数字だ。
イメージが沸かない我々のためにこんなYoutubeを作った人がいる⇒
【 Number of deaths in the WW2 per country 】(=第二次世界大戦における各国の死者数) という動画。
イタリア 514,000人
ロシア 27,000 000人
そして
アントニオが徴兵忌避したアフリカ戦線でも、実は知らなかったが、その動画を見るがよい。信じられない数の戦死者だ。
アフリカのほうが のんびりと駐留できて助かったのでは?と呑気に想像したが、そこでの死者の数には震撼する。
・・・・・・・・・・・・・
「ヒマワリ」
小学1年生がタネを蒔くのはアサガオ。そして2年生になると誰にでも簡単に育てられたのが「ヒマワリ」だった。
幼稚園では何を植えたか覚えて居られるか? お百姓さんの畑で、しゃもじを使ってサツマイモを掘ったあの楽しい思い出。
沖縄戦のあとには土が肥えて、沖縄の畑では大きなサツマイモがゴロンゴロンと穫れたんだそうだ。悲しいお芋だ。
ヒロシマやナガサキではどうだったんだろうか。
ウクライナのヒマワリ畑や麦の穀倉地帯では?
中国や亜細亜の各地では・・?
レビューしていてふと思い出した。
僕は小学校〜中学校と「学校の先生って女性専門の仕事なのだ」と思っていた。学校には男の先生がいなかったのだ。だから初めて男の先生を見たときには慣れていないので本当にびっくりしてしまった。
戦争でみんな死んだから、だから街に大人の男がいなかったわけだね・・
戦死者の数だけ、遺族と寡婦がいたわけで。
そして、うちの会社には「中国残留日本人の孫」が渡日して、いっとき片言の日本語で働いていた。
そうなのだ、
ミラノの駅や舞鶴の港では、いまだ待ち続ける女たちが、世界中に居るという事だ。
映画のエキストラの女たちは、みな本物の遺族の目。そして待ち続ける妻や母たちの目をしていた。
・・・・・・・・・・・・・
1970年
終戦から25年目のイタリアでの製作
監督ビットリオ・デ・シーカ
107分
本作、
ちゃんと鑑賞したのは今回が初。
名優マストロヤンニとソフィア・ローレンは言わずもがな。
あの義母と、ロシアの妻の、得も言われぬ悲しみの眼差しには
僕は胸が潰れそうだった。
やっぱり名作
40年ぐらい前に、テレビで偶然見て、見終わってすぐに立ち上がれず。その後もソフトを買ってみていましたが、午前十時というやつで上映ということで、初めて映画館で見ました。
前半の、見ているこちらが恥ずかしくなるぐらいのイチャイチャが、その後に効いてきますね。
ひまわり畑も小麦畑も、その下には戦争で犠牲になった人がまだ埋まっている、というセリフがありましたが、ウクライナでロケしたというひまわり畑に、更に埋まってしまう人が増えないことを祈るばかりです。
デジタルリマスターということで、どこまで修正されているのか分かりませんが、画質は確かにノイズもなくなめらかなものの、音、特に高音がビリビリしていて、映画館の音量が大きいこともありますが、せっかく盛り上がるテーマ曲が、聞きづらかったです。
全111件中、1~20件目を表示