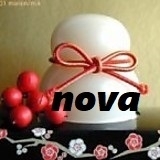地獄の黙示録のレビュー・感想・評価
全53件中、1~20件目を表示
SF映画にすればよかった
そうすれば戦争を風刺した、とてもエンターテイメントな映画になったことだろう。まじにベトナム戦争を使っちゃったから。エンターテイメントなのかエンタメ風の反戦映画なのか?なんなのかよくわからないものに仕上がってしまった。それはそれでいいのかもしれない。が、しかし、テーマからしてエンターテイメントとして受け入れることができず、私の心の整理がつかないことになっている。あるいはそれが狙いの映画だったか・・・
まだ中3だったが一人で劇場に観に行った
酷い内容
一皮剥けば、みんな「野蛮人」〜
CGやVFXの無い時代に、
本当にやっちゃった!づくしの映画で
なんという無茶なことをするんだ!!
森を丸ごと燃やしちゃうし
本物の牛を長回しで首跳ねちゃうし〜〜
怖い怖い〜〜
最後も難しい〜〜
そしてある意味悲しい〜〜
「野蛮人」なんて誰に向かって言えるだろうか??
人間なんか一皮剥けば、みんな同じ「野蛮人」だよな〜〜
でも、こういうとんでもない映画を
時々人は作っちゃうから凄いと言うのか、
モノを作る人の狂気って
映画の中の主人公と同化してしまうんだね〜〜
この映画がその後の作品に与えた影響の数々を思うと
一回は映画館で見ておくべき映画でしょうね。
「キングコング:髑髏島の巨神」なんか
この映画を観てからだったらもっと楽しめたと思う。
思い出しても、ゾクゾクするわ〜〜
@もう一度観るなら?
「キツイかな〜、無料ならチラ見程度で」
テーマは理性と狂気の境目はどこか 川登りをしていく過程で戦争の無意...
恐怖の回想
感想
アメリカの威信が大きく失墜した戦争、それはベトナム戦争である。アメリカ参戦の理由は国家の利権拡大と、防共有きのイデオロギーの拡大であった為、戦争の意義を最初から国民は見出すことが出来なかった。当時、アメリカは男性の皆徴兵制を牽いていた。
戦争の始まりは古く、フランス植民地復権をかけた、第二世界大戦後のインドシナ紛争まで遡る。
1954年フランス撤退後、ベトナムは南北に分裂。アメリカが極めてほぼ内政干渉に近い形で南ベトナム共和国を樹立、この頃より、軍産複合体が議会、政府に働きかけ、積極的に財政的軍事的支援を強化して行った。
1961年、JFKが大統領になり、派兵数は1万5千人を超える。人道的な面から一旦ベトナムからの一時撤退を画策するが、1963年、テキサス州ダラスで遊説途中に暗殺。それ以降、政府(大統領?)は軍産複合体と結託し、軍は増派の一途をたどる。最大派兵人数は約55万人にのぼり、1975年に撤退するまでに約5万8千人の戦死者を出した。
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
映画は特殊任務をベトナムで遂行している、アメリカ軍人の男の視点で物語か進んでいく。サイゴンのホテルの一室で任務の指令を待つ男。薬物中毒者のように挙動が明らかにおかしい。この時点で精神的に病んでいるという事がよくわかる。男の名はウィラード。
何日か経過し、ある日突然、ニャンチャンに置かれているアメリカ陸軍情報本部に出頭命令が来る。そこで下された指令はカーツという元アメリカ軍人を抹殺しろという指令であった。罪状は殺人。元は優秀な軍人であったが、ベトナムの地で特殊部隊に入ってから精神に異常をきたし、カンボジアの奥地で彼の事を神と崇める現地人の軍団を率いて、絶対服従を誓う彼らを意のままに動かしている。さらに数人のアメリカ軍の現地人スパイを二重スパイと決めつけ独断で処刑したという。
東南アジアの戦闘中の異国で、ベトナム人を殺した罪でアメリカ人を殺すという異常な秘密指令に、ウィラードは戦慄する。また情報本部の司令官たちはアメリカ人が常軌を逸して自分を神として行動しているカーツを人としていささかの容赦の余地もない人間なので秘密裏に殺せと断罪する。ここから、ウィラードの地獄への本当の旅がはじまる。
メコン川を特殊艇で遡り、途中、第一航空騎兵団に護送を依頼、さらに分岐点の奥のヌン川に入り更に上流のカンボジアに入りカーツの王国を目指す。
その間、カーツの経歴書に目を通すウィラード。そこには栄光に彩られた数々の叙勲が記され、完璧すぎる見事な経歴に困惑の度合いがさらに深まる。しかし、資料を読み終わる頃にはカーツが殺したベトナム人スパイは北に加担していた、本当の二重スパイである事が判明してくる。罪人告発は不当であり、正しい事をした人間を抹殺しようとしている事に気がつく。
特殊艇は分岐点のド・ラン橋まで進んでいく。それまでにウィラードは地獄に生きる様々な人間の姿と行動を様々な場面で目撃していく。
ヘリコプターでベトコンの主要地区を空襲、森をナパーム弾で焼き尽くす。
航空騎兵団隊長のキルゴアは言う。
朝のナパーム弾の焼き尽くすガソリンの匂いは格別だ。焼かれた跡には何も無い。ただガソリンの匂いと黒焦げの地肌があるだけ。そこで勝利を確信するのだ。と。
戦場という地獄で命懸けで生きる彼等は皆、外見はまともに見えても心の中の真実と脳内は全て破壊されていて、まともな考え方はできない。全てがまともなようで実は異常なのだ。全ての行動が、狂っているのだと気付いていく。
キルゴアは言う。この戦争もいつかは終わるー。
しかし、ウィラードは独白する。
たしかに、戦争は終わる。だが、戦争が終わって故郷に帰っても、もう元の故郷はないのだ。
俺は知っているー。
地獄からは誰も生身では生還出来ない事をー。
キルゴアの異常性が許され、カーツが責められるのか。狂気と殺人が理由?この場所(戦場)には狂気と殺人は有り余るほどある。
ド・ラン橋では、誰もが現実逃避のため、麻薬を使用しており、意識が朦朧として、指揮官も不明、誰が何処で誰と戦っているのかもわからない混沌とした国境守備の場所であった。
特殊艇はさらに河を遡る途中、現地民族、ベトコンさらには南ベトナム人、恐らく何人かのアメリカ人をも殺害したと思われる頑なに自分達の利権の領有を主張する、フランス人入植者の一団に出会う。今では時代遅れとなった植民地主義の終焉をウィラードはあらためて目撃する。
途中、ベトコンやカーツの王国の一員と思われる集団の襲撃を受けて、グリーンとチーフが命を落とす。それでもウィラードは任務を遂行し、カーツの支配する王国についに到着し、ついにカーツ本人に出会う。
カーツはウィラードが来ることは既に察知していた。ウィラードは暫く囚われの身であったが、死にかけたところを介抱され、一命を取り留め、放任される。カーツは自分が創った王国に自分自身嫌気がさし、潔く名誉の口実と共に死ねる機会を探していたのだ。この世界に生き続けることが恐怖であるという。ウィラードは逃走する事もできたが、最後には彼の希望通り(名誉の戦死、または予言の通り)、カーツをバイラムの祭事の夜に牛刀で殺害する。
その行動そのものが最たる恐怖であった。
カーツが残した書類の中に、『私が死んだらこの場所を爆撃で破壊しろ』という走り書きを発見する。望みのままウィラードは爆撃依頼の無線連絡をしてランスと特殊艇でその場を離れる。暫くして辺りは猛烈な炎と火柱が立ち、地獄の様相を呈し物語は終焉を迎える。
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
実質的に北ベトナムに敗北した事により、アメリカの世論は大きく変わり、国民も自信を喪失、黒人公民権運動、ヒッピームーブメント等、文化にも大きな影響を与え、様変わりしていった。
アメリカ映画も御多分に洩れず、アメリカンニューシネマムーブメントがベトナム戦争をきっかけとして学生運動を展開していた人々やヒッピー達にに支持され、アンチヒーロー、ヒール、アンハッピーエンド、不条理な結末、といったストーリー展開が持て囃された。
1970年代初頭までは大手の映画会社はムーブメントを無視、ロジャーコーマン(B級映画の帝王。自分史的にはB級SF映画の神様である。)などの独立系の映画会社で新進でキャリアを磨いていたマーティン・スコセッシ(タクシードライバー)やコッポラ達は制作費捻出に苦労したが、コーマンが映画会社、あるいはスポンサーに掛け合い資金を自身で調達したというトリビアがある。
本作はアメリカンニューシネマムーブメントの最後かつ最大の製作費をかけた映画で、監督のコッポラはゴットファーザー三部作を監督し、巨額の収入と名誉を得たが、その後に、国民感情的にも、政府にも、精神破壊と世界のリーダーたる威信を大きく失い、低迷したアメリカの悲劇を描くために、そのほぼ全額を様々な理由で撮影、制作が難航した本作に投入したとされる。それでも総製作費の半分程度にしかならなかった。残りは配給元のユナイトとヘラルド(主に日本ヘラルド)が出資したという。
本作は1979年に完成、世界公開されたが、公開当時はまだ様々な戦争の余波が残っていた頃で、余りの生々しい描写が賛美両論であった。時が経過して現在は概ね批評家の間では高評価を得ている。
映画は世界的ヒットを記録。製作費は回収され収益が出たのち、撮り貯めたフィルムで全長版や、特別編集版が制作された。
日本政府、日本人はベトナム戦争に関しては基本的に傍観者の立場で見ていた。ヒステリックな左翼は騒いでいたが、戦争のショックはアメリカ人ほどはは強くなかったであろう。人間のエゴや愚かさがよく反映された反面教師的な映画である。困難に逢いながら、創り上げた監督とスタッフを賞賛する。◎
脚本・配役◎
名匠ジョン・ミリアスがクレジットされている。元となった原作の映画化の版権はジョージ・ルーカスとジョン・ミリアスが所有していたとされる。配役も超大物から、ほぼ無名の若手俳優として出演、後に大スターになった方もいて面白い。
1980年3月にテアトル東京で初版を鑑賞。その後も追補版が出る度、TV放映する度に鑑賞。観る年齢により感想が変化する作品。
⭐️4.5
単純明快
朝のナパーム弾の香りは格別だ
ベトナム戦争の狂気を描いたという点ではマイケル・チミノ監督の「ディア・ハンター」と並ぶ金字塔‼️この作品は撮影中の様々なトラブルから伝説に包まれたような作品で、キャスティングの難航、台風直撃、アメリカ軍の協力拒否、長期のフィリピンロケによる病気の蔓延、私財を投じたコッポラ監督の破産など、そのあまりのパニックぶりは本編と同じくらい有名なメイキング「ハート・オブ・ダークネス」が製作されたほどで、そちらも必見の作品になってます。その撮影中の数限りない障害が、映画に異様なまでの迫力をもたらしており、ワーグナーの「ワルキューレの騎行」をバックにしたヘリ部隊の襲撃や、ドアーズの「ジ・エンド」を暗殺シーンに使用したりと、コッポラ監督の天才的なセンスが冴え渡って、一瞬たりとも目が離せません‼️映画史上No.1の呼び声高いあの作品に続くコッポラ監督とマーロン・ブランドのコンビぶりも素晴らしいのですが、それを凌ぐ圧倒的な存在感を示したのがキルゴア中佐を演じるロバート・デュバル‼️ベトナム戦争の狂気を体現したこのキャラクターのセリフ "朝のナパーム弾の香りは格別だ" は映画の歴史に残ると思うし、爆撃中、他の兵士全員が地面に伏せている中、ひとりで仁王立ちしているシーンとか、あまりにインパクトが凄すぎて夢に出てきそうです‼️出てきました、実際‼️ちなみに前述のキャスティングの難航では当初、マーティン・シーンの役にクリント・イーストウッド、マーロン・ブランド演じるカーツ大佐にスティーヴ・マックィーンが交渉されてたみたいです。今にしてみればマーティン・シーンとマーロン・ブランド以外考えられませんが、ひょっとするとマックイーンとイーストウッドの初共演が実現していたかもと思うと、何ともいたたまれない気持ちです‼️そういう逸話も含めてハリウッドの伝説と化した作品です‼️必見‼️
やや尻すぼみ
原爆経験後の戦争で「恐怖だ」は寝惚けた話
1 映画の手法と内容について
立花隆「解読『地獄の黙示録』」によれば、この映画は手法が従来の映画とは異なっており、ハリウッド式の巨額な予算を投じた”私的実験映画”だという。
その手法とはT・S・エリオットが「荒地」で用いた手法と同様、過去の文化的創造物の素材をモザイクのように配置し、それぞれの素材の持つ象徴的意味の関連によりストーリーと主張を語らせるものであり、素材を知らなければ理解できない。つまりコンラッドの「闇の奥」、エリオットの一連の詩、聖杯伝説、フレイザーの「金枝篇」、そしてドアーズ「ジ・エンド」を知る必要がある。
そのシンボルにより解読してみると、本作はベトナム戦争を批判し、戦争のない世界のヴィジョンを示すことにテーマがある。
戦争に関わる人間は、殺戮本能を発揮させる狂人とならざるを得ず、冷静に顧みるならそこには恐怖しかない。偽善的な米軍とは異なり、本能のままに殺戮を実行した結果、自分の王国を構築したカーツは、戦争の生み出した典型的人間である。
戦争の論理の行き着く先を見届けたウイラードは戦争を止めるために、もはや米軍の指令とは関わりなく自らの意志で戦争人間の殺害を決断。王殺しの象徴的儀式を通じてカーツの地位を引き継いだうえ、殺戮を放棄するため武器を捨て王国の民も従う。そこに象徴としての再生の雨が降り注ぐ…というストーリーになる。
立花は日本におけるこの映画を巡る論争を批判し、「前半のリアルな部分と後半のシンボリックな部分との区別ができていない根本的に無理解な議論」があまりに多いと述べる。
その上で、区分を理解しても「既成の映画文法の上にたって彼の実験的部分を失敗と批判」する人と、「その部分を映画の新しい可能性を開いたとして賞讃」する人に分かれ、自分は後者に属すると分析する。
2 コンラッドの原作を中心とした私的解読
この映画の手法そのものに関しては面白いと思う。しかし、そこでシンボルに使われた素材の中心となるコンラッド作品が、悲しいかな19世紀的古さなのである。
「闇の奥」は英国の作家コンラッドが1899年に発表した小説。アフリカのベルギー領コンゴ自由国を舞台に、一人の超人的会社員クルツが原住民を手なずけて当時の富の象徴となる象牙を独占したうえ、神のような権威を得るという話である。
そして、彼の末期の言葉が「恐怖だ。恐怖」というもので、映画はそれを利用している。(字幕では「地獄だ。地獄の恐怖だ」などという無意味な誤訳が使用されているが)
この小説が発表された当時、時代思潮は楽天的な啓蒙、進歩主義で、コンラッドはこれに対し「進歩の大義を掲げる連中」などと罵倒しつつ本作を書いた。そしてクルツの末期の言葉は、進歩主義の夢に耽りながら全世界を植民地化し、原住民を奴隷扱いしている帝国主義と欧州人の心の闇を暴き、糾弾する意味合いがある。
それを「『ゴッドファーザー』は米国帝国主義のメタファー」とうそぶくコッポラが、ベトナムにおける帝国主義戦争批判に使うのも自然と言えば自然な話だ。
しかし、もはや時代が全然違っていた。世界はコンラッドの頃から2つの世界大戦を経験し、人類の悲惨さは作家の想像力などを遥かに超え、現実が描きつくしているではないか。
原爆を「野蛮な黄色人種の国」(そう考えたと俺は想像する)日本に2発もぶち込んだ米国人に向かって、マーロン・ブランドが「恐怖だ。恐怖」と言ったって、観客は「何を今さら」と苦笑するしかないのである。あんた、トルーマンを普通の人間だと思ってるんだろ? その普通の人間が原爆の投下命令を下したんじゃねえか、と。
したがって、その狂気の戦争人間をマーチン・シーンが殺戮し、王位を承継して武器を捨てたら王国民も武器を捨てるシーン(戦争のない世界のヴィジョンの提示)に至っては、説得力がまったくない。
そんなものより、キルゴア中佐が「ワルキューレの騎行」をバックにベトナムの村落を破壊しつくす前半部分の方が遥かにメッセージ性が高く、本作は稀に見る痛快戦争アクション巨編として記憶されると思われる。皮肉としかいいようがない。
補足)雨の〈再生のシンボル〉としての不成立について
雨は、転機や再生のシンボルとされている。現にエリオットの「荒地」では、「ここは岩ばかりで水がない 岩があって水がないあの砂地」「ガンガ河は底が見え、うなだれていた木の葉は 遠くヒマラヤ山に暗雲がかかるまで 雨を待つのだ」と、乾いた不毛な土地に生命をもたらすものとして雨が使用されている。
「地獄の黙示録」でも最後に雨が降り出し、それが再生のシンボルとみられることを意図しているようなのだが、はたしてそのシンボルは成り立つのだろうか?
年間降水量は米国715mmに対し、カンボジア1904mm、ベトナム1821mmと倍以上である。ベトナム戦争では雨季に悩まされた体験が様々な反戦映画で描かれている。雨は恵みの雨というより、安楽を脅かすものなのだ。
だからラストシーンの降雨には、一般の観衆は何の意味も感じ取ることができない。ということは、雨の再生としてのシンボルは成立していないということである。
毒性はかなり強い映画
【あらすじ】
ベトナム戦争の中、失踪し奥地で現地人の国を作った大佐への殺害命令を受けた大尉の物語。
舟で戦地を進む中で、軍紀や統制が失われた殺戮や、正義のない戦争の矛盾等、戦地の異常な状況を見ていく大尉は、徐々に大佐への共感を感じていき。。。
【感想】
ベトナム戦争の異常さと、人が壊れていく怖さを通して、米国・米軍の不条理を弾劾する作品です。
毒性はかなり強い映画ですが、戦争映画として、アクションとドラマの両面で面白さが際立っています。
ラストに向けて現実が崩れていく世界観も秀逸でした。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ブログの方では、ネタバレありで個人感想の詳細とネット上での評判等を纏めています。
興味を持って頂けたら、プロフィールから見て頂けると嬉しいです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
地獄のクルージング
【作品自体の度外れた異様な世界観と、公開直後酷評されながらも今や20世紀を代表する映画になっている事実とともに、今作制作時のフランシス・コッポラが40歳だった事にも驚嘆する作品。】
ー 映画を愛する者であれば、今作を数度は鑑賞している前提でレビューする。ー
・原題:"APOCALYPSE NOW"
敢えて訳せば、”隠された真理の開示は、今”といったところだろうか?
・505大隊、173空挺所属、特殊工作員ウィラード大尉(マーチン・シーン)はサイゴンの気怠い暑さの中、ホテルで白いシーツの上で空虚な眼をして寝転がっている。傍らには飲みかけの”マーテル”の壜。
・そんな彼に、任務が告げられる。
それは、第5特殊部隊の作戦将校であり、祖父・父ともにウエストポイント士官学校を卒業し、”その男”も同校を首席で卒業し、朝鮮戦争時の戦歴を含め、軍部の最高幹部となるべき人物、ウォルター・E・カーツ(マーロン・ブランド)の殺害である・・。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今作上映までの過程も人口に膾炙していると思われるが、一応記載する。
・1976年3月20日から製作が始まった今作は、1200万ドルの予算で120日で終わるはずだったが、結果としては、540日の撮影期間、3100万ドルをかけて完成した。
コッポラは、”ゴッドファーザー”で得た利益を全て次ぎ込み、更に全財産を”抵当に入れ”それでも足らない制作資金を世界中に協力を仰ぎながら、作り上げた。
重ねて言うが、この所業を彼は40歳で行ったのである。信じ難い・・。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・オープニングの気怠いホテルの風景から、一気に場面はキルゴア中佐(ロバート・デュバル)率いる空軍騎兵隊第一中隊駐屯地に移る。
・キルゴア中佐は(この時点で、この映画の狂気性の片鱗が伺えるのだが・・)、ウィラード大尉が連れてきたランス・ジョンソン(サーフィンの名手らしい:サム・ボトムス)に気付き、”ランス・ジョンソンか!、ランスにサーフィンをさせよ!”と銃弾が飛び交う中、上着を脱ぎ棄て叫ぶ。
・そして、ベトコンが潜む村に数千発のナパーム弾を撃ち込む。後方援護はファントム・ジェット機。
炎を上げるベトナムの村の地獄絵図。
そして大音量で響き渡るワーグナーの”ワルキューレの騎行”
・静かなオープニングからの、この強烈な場面は何度観ても米軍のそして、この映画が孕む狂気に息を飲む。(ちなみに、このシーンはCGではない・・。)
・その後、ウィラード大尉は部下を引き連れ川を遡上していくが、途中で遭遇する”ラスベガス:ヘリコプターから降りて来るバニー・ガールたち”(目がクラクラする・・。何を観させられているのか、自問自答する力も無くなっている。。)
及び、怪しきヒッピー風体の、カーツを信奉するカメラマン(デニス・ホッパー)。
・そして、生首があらゆるところに曝されたカーツ王国に到着するウィラード大尉。
”神”と呼ばれるカーツ大尉との対面。
ー 学生時代、名画座で観て以来、この映画を何度観た事か。ー
・流れる”THE DOORS"の”THE END"の今作との見事なシンクロニシティ・・。
■最後に、この映画に対する黒沢明監督のコメントを記す。
<この映画は難解ではない。
これまでの映画の表現を数歩踏み越えた、勇猛でエネルギッシュな表現が掴んで見せた面白さがある。・・・・。
恐怖は人間を支配し、異常な状態に追い込む。
戦場で人間が異常に勇敢になるものも、残虐になるのも、また奇妙な事に熱中するのも、全て恐怖から逃避するためだ。
恐怖から逃れるためには、人間は何を考え何をするかわからない。
戦場は地獄だから怖いのではない。
戦場では、時に地獄は天国に見えるから怖いのだ。
そういう人間というものが怖いのだ。>
<2002年 劇場にて鑑賞 その後、幾度となく鑑賞。>
一皮剥けば、みんな「野蛮人」〜
CGやVFXの無い時代に、
本当にやっちゃった!づくしの映画で
なんという無茶なことをするんだ!!
森を丸ごと燃やしちゃうし
本物の牛を長回しで首跳ねちゃうし〜〜
怖い怖い〜〜
最後も難しい〜〜
そしてある意味悲しい〜〜
「野蛮人」なんて誰に向かって言えるだろうか??
人間なんか一皮剥けば、みんな同じ「野蛮人」だよな〜〜
でも、こういうとんでもない映画を
時々人は作っちゃうから凄いと言うのか、
モノを作る人の狂気って
映画の中の主人公と同化してしまうんだね〜〜
この映画がその後の作品に与えた影響の数々を思うと
一回は映画館で見ておくべき映画でしょうね。
「キングコング:髑髏島の巨神」なんか
この映画を観てからだったらもっと楽しめたと思う。
思い出しても、ゾクゾクするわ〜〜
@もう一度観るなら?
「キツイかな〜、無料ならチラ見程度で」
全53件中、1~20件目を表示