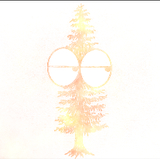野獣死すべし(1980/村川透監督)のレビュー・感想・評価
全31件中、1~20件目を表示
松田優作じゃなきゃダメなのだ、わかるか!?
2022年、「角川映画祭」で鑑賞。
先に『人間の証明』を観て、松田優作のカッコよさ、素晴らしさにあらためて気づいたので、優作さんを観るために、そしてわが思春期ど真ん中の80年代の懐かしさにひたるために映画館に足を運んだ。
そんなわけで40数年ぶりに観たけれど、いやぁ~面白かった。
むかし観たとき、当時、僕は中学生だったが、そのときよりも面白く感じたかもしれない(ちょっと、人、殺しすぎだな、と思ったけれど)。
考えてみると、凄絶な戦場体験と、現金強奪を目的とした大量殺人との因果関係に説得力がないなど、ストーリーにも腑に落ちないところがあるのだが……。
まあそれはそれとして、やっぱり松田優作はすごい。カッコよすぎる。すごすぎる。
あの演技は完全に憑依だな。もうあんな役者は出てこないだろう。鹿賀丈史もぶっ飛んだ演技をしているけれど、やっぱり優作さんには、かなわないと思う。
しかし、この映画、松田優作じゃなかったらどうだろう? おそらく、この異様な緊張感は出せなかったのではないかと思う。ほかの役者だったら、ちょっと安っぽい感じのするハードボイルド映画(クライムサスペンスといったほうがいいのかな?)で終わっていたんじゃなかろうか。というか、ほかの役者だったら、そもそもこの脚本を、狂気に満ちたこの役柄をこなせなかったのではないか。
まったく内容を憶えていない映画もたくさんあるけれど、何十年も前に観たこの作品はわりとよく憶えていて、とくに終盤の列車のシーン、「リップ・ヴァン・ウィンクル」のくだりは印象深く、むかし鑑賞したあともくり返し思い出していた。
でも、意外なことに「汝の家郷は有らざるべし」という萩原朔太郎の詩はまったく憶えていなかった。今回数十年ぶりに鑑賞して、主人公の空虚な内面に重なるようなこの詩は、とても胸に響き、印象に残った。
そんなこんなで、劇場を出たときに、僕はちょっと松田優作になったような気がした(実際は全然違うけどな)。でも、昭和の男なら、映画館を出たあと、自分が高倉健や松田優作やスティーブ・マックイーンやブルース・リーになったように感じたことが一度はあるはずだ。こうでないといけない、と僕は思うのだ。最近はこういう映画が少なすぎるのではないか。こういう映画は、いい映画なのだと言いたい。
中学生のときに「わかるか!? わかるか!? わかるか!?」と例のセリフを、真似してよく遊んだものだが、今回も家に帰ってまた「わかるか!? わかるか!? わかるか!?」と気がつけば、ひとりでモノマネをしていた。けっきょく、僕のやっていることは40数年前と同じなのだった。
それはともかく、「今さら角川映画かぁ」という気がしないでもなかったが、観てよかったです。
優作さんの演技を存分に堪能できたし、新しい発見もあったしね。
あっ、それから久しぶりに小林麻美を観ることができて、それにもグッときた。綺麗だなぁ。
追記
はじめて観たときは、全然わからなかったけれど、この作品には、ショスタコーヴィチ、ショパン、ベートーヴェン、モーツァルト、アルビノーニ……と様々なクラシック音楽の大御所の代表曲が使われています。知的で冷徹な「野獣」、伊達邦彦の愛聴する音楽は、ロックやジャズではなくて、やっぱりクラシックじゃないとダメですね。
それから、岡野等&荒川バンドの演奏する本作のテーマ曲も美しく、この映画の乾いた冷たい雰囲気を作り出すことに貢献していると思います。
いま聴いてもクールで瑞々しい演奏です。
高校の時観たがイマイチ響かず。しかし再度鑑賞すると非常に良かった。...
●映画ってより総合エンタメ
松田優作の
生誕75周年記念特集上映「松田優作の狂気
生誕75周年記念特集上映「松田優作の狂気」なるタイトルで上映していた『野獣死すべし』を見てきた。
村川透監督と明日香七穂さんの舞台挨拶付きの上映でした。
もちろん昔、何度か見た映画です。
原作の大藪春彦の小説もたくさん読んでたし、松田優作ファンの私はドキュメンタリー映画の『SOUL RED 松田優作』のDVDも持ってる。
大藪春彦原作の遊戯シリーズや蘇える金狼はハマって見ていた。
ただ、最後に見たのは20年以上前だと思う。
もちろん、映画館で見るのは初めて。
昨年、午前十時の映画祭で『ブラック・レイン』を見た。
それまで、世代的に松田優作の映画を映画館で見た事は無かったので、機会があれば見たいと思っていた。
この映画では役作りのために、激やせして、歯まで抜いたという松田優作。
たしかに鬼気迫る演技でした。
このへんは強く記憶に残っていたので、彼の演技を再確認できた。
それよりも、あらためて見る、鹿賀丈史、小林麻美、室田日出夫の存在感は凄かった。
昔は、濃くて良い役者さんがたくさんいましたね。
ドラマ探偵物語の山西道広、骨董屋の飯塚も出てた。。
懐かしい。。
村川透監督は、サービス精神旺盛で、いろいろ話してくれました。
野獣死すべしが松田優作と最後の共演の約束だった事、
だけど頼まれてドラマの『華麗なる追跡』を松田優作の癌の事は知らずに撮影した事など、
松田優作ファンの私には垂涎ものの話ばかりでした。
いわくつきのラストシーンだけが。。
1976年公開の『犬神家の一族』以降、
当時としては画期的・圧倒的・立体的なメディア戦略で次々とヒット映画と新しいスターを生み出した角川映画。
本作は(同時公開の『ニッポン警視庁の恥といわれた二人刑事珍道中』と併せて)、『復活の日』の後、『スローなブギにしてくれ』の前に公開された。1980年公開となっている。
絶好調の角川映画に乗ろうとしたのか、東映とのタイアップで製作されているが、実質的には角川春樹の一連の作品のひとつであることに変わりはない。
◆角川文庫が推していたハードボイルド作家、大藪春彦
◆本作のために10kg減量+4本抜歯した松田優作
◆「日本映画ではなく『角川映画』だ」の角川春樹
こんな時に限って?、興行的にはコケるんですね笑
ギリギリ1億円プラスと言われているので、たぶん、内情は赤字で終わったのでしょう。
松田優作は、妖気漂う独自の世界を完成の域に近付ける熱演をしたし、
鹿賀丈史も爪痕どころかしっかり記憶に残る迫真の演技を見せた。
ただ、松田優作が提案したとされる、ラストシーンの脚本書き換えによって、コメント不能な作品に仕上がってしまった感は否めない。
作中では、松田優作演じる伊達邦彦は、戦場記者として世界各地で ″地獄″ を見続けたことが示唆され、
予定外に華田令子(演:小林麻美)を殺してしまい、
完全に精神破綻もしくは闇堕ちした伊達邦彦は、現実なのか幻想なのか、演じていた松田優作本人がわからなくなったのかもしれない。
ただ、個人的には、
あのラストは唐突すぎる。
前段になんの伏線もないので、「撮っている最中に、気が変わったのか」くらいしか解釈しようがなかった。
と言いつつも、
松田優作はどこまでもカッコいいので、☆3.0
おもしろい
まさに狂気
...............................................................................................................................................
戦場カメラマンの優作が悲惨な場面を見るうちに狂気が目覚める。
知り合った鹿賀と共に銀行強盗を企てる。
鹿賀もたいがいの狂気やが、まだまともやった。
優作は警察官を殺して得た銃で、鹿賀に恋人を殺させる。
そして銀行を襲い、手当たり次第に殺しまくり。
コンサート会場で知り合い、自分に好意を寄せていた子までも殺す。
逃亡中の汽車で偶然知り合いの刑事と出会うが、これも殺す。
さらに逃亡中、急にフラッシュバックして鹿賀も殺す。
その後で戻って来てコンサートへ行き、そこから帰る時に、
実は何故か生きていた刑事に撃たれて優作死亡。
...............................................................................................................................................
とにかく難しい映画。
優作が狂気をやらせたら右に出る者はいないと改めて思った。
全ては見た人の解釈ってな扱いになってるみたいで、
死んだ刑事が最後生きてたのは優作の幻とも取れるし、
単なる夢オチと取ることも出来るとか。
戦場カメラマン
トンデモナイ名作だった
松田優作x村川 透(監督)x大藪春彦(原作)の連作になる。
子供の僕には「蘇る金狼」が面白かったから「野獣死すべし」も見に行ったのに今一だった記憶がある。
確かに「野獣死すべし」は人気が無かった。
大人になって「野獣死すべし」を見たら、色あせるどころかトンデモナイ名作だった事に気付いた。
それに比べ「蘇る金狼」は色あせている。
「蘇る金狼」のスマッシュヒットで、2作目として、思いの丈を開放して、全力で作ったのに、深すぎて大衆には受け入れられなかったのかもしれない。残念である。
まさにコッポラの「地獄の黙示録」と同じ地獄を見て狂った男の話であるが、ストーリーは、地獄の黙示録より優れている。映像は3ランクほど落ちるが、当時の日本映画としたら、よく頑張りました!である。
まあ映像で、脂の乗り切ったコッポラと対峙できるのは、キューブリックぐらいだから仕方がない。
でも電車のシーンは圧巻である。見事なカメラワークである。
松田優作は、ちょっと脚本を読み切れていない感じのする演技である。どの作品にも、ちょっとずつ感じる。
がんばって最後まで観た。
役者ありきですけど
リップヴァンウィンクルの野獣
原作・大藪春彦×監督・村川透×主演・松田優作。
『蘇える金狼』のトリオで同作の流れを汲む、ハードボイルド・アクション!
…と思ったら、大分違った。
大雨の夜の都内、一人の刑事が奪われた自身の銃で射殺され、さらにその銃で違法カジノのチンピラ2人も殺された。
犯人も動機も全く不明で、捜査は難航。しかし、その犯人は…。
元戦場カメラマンで今は翻訳の仕事をしている伊達。
普段は物静かで、クラシック音楽を愛す。演奏会では涙を流すほど。
そんな彼が何故こんな凶行を…?
チンピラだって殺されていい訳ないが、刑事は汚職刑事だったのか…?
否!
彼を凶行に駆り立てたもの。それは、内なる狂気。
いや、“野獣”。
それを目醒めさせたのは、戦場という名の地獄…。
今でこそ“PTSD”という言葉は一般的に知れ渡っている。
が、本作が公開された1980年はまだそれほどは。
戦闘ストレスによるPTSDが知れ渡るのは、ベトナム戦争から。時代背景としては同時期なのだが、日本の一般客にはおそらく全くと言っていいほど。
それは配収にも表れている。『蘇える金狼』に及ばず。松田優作のダーティヒーロー・アクション第2弾と思ったら、よく訳の分からぬキチ○イっぷりを見せられ、当時の観客も困惑した事だろう。
研究が進み、映画などでも描かれ、何より体験者の生の証言から分かってきているPTSDの苦しみ…。
伊達の次のターゲットは、大銀行襲撃。
が、さすがに一人では無理。仲間が必要。
ある時誘われた大学の同窓会。バカ連中に嫌気を感じていたが、そこでウェイターをしていた青年・真田に自分と似た匂いを感じ、仲間に引き込む。
“野獣”になるべく、徹底的に叩き込む。銃の扱い方、さらに自身で恋人を殺す非道さ…。
伊達の後を一人の男が追っている。刑事の柏木。誰も見向きもしない些細な証言から、密かに伊達をマーク。
そして遂に襲撃。が、客の中に、以前演奏会で出会いクラシック音楽好きから伊達に好意を寄せる女性・令子の姿があった…。
原作の伊達は野性的なタフガイらしい。
が、役作りで頬が痩せこけた不気味な風貌に監督は激怒、改変した脚本に原作者は批判したとか。
しかし、熱演と言うより、取り憑かれたような松田優作の怪演は凄まじい。
特に、夜の電車内である人物に銃を向け、“リップヴァンウィンクルの話”をするシーンの演技はまるで別次元にいるかのよう。
また、終盤の洞窟内で「君は美しい!」と狂おしく叫ぶ長回しシーンも圧倒される。
真田役の鹿賀丈史も強烈存在感。登場シーンからアブなさムンムン、「何見てんだ、こら!」で、あ、やっぱり! 松田優作に引けを取らず。昔から個性派。
生気が無い2人に対し、柏木役の室田日出男が血の通った人間味ある渋い好演を見せる。が、彼に恐怖の時間が…。
帰還兵とカメラマンの違いはあるが、何処か『タクシー・ドライバー』と通じる所がある。
社会と断絶した生活、狂気の目醒め、凶行…。
この苦しみ、あの地獄に気付いてくれ。
しかしだからと言って、彼の犯した事の弁護にはならない。
ただ単にあの地獄を見て、自分の中の野獣が剥き出しになっただけなのかもしれない。
世界は戦争が続いている。全く関心を示さず、平和ボケしている日本に怒りの銃口を向けたかったのかもしれない。
邦画史上難解の一つと言われるラストシーン。
一見、柏木が生きていて、伊達を射撃した…のように思えるが、確かな解説は未だ無く、様々な解釈があるそうだ。
こういうのはどうだろう。
彼は戦場で、“リップヴァンウィンクルの酒”を飲んでいたのだ。
酔って夢を見ていたのだ。
そして夢から醒めた時、彼はもう死んでいたのだ…。
役作りで奥歯抜いた優作
松田優作好きならマストなこのタイトル。改めて観てみると…
80年代邦画にありがちなリアリティ皆無な銃撃シーンと作り手の思い入れたっぷりな長回し。優作がのめり込み過ぎなのは明らかだ。
荒削りでデカダンなハードボイルド解釈。洗練されてるのは小林麻美だけ。物語の進み具合も妙に遅く付き合うのに骨が折れる。見る側にもハードボイルドを強いるスタイル。
しかし中盤に鹿賀丈史登場。優作の狂気に対抗できるキャラクターだ。この映画の見所は俳優の吹っ切れ具合のみかもしれない。
終盤まで付き合うと名台詞と名シーンは見れますのでハードボイルドモードで頑張りましょう。
全31件中、1~20件目を表示