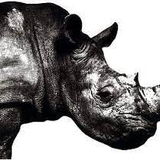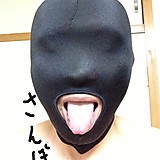鉄道員(ぽっぽや)のレビュー・感想・評価
全76件中、61~76件目を表示
キスシーンは違和感がある
『鉄道員(ぽっぽや)』(1999)
一人の愚直に仕事一筋に生きた男の死までと先立たれた生後2か月の娘と妻への回想を詩情
豊かに、北国の風情とともに描いている美しく悲しい束の間の映画だが、過疎化で廃線になってしまうほどの街の過程も同時に写されている。ただ残念なのは、検索しても幾つか出てくるが、
生後2か月で死んだ娘が成長した様子を3人でそれぞれ3姉妹ということで出て来るが、理由は
高倉健扮する駅長の父親が怖がるだろうから、父親が気づくまで姉妹ということにしたというが、
その2人めの当時12歳の子役に当時62歳の高倉健が駅長さんが好きだからということで、コーヒー牛乳を口移しで上げるシーンは、キスシーンと同様の行為だが、違和感ある失敗させてしまったシーンではなかったかと私も思う。妻と娘に先立たれると、老齢になってしまった男一人で子おおた孫が絶える。何代も何十代も続いてきたから人間生命が、自分が存在していることが途切れるということの大きさ。駅の仕事で抜け出せず、娘と妻の死に目に会えなかったことの男のコンプレックス。男の死の寸前に娘が成長して現れてくれたフィクションは、男のためのものだったのか。なぜ現れたのが娘だったか。回想で大竹しのぶが演じた妻も多く出てくるが。当時41歳だっただろうか。滅多に映画に出ないような志村けんが、うまい演技をしている。いかりや長介さんも渋くうまい演技だったが、舞台喜劇や若い頃の喜劇映画だけではない、シリアスな場面でもうまさを発揮できるバックボーンがドリフターズにはあったのだろうと思わせた。違和感あるキスシーンにしても、
幽霊と言ってしまっては簡単にすぎるが、フィクション性からあまり泣ける映画には感じなかったが、
真摯に生きた市井の男の一生を堂々と描いた。小林稔侍の演じる同僚との友情も感動的だったが、当時の日本アカデミー賞など数々の評価を得た映画との事だが、それゆえに3度も繰り返してしまうが、コーヒーの口移しシーンには違和感があり、そのシーンはないほうが良かっただろう。
人生をかけられる仕事とは
日本の雪の音
しばれてきたね~
回想シーンとリアルタイムのシーンが交互に映し出される。妻と娘が死んでしまったということをわかっていないと前半は理解しづらい。だけど、高倉健の演技だけで泣けてくる・・・大竹しのぶや娘が出てくる前で十分感動できた。
「いやぁ~、しばれてきたね~」という言葉が妙に似合ってる健さん。幽霊ものでは滅多に泣けないのに、泣かせてくれる演技力・・・というより存在感だろうなぁ。
高倉映画史上唯一泣ける感動映画。
初めてこの映画を見てホントに感動のあまり泣きそうでした。
大雪のなか、鉄道員の男(高倉健)は何のために駅に立ち続けたのか。
特にラストのとこだけ衝撃でした。
※来年で追悼5年となる高倉健さんのご冥福お祈りします。
高倉健さん以外、考えられない企画!合掌!
辛く、悲しくない訳がない。
仕事で死に目に遭えなかったことを、泣かないことを、他人が責めるのは筋違いだと思う。
辛く、悲しくない訳がない。
健さん、メチャ格好良い♪
広末涼子、メチャ可愛い♪(*^-^*)
最期が衝撃的だったけど、仙さん(小林稔侍)が言っていたように、「大往生」だったネ。(ρ_;)
思い出の映画・・
「鉄道員」を観て・・
追悼・高倉健 (ほとんど映画のレビューじゃありませんが…)
高倉健さん死去。
突然の訃報にただただびっくり。
「日本侠客伝」「網走番外地」「昭和残侠伝」などの任侠映画シリーズでスターとなったが、さすがにこの世代じゃない。
映画館で初めて“映画俳優・高倉健”を観、感じたのも、「鉄道員 ぽっぽや」だった。
なので、追悼作品チョイスも自然とこの作品が浮かんだ。(山田洋次とのコンビ作二本も捨て難いが)
廃線間近の北海道のローカル線で、鉄道員一筋に生きてきた乙松。妻が亡くなった日も、幼い娘が亡くなった日も、駅に立ち続けてきた乙松に、奇跡が訪れる…。
一人の男の生き様が心に染み入る、さながら雪国のファンタジー。
この年、最もお気に入りの一本となった。
よく高倉健の演技を、どれ見ても同じと言う意見は多い。
でもでもでも、「幸福の黄色いハンカチ」や「鉄道員」など、もし高倉健でなかったら、あれほどの画になっていただろうか。
僕は高倉健の映画や演技を、“高倉健は何を演じても高倉健だが、やはり高倉健でしか成り立たない”と思っている。
演技派、個性派は沢山居るが、出ただけで画になる人は今の日本映画界にほとんど居ない。
正真正銘の銀幕スター。
寡黙で不器用がほとんどの人が持つ高倉健のイメージ。
実際はユーモア溢れ、悪戯小僧でもあったという。
「幸福の黄色いハンカチ」撮影時、武田鉄矢と桃井かおりを別荘に招き食事を振る舞いながら溜まったグチやストレスを発散させたかと思いきや、実はそれをこっそり録音していて、「昨日こんな事言ってなかったか?」と悪戯したり。(先日武田鉄矢が出演した波瀾爆笑より。これには笑った)
「あなたへ」の宣伝でスマステに出演した際、緊張する香取と草なぎの両名を、「TVタックルのスタジオに行きたかった」とユーモアで和ましたり。
「単騎、千里を走る。」撮影中、エキストラにも謙虚に丁寧に接し、チャン・イーモウ監督は「中国の大物俳優にこんな人は居ない!」と感動したとか。
義理人情に厚く、誰に対しても心遣い、気配りを見せ、大スターなのに壁を作らず。
知り合ったら誰もが好きになると言われた高倉健。
知れば知るほどその人柄に惚れる。
銀幕スターではなく、人としてのお手本。
新作を準備中だったという。
今の今まで健さんを銀幕で見れたのは映画ファンとして喜び。
ご冥福お祈りします。
滅私奉公な生き方に必ずしも賛成しませんが、映画としては面白いです
総合:80点
ストーリー: 70
キャスト: 90
演出: 80
ビジュアル: 70
音楽: 75
不器用だけど自分の仕事に誇りを持って取り組む鉄道員。出演者の確かな演技力、感動を無理やり呼ぼうとして過剰演出になったりしていない控えめな淡々とした物語進行など、映画として質の高さを維持している。
ただし愛する家族の死とかすら後回しで仕事を優先するというこの時代の価値観というのが、今時の人には少し理解しがたいのではないかと思います。結局そういう鉄道員は仕事はきっちりこなして社会のためには大いに貢献しているのだけれど、その分個人としての幸せを犠牲にしている。
父親の死の直前に、幼くして死んだ娘が突然幽霊になって自分の成長ぶりを見せに来て彼の生き方を肯定してくれるという、通常はあり得ない奇跡が起きる。そして仕事を優先していて死に目に会えなかった彼の娘への心残りは氷解する。
でもそのようなことが起こらない限り、人生の幸せの損失分を多少なりとも取り戻すことが出来ないのだと思うと、感動というよりもそのような人々への哀れみや悲しさを先に感じてしまう。普通の真面目に働いている人にはそのような奇跡は起きないのだから、損失の補填はなく心残りを持ったまま死んでいくわけです。そのため図らずも他のことを犠牲にしてまで仕事一筋などで生きてはいけないよ、奇跡に頼らず自分の人生の幸せの価値基準をはっきりさせなさいという教訓を教えられたように感じてしまう。
だから必ずしもこの善良なる鉄道員の生き方を素直に支持出来ないのである。こういう滅私奉公な生き方っていうのはちょっと古い日本人のもの。特に欧米人なんかだと家族ほったらかしで仕事なんかばかりするなんて、最初から理解しがたい馬鹿な男の物語というふうに切り捨てられることになるんでしょう。
とはいうものの、こういう話は日本人にはわかりやすい。彼らが個を犠牲にして日本の経済発展に大きく貢献してくれたこと。彼らのような存在があったからこそ今の日本がある。だからいい映画だとは思います。
D51やC62が戦争に負けた日本を立ち上がらせ・・
映画「鉄道員〈ぽっぽや〉」(降旗康男監督)から。
鉄道員〈ぽっぽや〉としての誇りを持って生き続け、
戦後の高度経済成長期を支えてきた主人公・佐藤乙松を演じる
高倉健さんが、独特の口調で発した台詞が渋い。
自分が鉄道員になった理由を、若い吉岡秀隆さんに語るシーン。
自分の父親から言われた台詞のようだ。
「D51やC62が戦争に負けた日本を立ち上がらせ引っぱるんだって、
それでおじちゃん、機関車乗りになった。
そして、ぽっぽやを全うしようとしている、悔いはねぇ」
確かに、最近では「費用対効果」だけで、赤字を理由に
廃線に強いられることが多い鉄道だけれど、
ほんの少し前までは「旅行」と言ったら、乗り物は鉄道だったし、
駅弁を楽しみに、わざわざ鉄道を利用したこともある。
私は、鉄道ファン・鉄道オタク・鉄ちゃんではないけれど、
学生時代は、周遊券片手に北海道まで、急行で旅したものだ。
そんな思い出があるからこそ、廃線の記事を目にするたびに、
「鉄道」が立ち上がらせ引っぱてきた日本の「高度経済成長」を
思い出すことにしている。
私たちの小さい頃「大きくなったらなりたい職業」は、
電車の運転手さんに憧れた子どもたちが多かったんだよなぁ。
(新幹線だったかもしれないけれど・・)
鉄道を見直すきっかけとなった映画である。
全76件中、61~76件目を表示