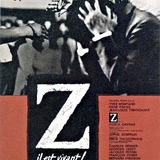ビルマの竪琴(1956)のレビュー・感想・評価
全17件を表示
70年前の映画だとは思えないほど洗練されている
善人な三国先輩
【“埴生の宿”ビルマで英国軍に囚われた日本軍の中で、只一人ビルマの地に残り、彼の地で死んだ同胞のために僧侶となって鎮魂する男の姿を描いた反戦映画の逸品。】
ー 竹山道雄氏の「ビルマの竪琴」を読んだのは、大学の頃であったろうか。
大岡昇平氏の「野火」とは、全く違うトーンの内容であり、且つ水島上等兵の、痛切且つ崇高な選択に、いたく感動を覚えたモノである。-
■1945年、夏のビルマ。
敗戦後も抵抗を続ける通称三角山に立てこもる日本軍の兵士たちのもとに隊長(三国連太郎)の依頼により、降伏の説得に向かったまま戻らない水島上等兵。
隊の仲間たちが水島を探す中、ある日彼らは水島にそっくりのビルマの僧を行違う橋の上で見かけて声をかける。
しかしその僧は、目を伏せ走り去ってしまう。
◆感想
・粗筋は分かっていたが、映像で観ると矢張り、水島が所属していた隊長が合唱好きだったために、常に歌を口ずさむ隊員達の姿や、美しい楽曲が印象的である。
・又、隊員たちが手名付けたオウムが”オーイ、ミズシマ、イッショニニッポンヘカエロウ”と啼くシーンは沁みる。
■特に、隊長が僧侶を水島と確信しつつ、彼の想いを汲み、無理に日本に連れ帰らない決断と、帰国の船上で隊員達に水島から託された手紙を読むシーンは、白眉である。
<映画の作り方としては、殺戮シーンは三角山のシーンのみで、英国側のナースが日本兵士の墓に対し、歌を手向けるシーンなどが、印象的であった。
更に言えば、兵士たちや水島上等兵の想いをモノローグで流す手法は効果的であると思った作品である。
いずれにしても、今作が、邦画の反戦映画の逸品である事には、間違いないであろう。
出来得れば、一度音響の良い劇場の大スクリーンで鑑賞したい作品である。>
竪琴の音に理想と祈りをこめて・・・‼️
わが敬愛する市川崑監督の数多くの名作の一本です‼️太平洋戦争末期のビルマで日本兵の悲惨な死に様を目の当たりにし、日本へ帰らず僧侶になって霊を慰めることを決意する水島上等兵の姿を描く‼️後にリメイク版も市川崑監督自身の手で製作されましたが、やっぱりオリジナルが好き‼️まずこの映画が素晴らしいのは、従来の反戦映画と違い、将校にも兵隊にも悪人はおらず、戦争そのものが悪いという主張で平和を祈る作品となっているところ、ヒジョーに格調が高いところですね‼️「金田一耕助」シリーズに代表されるテクニシャンな市川崑監督なんですが、ここではそのテクニックを封印し、ストレートに正攻法にこの素晴らしい名作を仕上げてくれています‼️印象的な場面がいくつもあります‼️僧侶姿の水島上等兵の肩に止まったオウムがしゃべる「ミズシマ、イッショニニホンヘカエロウ」という言葉‼️日本軍の、そしてそれに応えるイギリス軍の「埴生の宿」の大合唱‼️合唱シーンをはじめとする音楽の使い方もホント素晴らしい‼️そしてラストのビルマの荒れ果てた地で、小さく主人公の後ろ姿を捉えたショット‼️水島の行く手にある過酷な運命を暗示させる重く非情なショット‼️この後ろ姿にいつ観ても涙させられるんです‼️
戦争の虚しさを伝える名作
ビルマの土はあかい 岩もまたあかい
一度は聞いたことのある名作。
ビルマの竪琴も市川崑監督作もこれが初めてでしたが、とても良い映画でした。
中井貴一版の方が有名ですが、これはそれより30年も前、戦争からは10年ほどしか経っていない時に作られた作品です。
全編モノクロなんですが、観ているうちに色鮮やかに観えてくるようで、役者さんの表情も当時の不安と熱意に溢れていてとてもリアルでした。
話自体は淡々と進んでいき、特に大きな展開があるということもなく、展開は想像できる分かりやすいもの。
しかし、モノクロで淡々としているからこそ、強くて深いメッセージ性がありました。
どんどん映画の中に引き込まれ、まるで自分が水島の立場に立ったかのような感覚になるので、戦争の恐ろしさや悲惨さがよく伝わってきました。
そして、なんといっても戦争の恐ろしさを描きつつも、合唱で一つになる彼らや現代でもクスッと笑えるようなところがこの映画の良いところだと思います。
なぜか関西弁を覚えた現地のお婆さんはここ最近で観た映画で一番好きなキャラクターかも。
歌の力、琴の力、音楽の力。
観て良かったなと思える作品です。
同じく市川崑監督ですが、比較として中井貴一版も是非観てみたいと思いました。
音楽の力と白黒作品ながら色彩の力を極限まで引き出した圧倒的な名作です
純粋な本当の意味での正しい反戦映画です
変に左翼思想のイデオロギーに毒されて偏向していない本物であると言うことです
市川崑監督の演出力、構成力
それが音楽の持つ力を圧倒的なまでに引き出しています
ビルマの竪琴の音色は冒頭すぐ披露されます
思った以上の美しい音色と和音で誰もが驚くはずの音色です
そして部隊の合唱シーンに入って行きます
この冒頭のシーンこそ本作品の核心を象徴しているのです
続く村のシーンでは音楽の力が戦いを阻止するのです
音楽の力をこれほど引き出している映画は、そうないと思います
そして色彩
本作は白黒作品です
しかし色彩はあるのです
ビルマの
土はあかい
岩も
またあかい
冒頭とラストシーンで大写しされるテロップです
なぜあかいのでしょうか?
それは、もちろん元から酸化鉄を多く含んだ土の赤さなのでしょう
しかし、そのビルマの大地には戦争により、銃弾や砲弾、爆弾の鋼鉄の雨が降ったのです
その鉄の赤い錆びが大地に染み込んだのです
赤錆が雨で流れて大地に染み込んで行くさまはまるで血が流れたかのようにみえるのではと想像されます
そしてなにより、戦争では日英両軍の兵士達の血が流れ、赤錆の水よりもなお赤いその色をビルマの大地に染み込ませたのです
だからあかいのです
岩もまたあかい
戦場で死んでも、そのまま放置されたままの多くの日本兵の骸
それは鳥についばままれ、ビルマの灼熱の太陽が肉と血を干からびさせて、真っ赤に染まった軍服はボロ布になり果て、血で赤く染まった骨にまとわりついて、まるで赤い岩のようになっているのです
その岩が無数にビルマの赤い大地に転がっているのです
誰がその魂を鎮めてやれるのでしょうか?
生き残って日本に還る部隊の面々の心の中も、赤い大地と赤い岩が無数に転がっているのです
そしてまた、ビルマの土と岩のあかさだけでなく
ビルマの仏教僧侶のオレンジ色の僧服
仏塔の輝く金色、ビルマ寺院の鮮やかな彩色
ジャングルの濃い緑
インコの美しい色彩の羽
大河の川の泥水の色
そして、ルビーの鮮烈な赤さ
これらの豊かな色彩が、白黒作品なのに、確かに見えるのです
鮮やかな色彩でワイドスクリーンで、頭の中で見えるのです
カラーで撮る構想であったそうですが、当時の器材ではビルマロケは困難とされ白黒作品となったとのこと
本作はビルマロケの許可が遅れ、日本で撮った分だけで第一部、遅れて許可がでてビルマでロケ撮影した分で第二部として分けて公開されたそうです
監督は、第二部を止めて本当はロケ撮影分を第一部に加えて再編集したこの総集編で公開し直したいと願ったのにそのような結果になったそうです
これがもとで市川崑監督は日活を退社する事に至ったとのこと
1985年に市川崑監督が本作をセルフリメイクしたのは、そうした因縁があるのだと思います
カラーで撮り直ししたい
もっと完全なビルマの竪琴を撮りたい
その気持ちが如何に強かったか伺えます
リメイク作品は是非ともオリジナルのこの白黒作品を観てから、リメイク版でそのカラーを確かめてみたいものです
三國連太郎の隊長が見事な名演です
悪役が多いこの人が、演じることによってこの隊長の人間性の深みと厚み、ヒューマニズムが引き出されていると思います
兵隊の西村晃もしかりです
老け役が得意な北林谷栄の演じる物売りのビルマの老婆も見事でした
この時彼女はまだ45歳!
29年後の1985年版でも同じ役を務めています
あの喋り方での不思議な大阪弁のもたらす雰囲気
忘れられないものです
監督の配役の眼力が如何に優れていたということです
音楽の力と白黒作品ながら色彩の力を極限まで引き出した圧倒的な名作です
数々の国際的映画賞を受賞するのは当然です
しかし本作はキネマ旬報のオールタイムベスト200にはランクインされていません
本当の意味の反戦映画であることが影響しているのかも知れません
情けないことです
北林谷栄
インコが素晴らしい活躍
全17件を表示