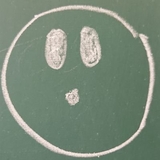新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君にのレビュー・感想・評価
全19件を表示
夕方18時半から放送されてたTVアニメの続きが
こんな話になることあるのか
気になったところ
・手があんなに白濁液まみれになる状態あるの?出口押さえてたの?
・今と比べるとアニメの線が太い
・ミサトさんが電話しながら本部へ向かう後ろ姿とか陸自の頭がニョキニョキ出てくるところとか構図がかっこいい
・TV見てから見ると「ああ、もう取り返しがつかない......」って絶望感を7段階ぐらいで感じる
・ネルフで働いてる職員って公務員なの?腹が座り過ぎている
・ミサトさんシンジ君に自分で決めなさいみたいなこと強要するけどシンジ君どれくらい現状把握してるの?決断下せるほど情報共有されてるの?
・リツコがGENDOに撃たれたとき普通の拳銃っぽいのにすごい体吹っ飛んだな
・弐号機とかデカ波とか重量感を感じてすごい
・これ作ってる人は精神的に大丈夫なの?
・なんか傷口とか肉の裂け目とかがいちいち性器の形になるの大丈夫なの?
・けっこう今見るとCGとか実写パート古臭く感じるものだなぁ
・実写のチェケラニキだいぶ解像度高くなってる
・シンジ君ここまでの話の流れでよく補完計画ひっくり返したな
・ミサトさんの墓標立ててからアスカの隣に寝ころびなおしたのはちょっと気持ち悪いかもしれない
・これはもう作ってる人ダメかもしれない......
テレビアニメの終わり方がこんなモヤっとした最後になることあるんだなと思ったけど面白かったです。なんか制作者のパッションを感じる映画だと思いました😊
これまで新劇場版の必要性をあまり感じてなかったけど、改めて旧劇をみるとまぁこいつらも最終的には幸せそうになってたし良かったのかもねという気持ちです😌
私見:なぜ首を?
私見と断っておきます。
エヴァは魂のある世界ということを認識すると・・・
どれほどかは不明だが、どうやら最後の海辺でシンジはしばらくすごしていたらしい。
ユイとの会話で予想されたのとは違って誰も戻ってこなかった。
補完された世界はすべての人にとって心地よかったのだろう。
(みんなたのしくやっている)
シンジはミサトさんのネックレスで墓標を立てた。
アスカがいつからいたのかは不明。
アスカをどうすべきか?
(あっちにいって
きっとまたうまくいかないから
ぼくはひとりでいいの
みんなのところでたのしくやってね
あっちにいって
それがぼくのできるたったひとつのやさしさ
まごころをきみに)
ぎゅっ。
・・・・・・・・・だが、昨日見直したら、あの海辺の墓標は帰ってきた人たちをシンジ君(もしかしたらアスカも)が魂に還した時の墓なのではないかと思えて余計鬱になりそうだ。
ONE MORE FINAL
2025年10月から行われている、期間限定のリバイバル上映企画を機に初めて劇場で鑑賞。
それまで何度もビデオなどで見慣れたと言えるだけの回数観たが、劇場で鑑賞することの重要さを改めて感じた。サービス精神旺盛なシリーズの為、またこうした再上映企画が起きると思うので、是非劇場で観て欲しい。映画は映画館で観るに限る。たとえアニメ映画であっても。
テレビアニメ版とは違う結末を描いた、新世紀エヴァンゲリオンの劇場版。
分からない、と一言で片づけるには勿体ない作品。
流石に劇場版だけあって、アニメーションのクオリティが異様に高い。GAINAXの基礎力の高さと、Production I.Gの息吹きを感じる。
音響の質も高い。劇場作品として映画館で観るだけの価値を感じる程度には、控えめに表現して最高だった。
演技も文句無し。感情が乗り切っていて、もはや「没入感が高かった」ではなく「誘引力が凄まじかった」
再上映という機会で以て、映画館で鑑賞出来て良かった。
内容について、よく誤解されがちだと個人的に感じているのだが、この作品は別に哲学を語っていない。これは最初に言っておきたい。
あまり表に出したくない男性的な鬱状態が、他の追随を許さない程の精度の高さで表現されている。このメンタリティと思考内容をそのまま作品として映し出している表現力の高さへの驚きと、同調しすぎてしまう人が居るんじゃないかと言う心配が同時に沸き立つ。
苦悩と葛藤の吐露が凄すぎて圧倒されてしまうが、内容をよく聞くと別に理解に苦しいような難しい事は言っていない。上記の通りの、高精度高解像度の鬱を映画という形で浴びる驚きの体験に頭が追い付かないだけなのだと私は思う。
設定上の出来事が(名前まで込みで)若干ややこしいが、その辺はセリフの雰囲気を感じ取って上辺だけ掬い上げて、あとは登場人物たちのドラマに注視して観るのが一番良いと考える。細かな設定や考察を全て把握しておく必要は無く、登場人物たちを知りたいと言う心だけで、しっかり楽しめるはず。
人間の内面を、綺麗も汚いも関係なく、映ったまま映し出す。そんな作品だ。
どうあってもテレビアニメから続く劇場版なので、テレビアニメ版を見ておいた方がいい。未見でも見所を楽しめるとは思うが、視聴済みのほうが、把握しておくべき状況の数が減って、観易いはずだ。
この作品を全力で楽しみたいのなら、今回の再上映のような機会を利用して劇場で鑑賞するか、劇場と同じだけ作品に集中できる環境で鑑賞すること、翌日がお休み確定な日に観ることをお勧めする。マトモに食らうと大ダメージ。だがそうなるだけの凄さが、この映画にはある。
◆
残酷表現と性的描写に意味はあるのかと言う問いが散見されるが、逆にそれらが無ければ終盤のシンジのグロテスクな独白が変に浮き上がってしまって歪な作品になるのではないかと私は感じた。失うことで気持ちに気付くという物語のつくりが故に物語は過激になり、物語の過激さ故に映像も過激になった。という、ただそれだけの話なのではないだろうか。
第25話 Air
冒頭の病室のシーン、レーダーサイト破壊の報告が上がるシーンなどが顕著だが、音響がサブスク版とは異なっていた。サブスク版だと、少なくともこのAirに於いては明らかな音ズレがあるのだが、見事に合っていた。流石に合ってるよな、と安心した。
映画館での鑑賞は初めてだったのだが、音響が違うだけで(私が)見慣れたサブスク版とは全く違う作品を観ているような感覚に陥った。超感動した。特にVTOL攻撃機によってSAMが破壊される場面!あんな迫力あったっけ?!と驚くばかりだった。
各種ビデオディスク版もまた違うのだろうか。有識者の登場を願う。
最初の最初に一番衝撃的な性的描写があることで、全裸の綾波レイとかいう激物が霞んで見える。若干警告的な思惑もあったのだろうが、それにしても思い切りが良すぎないか?
鶴巻監督渾身の演出が輝きに輝く戦闘シーン。後にフリクリ等でも見られるアクションカットの数々に魅了される。人類を守る為に生み出されたはずのエヴァンゲリオンが人間に向かって武力を振るう上、エヴァ同士の戦闘なんていう最悪な状況とは到底思えない高揚感が独特としか形容できない……
演出という名の選択、という考え方がちゃんとあるように思う。一番面白い撮り方は何か?
その結果、綺麗でないもの、良くないとされているものだって映し出す。それがエヴァンゲリオンの魅力であり、本作最大の特徴だと私は感じた。
第26話 まごころを、君に
本作一番の見所。再上映で一番体験したかったエピソード。
感想としてはたった一言。「こーれ初見で劇場で浴びたら訳分かんなくなるだろうな」
独白の痛々しさに飲み込まれる。碇シンジが抱える心の闇。
とにかく寂しい、愛が欲しい、心の隙間の全てを誰かに埋めて欲しい。自分の周りにいる人たちに密かにそう願うが、決して思った通りに自分を慰めてくれる事は無いことに憤る。正直に言えば誰でもいい。誰でもいい癖に願いの矛先は女性ばかり。しかも無意識に性的な欲求も抱いており、それに自覚があり、自分の事ながらそれらすべてを心から嫌悪している。
これを私は『男性的な鬱状態』とよく言っている。男性的、と括りが大きい気もするが、少なくとも私がこれに覚えがある。これがそのまま映像にできるのは、庵野秀明ただ一人だと思う。こんなものを映像に乗せてしまおうと思い至って実行できる表現者は他にないはずだ。正直言って、観てて心地の良いものではない。でも、そんな醜く見える心の内も映し出したからこそ、踏ん張って前を向こうとするというプロットに、私は心打たれたのだと思う。
肝心の映像だが、正直何をどう言えば良いか分からない。印象を巧みに操る超絶技巧の数々に脳が翻弄されるばかり。パワータイプすぎるモンタージュの使い方だが、しかし絶対に真似できない程にこだわり抜かれている。
新世紀エヴァンゲリオンの終わり方としては、これ以上無いだろう。最高だった。
これを、訳の分からない作品として片付けるのは、本当に勿体ない。私はそう思う。
「ヤマアラシのジレンマ」の映画
30周年記念のリバイバルで再見。TV放映から30年経つのかと思うと感慨深い。DVDでもこの映画は繰り返し見ているので、展開はすべて分かっている。それでも見入ってしまう。しかも見ていて涙が止まらないというのは、歳をとったせいか?それともビールのせいで前頭葉の規制が緩くなったせいか?
この映画、特に第26話の「まごころを、君に」がよく分からないという人は多い(「まごころを、君に」は、『アルジャーノンの花束を』を原作とした『まごころを君に』のエンディングロールがない点を踏まえているのだろう)。それは分からない訳でもない。TVシリーズを観ていないと分からず、しかも映画単独としては説明不足である上に、初公開当時の状況を踏まえないと理解できないからである。ただ、この映画の主題は「ヤマアラシのジレンマ」であることは明らかであって、「人類補完計画」などの表層的なストーリーを追いかける必要もない。他人との距離感がテーマの映画なので、性描写も含めて、登場人物たちのセリフをそのまま理解すればよい。
改めてこの映画を観て思ったのは、この映画が約30年(正確には28年)の月日を経てもなお鑑賞に堪える作品であるということである。しかも、年齢を重ねると共感できることが多い映画である。この映画を観てよく分からないという若い人たちは、(恋人も含む)他人との距離感についてあちらこちらと頭をぶつけて、一通りの経験をした40代以降に観てもいいかもしれない。
Airまごころを君に
意味がわからん。俺の理解力が無いのはあるが大半の人は理解出来ないのではないか?原作アニメは観てるがそれでもよく分からん。哲学みたいな展開してる。終盤のごちゃごちゃ具合はなんかキューブリックの「2001年宇宙の旅」
をふと思い出したね。
シンジ君がサードインパクトを起こしたで合っているのか?そもそもサードインパクトとは何なのか起きた後何が起きてるかもよく分からん。謎が謎で謎すぎる。いちいちツッコんでいたらきりがないだけどね笑
あと、グロい感じとエロい感じは必要だったのか?
評価したい点は音楽と声優さんの演技。それは評価したいです。
劇場で観たけど冒頭で緒方恵美に謝らすなと思った。演者は関係無いのでは?庵野秀明を出せよ。
生存か、実存かーー“自分探し”の果てに見えてくるもの
1997年公開。28年前の作品だ。
当時、僕は20代で、仕事に追われつつ「こんなはずじゃなかった」という感覚が強く〝自分探し〟の最中で、エヴァは切実な物語だった。96年のテレビ版のラスト2話で、ロボットアニメとしてのエンディングは放棄された。テレビ版のエンディングを作り直す本作を、すごく期待をして待った。そして、この2話を見て圧倒されつつも、再び「?」となった。
エヴァが描く「自分とは何か?」「どうすれば自分は幸せになれるのか?」といった実存的な自己探究は、当時の若者にとって切実だった(現代も、それは変わらないと思う)。「自分探し」という言葉の流行も、本作公開と前後する90年代である。
当時は自己探究の問いに答える一般書籍はすごく少なかった。ポストモダン哲学や、またそれ以前のサルトルやニーチェなどの実存系哲学書など知らなかったし、普通の若者には難易度が高すぎた。そうした状況の中で、庵野がこの時期、本作に自己探究の物語を埋め込んだのは画期的だった。
自己啓発の源流の一つでもある『7つの習慣』は1996年発売。その頃から、食べていくため、儲けるための軍隊組織論的なビジネスから、自己実現する働き方へという流れが生まれた。その後2000年前後から、そうした一般書籍が盛んに出版されるようになった。僕が、そうした本を読んだのも、この作品を理解するためであった気がする。それは自己と世界の理解のためでもあった。
あっという間に30年近くが過ぎてしまった。かなり久しぶりに本作を見たので、現時点での解釈を、できるだけ簡単に整理してみたい。
エヴァという物語は常に、人間関係の葛藤に突き当たる。葛城美里が語る〝ヤマアラシのジレンマ〟である「遠ざかると寒く(不安・孤独)なる」「近づくと傷つけられる」という葛藤をシンジも美里も抱えている。
エヴァに自分だけが乗れると言うことは、これ以上ない万能感や自己肯定感を得られることだが、シンジはそれを感じられない。それ以前に、自分を危険に晒し、傷つけられ、時に他人を傷つけるという葛藤にぶつかっている。
「あなたはすごい」「あなたはよくやっている」「あなたが好きだ」と承認してもらわないとシンジは自分を保つことができない。言葉で承認されてもそれも信じられない。そして、相手を試すような行動を取る。
これは庵野自身の、そして本作に当時エヴァにハマった僕ら共通の実存的不安でもあった。
庵野は当時テレビ版への猛烈な批判にさらされて、抑鬱状態の中で本作を制作している。切実な悩みをエヴァという作品で自己開示した。それなのに観客は、エヴァというアニメ作品世界の中に耽溺し、「庵野、死ね」などと批判を突きつけてくる。
「みんな現実を見ない。自分もそうだった」「現実に戻れ」
「自分を閉じること(実存的内省)にはもう限界がある」
…というような彼の言葉からもわかる通り、庵野は自分探しに疲弊し、他人との幸福なつながりを模索していた。
自己を放棄して、他人とつながる。自我のない世界、生命誕生前の溶け合った状態が幸福だ…という人類補完計画の解決策は、日本人的には共感できる方法だ。言葉にせず察し合う、自分を殺し同調する、自己主張より一体感…というような文化が私たちにはあるからだ。
本作は欧米では理解されなかった。サルトルがいう「他人は地獄」という認識はあっても、自立した個人という前提は揺るがしようがないからだろう。補完計画は、西欧の個人主義やキリスト教的人間観と相容れず、全体主義・ファシズムの隠喩に見える。
実際、欧米での批評は、一部アカデミック層から、フロイト的無意識の世界を描く作品としての評価を得つつも、多くは理解不能・意味不明、カルト的という厳しい評価であったようだ。
本作を切実な思いで観れたのは、周りと溶け合い同調したいという方向と、自分らしさを確立したいという両方の思いで引き裂かれる90年代の日本の若者ならではであった(その状況は今も続いているように思える)。日本的感性において、無我(個を滅する)的な方向による調和と一体化は一定の説得力があり、その危険な魅力がエヴァの根幹にある。
人類補完計画は冷戦後の世界のグローバリズムの隠喩として読み取ることもできるかも知れない。グローバリズムの理想は「争いのない一体化した世界」。これはゼーレの理念「全ての人の心が一つになれば、争いも悲しみも消える」と酷似している。
しかし、強制的に人間の差異を奪ってしまえば、個性も消える。「らしさ」が消えた世界に幸せはない。これが現在世界で起きている国家・地域性・人種といったATフィールドの復活の動きと見ることもできると思う。
自己探究の物語は“自己をどう構築するか”という心理的な問いに通じていて、本作を脳科学的視点から読み解くこともできると思う。
脳科学者ジル・ボルト・テイラーの「Whole Brain」という本がある。この本は、左脳が機能停止した脳科学者が、自らの体験を元に左脳と右脳の仕組みを解説した本だ。
エヴァに登場するMAGIシステムは3つのキャラクター(科学者、母、女性)が合議制で判断するが、テイラーの主張は、人間の脳には4つのキャラクターがあり、その4者が合議制で機能しているというものだ。
4者はそれぞれ個性的だから、合議はなかなかうまくいかない。同時にうまく働くのは困難で、左脳優位になることで、暴走気味になる。
左脳は〝生存〟を司る脳だ。個人が生き延びるための機能が集約されている。現実世界をサバイバルするための自我と理解していいと思う。つまりATフィールド=自我境界という生物的な基盤による自己保存の脳だ。
左脳には、論理的思考を司るキャラクター1と、危険を察して警告するキャラクター2がある。
シンジは多くの現代人もそうであるようにキャラクター2が優位だ。自分を守ってくれる父母が不在だったこともあり、生存アラート機能が肥大している。転校先やネルフで出会った人々も味方であると感じられないまま、危険な戦いに放り込まれて、このキャラクター2がさらに強く機能している。
人間は社会的動物だ。周囲とうまくつながることで安心できる。「自分は周囲に認められているか?」「今の自分でOKなのか?」ーー他人の中で生きる時、こうした問いが常に頭の中を駆け巡っている。
キャラクター1による、計画や現状分析、戦略的努力によって「うまくやっているOKな自分」を作る。その場に貢献し、自分で自分を承認することで、キャラクター2の不安を鎮めていくのが、左脳の2つのキャラクターの健全な働きだ。
アスカや綾波がそれを体現している。アスカにとっては有能であることが、不安から逃れる手段だ。また、綾波は、周囲との絆を作る手段としてエヴァを捉え、それに献身している。
シンジくんは、キャラクター1がうまく機能していない。周囲からOKだと承認を得たいが、自分で察することができず、常に他人からの言葉と態度での承認を求め続ける。他人の言葉も口先だけとしか思えない。「自分が有能(エヴァに乗れる)だから、僕を承認するんでしょ」「個人としての僕じゃなくて、パイロットとしての僕が必要なだけでしょ」とキャラクター2の警告はとどまるところがない。周囲に同調し、組織に違和感を感じつつ献身する私たち日本人の中から消しがたい承認欲求をシンジは体現している。
左脳優位になるのは、〝実存〟を司る右脳を意識するのが難しいからでもある。(左脳は自分を周囲から切り離された存在と捉えるのに対し)右脳は周囲と自分を一体化したもの、全体的なものとして捉える。つまり、右脳は、人類補完計画的な、個人と時間が消失した世界、全てが繋がった世界という認識をする脳なのだ。
実際、左脳が機能喪失したジル・ボルト・テイラーは自分の体がどこまでかが分からなくなった。過去や未来が認識できず〝今ここ〟を全体的に感じるようになった。そして、自分が周囲と調和した至福の時間を過ごしたという。
本作でアスカが覚醒する場面では、ATフィールドが、分離し自己防衛するだけではなく、亡き母という全体性とつながる機能があることが示される。これが右脳の機能だ。
右脳は意味を感じる脳でもある。マインドフルネス瞑想やメメントモリ(死を想う)的な認識によって、左脳は静かになり、右脳が認識する世界が現れる。
花びらが散った、雲が流れる、夕日で周囲が赤く染まる…そんな意味がなさそうな些細なことに、言葉にできない深い意味があるように感じるようになる(「秒速5センチメートル」は、その右脳的感覚を描く映画でもあると思う)。
エヴァの構造は、この左右の脳の対話と対比で成り立っている。
左脳だけでは、世界や他者とのつながりを失い、孤立する。
右脳だけでは、現実的判断ができなくなり、自己が不在になる。
脳科学的にも人間とは、その左右を行ったり来たりすることでなんとか生きていく存在だ。個の確立・自律(自立)といった周囲からの切り離し(デタッチメント)と、周囲との繋がりと協調(アタッチメント)の往復運動は、一生をかけた人の発達過程でもある。
本作でのシンジくんは、他者との完全な融合を選ばず、個として生きることを選んだ。そしてサルトルのいう「他人という地獄」の世界へ戻っていったーー。
その地獄を象徴するのが「気持ち悪い」という言葉だ。
左脳は拒絶・否定の言葉として受け取るだろう。本作のラストのセリフも激しい拒絶と否定のニュアンスが込められている。
サルトルも「他者からの解放」を実現できなかった思想家でもある。自由とは他者との闘争であり、その代償として孤独を引き受ける必要があった。
エヴァシリーズは、そのサルトル的見方を一歩進める試みでもあると思う。他者は地獄であると同時に救いでもある。他人はコントロール不能だけれど、その不完全な状況を受け入れ、関係性の中に自己が生じるという視点を導入した。
ただ、まだ本作では、他人との繋がりを温かなものとしては捉えきれておらず、それゆえショッキングで希望を感じにくいラストになったのだと思う。それが「シン」シリーズでより成熟した庵野によって改定された。
同じ状況でも受け止め方は様々だ。人間が意味を感じる時、右脳の文脈的な統合が働いて「自分と世界は繋がっている」と安心する関係として世界や他人を認識する。
その右脳的認識が働かないと、言葉は単なる情報で、字義通りの拒絶の言葉と感じられる。そして、自己保存のために、逃げる、闘う、固まって動かないかという選択肢から選ぶことになる。シンジも、多く場合、逃げたり固まって動かないことを選び、そんな自分がダメだとも思っている。
右脳的なつながりの感覚がしっかりと働いていれば、アスカの言葉は「ちょっと気持ち悪い、やめてよ〜」みたいな響きになるかもしれない。そして「アスカはいつも厳しいなあ。傷つくよ」くらいのグルーミング的じゃれあいとして描けたかもしれない。
現代では男性的暴力性とハラスメントといった視点も入ってくることで、なかなか難しいところだ。シンでは身近な人々と繋がって一緒に生きていく姿が描かれ、共同体主義・コミュニタリアン的な成熟として描かれることになる。
この辺り、現代思想や政治的世界の変遷と、エヴァという作品の変遷、そしてその背後には庵野という作家の成熟の過程が絡み合っている。「自分と他者をどう捉えるか」が変化し成熟していくから、その反映としてのエヴァも何度か描き直すことになった。
本作は、作者と時代と共に成熟する作品としてのエヴァの方向性を示した重要な1作だ。「これで本当にOK?」という疑問が残るからこそ、その後も多くの人がそして何より庵野自身考え続けることになった。
エヴァが示したのは、救済ではなく成熟だった。それは、他者と世界を〝完全なものにする〟のではなく〝不完全なまま関係し続ける勇気〟の物語でもある。
本作の変遷を追いかけることは、自分自身の成熟や成長を問い直すことにもなることだと感じる。改めて、エヴァと同時代に生きられたことを幸運に思い、感謝したくなった久しぶりの再鑑賞だった。
製作当時の精神状態がそのまま作品に!鑑賞者にも突き付けたカオス!
前回、2023年に劇場で、やっと観ました。
取り壊し前の「新宿ミラノ」でリアタイで観たかった。
今回再鑑賞。公開から30年!
とにかく、やっぱ凄かった!
ある程度予想はしていたが、クライマックスのカオスにはただ驚くばかり。
観ながら、当時の庵野秀明、スタッフの精神的に追い詰められていく感じが伝わってくる。
鑑賞者をも安穏とさせない、当事者であることを突き付ける。
ラストのラスト、あのセリフで、こんな終わり方は、さすがにない。
いや、これがその時の率直な感情だったに違いない!
と、同時に、これをそのまま世界に発信したい。
世界の人たちは、どう観るか。
こんなアニメ、特にロボットアニメ!世界のどこにもない!!
庵野秀明の魂がここにある
最初に、この「まごころを、君に」という作品はTV版の旧劇における真の完結作品であり、新劇がある今においてはエヴァという世界の1つの結末を描いた作品である。エヴァがループ世界であるという設定がある今において、この作品単体で評価する事は非常に難しいという事を最初に述べさせて頂く。
まずこの新世紀エヴァンゲリオンには庵野監督の3つの心があると考えている。(故意的にマギシステムと被せている訳では無い…多分。)
➀子供心…これは主人公だけでなく多くのキャラに該当するが、どのキャラも欲望に素直で何処か捻くれていて、それでいて稚拙だ。如何してもアニメという創作の中では大人を大人らしく描きがちだが、庵野監督は違った。これは敢えてなのか、庵野監督が大人のイメージを持てなかった(我々と違った)のかは言及しないが、結果キャラ1人1人が生きているアニメとなった。
②オタクとしての心…庵野監督の作品は隙があれば、電車や鉄塔、戦車等が登場する。これは庵野監督が好きだからとしか言い様が無いシーンでも出て来るが、何故か私達鑑賞者は納得と理解を示してしまう。これは新世紀エヴァンゲリオンとの相互性が高いからに他ならない。何故か?新世紀エヴァンゲリオンは庵野監督のオタクを体現した作品であるからだ。
③庵野秀明の心…これの子供心と異なる点は庵野秀明は実際には大人でありこの社会の不合理、人間の邪悪さを知っているという点だ。だから子供心を持っていても決して子供には無い心の歪と空虚を持ち合わせている。その空虚(都合の悪い部分)は大好きな電車や戦車に、クラシック音楽が埋めている。これは私達鑑賞者も同様だ。この新世紀エヴァンゲリオンという作品を私達は目をかっぽじって夢中で鑑賞し、そして作品と庵野秀明の心の深さから空虚を味わう。そこに流れるクラシック音楽の救いと絶望。なんと恐ろしい作品か、我々はいつの間にか庵野秀明と同一になってしまっているのだ。まるで人類補完計画ではないか!
というつまらない冗談は置いておいて、あくまでこの作品はシンジの成長物語である。かっこいいロボット(人造人間)も、癖の強い登場人物も、ど迫力な戦闘シーンも、深い設定やストーリーも、この作品とクラシック音楽を合わせるという天才的な采配も、全てはシンジの成長物語の一助を担うに過ぎない。最も重要なのはこの作品に庵野監督の魂が込められているという事である。この子供心とオタク心と稚拙で邪悪で破滅的な文学性を持ち合わせている男が居たからこそこの作品は完成したのだ。
勿論、この作品は賛否が分かれる。上記に示した通り子供心を持つ庵野監督から見た自身と他人の醜悪な様も表現されているからだ。自己嫌悪に陥り、他人を信じられなくなる様なアニメを毛嫌いするのは決しておかしくないが、それを飲み込み表現したこの作品の価値の高さは相当なものである。更にはシンエヴァではその境地を超えたとも思える。これ程エヴァファンとして嬉しい事があろうか。
新世紀エヴァンゲリオンとはシンジと庵野監督と私達の心を同一とし、同じ希望と絶望を味わう作品である。であるからして、また明日が来る希望のコンテニューを庵野監督は結末として描いたのであり、それこそが庵野監督の最上級のまごころなのである。そして私達はオタクから1人間に戻りまた社会を生きるのである。
だからこそ言わせてもらう、おめでとう。
そして、ありがとう。全てのエヴァンゲリオン。
なんだかんだハッピーエンドなのかも
冬月先生やゼーレの人達が始まりと終わりの場所は同じと言っていて、エヴァンゲリオンの始まりは碇シンジが綾波レイを一人で見るシーンから始まった。そして終わりは碇シンジが、惣流・アスカ・ラングレーという他者を受け入れた状態で綾波レイを見る。あれだけ劇中で他者を拒絶していたシンジ君が最後は他者といて、映画が終わる。自分は以上のことからこの映画はハッピーエンドだと想えた!
豊かさと不安と逃避と狂気の作品
感想その1
この頃はテレビやビデオやパソコンが大衆に浸透した直後であり日本の若者人口も非常に多かったためアニメやゲームなどの産業の盛り上がりが日本国内でかつてないほど最高潮に達しました。その1999年ごろに当時の若者の間で大ブームになったテレビSFアニメの25話と26話を映画化した作品。テレビ版アニメ全26話では町を防衛する巨大ロボットのパイロットにある日突然選ばれた主人公の少年シンジが下宿しているマンションや学校で学生生活を送りながらも基地でパイロットとしての任務をこなす日々を描く。25話と26話は物語のクライマックスにあたる。敵ロボットの襲来がくりかえされるなかでシンジの仲間たちが次々と再起不能になるがついに敵ロボットの黒幕の陰謀の正体が明らかになろうとする。シンジは多くの仲間を失い一人で困難に立ち向かわなければならなくなる。シンジはこの苦境に悩み、非常事態にもかかわらず現実逃避ともいえる行動をとる状況から映画はスタートする。劇中で状況がどんどん悪化するなかついにシンジは世界が崩壊していくさまを目撃する。常識だった世界が終わりをむかえて非常識な世界が再構築されシンジとヒロインのアスカの二人だけが生き残り物語が終わる。「1999年に人類が滅亡する」というオカルト的デマが当時の日本で流行りましたがそれに着想をえた世界滅亡がテーマの作品がこの映画だと思います。90年代ごろの日本の人々は明治維新以後や第二次大戦後苦労して手に入れた経済的に繁栄し豊かな日本が突然滅亡して豊かな生活を失ってしまうことが不安だったのだと思います。主人公の少年シンジは生活は豊かですがいつも不安で自信がない少年ですがシンジはこのころの日本を反映したキャラクターだと思います。エヴァンゲリオン初号機という圧倒的な力をもったロボットに乗っていてもシンジの不安がなくならずアスカの肉体に逃避しようとしたさまは当時世界2位の経済大国だった豊かさをいつ失うかと不安で娯楽に逃避した当時の日本社会に似ているとおもいます。漠然とした未来への不安から娯楽へ逃避する行為が本当に世界を滅亡させないようにラストシーンで作者ははっきりとこの状況を気持ち悪いと表現していると思いました。
結論1:この作品の作者のいいたいことは豊かさと不安からくる現実逃避は世界の滅亡につながることへの警鐘。
感想その2
学生のころ友人の家で初めて観たとき、高品質の戦争映画やサスペンスやメロドラマやエロビデオの詰め合わせを見せられたような1秒も目が離せない展開の映像にくぎ付けになる90分間のあと突然ラストでわけわからない実写映像や不気味な絵画に入り込んだようなシーンになりあっけにとられました。当時の視聴直後、私は作者にからかわれたような気がして困惑した気分にさせられました。特にラストシーンで主人公のヒロインの二人だけが生き残り、ヒロインのアスカが主人公のシンジに言う「気持ち悪い。」という言葉は何十年も私の頭に残り続けています。ラストシーンはアスカは意識がもうろうとしながら顔を空に向け寝ていてシンジはその上におおいかぶさってアスカの首に手をかけようとするが涙を流してその行為を途中でやめます。そのとき意識がもうろうとしているアスカがつぶやいた言葉が「気持ち悪い。」でした。このシーンはアダルトな内容のビデオを連想させますがそもそも90年代はビデオデッキやパソコンの普及率上昇などによりアダルトな内容のビデオやゲームなどの生産が盛んな時期でした。それらの内容や行為は生理的に気持ち悪いと感じるのがあたりまえですがこの作品の作者のいいたいことは気持ち悪くないと人類は成り立たないということだと思います。現実世界とは人類には永久に理解できないカオス(不条理)なものゆえに個人個人にとって気持ち悪いことだらけですがそれは整然とした美しい現実世界を愛するがゆえにおこる当然の反応なのだと思いました。しかし本当の現実世界は狂気も内包していると思いました。
結論2:作者が言う気持ち悪いという言葉の本質はカオスな面をもつ現実世界への深い愛情からきている。
エヴァンゲリオン初心者で若者の意見
「気持ち悪い」
オ◯ニーする主人公は恐らくこの作品のみであろう。
そして軍団のNERV職員惨殺シーン「大人のキス」の下り、アスカの覚醒。心が踊ると同時に脳内がバグる感覚。
トドメはシンジからアスカの首絞めや人類補完計画。
全て含めての「気持ち悪い」
本来、ファーストインパクトはグレートインパクトと見るのだろうが、人類はファーストインパクトで終わる運命が決まっていた。と言いたいのか?
石森章太郎先生の『リュウの道』みたいな終わり方。観念的に曖昧に終わらせるのは良いが、商業ベースにのせるのはどうかと思う。
『人は互いに理解できる?』現状からして出来る訳がない!
2001年宇宙の旅を模倣している。しかし、宗教が違えば、この解釈が成り立たないと理解すべき。少なくとも、キリスト教に生まれ変わりと言う概念はあったろうか!
まぁ、でも、シンエヴァンゲリオンと比較した場合、この終わり方の方が良かったのではと感じる。
ラストシーンが意味不明も、いつも予想を覆す庵野監督らしさは満載
テレビシリーズの大円団からの一転し、ミサトは銃撃で戦死し、赤木リツコはゲンドウに射殺され、アスカの弐号機は量産機により貪り食われてしまうという見る者たちの予想を覆す展開。
そういえば、映画館でエヴァを見る観客の姿も映し出され、相当にオタクファンに挑発的でもあった。
そしてラスト赤い海の海岸で、シンジはアスカの首を絞めるが止め、アスカが気持ち悪いと呟いて、映画はいきなり終わる。色々な解釈有る様だが、未だに自分には大いなる謎のままのラストシーン。
ひとつになりたい
渚カヲルを死なせてしまった碇シンジは心を閉ざしてしまう。やがてNERVと決裂した“人類補完計画」をすすめるゼーレは本部を攻撃し始める。アスカは意識不明だったが、弐号機に放り込まれ、自然回復を待つことに。襲い掛かる羽根のあるエヴァシリーズ9体。活動限界まで3分半の間に倒さねばならないという危機的状況でアスカが復活して撃破したかのように思われたが、思わぬところから“ロンギヌスの槍”が・・・
TV版25話と26話の別バージョンではあるが、アクション満載の25話と、シンジの精神世界が描かれていて、大人向けのエロいシーンもある。綾波は何してるんだよ~と思っていると、ゲンドウにあちこちまさぐられてからリリスと一体化してしまう。
人間もリリスと呼ばれる生命体から生まれた第18の使徒だった?神のような存在となった綾波が巨大化して、結局はサードインパクトが起きてしまったということなのか。映像が気持ち悪いぞ!そして、人類は滅亡しても意識は残る。綾波とカヲルが一体化しちゃったぞ!どうするシンジ?!終盤には街並みだとか劇場の様子という実写が織り込まれ、これは過去か未来かと、いろいろ想像させられる。
その色んな想像の中で、シンジの妄想世界と実直なアスカ、未来をシンジに託すミサト、一体化したり液状化したりと忙しい綾波がそれぞれ個性をぶつけてくる。多分、シンジは綾波のことをプラトニックラブの対象、同志として助け合う存在としてとらえているのだろう。また、アスカは自慰のためのオカズとしてとらえ、精神的にSとMの関係を築きあげている。ミサトは母のイメージとして、性的対象にはしていない・・・だけでキスしてみたい関係。それにしても綾波との一体化はエロいけど、アンチATフィールドで液状化してるからなぁ・・・最後には海岸で倒れているシンジと左目を失った上に傷だらけのアスカ。ここから新しい世界が始まるのね(多分)。
庵野秀明の頭の中を覗きたい。
※本レビューは「REVIVAL OF EVANGELION 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 DEATH(TRUE)2/Air/まごころを、君に」のページに投稿したレビューを再構成したものです。内容は殆ど同一となっております。ご了承下さいませ。
――
DVDで鑑賞。
テレビシリーズの最終回があられもない姿で、「こりゃあ、納得いかんわなぁ」と思える代物だし、本作がつくられて良かったな、と…。内容のことは度外視して、ですが…(笑)
「Air」はアクションたっぷりで、手に汗握る場面の連続でした。最後の敵がまさかの人間だなんて…と云う絶望感がハンパなかったです。次々に死んでいくネルフ本部の人々…。
不慮の事故でアスカの生おっぱいを見てしまい、それをオカズに自慰行為をしてしまったせいで、もっと病んでしまったシンジくんを救うために、ミサトさんが決死の突撃! “大人のキス”に痺れた男性多いのでは? さらに続く悲惨・凄惨な場面の数々に、シンジくんの精神は臨界点を突破し、ついに“サード・インパクト”が発動してしまいました。
「まごころを、君に」では、第弐拾六話よりは緻密になりはしたものの、再びシンジくんの精神世界での葛藤が描かれていきました。哲学的な問い、答えの出ない問い、蝕まれて行く私の脳髄…。正直頭痛くなりました。気分がとても沈みました。胸を掻きむしりたくなるような激情がこみ上げたかと思えば、すぐに虚ろな感傷へと持って行かれてしまったような、なんだか意味の分からない精神状態になりました…。
難解さは変わらず、全ての謎が解き明かされたのかそうでないのかもよく分からないまま、首を絞められて「気持ち悪っ」で終劇してしまうとは。呆気に取られました。どゆこと?
庵野秀明監督の頭の中を開いて見てみたい衝動に駆られました。どうやったらこんな発想が湧いて来るのか? もはや異次元です。自分なりの解釈を考えないと…。
※リライト(2021/03/14)
「旧エヴァ」?「本家エヴァ」じゃ!
約15年前に初めて観たときの衝撃(トラウマ?)はいまだに引きずっている気がします。
弐号機が暴れまわったり喰われたり、後半はみんな溶けたり実写が入ったり、「これマジか!?」ってなりました。
いや、フィクションなんでマジなわけないいんですが、それくらい取り込まれていました。
難解な話ですが、シンプルに言えば、好きな人を遠ざけて、楽しかったことまで全て嫌になってしまうという、僕たちがよくやってしまいがちなことを超脚色して書いてるだけなのではと感じました。
新劇場版によってブームが再燃しましたが、こちらを観ていないという人があまりにも多いというのは愕然としています。
旧エヴァ(この言い方も嫌だ)最高です!
アスカのシンジに対する狂おしい程の好意がわかります。
アスカの「あんたが全部私のものにならないのなら、私なにもいらない」
これはもう加持リョウジは父親としてで、異性としてシンジがやばいくらいに大好きで、そんな自分を見向きもしないシンジを同時に非難しています。愛憎ってやつです。
ラストがそれを象徴しているようです。
シンジに首を絞められても怖い顔をしながらでもあるがシンジの頬をやさしくなでる。愛憎そのものですね。
レイがリリスとしての記憶、シンジに纏わる記憶も全て思い出し、ゲンドウを拒絶しシンジの願いを叶えるのも見ものです。
発想が怖すぎて凄い
序、破と観るとまた見直したくなるのがエヴァシリーズ。(そしてまた長々と考察しちゃうw)
ただこの旧劇場版は観る前に一呼吸置いてしまう。
もうね怖いんです。w
怒り、悲しみ、苦しみ、狂気、変態性、嫌悪感作り手のそんな感情を感じるすごくエネルギーを使う映画なのです。
ただやっぱり映画としてはすごく高度なものだと思うし、その数々の発想の斬新さは笑っちゃうくらい凄いです。
歳を重ねる毎にエログロを芸術的だと思うようになってきたんですが、アニメでそれを感じたのはこの作品だけかも。
特に補完最中は何その発想…と引きつつ感心していましたw
アウトなのも多いですけどねw
心理描写にあてた25、26話に起きていたことを描いたエヴァンゲリオンのもうひとつの最終回。
おもうことがありすぎて、うまく言葉にできません。
善悪、幸不幸、子供大人、本能理性、欲求、生きるとは何か、人間って何か、そんなことを考えずにはいられなくなります。
こんなことを考えるのもまた人間だけ。
それすら驕りなのかもしれません。
わかりません。w
25、26話と交互に観てみるのも面白いです。
エヴァがより一層好きになりました(w´ω`)
エヴァの映画初めて見ましたw
やっぱり難しいですね…。笑
大人の方でも理解するのは難しいでしょうね(;´ω`)
高校生のボクの頭では、理解不能です。笑
でもエヴァンゲリオンが社会現象を起こした理由がわかった様な気がします(w・ω・)
ボクも今ではすっかり『エヴァファン』です(w´ω`w)笑
エヴァンゲリオンの第2の最終回だけあって、
捉え方は様々だと思います。
にしても…。
『怖い!!!』
エヴァンゲリオンがこれほどまで
怖いものとは思いませんでした…(; ̄□ ̄)
でも、もちろん怖いだけでなく
感動するとこもありました(w・ω・)b
ミサトさんのシーンは涙ものでした・・・。(泣)
『大人のキスよ。帰ってきたら続きをしましょ。』
ヤバイですょ(w・ω・)??
アニメはもちろんのこと…
映画もみたら、あなたもすっかり
『エヴァファン』になるでしょう(w´ω`)!!
全19件を表示