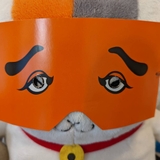ゴンドラ(1987)のレビュー・感想・評価
全9件を表示
ゴンドラは海に浮かぶ・・
都会の高層マンションで気の合わない水商売の母と暮らす小学生の孤独な少女かがり(上村佳子)と青森から上京しゴンドラに載って窓ふきをしている、これまた孤独な青年良(界健太)が少女の飼っていた文鳥の怪我を機に出会いを深めて、青年の故郷の海に死んだ文鳥を流すまでを追った感傷的ドラマ。
感想としては何よりも伊藤監督の作家性の強さ、手法・表現が特徴的でした。
主人公の視線の光景が歪んだり揺らいだり、あとで独白していましたが故郷の海が好きで空中ゴンドラから観る光景が海面のように揺らいで見えると言っていましたから心象描写なのでしょう。
割れた皿から蜘蛛がひしめき合う描写、気になったので調べてみたら文鳥は昆虫も食べる雑食だそうですから、おそらく餌用だったのでしょう、兎に角この映画はセリフも少ないですし解説めいた演出は封印されているようです。
それだけでなく、突然モノクロ映像になったり、音響も、音叉の純音に対して金属打音や不協和音のBGM、工事の音などをふんだんに入れてわざと聞きづらくしてみたり、「どんどはれ」という岩手の難解な方言のセリフなどをあえて交えた刺激的演出が綿々と続きました。
感性を刺激することで飽きさせない工夫かも知れませんが度を越しているので稚拙で胡散臭く思えてしまいました。
映画は伊藤智生、脚本・監督が主人公のかがりを演じる、当時小学4年生の上村佳子に出会い、家庭にも学校にもなじめない孤独に苛まれる表情に心を痛め、少女の心を開く映画を作りたいと思ったことがきっかけだったそうです。
また、監督は映像表現についても「私がつくりたいのはドラマではなく、ごく日常的な情景の中で人々が繰り広げる心の対話をフィルムに彫刻したかった」と言っていることから本作で撮った手法がうなずけます。
本作は5000万円の借金をして自主製作したそうで、返済も大変だったので本作を観た友人に勧められて伊藤監督はAV製作に進んだようですが、本作にも必然性のない母親、小学生からおばあさんまでの裸身の入浴シーンの挿入があり、その兆候が見られました。
ゴンドラというタイトルの割に窓ふきのゴンドラは前半にちょっと出るだけでしたがラストにちゃんと本当の小舟、ゴンドラが出てきました。
視線の揺らぎなどからも海が裏テーマのようです、少女が死ぬとどうなるのかと青年に聞くと皆、海に帰ると答えます、波は死んだ人の感情の揺らぎが起こすのさ、何でと聞くと生きているものを守ってくれていると言っていましたが本作は1986年製作で3.11以前なので美化できたのでしょう・・。
著名な俳優、監督、詩人などから絶賛され映画賞もとっている作品ですから平凡なおじさんが評するのは憚られるでしょうが作家性が強すぎて好みからは外れました、ごめんなさい。
除け者同士の青年と少女が当て所なく探す"命の意味" "人は一人では生きていけない"を瀟洒に描く自主映画...
公開当時からその筋では有名な作品だったようですが、数年前の公開30周年でのリバイバル上映やソフト化の際には結構話題になってましたね。旧作にしても最新公開映画にしても上映に際しては著名監督、俳優さんやコメンテーターさんが絶賛コメントを寄せるのが常ですが、本作については斎藤工さんの「何百何千本観なくても この一本だけ観たい そんな作品」というコメントがなんとも印象的でした。
己が生に孤独と違和感を抱える青年と少女の二人が死生観をきっかけに交流を持ち、現実を見つめ直す物語です。
予告や解説等でも引き合いに出される作中のセリフとして、
あかり「死んじゃうと、生きてたことってどこいっちゃうのかな.....」
良「俺の田舎じゃさ・・・・・死んだ者は海に帰るって言われてんだ」
というものが有りますが、作中の総てがそこに収斂しているように思います。
孤独を描いた作品は当然の如く画面も寒々としたものが多いかと思いますが、本作は"水"が頻出しますがそれすらもどこかしら暖かく、そのあたりの人を拒むわけではない孤高さが国内外での評価の高さに繋がっているのかもしれません。
なんだかとってもいい
便所は汲み取り
アート系作品かと思ってしまった序盤から、ハートフルドラマへ。説明なんてまどろっこしいものは要らない。孤独を感じている青年・良からすれば、都会で見つけたたった一人会話の相手。街並みが海に見えるというところが絶妙でもあった。一方の11歳の少女かがりは音のない高層マンションの一室で文鳥のさえずりに癒やされていた。
鳥の死骸を扱ったことから、ちょっと間違えればホラー、エロチックなものになってしまうだろうに、純粋な心を持つ主人公のおかげでファンタジーさえ感じてしまう。下北半島のロケ地もいいし、良の母親(佐々木すみ江)の演技がとてもいい。
好きなシーンは廃校となった学校の音楽室。壊れたオルガンを弾いて目眩を起こすところが不安定さを醸し出していた。
まさしく掘り出し物の作品だった。木内みどりも佐々木すみ江も入浴シーンがあるし、少女かがりも一緒に入ってる。少女ヌードシーンがある映画ってのは何故か埋もれちゃうんですよね(勝手に思ってます)。
煌めきの中に漂う危うさ
その時代の古さがしっかりと出ているのに、スタンダードの映像が非常に美しくて、映画特有の普遍性を強く感じた作品。
明瞭な映像の中に挟み込まれてくる、生の危うさ、危うい性…。決してよい内容でもよい演出でもないけれど、ぎこちなくて不自然な関わり合いが、目を離すことができないような緊張感を生み出しているような印象。
東京の風景、東北・靑森・下北半島の風景、その描写がことごとく見事なものだが、それに反して登場してくる人々の描かれ方は決して美しくも気持ち良いものでもない。人間臭いところが丸出しになっているように見えるのだが、不思議と嫌悪感はなくて、むしろ愛おしく思えてくる。
どろどろとした中で光輝くピュアなもの─その輝きはあまりにまぶしくて、まぶしすぎるが故に、すぐに消えてしまいそうな刹那…。短いスパンで考えれば幸福感を強く感じるけれど、長いスパンで感がると悲劇的な思いになってしまう。
恋しさと せつなさと 心強さと
キネカ大森で「ゴンドラ」を観た。上映終了後、後ろの出口から聞き覚え...
感動しました
この映画が30年前に作られたものとは驚き。
まず、映像が綺麗。特に青森県下北半島の風景を、わたしは実際に見ているだけに、そのまま切り取ってスクリーンに貼り付けたような印象を受けた。35ミリフィルムに焼き付けられた鮮やかな色が、そのまま残って再現されていたのはほとんど奇跡に近い(上映後の伊藤監督の挨拶でもそう語っていた)。デジタル全盛のご時世だけど、アナログの映像は柔らかくて暖かい。心まで包み込む。
ストリーは単純。夫婦仲が悪くなって父親が出て行った後の母子家庭。心を閉ざしている少女は、窓拭きの青年に会って少し心を開く。青年の故郷に一緒に行き、青年の両親に会ったり青森の自然に触れてまたもう少し心を開く。ラストは、少女のちょっとだけの成長と夫婦が和解してまた家族で暮らすことを暗示して終わる。それだけ。
心の癒しと救いというテーマが、美しい映像と役者の朴訥とした演技の一番深いところを静かに流れている。
いつまでも心に残る映画には一生の内そんなに出会えることはないが、わたしにとってこの映画はその1つになる。今回のリバイバル上映においてデジタルリマスターされたので、メディアが販売されたら購入したい。でもやはり35ミリを何度も見たい。
全9件を表示